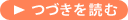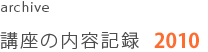


『「民衆演劇」と「公共の演劇」の構想−フランスの場合を参照しつつ』
Vol.2(続編 2010年版)
「歴史家ミシュレの思想と『民衆演劇』の誕生」
「『公共劇場』運動と文化政策」
「歴史家ミシュレの思想と『民衆演劇』の誕生」
「『公共劇場』運動と文化政策」
2010年11月18日(木) 19時〜21時 / 2010年12月2日(木) 19時〜21時
佐伯 隆幸
(演劇評論家/学習院大学教授 2011年3月で定年退職)
《所 感》
フランス革命(の初期)において、自発的に組織された「連盟兵」が新たに生まれた人々、人民=民衆peupleの“紐帯”の核心を担った。これがあとで述べられるミシュレの言説の最大のポイントである。連盟兵はルソーのいう「一般意志」volonté générale によって導かれ、それを体現したのである。それぞれが対等であるこの「思想」の共同体において、人々は互いをcitoyen, citoyenne市民と呼びあった。この市民こそが、民主主義実現の前提であり、彼らがpeupleと一致するところにしか真の民主主義はありえない。同時に、「祭り」の自発性、連帯、決定的な意味での一回性は「大革命」にこそその淵源を有する。「民衆演劇」がもとめたものは何であったか。それは、citoyenとpeupleの一致であり、演劇と「祭り」の融合を目指す理念へのひとつの解答であった。論はそこから日本現在の暗黙の全体主義、劇場における自由、演劇としてのエロスという領域にまで及んだ。戦後も今も日本にcitoyenはいるのかという依然出される問いによって私たちは自らの状況の曖昧さを突きつけられた。「公共劇場」の基本はcitoyenをどう考え、捉えるかの問題であり、私たちはそれに向き合わざるをえないのである。
前回を受けての第2回は、あるべき公共劇場の姿を模索、提示する、刺激的な内容であった。公共劇場を考えるということは、市民社会の実際のありようを考えるということにつながっていく。それをみないで成り立つ演劇は空疎である。舞台表現は現実の鏡として、この社会の一般意志を表象する可能性を秘めている。劇場という鍵穴を通して、私たちは現代社会の闇を見通すことができた。私たちは、現在のメディア社会のつくり出す「仕掛け」に意識的あるいは無意識的に踊らされていることに気づくかもしれない。舞台にすら、現実を映し出すことのない、無関係という「虚構」がある。文字とおりに受けとれば虚構が在ることに私たちはさしたる疑問も抱かずに通り過ぎてしまう。クロスすることのまったくないまま。フランスにおいて、「国民的共有財産」としての演劇はいかにあったのか。そこから、反照される日本の演劇の現在を追う。
その照射によって、民衆演劇における「民衆」とは今何かをようやく垣間みることができるのである。
フランス革命(の初期)において、自発的に組織された「連盟兵」が新たに生まれた人々、人民=民衆peupleの“紐帯”の核心を担った。これがあとで述べられるミシュレの言説の最大のポイントである。連盟兵はルソーのいう「一般意志」volonté générale によって導かれ、それを体現したのである。それぞれが対等であるこの「思想」の共同体において、人々は互いをcitoyen, citoyenne市民と呼びあった。この市民こそが、民主主義実現の前提であり、彼らがpeupleと一致するところにしか真の民主主義はありえない。同時に、「祭り」の自発性、連帯、決定的な意味での一回性は「大革命」にこそその淵源を有する。「民衆演劇」がもとめたものは何であったか。それは、citoyenとpeupleの一致であり、演劇と「祭り」の融合を目指す理念へのひとつの解答であった。論はそこから日本現在の暗黙の全体主義、劇場における自由、演劇としてのエロスという領域にまで及んだ。戦後も今も日本にcitoyenはいるのかという依然出される問いによって私たちは自らの状況の曖昧さを突きつけられた。「公共劇場」の基本はcitoyenをどう考え、捉えるかの問題であり、私たちはそれに向き合わざるをえないのである。
前回を受けての第2回は、あるべき公共劇場の姿を模索、提示する、刺激的な内容であった。公共劇場を考えるということは、市民社会の実際のありようを考えるということにつながっていく。それをみないで成り立つ演劇は空疎である。舞台表現は現実の鏡として、この社会の一般意志を表象する可能性を秘めている。劇場という鍵穴を通して、私たちは現代社会の闇を見通すことができた。私たちは、現在のメディア社会のつくり出す「仕掛け」に意識的あるいは無意識的に踊らされていることに気づくかもしれない。舞台にすら、現実を映し出すことのない、無関係という「虚構」がある。文字とおりに受けとれば虚構が在ることに私たちはさしたる疑問も抱かずに通り過ぎてしまう。クロスすることのまったくないまま。フランスにおいて、「国民的共有財産」としての演劇はいかにあったのか。そこから、反照される日本の演劇の現在を追う。
その照射によって、民衆演劇における「民衆」とは今何かをようやく垣間みることができるのである。
記録:松浦耕平(東京大学大学院人文社会系研究科修士課程在学)
※本記録は、講座の記録をもとに、講師による大幅な加筆を加えて掲載しています
※本記録は、講座の記録をもとに、講師による大幅な加筆を加えて掲載しています

序. フランス革命と「一般意志」
「引かれ者の小唄」とか「雀百まで」とかいわれようがどうしようが、原則は原則で、勝手には動かないし、動かしえない。ルソーの「一般意志volonté générale」を置くところからもう一度始めてみよう。さて、ここで注意を要するのは意志であって、「意思」ではないことだ。「意志」でないと無内容だし、ただの自己充足の作為に乗ぜられる、とくに現在は。

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.