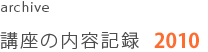


『「民衆演劇」と「公共の演劇」の構想−フランスの場合を参照しつつ』
Vol.2(続編 2010年版)
「歴史家ミシュレの思想と『民衆演劇』の誕生」
「『公共劇場』運動と文化政策」
「歴史家ミシュレの思想と『民衆演劇』の誕生」
「『公共劇場』運動と文化政策」
2010年11月18日(木) 19時〜21時 / 2010年12月2日(木) 19時〜21時
佐伯 隆幸
(演劇評論家/学習院大学教授 2011年3月で定年退職)
《所 感》
フランス革命(の初期)において、自発的に組織された「連盟兵」が新たに生まれた人々、人民=民衆peupleの“紐帯”の核心を担った。これがあとで述べられるミシュレの言説の最大のポイントである。連盟兵はルソーのいう「一般意志」volonté générale によって導かれ、それを体現したのである。それぞれが対等であるこの「思想」の共同体において、人々は互いをcitoyen, citoyenne市民と呼びあった。この市民こそが、民主主義実現の前提であり、彼らがpeupleと一致するところにしか真の民主主義はありえない。同時に、「祭り」の自発性、連帯、決定的な意味での一回性は「大革命」にこそその淵源を有する。「民衆演劇」がもとめたものは何であったか。それは、citoyenとpeupleの一致であり、演劇と「祭り」の融合を目指す理念へのひとつの解答であった。論はそこから日本現在の暗黙の全体主義、劇場における自由、演劇としてのエロスという領域にまで及んだ。戦後も今も日本にcitoyenはいるのかという依然出される問いによって私たちは自らの状況の曖昧さを突きつけられた。「公共劇場」の基本はcitoyenをどう考え、捉えるかの問題であり、私たちはそれに向き合わざるをえないのである。
前回を受けての第2回は、あるべき公共劇場の姿を模索、提示する、刺激的な内容であった。公共劇場を考えるということは、市民社会の実際のありようを考えるということにつながっていく。それをみないで成り立つ演劇は空疎である。舞台表現は現実の鏡として、この社会の一般意志を表象する可能性を秘めている。劇場という鍵穴を通して、私たちは現代社会の闇を見通すことができた。私たちは、現在のメディア社会のつくり出す「仕掛け」に意識的あるいは無意識的に踊らされていることに気づくかもしれない。舞台にすら、現実を映し出すことのない、無関係という「虚構」がある。文字とおりに受けとれば虚構が在ることに私たちはさしたる疑問も抱かずに通り過ぎてしまう。クロスすることのまったくないまま。フランスにおいて、「国民的共有財産」としての演劇はいかにあったのか。そこから、反照される日本の演劇の現在を追う。
その照射によって、民衆演劇における「民衆」とは今何かをようやく垣間みることができるのである。
フランス革命(の初期)において、自発的に組織された「連盟兵」が新たに生まれた人々、人民=民衆peupleの“紐帯”の核心を担った。これがあとで述べられるミシュレの言説の最大のポイントである。連盟兵はルソーのいう「一般意志」volonté générale によって導かれ、それを体現したのである。それぞれが対等であるこの「思想」の共同体において、人々は互いをcitoyen, citoyenne市民と呼びあった。この市民こそが、民主主義実現の前提であり、彼らがpeupleと一致するところにしか真の民主主義はありえない。同時に、「祭り」の自発性、連帯、決定的な意味での一回性は「大革命」にこそその淵源を有する。「民衆演劇」がもとめたものは何であったか。それは、citoyenとpeupleの一致であり、演劇と「祭り」の融合を目指す理念へのひとつの解答であった。論はそこから日本現在の暗黙の全体主義、劇場における自由、演劇としてのエロスという領域にまで及んだ。戦後も今も日本にcitoyenはいるのかという依然出される問いによって私たちは自らの状況の曖昧さを突きつけられた。「公共劇場」の基本はcitoyenをどう考え、捉えるかの問題であり、私たちはそれに向き合わざるをえないのである。
前回を受けての第2回は、あるべき公共劇場の姿を模索、提示する、刺激的な内容であった。公共劇場を考えるということは、市民社会の実際のありようを考えるということにつながっていく。それをみないで成り立つ演劇は空疎である。舞台表現は現実の鏡として、この社会の一般意志を表象する可能性を秘めている。劇場という鍵穴を通して、私たちは現代社会の闇を見通すことができた。私たちは、現在のメディア社会のつくり出す「仕掛け」に意識的あるいは無意識的に踊らされていることに気づくかもしれない。舞台にすら、現実を映し出すことのない、無関係という「虚構」がある。文字とおりに受けとれば虚構が在ることに私たちはさしたる疑問も抱かずに通り過ぎてしまう。クロスすることのまったくないまま。フランスにおいて、「国民的共有財産」としての演劇はいかにあったのか。そこから、反照される日本の演劇の現在を追う。
その照射によって、民衆演劇における「民衆」とは今何かをようやく垣間みることができるのである。
記録:松浦耕平(東京大学大学院人文社会系研究科修士課程在学)
※本記録は、講座の記録をもとに、講師による大幅な加筆を加えて掲載しています
※本記録は、講座の記録をもとに、講師による大幅な加筆を加えて掲載しています

序. フランス革命と「一般意志」
「引かれ者の小唄」とか「雀百まで」とかいわれようがどうしようが、原則は原則で、勝手には動かないし、動かしえない。ルソーの「一般意志volonté générale」を置くところからもう一度始めてみよう。さて、ここで注意を要するのは意志であって、「意思」ではないことだ。「意志」でないと無内容だし、ただの自己充足の作為に乗ぜられる、とくに現在は。
民主主義の根には「一般意志」がある。フランスの革命は一般意志とともに存在した。ロシアとどこか違うのはそこだ。大革命を底部で推進し、それぞれの地区で暴動を起こしたのは、ダントン派だったり、エベール派だったりする相違はあるにせよ、まずはサンキュロットsans - culottesだ。キュロットとは、往時の特権階級が穿いていた半ズボンを指す。サンキュロットとはキュロットを穿いていないという意味だ、絵もある、長ズボン姿だ。革命指導者の一人であったジャン=ポール・マラーは「自由の専制」と言った。その専制の基に一般意志はある、それ自体難問(アポリア)だが留意の要あり。やがて革命は「国民公会」を設置したが、ロベスピエールを頭とする公安委員会が独裁制を布くことになる。一般意志はそういう形態をとる、不可避的にそうなるときがあることは歴史の教訓に知っておくべきだろう。で、「テルミドール反動」というので大公安委員会の面々は逮捕、処刑され、総裁政府が成立した。フランス革命はブルジョワ革命だったし、ナポレオン帝政が加速させた資本の運動の阻害物除去を含め、19世紀はブルジョワの世紀であったといっていい。総裁政府は上層ブルジョワがいわば欲望の限りを尽くす政権だった。が、面白いことに、革命時に減衰した劇場が解放を横溢するのはこの時期なのだ。ルソー的な一般意志の革命──“清廉の人”ロベスピエールはその純粋結晶だった。そのときも若いが、ずっと若年期に「ポルノ」を書いた経験のあるサン=ジュストが彼と組んだのも不思議な感じ!! ──がブレーキを掛け、抑止する「劇」の想像力と一種ブルジョワ的な自由がもたらすその快楽と、舞台にはこの両軸、二方向に延びる幅があることは押えておかなくてはならない。演劇には、革命時にコンドルセらが構想した(民衆)教育という面と見世物(ときによって、それは他人の血であった)の享受という、ギリシア型とローマ型とが混じっている。この矛盾のなかにいつも演劇は極限的にはある。
サンキュロット(G・ルフェーヴルによると、大革命期の「直接民主主義」要求者の実体は概ね手工業者ら、「小ブル」だったらしいが)は歴史上いろんな意味がこめられ、名を変えた。あるときは要するに下層民、貧民とされたし(事実そうだった)、のちには、プロレタリアがそれにとって代わる。社会主義と人民の登場だった1848年の二月革命で重要な役割を担う労働者階級(トクヴィルの証言ではパリに十万。フランスは産業革命の真只中である)もまたサンキュロットの末裔だった。それは束の間の社会主義Commune民衆の自治自決権力の出現をみた世紀最後の革命「71年」、ランボーの言う「大洪水」まで続く。単なる政治を超えた位相で一般意志とサンキュロットは存続してきたと思える。その意味で、依然として仏は英国とも合州国とも違う革命の国である。1968年の五月革命のときも学生が中心にいたし、近年はリセアンがデモの口火を切るということも珍しくない。それを永遠の夢と片づけるのは容易だし、竹内好の皮肉なら、賢く、「敗けることを知らぬ優秀民族」が蝟集する日本では感受しにくい事態には違いない。かの地ではつねに一般意志というものが枢要な軸になってきた。つまり、一般意志とは「民衆」が場合によっては街頭に下りるということも意味している。ひるがえって、日本にはこの戦後もはたして一般意志なるものはあるのだろうか、それを形成する「運動」はあるか。ここで戦後というのはもちろん憲法もすこぶるからむ。いまださまざまな論議があるが、わたしがいちばん先に論議すべきだと考えるのは、同憲法には、大革命後の多くの憲法にある人民の抵抗権、「自然法は不文のものであり、ただ人の精神の中以外にはどこにもそれを見出すことのできないものであるから、感情または利害によってそれを誤って引用したり適用したりするものも、定まった裁判官のないところでは、その誤りを容易には悟ることができない」といういささか今の日本、同化と感情的リンチの二項しかない「共感共同体」(酒井直樹)にぴったりしそうな言を吐いた十七世紀のロックですら言う究極的な「大権」がないことのほうである(『市民政府論』、鵜飼信也訳)、ただし、それは一般意志が現存するという前提での話だ、あくまでも、それはいうまでもない。そこらは日本国籍をもつ者にとっては途方もない隘路であって、ここで深入りするのは無理。単純に、戦後憲法は第九条に縮約されもしなければ、いわんやその条項に我を託せば市民や世界の安寧が自然に在るという話ではないだろう。手品の共同体を一般意志の表示とみなすのは幻覚だし、ましてその手の物神化は呪術にすぎない。今は「閉塞感」だらけとか。そこには種々要因があって、急に大風呂敷を広げるつもりはないが、ことは長い年月の作為の自然のつけだというくらい素直に認めよう。公共=劇場もそれと無縁ではありえない。
ミシュレに戻ると、『フランス革命史』で有名な歴史家の彼(教育者でもある)は1790年の革命記念日の祭典をその著で書いている。連盟(兵)Fédérationの祭典。ミシュレは若い共和国の理想をこの祭りにあった人民の協和に視、それを熱狂的に記す。しかも、それを市民共同体のギリシア型の演劇的発揚と考えた。それは、彼が当時のウルトラ教権派、イエズス会と対立したために教権寄りの政府によって禁止され、学生たちがデモで擁護したコレージュ・ド・フランスでの講義ノート、48年刊行の『学生』にもはっきり脈絡としては示されている(46年に彼は『民衆』を上梓してもいる)。ミシュレはとても複雑で、一筋縄ではいかないけど、フランスでは共和国の根拠が「連盟」という価値だとする精神が間違いなくあった。例えばvolontaireという言葉は現在の日本は「ボランティア」としか解さないが、本来は「義勇兵」を意味する語、共和国républiqueとは公共publicの再生の謂いだった。7月14日の記念日に集まってきた連盟兵は各人の自発性に支えられ、自発性=祝祭が現存する。流れ進む時間の停止としての祭り、大革命の記憶が惰性的な日常を喰い破る層、循環、永劫回帰、生成され続ける共同体=革命の今という神話空間。それがミシュレ、またいずれミシュレ論を書くバルトがとりわけ強調したことだし、それを指針に、そこから19世紀の「民衆演劇」の思想は生まれる。少なくとも1920年に国立民衆劇場(T・N・P)の主宰者となるフィルマン・ジェミエの活動の代まではそうだったと考えていい。
民主主義の根には「一般意志」がある。フランスの革命は一般意志とともに存在した。ロシアとどこか違うのはそこだ。大革命を底部で推進し、それぞれの地区で暴動を起こしたのは、ダントン派だったり、エベール派だったりする相違はあるにせよ、まずはサンキュロットsans - culottesだ。キュロットとは、往時の特権階級が穿いていた半ズボンを指す。サンキュロットとはキュロットを穿いていないという意味だ、絵もある、長ズボン姿だ。革命指導者の一人であったジャン=ポール・マラーは「自由の専制」と言った。その専制の基に一般意志はある、それ自体難問(アポリア)だが留意の要あり。やがて革命は「国民公会」を設置したが、ロベスピエールを頭とする公安委員会が独裁制を布くことになる。一般意志はそういう形態をとる、不可避的にそうなるときがあることは歴史の教訓に知っておくべきだろう。で、「テルミドール反動」というので大公安委員会の面々は逮捕、処刑され、総裁政府が成立した。フランス革命はブルジョワ革命だったし、ナポレオン帝政が加速させた資本の運動の阻害物除去を含め、19世紀はブルジョワの世紀であったといっていい。総裁政府は上層ブルジョワがいわば欲望の限りを尽くす政権だった。が、面白いことに、革命時に減衰した劇場が解放を横溢するのはこの時期なのだ。ルソー的な一般意志の革命──“清廉の人”ロベスピエールはその純粋結晶だった。そのときも若いが、ずっと若年期に「ポルノ」を書いた経験のあるサン=ジュストが彼と組んだのも不思議な感じ!! ──がブレーキを掛け、抑止する「劇」の想像力と一種ブルジョワ的な自由がもたらすその快楽と、舞台にはこの両軸、二方向に延びる幅があることは押えておかなくてはならない。演劇には、革命時にコンドルセらが構想した(民衆)教育という面と見世物(ときによって、それは他人の血であった)の享受という、ギリシア型とローマ型とが混じっている。この矛盾のなかにいつも演劇は極限的にはある。
サンキュロット(G・ルフェーヴルによると、大革命期の「直接民主主義」要求者の実体は概ね手工業者ら、「小ブル」だったらしいが)は歴史上いろんな意味がこめられ、名を変えた。あるときは要するに下層民、貧民とされたし(事実そうだった)、のちには、プロレタリアがそれにとって代わる。社会主義と人民の登場だった1848年の二月革命で重要な役割を担う労働者階級(トクヴィルの証言ではパリに十万。フランスは産業革命の真只中である)もまたサンキュロットの末裔だった。それは束の間の社会主義Commune民衆の自治自決権力の出現をみた世紀最後の革命「71年」、ランボーの言う「大洪水」まで続く。単なる政治を超えた位相で一般意志とサンキュロットは存続してきたと思える。その意味で、依然として仏は英国とも合州国とも違う革命の国である。1968年の五月革命のときも学生が中心にいたし、近年はリセアンがデモの口火を切るということも珍しくない。それを永遠の夢と片づけるのは容易だし、竹内好の皮肉なら、賢く、「敗けることを知らぬ優秀民族」が蝟集する日本では感受しにくい事態には違いない。かの地ではつねに一般意志というものが枢要な軸になってきた。つまり、一般意志とは「民衆」が場合によっては街頭に下りるということも意味している。ひるがえって、日本にはこの戦後もはたして一般意志なるものはあるのだろうか、それを形成する「運動」はあるか。ここで戦後というのはもちろん憲法もすこぶるからむ。いまださまざまな論議があるが、わたしがいちばん先に論議すべきだと考えるのは、同憲法には、大革命後の多くの憲法にある人民の抵抗権、「自然法は不文のものであり、ただ人の精神の中以外にはどこにもそれを見出すことのできないものであるから、感情または利害によってそれを誤って引用したり適用したりするものも、定まった裁判官のないところでは、その誤りを容易には悟ることができない」といういささか今の日本、同化と感情的リンチの二項しかない「共感共同体」(酒井直樹)にぴったりしそうな言を吐いた十七世紀のロックですら言う究極的な「大権」がないことのほうである(『市民政府論』、鵜飼信也訳)、ただし、それは一般意志が現存するという前提での話だ、あくまでも、それはいうまでもない。そこらは日本国籍をもつ者にとっては途方もない隘路であって、ここで深入りするのは無理。単純に、戦後憲法は第九条に縮約されもしなければ、いわんやその条項に我を託せば市民や世界の安寧が自然に在るという話ではないだろう。手品の共同体を一般意志の表示とみなすのは幻覚だし、ましてその手の物神化は呪術にすぎない。今は「閉塞感」だらけとか。そこには種々要因があって、急に大風呂敷を広げるつもりはないが、ことは長い年月の作為の自然のつけだというくらい素直に認めよう。公共=劇場もそれと無縁ではありえない。
ミシュレに戻ると、『フランス革命史』で有名な歴史家の彼(教育者でもある)は1790年の革命記念日の祭典をその著で書いている。連盟(兵)Fédérationの祭典。ミシュレは若い共和国の理想をこの祭りにあった人民の協和に視、それを熱狂的に記す。しかも、それを市民共同体のギリシア型の演劇的発揚と考えた。それは、彼が当時のウルトラ教権派、イエズス会と対立したために教権寄りの政府によって禁止され、学生たちがデモで擁護したコレージュ・ド・フランスでの講義ノート、48年刊行の『学生』にもはっきり脈絡としては示されている(46年に彼は『民衆』を上梓してもいる)。ミシュレはとても複雑で、一筋縄ではいかないけど、フランスでは共和国の根拠が「連盟」という価値だとする精神が間違いなくあった。例えばvolontaireという言葉は現在の日本は「ボランティア」としか解さないが、本来は「義勇兵」を意味する語、共和国républiqueとは公共publicの再生の謂いだった。7月14日の記念日に集まってきた連盟兵は各人の自発性に支えられ、自発性=祝祭が現存する。流れ進む時間の停止としての祭り、大革命の記憶が惰性的な日常を喰い破る層、循環、永劫回帰、生成され続ける共同体=革命の今という神話空間。それがミシュレ、またいずれミシュレ論を書くバルトがとりわけ強調したことだし、それを指針に、そこから19世紀の「民衆演劇」の思想は生まれる。少なくとも1920年に国立民衆劇場(T・N・P)の主宰者となるフィルマン・ジェミエの活動の代まではそうだったと考えていい。
1.「演劇」と「祭り」
ルソーは演劇と祭りを厳密に区別した。演劇は観る者と演じる者とのあいだに仕切りがある。加えて、俳優は身もちの悪いのが普通であり、劇場は不道徳で、彼のいるジュネーヴのような小都市に演劇は不要であるとした。プラトンの共和国に芝居は要らないという意見から、他人を演ずることはいかがわしいという考えはブルトンあたりまで連綿とある。芸術が不実であってはならないとする「演劇嫌い」の系譜。ルソーは一切が融合した祭りこそ要なので、祭りだけが存在が自己を証し立てる場処と見定める。広場の真ん中に一本の杭を立てなさい、そうすれば、自発的に祭りがはじまると言った。とてもわかりやすい。共和国はその永劫回帰によって現存するという思考。この提起は非常に重要である。だけれども、日本で今自発性の祭りはあるか。かつて解放区と称す場所で強行されたハプニングやロックの大会といった自発の非日常=侵犯性があったが、現在、パフォーマンスはメディアが「アート」と名づけて煽るものだし、花火からオリンピックまで、お祭りはつくられた非日常の仕掛けと小細工、拵えられた行事が出来事として「消費」されている。氏子もいない町で行なわれる夏祭りは商店街主催のカラオケ大会に近い。祭りは自発の侵犯力を失ったし、そもそもわれわれにとっての肝要な層、記憶をもたない。戦後民主主義は過去を清算的に消したうえに、あまつさえ、その空白を埋めたのは高度成長以後の記号の文化だったというのが偽らざる実底。そうした場に共同体を前提した「公共」の演劇を到来させるのがいかに困難か、どう難しいかは二重の意味で即座に納得されよう。一方に祭りの大衆的出来事振り、イベントがあり、他方に演劇の事実としてのいかがわしさ(知的「前衛」の創造振りという自己消費と「創造」への、畢竟「他人事」性、ないし仮にそんな模造でない場合でも受容と共有の土台の欠如、結果は畢竟小ブル趣味、スノッブを含めそれを変える層の不在)が待ち受けているのである。
われわれにとって問題なのは、祭りであるような演劇はどう可能かをつねに問うことだ。観ている者と演じている者とのあいだに境がないことはどうしたら成立するだろうか。祭りがもう役に立たないのはおそらくはっきりしている。演劇が問題である。劇で演じ手はなるほど他人の言葉をしゃべる、他人の言葉で自己を表現するという、ほとんど分裂症(スキゾフレイニー)的な「行為」をする。とはいえ、舞台は演じられる度に異なり、それぞれの一回性をもっている。演劇と祭りの違いはそこにある。持続し、繰り返されるがゆえに演劇はいかがわしいとみなされたのだった。1790年の連盟兵の祭りで革命の日々の者たちは老若男女区別なく踊ったとミシュレは書く。出身地も違う個々が自発性においてあるとき、そこに言葉ではないものによる共有の「今」が現出する。この祭りの原型は歴史時間を切断する革命であった。彼が詩にした祭りは持続しえず、絶頂の瞬間に終焉する。その力は永劫回帰しはしても、持続は不可能なる相をもつ。それに対し、演劇はそこに胡乱さがあるには相違ないにしろ、持続可能性を有する。でも、一体何が持続するのだろうか。反復だけだろうか。けれども、舞台とは一回性であったし、ありうる。演劇は観る度に異なり、演じ手は同じ約束をやっているだけではない。軸はここだろう、他人を演ずるという約束、反復だという約束にもかかわらず、演者はいる、強固に在る、だれか一個の現存が必ずおり、演劇の約束と同時にその一回性を表現している。どういうことか。スキゾの極、こう、存在が演劇を演じながら祭りの永劫回帰を呼びこみ、その死を生きて、みえない共同体を召還し、そうやって毎たび演劇を廃絶している、それが舞台の一回性ということ、その呼びこむ存在本体が「演劇人」だということになろう。かくて、わたしは舞台なる「虚構を演ずる」の約束を演ずる態の「役」者に疑いを抱きはじめた。それでは、公共性も公共の演劇も発見・形成できないのだ。
われわれにとって問題なのは、祭りであるような演劇はどう可能かをつねに問うことだ。観ている者と演じている者とのあいだに境がないことはどうしたら成立するだろうか。祭りがもう役に立たないのはおそらくはっきりしている。演劇が問題である。劇で演じ手はなるほど他人の言葉をしゃべる、他人の言葉で自己を表現するという、ほとんど分裂症(スキゾフレイニー)的な「行為」をする。とはいえ、舞台は演じられる度に異なり、それぞれの一回性をもっている。演劇と祭りの違いはそこにある。持続し、繰り返されるがゆえに演劇はいかがわしいとみなされたのだった。1790年の連盟兵の祭りで革命の日々の者たちは老若男女区別なく踊ったとミシュレは書く。出身地も違う個々が自発性においてあるとき、そこに言葉ではないものによる共有の「今」が現出する。この祭りの原型は歴史時間を切断する革命であった。彼が詩にした祭りは持続しえず、絶頂の瞬間に終焉する。その力は永劫回帰しはしても、持続は不可能なる相をもつ。それに対し、演劇はそこに胡乱さがあるには相違ないにしろ、持続可能性を有する。でも、一体何が持続するのだろうか。反復だけだろうか。けれども、舞台とは一回性であったし、ありうる。演劇は観る度に異なり、演じ手は同じ約束をやっているだけではない。軸はここだろう、他人を演ずるという約束、反復だという約束にもかかわらず、演者はいる、強固に在る、だれか一個の現存が必ずおり、演劇の約束と同時にその一回性を表現している。どういうことか。スキゾの極、こう、存在が演劇を演じながら祭りの永劫回帰を呼びこみ、その死を生きて、みえない共同体を召還し、そうやって毎たび演劇を廃絶している、それが舞台の一回性ということ、その呼びこむ存在本体が「演劇人」だということになろう。かくて、わたしは舞台なる「虚構を演ずる」の約束を演ずる態の「役」者に疑いを抱きはじめた。それでは、公共性も公共の演劇も発見・形成できないのだ。
2. 現在の全体主義の「空気」と市民
現在の日本社会は閉塞感に満ちているというのが今やメディアの常套句。それはそのとおりでも、その「空気」を醸成しているのもまたメディアだ。消費文化の言説の顕著な特性はのべつ一過性のトートロジーを叫ぶことである。ほんの一例で清潔という標語、強迫観念のようなもの。豚インフル以来、いたるところに消毒液が設置された(この三軒茶屋にもある)。そんなに東京は不潔だろうか。検挙率99%に映る日本がそんなに危険というわけはなかろうに、これほどあらゆる場所に安全という標語が、プラス、けたたましい放送や貼り紙が蔓延している時代はない。「落書きのないトイレを目指します」の一方で、商品である表現は街頭のスクリーンを頭に、したい放題の落書きそのものだ。無制限な夜郎自大とはなはだしい不自由との二重規範。これが時代の徴だ。賢い者はタテマエで済ませるだろうが、発語を仕掛けとはしない、表現を個々信ずる不器用な者にとっては結構難事、いたるところ指図だらけ、「人」はまるで幼稚園児か戦時捕虜のように扱われている。園児にされて大人しい市民は普通いない。犯罪=法を犯す者のいる可能態は常時ある、それに対し終始油断怠りなく、自己を防衛しつつ暮らすというのがまずもって近代市民の条件だろう。憲法と思考枠は同断、ここでも他律本願の機制支配が際立つ。
戦時捕虜の最たるものが電車内だ。一々遅延を詫びる放送音そのものが迷惑で、暴力でないとでも? 理解・協力をいうなら、そうしない選択肢のあるのが約定だろうに、それは「不審者」という構図になった。無前提、暗黙の強制装置。これも頻繁、舞台をただの約束とする表現と実によく似ている。創造が他者に観られるものだという回路が欠けているのだ。演劇は繁栄しているようだけど、実際はその幅でしかない。車中と劇場は異なるはずだが、その劇場ですら、うしろの人の迷惑になりますので、身を乗り出さないで下さいのアナウンスを聞かされる。それで、そんな劇場で雨の6・15の夜に、「50年前のオレたちは」とシュプレヒコールまがいを喚かれても冗談をすら構成しない。舞台は劇場が在る現実の範囲にしかないのだ、今も昔も。ついでに言及する、広場や公園とはどういうものか、真ん中に杭が立てられるものだ。しかるに、野宿者が増える、自転車が入るからと今や柵で囲われた。あまつさえ、その柵内にテントが立ち、幸徳秋水と菅野スガの芝居がやられていたりする。噴飯も大概にしろ、だ。かくして、わたしには現在の(公共)演劇がこの安っぽいが危険な現実に立ち向かう創造力や意志があるとは相当いいにくいのである。この現実を腹でみよ。ルンペン・プロレタリアは半革命にまわると言ったのはマルクスか、さてどうだろう、ブレヒトのいう小市民こそが右へならえとなるのではないのか、ナチはクー=デタで権力を掌握したわけではない、投票で支持され、そこから十三階段への路を辿ったのだ。皆が二重原理を演じている国に市民なんていようがあるのかという疑問は再度出されていい。
戦時捕虜の最たるものが電車内だ。一々遅延を詫びる放送音そのものが迷惑で、暴力でないとでも? 理解・協力をいうなら、そうしない選択肢のあるのが約定だろうに、それは「不審者」という構図になった。無前提、暗黙の強制装置。これも頻繁、舞台をただの約束とする表現と実によく似ている。創造が他者に観られるものだという回路が欠けているのだ。演劇は繁栄しているようだけど、実際はその幅でしかない。車中と劇場は異なるはずだが、その劇場ですら、うしろの人の迷惑になりますので、身を乗り出さないで下さいのアナウンスを聞かされる。それで、そんな劇場で雨の6・15の夜に、「50年前のオレたちは」とシュプレヒコールまがいを喚かれても冗談をすら構成しない。舞台は劇場が在る現実の範囲にしかないのだ、今も昔も。ついでに言及する、広場や公園とはどういうものか、真ん中に杭が立てられるものだ。しかるに、野宿者が増える、自転車が入るからと今や柵で囲われた。あまつさえ、その柵内にテントが立ち、幸徳秋水と菅野スガの芝居がやられていたりする。噴飯も大概にしろ、だ。かくして、わたしには現在の(公共)演劇がこの安っぽいが危険な現実に立ち向かう創造力や意志があるとは相当いいにくいのである。この現実を腹でみよ。ルンペン・プロレタリアは半革命にまわると言ったのはマルクスか、さてどうだろう、ブレヒトのいう小市民こそが右へならえとなるのではないのか、ナチはクー=デタで権力を掌握したわけではない、投票で支持され、そこから十三階段への路を辿ったのだ。皆が二重原理を演じている国に市民なんていようがあるのかという疑問は再度出されていい。
3. 劇場の自由
発語である言葉と身体はしばしば含意を発する。演じている当人が気づかなくても、観客の想像力がそれを観ることはよくあることだ。できるなら、演出家も俳優もその想像力の力を内化して表現して欲しい、それが観客席にはあることを。そのくらいとりあえずの現実=客席を自由にして貰いたい。舞台が自由なだけでは不可。それは現実の自由に応じてのみ存続可能なのである。最近「小言」を極論する傾きが強くなって、われながら感心しないと反省はするが、それでも、最低限のことは口にしなくてはならない。かつてサルトルは「飢えた子供の前では文学は無力だ」と言った。名言だが、が、わたしはこういう二項対立は択らない。想像力≠創造はそれ自体で力だと思考する、真向かいにある現実を無視していない限りにおいて。その意味で、わたしとて想像力の徒だという立場で続けるけども、例えば舞台に銃があるということはどういうことか。あってはならないという符牒的合言葉で現実のどっかには必ずある、ありうるものに眼を塞ぐのであれば、そんなものが舞台に出たとしてなんの価値があるか、けちな小道具にすぎず、世界への想像力を痩せ衰えさせるだけだろう。現実世界にその実在への想像力が奪われて、舞台にだけ出せるというのは逆立ちではないのか。火のついた煙草が最大の象徴的物質、それは舞台だろうと巷と同様に実在する。舞台は現実という根拠のうえで成り立つのだ。劇場とその周辺を全禁煙にして、舞台では煙草が吸えるというのは実に面妖。俳優の身体だって同じことだ、芸術はどんなに些末な日常的を扱おうと、天下国家を相手にしている。その限りで、テレビとは違う、テレビはメディアが拵えたイベント性、デキゴトロジーが事件を隠蔽してしまう仕掛けだ。身体の在る舞台は、それ自体が出来事のはずなのだ。そのことが忘れられかけているという気がしきりとする。
演劇にはギリシア型とローマ型があることはすでに述べた。ギリシアでは劇場が共同体の政治教育や歴史記憶喚起の場所だった。対極で、ローマ期に新たに発達したのは闘技場(サーカスの前身でもある)やキャバレエといった見世物である。見世物が演劇でもあった。演劇には知的次元とともに欲望という次元もある以上(サドはとまれ、ダントンを想起するとよい)、ギリシア型だけが模範というわけではない。たしかに大革命期には、民衆の教化としての演劇という理念が先立っており、市民が相互教育することが革命劇場の目的であった。劇場のモデルの一つはそれだ。それは総裁政府時代のキャバレエやポルノとは異なる。民衆演劇は一般意志の強化という磁場から着想し、命題を立てたのである。ところで、キャバレエや19世紀に伸張をみるミュージック=ホール的なものはそんなに無下にでき、侮れるものなのか。演劇の機能は教育だけか。見世物が演劇だという項もありはしないか。この問いはすべて劇場の(想像力の)の自由に関わる。舞台の自由はときに現実逃避のアリバイになりうる。表現派であれ、メイエルホリドであれ、20世紀「前衛」が抱えていた両義性はそこにある。だとすれば、見世物という演劇の現実にもふれなくてはならない。
それで話を飛躍させるが、例えばエロスという問題域は演劇とも祭りとも違う第三の領域だとわたしには思える。商業主義でないエロスは資本主義社会において可能だろうか。その問いを抱えつつ、その領域を舞台が商売から奪還してもいいのではないか。商売人の作る性消費機構とも素人の自堕落とも異なる表現域。映像に勝てないというのであれば、革命劇だって映像に勝てないだろう。なるほど、演劇には字義どおり性をさらすという表現はない、紛れもなくその種の実演は別のジャンルである。そうだとはいえ、身体性という観点からいえば、「ポルノ」も舞台も本来同じ地平にあるのだ、喩的にも劇的想像力の枠組からみても。その眼=姿勢を演劇は帯同しておらなくてはならない。というのも、同ジャンルの実演や映像において、身体たちは、フロイト的というか、いや、むしろバタイユ的にいうなら、刻一刻「小さな死」(プティット・モール)を演じているのであり、その肉体は、なぜわざわざそんなことをするんだろうという愚問をわれわれに招くにしても(演劇に比べ、エロスの実際を演ずることははるかに苦役である)、観る者に死の快楽を呼びこみ、時間を停めるからであるし、そこにおいて、演劇と祭りのちょうど中間孔を成すからだ。演劇の身体はそういうもののあることを、虚構を抜ける“劇”があることも等閑視しないほうがよくはなかろうか。今度はサルトルではない、アルトーのいう「飢え」と同じだけの力で世界本質が本当に抉れないならば、演劇など糞にも立ならないという話だし、飢えが万一今やわれわれの場所では遠くても、エロスは依然現存に近いのだから。
演劇にはギリシア型とローマ型があることはすでに述べた。ギリシアでは劇場が共同体の政治教育や歴史記憶喚起の場所だった。対極で、ローマ期に新たに発達したのは闘技場(サーカスの前身でもある)やキャバレエといった見世物である。見世物が演劇でもあった。演劇には知的次元とともに欲望という次元もある以上(サドはとまれ、ダントンを想起するとよい)、ギリシア型だけが模範というわけではない。たしかに大革命期には、民衆の教化としての演劇という理念が先立っており、市民が相互教育することが革命劇場の目的であった。劇場のモデルの一つはそれだ。それは総裁政府時代のキャバレエやポルノとは異なる。民衆演劇は一般意志の強化という磁場から着想し、命題を立てたのである。ところで、キャバレエや19世紀に伸張をみるミュージック=ホール的なものはそんなに無下にでき、侮れるものなのか。演劇の機能は教育だけか。見世物が演劇だという項もありはしないか。この問いはすべて劇場の(想像力の)の自由に関わる。舞台の自由はときに現実逃避のアリバイになりうる。表現派であれ、メイエルホリドであれ、20世紀「前衛」が抱えていた両義性はそこにある。だとすれば、見世物という演劇の現実にもふれなくてはならない。
それで話を飛躍させるが、例えばエロスという問題域は演劇とも祭りとも違う第三の領域だとわたしには思える。商業主義でないエロスは資本主義社会において可能だろうか。その問いを抱えつつ、その領域を舞台が商売から奪還してもいいのではないか。商売人の作る性消費機構とも素人の自堕落とも異なる表現域。映像に勝てないというのであれば、革命劇だって映像に勝てないだろう。なるほど、演劇には字義どおり性をさらすという表現はない、紛れもなくその種の実演は別のジャンルである。そうだとはいえ、身体性という観点からいえば、「ポルノ」も舞台も本来同じ地平にあるのだ、喩的にも劇的想像力の枠組からみても。その眼=姿勢を演劇は帯同しておらなくてはならない。というのも、同ジャンルの実演や映像において、身体たちは、フロイト的というか、いや、むしろバタイユ的にいうなら、刻一刻「小さな死」(プティット・モール)を演じているのであり、その肉体は、なぜわざわざそんなことをするんだろうという愚問をわれわれに招くにしても(演劇に比べ、エロスの実際を演ずることははるかに苦役である)、観る者に死の快楽を呼びこみ、時間を停めるからであるし、そこにおいて、演劇と祭りのちょうど中間孔を成すからだ。演劇の身体はそういうもののあることを、虚構を抜ける“劇”があることも等閑視しないほうがよくはなかろうか。今度はサルトルではない、アルトーのいう「飢え」と同じだけの力で世界本質が本当に抉れないならば、演劇など糞にも立ならないという話だし、飢えが万一今やわれわれの場所では遠くても、エロスは依然現存に近いのだから。
4. citoyenと民衆演劇
citéは、もともと都市シテ周辺部の人口密集地帯を指したville都とも商業の自由に由来するbourg町とも異なる肌合いをもっている。それはギリシア以来、人間が互いに対等でありえる(ただし、女と奴隷は除かれていたわけで、それはそれで大問題ではある。もっとも、2009年度に語ったように、その問題点をただ逆転させて、自称「排除された者」で劇場を満杯にすれば、それでことが片づくわけではない。現在に日本という「共感共同体」は眼にみえる“被害者”には著しく同化し、それを“不幸”としてもち上げるが、それ以外は何もみない、“肝心の他者”はみないという構造をもっている。ややにべもなくいえば、それこそが“不幸”の「消費」=善意というおためごかしだろう。可視的に“被害者”とならなければ、この現実において「不幸/不運」である者にはなれないとでもいうのだろうか。その問いを不問に付すのがデキゴトロジーなる名のイデオロギーである)共同体を意味する。フランスでは、人々がムシュー、マダムではなく、シトワイヤン、シトワィエンヌと呼びあったときがあった、大革命期。ムシュー、マダムは当時特権階級の言葉であったからだ。民主主義はcitoyenがいることをまずは前提しているわけだ。(ミシュレの『革命史』はサドが牢獄を出てきた際、ふたたびムシュー、マダムが復活した印象的な光景で終わっている)。シトワイヤンとはシテを内包する人々のことである。便宜に応じて大衆であり、庶民であり、場合によっては中産階級、「小市民」とされ、使い分けられてしまうわれわれは、ルンペンでないことはたしかだとしても、まことにシトワイヤンだろうか。ミシュレ流にいえば、シトワイヤンとpeuple が重なってはじめて理念的な近代共同体・都市は成立するのである。
ミシュレから半世紀後の1895年、アルザスの山中に民衆劇場が生まれた。ストラスブール郊外の田舎ビュッサンBussangという、ビュヒナーの『狂っていくレンツ』を彷彿とさせるドイツ国境と踵を接する村である。ロマン・ロランの友人で(大杉栄が訳した『民衆劇論』の著者)、クローデルと書簡を交わしてもいるモーリス・ポッシェール(現地読み)Maurice Pottecherが構想し、財政を負担して(彼の家は名家で、鉄道でビュッサンに着くと、駅前にどこの小都市とも同じ「一次大戦の死者の墓碑銘」があり、ポッシェール名が沢山並ぶ)、一年に一回、夏に村人が集まり、村人自身が演ずる劇場だ。ビュッサン民衆劇場Théâtre du peupleの誕生。冬にはスキー場になる山の中腹にあって、現在は若干プロ化し、観光化したとはいえ(ホテルは二つ程度しかない)、なお続いている。市民と民衆は一致できるかという問いにポッシェールは一つのやり方を示した。ありものの戯曲を極力避け、自分の書いたものを村人が演ずるという村民演劇。前述したごとく、演劇と祭りの対立は超えられるかというところに民衆演劇の命題はあった。それによって「連盟兵」が生み出せるかという意味でもあるが、それでいうと、これが好個の実例であるかどうかは申すまでもなく微妙である。
もちろん、村民演劇だけがこの時代の民衆演劇だったわけではない、労働者の擡頭に伴って労働者大学やそうした系列の演劇の試みは種々あった。そして、どれもが啓蒙主義的だったという点は共通している。他方、第二帝政期に産業革命を刻印してパリが変化すると、かつての軽業師や綱渡り芸人が縁日foireから移動してきた見世物小屋の地区、「犯罪大通り」は潰され、都市の景観を一新したオスマンの改造によってグラン・ブールヴァール沿いに建物としての劇場が造られ、そこに収容できる演劇形式のみが──メロドラム、オペレッタ等──生き延びられることになった、いわゆるブールヴァール演劇。もっとも、キャバレエその他、怪しげなものは消え去ってしまったわけではない、別種の、ときに時代の「前衛」が集うアングラ文化を構成しゆくのだ(とくにモンマルトル界隈)。舞踊場、ミュージック=ホール、シャンソン小屋等。ここでブルジョワ演劇とそうでないもの、相違自体はロマン派にあったものだが、通りや容器での区分が可能になる。どちらもが都市パリの名物とされていく。ポッシェールが啓蒙主義だという話を一言。彼は労働者が僅かな給金を酒や見世物で徒費することを嘆いて、例えばアル中反対の教育として演劇に私費を投入したのだった。パリなら、労働者階級を堕落させる悪、居酒屋に入り浸る「スブリーム」の悪、仮想敵は舞踊場やキャバレエだろう。この時代の労働者の飲酒が凄かったのは事実だし(ドニ・プロ『崇高なる者』岩波文庫)、なるほどオペレッタや軽喜劇、なかんずくカンカンはドラマに比すると低級だ。さりとて劇場は清教徒の巣ではない、祭りもエロスも含む。でないと、ミュージック=ホールと演劇が区分けされ、コポー型の純粋演劇しか残らぬ結果に陥るだろう。それはそれでいいが、思うに、少しもの足りない、それに、この巷の喧騒のなかに純粋は置きえまい。「悪」も綜合して劇場を定立することはできないか。それがアングラ出のわたしの思考だ。ギリシアからシトワイヤンははじまったが、同時にそれは広義の芸能、キャバレエ的はと限らぬエロス=「刻一刻の死」をもとめる民衆だし、その想像力の養分や回路や射程を劇=場にとり戻すことは決してわるくないだろう。そしてまた、民衆とは他の誰でもなく、自分でなければならない。なぜなら、演劇人はお芝居の死と廃絶=「現実」に今いるという究極的な命題をもつからだ。
ミシュレから半世紀後の1895年、アルザスの山中に民衆劇場が生まれた。ストラスブール郊外の田舎ビュッサンBussangという、ビュヒナーの『狂っていくレンツ』を彷彿とさせるドイツ国境と踵を接する村である。ロマン・ロランの友人で(大杉栄が訳した『民衆劇論』の著者)、クローデルと書簡を交わしてもいるモーリス・ポッシェール(現地読み)Maurice Pottecherが構想し、財政を負担して(彼の家は名家で、鉄道でビュッサンに着くと、駅前にどこの小都市とも同じ「一次大戦の死者の墓碑銘」があり、ポッシェール名が沢山並ぶ)、一年に一回、夏に村人が集まり、村人自身が演ずる劇場だ。ビュッサン民衆劇場Théâtre du peupleの誕生。冬にはスキー場になる山の中腹にあって、現在は若干プロ化し、観光化したとはいえ(ホテルは二つ程度しかない)、なお続いている。市民と民衆は一致できるかという問いにポッシェールは一つのやり方を示した。ありものの戯曲を極力避け、自分の書いたものを村人が演ずるという村民演劇。前述したごとく、演劇と祭りの対立は超えられるかというところに民衆演劇の命題はあった。それによって「連盟兵」が生み出せるかという意味でもあるが、それでいうと、これが好個の実例であるかどうかは申すまでもなく微妙である。
もちろん、村民演劇だけがこの時代の民衆演劇だったわけではない、労働者の擡頭に伴って労働者大学やそうした系列の演劇の試みは種々あった。そして、どれもが啓蒙主義的だったという点は共通している。他方、第二帝政期に産業革命を刻印してパリが変化すると、かつての軽業師や綱渡り芸人が縁日foireから移動してきた見世物小屋の地区、「犯罪大通り」は潰され、都市の景観を一新したオスマンの改造によってグラン・ブールヴァール沿いに建物としての劇場が造られ、そこに収容できる演劇形式のみが──メロドラム、オペレッタ等──生き延びられることになった、いわゆるブールヴァール演劇。もっとも、キャバレエその他、怪しげなものは消え去ってしまったわけではない、別種の、ときに時代の「前衛」が集うアングラ文化を構成しゆくのだ(とくにモンマルトル界隈)。舞踊場、ミュージック=ホール、シャンソン小屋等。ここでブルジョワ演劇とそうでないもの、相違自体はロマン派にあったものだが、通りや容器での区分が可能になる。どちらもが都市パリの名物とされていく。ポッシェールが啓蒙主義だという話を一言。彼は労働者が僅かな給金を酒や見世物で徒費することを嘆いて、例えばアル中反対の教育として演劇に私費を投入したのだった。パリなら、労働者階級を堕落させる悪、居酒屋に入り浸る「スブリーム」の悪、仮想敵は舞踊場やキャバレエだろう。この時代の労働者の飲酒が凄かったのは事実だし(ドニ・プロ『崇高なる者』岩波文庫)、なるほどオペレッタや軽喜劇、なかんずくカンカンはドラマに比すると低級だ。さりとて劇場は清教徒の巣ではない、祭りもエロスも含む。でないと、ミュージック=ホールと演劇が区分けされ、コポー型の純粋演劇しか残らぬ結果に陥るだろう。それはそれでいいが、思うに、少しもの足りない、それに、この巷の喧騒のなかに純粋は置きえまい。「悪」も綜合して劇場を定立することはできないか。それがアングラ出のわたしの思考だ。ギリシアからシトワイヤンははじまったが、同時にそれは広義の芸能、キャバレエ的はと限らぬエロス=「刻一刻の死」をもとめる民衆だし、その想像力の養分や回路や射程を劇=場にとり戻すことは決してわるくないだろう。そしてまた、民衆とは他の誰でもなく、自分でなければならない。なぜなら、演劇人はお芝居の死と廃絶=「現実」に今いるという究極的な命題をもつからだ。

「『公共劇場』運動と文化政策」
5. 演劇における三つの層
オスマンのパリ改造計画が1862年にひとまず完了し、グラン・ブールヴァールにブルジョワの劇場が建ち並ぶことになった。官製のテアトル・フランセ、そのあとの時期に_落しをみるガルニエのオペラ座を入れ、概ね裕福な階級の知的社交場としてあったプロフェショナルの劇場である。それらに対抗して、アンドレ・アントワーヌがゾラらの自然主義文学運動の連携として1886年に旗揚げしたのが自由劇場Théâtre libreである。自由劇場はブールヴァールへの抵抗軸として、三つの線を出した。小屋は小劇場であること、アマチュアが演ずること、観客は会員組織で集められることであり、それに足して、これが20世紀の基調となるものだが、舞台を統括する者としての演出家という職分の明確化があった。路線はやや遅れてはじまる反自然主義の象徴派系統でも受けつがれ、そこにいわば「20世紀前衛」の萌芽をみることができる。民衆演劇運動も大略80年代から90年代に掛けての擡頭だし、メルクマールだったのは前回語ったビュッサン民衆劇場だったということはもうよかろう。問題はこの三区分だ。
フランスの演劇には三つの層があるという仮説、その相違と共通性から考えてみたい。19世紀のとりわけパリでまずもって隆盛をみたのは大枠のところブルジョワが自己の似姿を観て喜ぶブールヴァール演劇、今なら、商業演劇と呼べる、ただし、かなり小資本の劇場である。ヴォードヴィルのような軽ジャンルを含めて、この系列はブルジョワ家庭内のもめごと、主には姦通や三角関係を主題にしたものだった。結婚と金銭と色恋をめぐる、大体はそう深刻でない劇。深刻に世界が広がるのは写実主義や自然主義、象徴派にいたる世紀末の「前衛」からで、アントワーヌの運動から1897年モスクワ芸術座創立までの系列がその「前衛」揺籃期ということになろうか。そして、どちらにも属さない、強いていえば、アントワーヌに啓発された(ジェミエは彼の弟子だ)民衆演劇の流れがあった。あとの二つは、基本的には知識人の運動である。例えばポッシェールはクローデルを知っていたけれども、そういうものよりは、アル中撲滅といった主題で教育を実践したわけだし。ロマン・ロランの革命劇も同様にミシュレ的な祭りの甦りというより革命思想の分節化、啓蒙である。とはいえ、村民演劇という形態をとったことは失念すべきでない。演劇のパリ一極集中の反措定たる民衆演劇は同時期の階級分化とともに、プロレタリア演劇や労働者演劇の土壌を用意するが、しかし、フランスではドイツやロシアにあった大規模なアジ=プロ劇は出てこなかった(ルイーズ・ミシェルが劇を書くとか、詩人ジャック・プレヴェールらの「十月グループ」の動きが例外的には存在する)。よかれあしかれ、民衆演劇の理念がずっと存続した。その逆説が「共和国」を後景にした革命の国フランスの特徴だといえそうである。
現代日本にはこのような演劇のおける三層はない。そもそも、階級を背負うような劇場は成立しなかったし、成立しようがなかったのだともいえる。「前衛」は新劇の誕生時に意識されたにしても(島村抱月の「二元の道」や小山内薫の翻訳劇路線)、築地小劇場はすぐに当時のロシアやドイツを倣う急進化をして、党綱領や指令とときに共犯、ときに格闘しながら実践的に役に立つ(演劇においても、この国の近代化においても)演劇をつくり出そうとしたし、そうでない者は芸術的な演劇の路線をさまざまに解釈して、集まっては離散し、そして、その複数の急進主義が「大同団結」したときは大政翼賛会とともに転向演劇、移動演劇に雪崩を打ったときであり、戦後も新劇は転向以前に戻って切断なく続いた。その批判として起こったアングラに民衆演劇という思想の芽はあったにせよ、当然ながら、それは党にも階級にも依拠しない自前の演劇人の運動だった。ここはいかんともし難く客観主義的にならざるをえない、したがって、日本にはドイツ的なプロレタリア演劇もフランス的な民衆演劇も続かず、痕跡を留めず、厳密にはごく稀有な場合にのみ顕在化したとしかいいようはない(どちらも背負おうとした演出家や運動者がいなかったわけではむろんないが、その過半は今や忘却されている。ここでは記憶は一向に根づかない)。そこに「公共劇場」なる今一つ新しい(と映る)ものが出現、十年を経たわけだ。
フランスの演劇には三つの層があるという仮説、その相違と共通性から考えてみたい。19世紀のとりわけパリでまずもって隆盛をみたのは大枠のところブルジョワが自己の似姿を観て喜ぶブールヴァール演劇、今なら、商業演劇と呼べる、ただし、かなり小資本の劇場である。ヴォードヴィルのような軽ジャンルを含めて、この系列はブルジョワ家庭内のもめごと、主には姦通や三角関係を主題にしたものだった。結婚と金銭と色恋をめぐる、大体はそう深刻でない劇。深刻に世界が広がるのは写実主義や自然主義、象徴派にいたる世紀末の「前衛」からで、アントワーヌの運動から1897年モスクワ芸術座創立までの系列がその「前衛」揺籃期ということになろうか。そして、どちらにも属さない、強いていえば、アントワーヌに啓発された(ジェミエは彼の弟子だ)民衆演劇の流れがあった。あとの二つは、基本的には知識人の運動である。例えばポッシェールはクローデルを知っていたけれども、そういうものよりは、アル中撲滅といった主題で教育を実践したわけだし。ロマン・ロランの革命劇も同様にミシュレ的な祭りの甦りというより革命思想の分節化、啓蒙である。とはいえ、村民演劇という形態をとったことは失念すべきでない。演劇のパリ一極集中の反措定たる民衆演劇は同時期の階級分化とともに、プロレタリア演劇や労働者演劇の土壌を用意するが、しかし、フランスではドイツやロシアにあった大規模なアジ=プロ劇は出てこなかった(ルイーズ・ミシェルが劇を書くとか、詩人ジャック・プレヴェールらの「十月グループ」の動きが例外的には存在する)。よかれあしかれ、民衆演劇の理念がずっと存続した。その逆説が「共和国」を後景にした革命の国フランスの特徴だといえそうである。
現代日本にはこのような演劇のおける三層はない。そもそも、階級を背負うような劇場は成立しなかったし、成立しようがなかったのだともいえる。「前衛」は新劇の誕生時に意識されたにしても(島村抱月の「二元の道」や小山内薫の翻訳劇路線)、築地小劇場はすぐに当時のロシアやドイツを倣う急進化をして、党綱領や指令とときに共犯、ときに格闘しながら実践的に役に立つ(演劇においても、この国の近代化においても)演劇をつくり出そうとしたし、そうでない者は芸術的な演劇の路線をさまざまに解釈して、集まっては離散し、そして、その複数の急進主義が「大同団結」したときは大政翼賛会とともに転向演劇、移動演劇に雪崩を打ったときであり、戦後も新劇は転向以前に戻って切断なく続いた。その批判として起こったアングラに民衆演劇という思想の芽はあったにせよ、当然ながら、それは党にも階級にも依拠しない自前の演劇人の運動だった。ここはいかんともし難く客観主義的にならざるをえない、したがって、日本にはドイツ的なプロレタリア演劇もフランス的な民衆演劇も続かず、痕跡を留めず、厳密にはごく稀有な場合にのみ顕在化したとしかいいようはない(どちらも背負おうとした演出家や運動者がいなかったわけではむろんないが、その過半は今や忘却されている。ここでは記憶は一向に根づかない)。そこに「公共劇場」なる今一つ新しい(と映る)ものが出現、十年を経たわけだ。
6. 国民的共有財産としての演劇
フランスの民衆演劇運動にはビュッサンとともに、もう一つの系譜があることは見逃せない。むしろそっちが主流である。1920年、パリにThéâtre national populaire国立民衆劇場がつくられた。当初これはミシュレの提起に近いものだったし、初等「教育」の無償化と同じように、演劇もまた「市民」社会がもつ知の制度、「民衆」の権利であると考えられた思考の産物であった。民衆劇場が国立であるのは日本では考えにくい位相だろうが、革命後1世紀余経って、やっと共和国国家が演劇文化を全認知したということであり、演劇を国民国家の共有財産として、それに政府が財源を投ずるということである。T.N.P.は国立民衆劇場というより、国民民衆劇場と訳したほうがよいのかもしれない。国民全員が共有すべき財産とは、国民国家の「教育」(国民国家では教育は権利ではなく、義務であることはそれ自体問題であるが、その点はここでは立ち入らない)と並ぶもう一本の柱たる「演劇の知」である。教育と演劇の並列に大革命の記憶の痕跡があるということになる。
日本には、そうした国民的共有財産、「一般」が分ちあえるようなものは、教育を介してさえ、絵画や音楽はともかく(音楽は伊沢修二主導の西洋音楽、美術は西洋絵と日本の伝統とに分かれたうえ、やがて竹下夢二から蕗谷虹児にいたる少女マンガの走りまで出てくることは知られる通り。例えば阿刀田高『夢の宴 私の蕗谷虹児伝』)、演劇にはなかったし、国民国家そのものが上から拵えられたことは兵藤裕巳の『〈声〉の国民国家』などを読めば明瞭である。政治が市民社会を上から構築した日本では、国民的財産としての「知」などというものが成り立つべくもなく、成り立ったとしても、そこには、鶴見俊輔・久野収の語を使えば、「顕教」と「密教」があった。見世物なら顕教的に近づけるが、思想を秘めた芸術=演劇は元来が密教のレヴェルにある。それゆえに、国家に対して自覚的に対峙する知識人は多く少数の特権階級だったし、彼らに演劇を作ることはできたが、客席を同質の自覚で埋めるというところまで簡単に進められるはずもなかった。徹底したスノッブは育たなかったし、大衆には大衆文化があり、演劇には所定の教育機関もなかった。一高・東大出身者と士官学校出の将校は密教を_みえたろうが、兵は与り知らず、労働者は労働者演劇を希求したにしろ、胎動に留まった。共有される「知」そのものの位相に見合う階級が鋭く区分されたようでいて、未分化のままできた(顕教といい密教といい、政治思想には適応可能だが、文化を支える階級としては茫漠なままなのだ。その角度からみると、演劇人にとって、ことは相当厄介である)。昭和10年代前後の演劇人たちの転向はいわば必然だった。文化としての階級がないまま総中産階級、「小市民」にされるのだ、戦後に、高度成長期に、バブル期に。
日本には、そうした国民的共有財産、「一般」が分ちあえるようなものは、教育を介してさえ、絵画や音楽はともかく(音楽は伊沢修二主導の西洋音楽、美術は西洋絵と日本の伝統とに分かれたうえ、やがて竹下夢二から蕗谷虹児にいたる少女マンガの走りまで出てくることは知られる通り。例えば阿刀田高『夢の宴 私の蕗谷虹児伝』)、演劇にはなかったし、国民国家そのものが上から拵えられたことは兵藤裕巳の『〈声〉の国民国家』などを読めば明瞭である。政治が市民社会を上から構築した日本では、国民的財産としての「知」などというものが成り立つべくもなく、成り立ったとしても、そこには、鶴見俊輔・久野収の語を使えば、「顕教」と「密教」があった。見世物なら顕教的に近づけるが、思想を秘めた芸術=演劇は元来が密教のレヴェルにある。それゆえに、国家に対して自覚的に対峙する知識人は多く少数の特権階級だったし、彼らに演劇を作ることはできたが、客席を同質の自覚で埋めるというところまで簡単に進められるはずもなかった。徹底したスノッブは育たなかったし、大衆には大衆文化があり、演劇には所定の教育機関もなかった。一高・東大出身者と士官学校出の将校は密教を_みえたろうが、兵は与り知らず、労働者は労働者演劇を希求したにしろ、胎動に留まった。共有される「知」そのものの位相に見合う階級が鋭く区分されたようでいて、未分化のままできた(顕教といい密教といい、政治思想には適応可能だが、文化を支える階級としては茫漠なままなのだ。その角度からみると、演劇人にとって、ことは相当厄介である)。昭和10年代前後の演劇人たちの転向はいわば必然だった。文化としての階級がないまま総中産階級、「小市民」にされるのだ、戦後に、高度成長期に、バブル期に。
7. 共和国の幻想
第二次大戦後、文化省の辣腕官僚だったジャンヌ・ローランJeanne Laurentは(「文化省のツァーリ」と異名をとった彼女があるべき端緒を開いたのだ)、カルテル四人組の一人シャルル・デュランの高弟だった俳優・演出家のジャン・ヴィラールにアヴィニョン演劇祭の開催と、ジェミエののちほぼ空位だった国立民衆劇場再生の提案をする。それがそれ以前さまざまに企てられてきた演劇の地方分散化とパリのなかでの非/反「ブールヴァール」系譜の徴たる公共演劇の実質的スタートとなった。1947年アヴィニョンが開始され、今ここは毎夏10万人以上の観光客が訪れ、秋のミラノにファッション・デザイナーが集まるように、世界中の演劇バイヤーが集結する一大拠点になっているのはご存じだろう。フェスティヴァル主義にわたしは断然反対だけれども、これは厭味ではない、バイヤーもまたスノッブの変種なのだ。他方、国立民衆劇場は民衆の名を冠しながら、民衆がこないというジレンマを抱える。というか、ヴィラールが悩んでいたのは労働者観客が少ないことだった。アヴィニョンにしてもそう、客層を占める最大の階層は教員である。わたし自身は別にそれでいいと思うが、悩むだけ立派というもの。ヴィラールはやがてブレヒトをとり入れて、フランス・ブレヒチアンの一人となるけれど、いってみれば、労働者が労働者演劇をつくるような形態では、国立民衆劇場は展開していかず、その路線は結局東ドイツのような場処が引き受ける格好になったというと型通りにすぎようか。
こうしたパリ内とパリの外での「演劇の地方分散化」はヴィラールが専売特許にしたわけではもちろんのことない。リヨン郊外のヴィルールバーヌで活動を始め、生涯そこを離れなかったロジェ・プランションもブレヒトを方法化することを率先し、それを基盤に70年代以降の演出家の時代を特質づける古典の再解読という方向の先鞭者となる。「前衛」と地方住民との結びつきという点ではこっちのほうがむしろ重要かもしれない。このような地方分散化と連動する民衆演劇構想と競合、相前後して、ド・ゴール政権下で文化大臣をつとめたマルローによる文化政策がある。マルローは宗教をもたない者たちが同じ文化を集団として経験するための空間を具現化しようとした。文化を通して国民が共和国の「幻想」を(場合によっては、イデオロギーを)共有するという計画に手を染めるのである。この国からのアイディアと下からの運動に相まって、各地に「文化の家」や「演劇センター」が発足しはじめ、そうした機構に一定の公的予算が下りる案配になって、演劇人が行政上の責任者として任命されていく。彼らは演劇人でありつつ、半ば公務員であって、レパ、プラン、予算処置、実際の結果などを文書で提出することをもとめられる。太陽劇団のように、行政とはまったく離れた場所にあって、それでも厖大な助成金を受け、稽古に長い時間を掛けて革命劇を演じたりする団体はフランスでもたぶん例外だろう。さまざまな困難はむろんあるらしい、が、それぞれが制度の場所にありながら、自己の演劇を出すという地平に、ブールヴァールでない限り、一応は立っているのだと概論していいのではないかと思う。
マルローにとって劇場は国家がつくる無宗教の教会、共和国の文化財産であったし、ヴィラールやプランションは下から共和国を当座の前提にしたうえで批判的演劇を現出せしめようとした。それらを木っ端微塵にするのが68年5月。共和国なる幻想はすでに失効、消費社会があるだけではないかとこの幻想を否定したのである。プランションは対応しえたし、5月を引きうけたが(72年に国立民衆劇場はリヨン郊外に移転し、プランションとパトリス・シェローが主宰者になった。シェローは80年代にパリ郊外のナンテールに赴任する)、ヴィラールのほうは崩れた。共和国幻想の瓦解、共和国の夢とは、市民社会と共同体が一致するという図にほかならない。近代市民だろうと、共同体だろうと、集合とみなされ、商品の単位、消費者に還元されてしまう「人」の生きざまの前ではただの夢想にすぎないというところにぶち当たったのだ。共和国であれ、ないであれ、集合が発語することはない。われわれはひとりひとり異なる、そういう主張に対して、一体何をもって、自分が民衆といいうるだろうか。
こうしたパリ内とパリの外での「演劇の地方分散化」はヴィラールが専売特許にしたわけではもちろんのことない。リヨン郊外のヴィルールバーヌで活動を始め、生涯そこを離れなかったロジェ・プランションもブレヒトを方法化することを率先し、それを基盤に70年代以降の演出家の時代を特質づける古典の再解読という方向の先鞭者となる。「前衛」と地方住民との結びつきという点ではこっちのほうがむしろ重要かもしれない。このような地方分散化と連動する民衆演劇構想と競合、相前後して、ド・ゴール政権下で文化大臣をつとめたマルローによる文化政策がある。マルローは宗教をもたない者たちが同じ文化を集団として経験するための空間を具現化しようとした。文化を通して国民が共和国の「幻想」を(場合によっては、イデオロギーを)共有するという計画に手を染めるのである。この国からのアイディアと下からの運動に相まって、各地に「文化の家」や「演劇センター」が発足しはじめ、そうした機構に一定の公的予算が下りる案配になって、演劇人が行政上の責任者として任命されていく。彼らは演劇人でありつつ、半ば公務員であって、レパ、プラン、予算処置、実際の結果などを文書で提出することをもとめられる。太陽劇団のように、行政とはまったく離れた場所にあって、それでも厖大な助成金を受け、稽古に長い時間を掛けて革命劇を演じたりする団体はフランスでもたぶん例外だろう。さまざまな困難はむろんあるらしい、が、それぞれが制度の場所にありながら、自己の演劇を出すという地平に、ブールヴァールでない限り、一応は立っているのだと概論していいのではないかと思う。
マルローにとって劇場は国家がつくる無宗教の教会、共和国の文化財産であったし、ヴィラールやプランションは下から共和国を当座の前提にしたうえで批判的演劇を現出せしめようとした。それらを木っ端微塵にするのが68年5月。共和国なる幻想はすでに失効、消費社会があるだけではないかとこの幻想を否定したのである。プランションは対応しえたし、5月を引きうけたが(72年に国立民衆劇場はリヨン郊外に移転し、プランションとパトリス・シェローが主宰者になった。シェローは80年代にパリ郊外のナンテールに赴任する)、ヴィラールのほうは崩れた。共和国幻想の瓦解、共和国の夢とは、市民社会と共同体が一致するという図にほかならない。近代市民だろうと、共同体だろうと、集合とみなされ、商品の単位、消費者に還元されてしまう「人」の生きざまの前ではただの夢想にすぎないというところにぶち当たったのだ。共和国であれ、ないであれ、集合が発語することはない。われわれはひとりひとり異なる、そういう主張に対して、一体何をもって、自分が民衆といいうるだろうか。
8. 現実の鏡としての舞台と劇場
駆け足にせざるをえなかった。フランスでも日本でも、いうまでもなく、舞台は個別である、均しなべには語ることはできないのは存分に承知したうえであえて図式を出している。フランスには民衆という理念があった、プロレタリアや労働者以上に幻惑力をもった。今も、かすかではあれ、存続している。それは、大元を辿れば、ルソーのいう一般意志であった。それは、数的全体が現存の民衆を装い、拵えられ、メディア記号とされたマジョリティと自明にイコールではない。民主主義は多数とは間違えないものだという原則に則ってこそ有効だが、マジョリティは、それが多数派をふるまえばふるまうほど間違えることが起こる。そのふるまいはしばしばあなた依存、眼が開き、分かっている気で、なのに、何か自分ではないもの、物神への自己委託、「無限抱擁」(丸山眞男)になるケースが少なくないからである。「意思」とは隠蔽され、消滅させられた意志を騙るトリックでないとは断言しづらい。ヨーロッパ最大の共産党を有したドイツ国民はナチに票を投じた、そのとき、なにも剣呑なことが出来するとは思っていなかった、けども、反対する者が街頭の闇で棍棒によってやられる事態の連続があとを継ぎ、それにはもう抵抗する術を多数はもたなかった。穏やかであっても暴力の抑止はそれ自体が暴力になるし、だれかが強制力をもつということを意味する、そのだれかが、数だけの本体なき徒党だとしたら、一層不気味な、これも暴力なのだ。親切やおためごかしによる強制とそれにちょろまかされることは近代にもありうる呪術の世界である。そんなものが横行すれば「人」は通常臆病になるし、一々異和を公明正大に公表、わが身で行為にするのはしんどく、時間も喰う、そんなわけで、率直さが無謀として現象させられてしまう状況を勇敢さだけで生きている者は極少だろうから(わたしもまたこの通常の域にある)、今あえていおう、一般意志とは、ニーチェ的な「愚民」の集合、記号が煽動・先導するポピュリズムのことでは断じてない。では、はたして一般意志は存在するのだろうか。政治はもはやわたしにはてんからわからないから、演劇を通じて残りを思考してみる、尖端的だが、もっとも皮肉な場処だということを噛みしめつつ、勇敢にでも無謀にでも小心にでもなく。
ニーチェは愚かであるところの大衆を蔑んで「畜群」と呼んだ。だからといって、自分こそが「超人」であるというのはいくらなんでも傲慢すぎよう。畜群も超人も結果はファシズムの苗床に盗られた。もとより、「小ブル」がそうでないという保証はどこにもない。そのニーチェ的「超人」は、だが脇からのある参照項程度にはなる、もとめられているのは「透明なゼロ」(ベルナール=マリ・コルテス)であるような身体、民衆を受肉できるような個体の相互性である。芸術は「世界本質」(ニーチェ)を意志的に_まえなければならない。すなわち、一人の「超人」でも、多数派をふるまう「畜群」でもない、そのような位相にある民衆を「発見」しなければならない。民衆演劇は民衆を所与にしてはなしえなかった。ヴィラールのように「水道やガスのように必要な演劇」でも、あるいは、アントワーヌ・ヴィテーズのようにthéâtre élitaire pour tous「万人のための選ばれた演劇」というにしても(これがフランス型民衆演劇の最後の言葉だった)にしても、「必要」も「万人」も依然われわれにはとてつもなく欠如の相にあるというのがわれわれの掛け値なき現実に相違ない。万民とは「皇民」のことだった過去をもっている──過去と、割り切れるかどうか──だけになおさら。だからといって、策を凝らせば、なんとかなるというものではない、ときとしてわたしには現在の東京の舞台がその凝らされた、否、弄されたただの策に見える。舞台が現実抜きで、それがなくてもいいように在るかのごとく見えてくる(もう一度いう、もちろん舞台は個別、一つ一つだ。わたしは現象を誇大に描写しているだろう。だが、誇大にしないと嗅ぎとれぬ趨勢があるのだ)。それがつまらない、へこたれる、むくれる。そうではなくて、自分が民衆である、一般意志であるということの責務を、いや、意志を一回きちんと引きうけてみようではないか、超人思想に惑わされることなく(「アート」とはそのメディア形態だ)、畜群にすり寄ることもなく。演劇人は表現によって一般意志を創成しうる、その可能性に向かって立つ腹を据える、その持続においてもし錯誤を感じたら、演劇人を退くだけではないか。なぜ舞台はやたら跳ねるか、多数派に阿るかしかないのだろうか。それは同一の貨幣の裏表だということがわからないはずはないのに。
正直いえば、やや堂々めぐりになっている感は否めない。でも、これが今のわたしにある精一杯の力量だ。続ける。ここには、劇場が象牙の塔でさえない(大学に務めている者にいえる最大の皮肉的形容)、密封的な空間になっているという現実が働いている。問題は舞台や劇場が自動で在るわけではないということだ。演劇は「劇場」という許容された制度での好きなふるまいというのに留まらない表現層=行為をもっているはずであるし、それがおそらくは民衆はいかに形成できるかという問題系につながっている。演劇は『マラー/サド』流の施設内での仕掛けや額面としての「例外状態」(アガンベン)ではない、現実を超えているか、超えるという仕方で現実を内化している「行為」である。舞台に遊びは許されよう、さりながら、客席はいつも現実である、電車内と同定されるかもしれない、そう追いやられたかもしれない、実態はどうあるにしろ、一つの現実だ。そう認識してはじめて、演劇表現の公共性は担保される。劇場は公共のものであるのが文化の本源であり(「資本の劇場」とかブールヴァール劇場とか選り分けできるのなら、議論はせずに済む、あそこは商売の劇場だといって片づく、楽だ。それはそれで特定のジャンルをもっているし、観るときの構えも違うのだから。それが日本ではごっちゃ、でたらめであり、面倒のトバ口はそこにある)。公共性とは政府や区や地方自治体、公共輸送機関のホームのマイクといった「命令」や「指図」をしてくる可視的な実体機構の独占物、ないし、少なくともその私有物ではない。個々表現者の現場の発語の束ねとしての一般意志の発揚こそが公共性だろう。事例をフランスに学ぶことはできるが、そっくり真似ることが莫迦げていることはいわずもがな、公共劇場はけだし必要ではあるが、今のところそのあり処はどこにも定められない、立ち位置を自力でほとんどゼロから(再)発見しなければならないのだ。芸術監督はおのれが一般意志を体現するという表現を突き出す意志とともに、責務があるのだ、それ以外の任務はないのだといってはばからない、才能などは現在ではあるほうがいいというほどのことだ。その経費や人気ではいささかも測れない場処に彼は現存せねばならないのである。舞台だけに自由があって、しかも、それが少なからずタレントの名とギャラ稼ぎの自由にすぎないのだとしたら、筋違いというものだ。「豊かさ」のなかの貧しさが、自由のなかの途方もない不自由があるというこの現実を演劇人であれば、芝居にするだけではなく、演劇として見据え、対峙しなければならない、その趨勢を演劇人たちには直視してもらいたい(わたしもまた演劇人のはしくれである)。というのも、公共劇場10年でようやくわかってきたたった一つのことはほぼそれに尽きるからだ。舞台で「無政府共産」といえる自由は大切で、貴重である、わたしとて腹の底から応援する。ではあれ、それと同時に、それを他人事性の虚構と嘯かない、それに左袒したり、胸の内で異義申し立てをしたりする実存の身体のいる場がなくてはならない、それも同じだけ自由に。それが市民というものだろう。舞台は例外でも、平べったい現実の複写でもない。なのに、今では大半が「お芝居=商品」だと受けとり、安心し、命令され、指図されて得々なのだとしたら、演劇表現それ自身が危うくはなかろうか。万一そうだとしたなら、劇場は『阿Q』の世界にすぎない、宮本研の、ではなく、魯迅の、だ。現在の日本、また、中共中国が辛亥革命をミリも超えていないと映りかねない現実が問題なのだ。思い出した、これはさる演劇人の手紙から知ったことだ、日本の一作家のある芝居が韓国で上演された際、トークで客席から「この喧嘩、買う」という啖呵が切られたという。客席による舞台の遇し方としてこれ以上に最高の敬意の表示があるだろうか、こんな観客席もあるというのが民衆演劇の根元ではないだろうか。その劇作家はともかく、わたしにはつくづくそう思えてきてしまう。
舞台は虚構であるとはいえ、自己充足できない、開かれ、現実の他者にさらされた空間だ。現実の鏡、もしくは、それが現実そのものである。商売もからんでもいるのだし。しかし、舞台も劇場も決して「仕掛け」ではない、仕掛けにされてはならぬ何かである。仕掛けにされるから、所詮の本態がばれ、額面通りに受けとると、おかしな事態になるか、かつ、おかしなことでもまかり通ってしまう。ルールでもマナーでもタテマエでもなく、そのままの現実、エチカとしての表現が今や必須命題ではないのかとわたしには思える。舞台というのは、嘘をつかないでいいときを招き寄せるための仮の嘘であった。演劇は演劇という虚構を廃絶するためにある絶対的な虚構だ。各時代に「前衛」も民衆演劇もそのアポリアと死闘した。劇場が無数に、ありすぎるほどある現在、劇=場にないのはとどのつまりはその死闘の痕跡と記憶なのだというべきだろうか。明治開化が『支那革命外史』の北一輝のいう「維新革命」だったか、左翼が位置づけるブルジョワ革命だったかどうかなどということはもはやどうでもいい、つねに大事なのは記憶における、または、それと同じもののはずだが、身体の眼にみえる「今」であるし、身体が生きている浮き世であり、その現実である、まずもって。舞台だけあるような現実はただ細工がばれてしまった安い虚構である。アジ臭いことを語った=騙ったかもしれぬことは充分わかったうえで最後に。例えば「非戦」というようなことを平気で宣う演劇人がいる。そんなことがなぜそう気楽にいえるだろうか。戦争は現に在る。いつだったか、友人の一人が教えてくれた、10年で30万人の自殺者を出した日本は裕福と貧困という名の内戦下にあるのだと。至言なり。演劇の表現者も劇場という経済機制のなかにいる限り、その現実に参加している。戦争反対結構、だが、それで終わらない、ではどうするかというところに舞台も劇場もあるだ。どちらも表現者の身体が担う現実をもっていなくてはならない、その現実が一般意志を衝いているかどうかが、民衆演劇、ひいては公共の演劇の礎/標石を分けるだろうというのが当座のわが結論。詮ないことをしゃべったような気分もする。ただ含んで頂かねばいけないのは、わたしは挑発しているのではなく、自分の実存の場処、演劇が不安で、それを憂いているということだ、同事態を身体化して、向後もこの現実内で/に対して発語する覚悟だということだ。再見!!
ニーチェは愚かであるところの大衆を蔑んで「畜群」と呼んだ。だからといって、自分こそが「超人」であるというのはいくらなんでも傲慢すぎよう。畜群も超人も結果はファシズムの苗床に盗られた。もとより、「小ブル」がそうでないという保証はどこにもない。そのニーチェ的「超人」は、だが脇からのある参照項程度にはなる、もとめられているのは「透明なゼロ」(ベルナール=マリ・コルテス)であるような身体、民衆を受肉できるような個体の相互性である。芸術は「世界本質」(ニーチェ)を意志的に_まえなければならない。すなわち、一人の「超人」でも、多数派をふるまう「畜群」でもない、そのような位相にある民衆を「発見」しなければならない。民衆演劇は民衆を所与にしてはなしえなかった。ヴィラールのように「水道やガスのように必要な演劇」でも、あるいは、アントワーヌ・ヴィテーズのようにthéâtre élitaire pour tous「万人のための選ばれた演劇」というにしても(これがフランス型民衆演劇の最後の言葉だった)にしても、「必要」も「万人」も依然われわれにはとてつもなく欠如の相にあるというのがわれわれの掛け値なき現実に相違ない。万民とは「皇民」のことだった過去をもっている──過去と、割り切れるかどうか──だけになおさら。だからといって、策を凝らせば、なんとかなるというものではない、ときとしてわたしには現在の東京の舞台がその凝らされた、否、弄されたただの策に見える。舞台が現実抜きで、それがなくてもいいように在るかのごとく見えてくる(もう一度いう、もちろん舞台は個別、一つ一つだ。わたしは現象を誇大に描写しているだろう。だが、誇大にしないと嗅ぎとれぬ趨勢があるのだ)。それがつまらない、へこたれる、むくれる。そうではなくて、自分が民衆である、一般意志であるということの責務を、いや、意志を一回きちんと引きうけてみようではないか、超人思想に惑わされることなく(「アート」とはそのメディア形態だ)、畜群にすり寄ることもなく。演劇人は表現によって一般意志を創成しうる、その可能性に向かって立つ腹を据える、その持続においてもし錯誤を感じたら、演劇人を退くだけではないか。なぜ舞台はやたら跳ねるか、多数派に阿るかしかないのだろうか。それは同一の貨幣の裏表だということがわからないはずはないのに。
正直いえば、やや堂々めぐりになっている感は否めない。でも、これが今のわたしにある精一杯の力量だ。続ける。ここには、劇場が象牙の塔でさえない(大学に務めている者にいえる最大の皮肉的形容)、密封的な空間になっているという現実が働いている。問題は舞台や劇場が自動で在るわけではないということだ。演劇は「劇場」という許容された制度での好きなふるまいというのに留まらない表現層=行為をもっているはずであるし、それがおそらくは民衆はいかに形成できるかという問題系につながっている。演劇は『マラー/サド』流の施設内での仕掛けや額面としての「例外状態」(アガンベン)ではない、現実を超えているか、超えるという仕方で現実を内化している「行為」である。舞台に遊びは許されよう、さりながら、客席はいつも現実である、電車内と同定されるかもしれない、そう追いやられたかもしれない、実態はどうあるにしろ、一つの現実だ。そう認識してはじめて、演劇表現の公共性は担保される。劇場は公共のものであるのが文化の本源であり(「資本の劇場」とかブールヴァール劇場とか選り分けできるのなら、議論はせずに済む、あそこは商売の劇場だといって片づく、楽だ。それはそれで特定のジャンルをもっているし、観るときの構えも違うのだから。それが日本ではごっちゃ、でたらめであり、面倒のトバ口はそこにある)。公共性とは政府や区や地方自治体、公共輸送機関のホームのマイクといった「命令」や「指図」をしてくる可視的な実体機構の独占物、ないし、少なくともその私有物ではない。個々表現者の現場の発語の束ねとしての一般意志の発揚こそが公共性だろう。事例をフランスに学ぶことはできるが、そっくり真似ることが莫迦げていることはいわずもがな、公共劇場はけだし必要ではあるが、今のところそのあり処はどこにも定められない、立ち位置を自力でほとんどゼロから(再)発見しなければならないのだ。芸術監督はおのれが一般意志を体現するという表現を突き出す意志とともに、責務があるのだ、それ以外の任務はないのだといってはばからない、才能などは現在ではあるほうがいいというほどのことだ。その経費や人気ではいささかも測れない場処に彼は現存せねばならないのである。舞台だけに自由があって、しかも、それが少なからずタレントの名とギャラ稼ぎの自由にすぎないのだとしたら、筋違いというものだ。「豊かさ」のなかの貧しさが、自由のなかの途方もない不自由があるというこの現実を演劇人であれば、芝居にするだけではなく、演劇として見据え、対峙しなければならない、その趨勢を演劇人たちには直視してもらいたい(わたしもまた演劇人のはしくれである)。というのも、公共劇場10年でようやくわかってきたたった一つのことはほぼそれに尽きるからだ。舞台で「無政府共産」といえる自由は大切で、貴重である、わたしとて腹の底から応援する。ではあれ、それと同時に、それを他人事性の虚構と嘯かない、それに左袒したり、胸の内で異義申し立てをしたりする実存の身体のいる場がなくてはならない、それも同じだけ自由に。それが市民というものだろう。舞台は例外でも、平べったい現実の複写でもない。なのに、今では大半が「お芝居=商品」だと受けとり、安心し、命令され、指図されて得々なのだとしたら、演劇表現それ自身が危うくはなかろうか。万一そうだとしたなら、劇場は『阿Q』の世界にすぎない、宮本研の、ではなく、魯迅の、だ。現在の日本、また、中共中国が辛亥革命をミリも超えていないと映りかねない現実が問題なのだ。思い出した、これはさる演劇人の手紙から知ったことだ、日本の一作家のある芝居が韓国で上演された際、トークで客席から「この喧嘩、買う」という啖呵が切られたという。客席による舞台の遇し方としてこれ以上に最高の敬意の表示があるだろうか、こんな観客席もあるというのが民衆演劇の根元ではないだろうか。その劇作家はともかく、わたしにはつくづくそう思えてきてしまう。
舞台は虚構であるとはいえ、自己充足できない、開かれ、現実の他者にさらされた空間だ。現実の鏡、もしくは、それが現実そのものである。商売もからんでもいるのだし。しかし、舞台も劇場も決して「仕掛け」ではない、仕掛けにされてはならぬ何かである。仕掛けにされるから、所詮の本態がばれ、額面通りに受けとると、おかしな事態になるか、かつ、おかしなことでもまかり通ってしまう。ルールでもマナーでもタテマエでもなく、そのままの現実、エチカとしての表現が今や必須命題ではないのかとわたしには思える。舞台というのは、嘘をつかないでいいときを招き寄せるための仮の嘘であった。演劇は演劇という虚構を廃絶するためにある絶対的な虚構だ。各時代に「前衛」も民衆演劇もそのアポリアと死闘した。劇場が無数に、ありすぎるほどある現在、劇=場にないのはとどのつまりはその死闘の痕跡と記憶なのだというべきだろうか。明治開化が『支那革命外史』の北一輝のいう「維新革命」だったか、左翼が位置づけるブルジョワ革命だったかどうかなどということはもはやどうでもいい、つねに大事なのは記憶における、または、それと同じもののはずだが、身体の眼にみえる「今」であるし、身体が生きている浮き世であり、その現実である、まずもって。舞台だけあるような現実はただ細工がばれてしまった安い虚構である。アジ臭いことを語った=騙ったかもしれぬことは充分わかったうえで最後に。例えば「非戦」というようなことを平気で宣う演劇人がいる。そんなことがなぜそう気楽にいえるだろうか。戦争は現に在る。いつだったか、友人の一人が教えてくれた、10年で30万人の自殺者を出した日本は裕福と貧困という名の内戦下にあるのだと。至言なり。演劇の表現者も劇場という経済機制のなかにいる限り、その現実に参加している。戦争反対結構、だが、それで終わらない、ではどうするかというところに舞台も劇場もあるだ。どちらも表現者の身体が担う現実をもっていなくてはならない、その現実が一般意志を衝いているかどうかが、民衆演劇、ひいては公共の演劇の礎/標石を分けるだろうというのが当座のわが結論。詮ないことをしゃべったような気分もする。ただ含んで頂かねばいけないのは、わたしは挑発しているのではなく、自分の実存の場処、演劇が不安で、それを憂いているということだ、同事態を身体化して、向後もこの現実内で/に対して発語する覚悟だということだ。再見!!

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.


