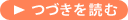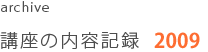


『舞台芸術/史論III』Bコース : 演劇 (2)
「<演じること>のアルケオロジー ― 現代口語演劇の彼方へ」
2009年8月26日(水) 、27日(木) 19時〜21時
森山 直人
(演劇批評家)
《所 感》
これまでのレクチャーでも「観客の視線」についてとりあげられていたが、視線がどのように変わってきているのか、ということを演劇でないメディアを通してとらえている点が興味深かった。<演じる>という行為は、映画やテレビでも行われていることで、ほかのメディアで<演じること>やリアリティが変化すれば、舞台上での<演じる>ことも、それを観る意識も変わっていくだろう。作品の良し悪しに、観客の視線が含まれているのも当然のことであり、またその視線がメディアや社会を通して変わっていき、自分たちの視線が何によって成り立っていくのか、常に考えることで作品もより深く知っていくことができると感じた。
これまでのレクチャーでも「観客の視線」についてとりあげられていたが、視線がどのように変わってきているのか、ということを演劇でないメディアを通してとらえている点が興味深かった。<演じる>という行為は、映画やテレビでも行われていることで、ほかのメディアで<演じること>やリアリティが変化すれば、舞台上での<演じる>ことも、それを観る意識も変わっていくだろう。作品の良し悪しに、観客の視線が含まれているのも当然のことであり、またその視線がメディアや社会を通して変わっていき、自分たちの視線が何によって成り立っていくのか、常に考えることで作品もより深く知っていくことができると感じた。
記録:白石みち子(世田谷パブリックシアター研修生)

メディアの変遷と観客の変容
舞台芸術において、「演技」はいうまでもなく重要な要素の一つである。だが、舞台上で演じられるどのような「演技」に観客がリアリティを感じるかどうかは、時代や場所によって異なる。日本の現代演劇における演技のリアリティを考えるとき、1995年に刊行された平田オリザの『現代口語演劇のために』は、一つのメルクマールとなった。だが、「現代口語演劇」だけが演技のすべてではないことはいうまでもない。現代口語演劇の彼方に、多様な演技のリアリティの可能性を想像するために、とりあえず、ここで「1960年代」を取り上げてみたい。
「1960年代」を、どのようにして考えるか。この時代は、新劇に変わりアングラ演劇が台頭し、暗黒舞踏のピークの時代だった。だが、この時代の舞台作品で映像記録が残っているものはごくわずかで、証言や文章で検証するしかない。また、「1960年代」は、すでに半世紀近くが経過しているとはいえ、いわゆる「アングラ的な演技」に関しては、まだまだ神話的なヴェールが破られていない。この講座では、そうした観点とはやや違った観点から、「演じること」のアルケオロジーを考察してみたい。「1960年代」において無視できないことは、批評家のスガ秀実が「メディア論的展開」という言葉を使っているが(『革命的な、あまりに革命的な』)、活字メディア的なもの(広い意味では「新劇」もそうである)から、視聴覚メディア的なものに、人々の感性を働きかけるメディアのヘゲモニーが変わっていったということである。とくに、1970年代以降にそのヘゲモニーが確実なものとなるテレビというメディアは、人々の日常/非日常のリアリティを、現在に至るまで大きく決定づけている。もちろん「現代口語演劇」という形式に人々が感じるリアリティも、そのことと無関係ではないし、近年の「ドキュメンタリー演劇」の流行にも同じことがいえる。支配的なメディアがつくりあげるリアリティは、同時代の演劇やダンスにおける「演じること」のリアリティにも、何らかの形で影響を及ぼしてくるのである。
「1960年代」を、どのようにして考えるか。この時代は、新劇に変わりアングラ演劇が台頭し、暗黒舞踏のピークの時代だった。だが、この時代の舞台作品で映像記録が残っているものはごくわずかで、証言や文章で検証するしかない。また、「1960年代」は、すでに半世紀近くが経過しているとはいえ、いわゆる「アングラ的な演技」に関しては、まだまだ神話的なヴェールが破られていない。この講座では、そうした観点とはやや違った観点から、「演じること」のアルケオロジーを考察してみたい。「1960年代」において無視できないことは、批評家のスガ秀実が「メディア論的展開」という言葉を使っているが(『革命的な、あまりに革命的な』)、活字メディア的なもの(広い意味では「新劇」もそうである)から、視聴覚メディア的なものに、人々の感性を働きかけるメディアのヘゲモニーが変わっていったということである。とくに、1970年代以降にそのヘゲモニーが確実なものとなるテレビというメディアは、人々の日常/非日常のリアリティを、現在に至るまで大きく決定づけている。もちろん「現代口語演劇」という形式に人々が感じるリアリティも、そのことと無関係ではないし、近年の「ドキュメンタリー演劇」の流行にも同じことがいえる。支配的なメディアがつくりあげるリアリティは、同時代の演劇やダンスにおける「演じること」のリアリティにも、何らかの形で影響を及ぼしてくるのである。

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.