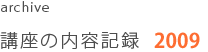


『舞台芸術/史論III』Bコース : 演劇 (2)
「<演じること>のアルケオロジー ― 現代口語演劇の彼方へ」
2009年8月26日(水) 、27日(木) 19時〜21時
森山 直人
(演劇批評家)
《所 感》
これまでのレクチャーでも「観客の視線」についてとりあげられていたが、視線がどのように変わってきているのか、ということを演劇でないメディアを通してとらえている点が興味深かった。<演じる>という行為は、映画やテレビでも行われていることで、ほかのメディアで<演じること>やリアリティが変化すれば、舞台上での<演じる>ことも、それを観る意識も変わっていくだろう。作品の良し悪しに、観客の視線が含まれているのも当然のことであり、またその視線がメディアや社会を通して変わっていき、自分たちの視線が何によって成り立っていくのか、常に考えることで作品もより深く知っていくことができると感じた。
これまでのレクチャーでも「観客の視線」についてとりあげられていたが、視線がどのように変わってきているのか、ということを演劇でないメディアを通してとらえている点が興味深かった。<演じる>という行為は、映画やテレビでも行われていることで、ほかのメディアで<演じること>やリアリティが変化すれば、舞台上での<演じる>ことも、それを観る意識も変わっていくだろう。作品の良し悪しに、観客の視線が含まれているのも当然のことであり、またその視線がメディアや社会を通して変わっていき、自分たちの視線が何によって成り立っていくのか、常に考えることで作品もより深く知っていくことができると感じた。
記録:白石みち子(世田谷パブリックシアター研修生)

メディアの変遷と観客の変容
舞台芸術において、「演技」はいうまでもなく重要な要素の一つである。だが、舞台上で演じられるどのような「演技」に観客がリアリティを感じるかどうかは、時代や場所によって異なる。日本の現代演劇における演技のリアリティを考えるとき、1995年に刊行された平田オリザの『現代口語演劇のために』は、一つのメルクマールとなった。だが、「現代口語演劇」だけが演技のすべてではないことはいうまでもない。現代口語演劇の彼方に、多様な演技のリアリティの可能性を想像するために、とりあえず、ここで「1960年代」を取り上げてみたい。
「1960年代」を、どのようにして考えるか。この時代は、新劇に変わりアングラ演劇が台頭し、暗黒舞踏のピークの時代だった。だが、この時代の舞台作品で映像記録が残っているものはごくわずかで、証言や文章で検証するしかない。また、「1960年代」は、すでに半世紀近くが経過しているとはいえ、いわゆる「アングラ的な演技」に関しては、まだまだ神話的なヴェールが破られていない。この講座では、そうした観点とはやや違った観点から、「演じること」のアルケオロジーを考察してみたい。「1960年代」において無視できないことは、批評家のスガ秀実が「メディア論的展開」という言葉を使っているが(『革命的な、あまりに革命的な』)、活字メディア的なもの(広い意味では「新劇」もそうである)から、視聴覚メディア的なものに、人々の感性を働きかけるメディアのヘゲモニーが変わっていったということである。とくに、1970年代以降にそのヘゲモニーが確実なものとなるテレビというメディアは、人々の日常/非日常のリアリティを、現在に至るまで大きく決定づけている。もちろん「現代口語演劇」という形式に人々が感じるリアリティも、そのことと無関係ではないし、近年の「ドキュメンタリー演劇」の流行にも同じことがいえる。支配的なメディアがつくりあげるリアリティは、同時代の演劇やダンスにおける「演じること」のリアリティにも、何らかの形で影響を及ぼしてくるのである。
「1960年代」を、どのようにして考えるか。この時代は、新劇に変わりアングラ演劇が台頭し、暗黒舞踏のピークの時代だった。だが、この時代の舞台作品で映像記録が残っているものはごくわずかで、証言や文章で検証するしかない。また、「1960年代」は、すでに半世紀近くが経過しているとはいえ、いわゆる「アングラ的な演技」に関しては、まだまだ神話的なヴェールが破られていない。この講座では、そうした観点とはやや違った観点から、「演じること」のアルケオロジーを考察してみたい。「1960年代」において無視できないことは、批評家のスガ秀実が「メディア論的展開」という言葉を使っているが(『革命的な、あまりに革命的な』)、活字メディア的なもの(広い意味では「新劇」もそうである)から、視聴覚メディア的なものに、人々の感性を働きかけるメディアのヘゲモニーが変わっていったということである。とくに、1970年代以降にそのヘゲモニーが確実なものとなるテレビというメディアは、人々の日常/非日常のリアリティを、現在に至るまで大きく決定づけている。もちろん「現代口語演劇」という形式に人々が感じるリアリティも、そのことと無関係ではないし、近年の「ドキュメンタリー演劇」の流行にも同じことがいえる。支配的なメディアがつくりあげるリアリティは、同時代の演劇やダンスにおける「演じること」のリアリティにも、何らかの形で影響を及ぼしてくるのである。
ドキュメンタリー映像『テレビにとって「私」とは何か』
○歴史的にみた「公共劇場」
そこで注目すべきことは、「1960年代」が、テレビの草創期であり、リアリティをめぐるさまざまな試行錯誤が行われていた時期だったということである。おそらく演劇人のなかで、その種の動向に最も敏感に反応したうちの一人が寺山修司だったことは間違いない。そのことをたしかめるために、最近テレビで放映された、テレビをめぐる一本のドキュメンタリー番組の一部をみてみたい。番組のタイトルは、『あの時だったかもしれない〜テレビにとって「私」とは何か〜』。ディレクターは、映画『空気人形』や『誰も知らない』の監督である是枝裕和である。
番組の登場人物は、1950年代末に、ラジオ東京(TBS)を経てTBSテレビの世界にうつり、テレビの草創期に大きく関わった有名な3人のテレビマン、今野勉、村木良彦、萩元晴彦である。3人は1968年に、三里塚闘争の報道にかかわる問題で上層部と対立し、大手放送局であるTBSを飛び出して、日本初のテレビ制作会社「テレビマンユニオン」(1970年―)を設立したことで知られている(是枝も元テレビマンユニオンの社員であり、テレビ・ドキュメンタリーの制作からキャリアをスタートさせている)。
初期テレビの時代は、1950年代末から1960年代にかけてで、同時期の日本の演劇では、新劇の全盛時代からプレ・アングラの時期を経て、アングラの興隆に至る時期にあたる。寺山修司が天井桟敷の活動を開始するのは1967年であるが、彼はアングラ演劇をはじめる以前にラジオやテレビのドラマやドキュメンタリーの構成に積極的にかかわっていたことはよく知られている。
今野、村木、萩元の3人とも、1950年代後半に徐々に社会に浸透しつつあった新しいメディアであるテレビには、当初は疑問を持っていた。萩元は、ラジオで野球中継のように心臓外科手術の生中継を行うなど、メディア社会のリアリティにかかわる革新的な番組を制作していたが、テレビには当初は否定的だった。3人のそうした姿勢が決定的に変わるきっかけとなったのは、1959年の「ご成婚パレード」の放送である。村木はTBSで生中継を担当し、テレビカメラ設置場所の関係で、パレードを撮影できない場面で、すでに録画されたフィルムを中継にさしはさみ、お二人の生い立ちやテニスのシーンをいれた。ところが日本テレビは、パレードがまだ現れない街路の映像を延々と放送した。この生の感覚が迫力を生み、TBSは結果的に敗北したという。このとき日本テレビのプロデューサーであった牛山純一もまた、初期テレビの代表的なディレクターの一人である。
映画もテレビも映像を介するメディアだが、映画は過去が編集されたものであるのに対し、テレビは「生のもの」であり、次に何が起こるか分からない状態である。「つねに現在でありつづける状態」がテレビのリアリティの可能性であることが、3人の若手ディレクターには強烈に意識された。1966年に放送された萩元、村木がディレクターとなる「現代の主役」シリーズ『あなたは…』は、寺山修司構成の番組で、800人を超える人に街頭インタヴューで、同じ質問を繰り返した(この手法は、1960年前後のシネマ・ヴェリテにおいて、ジャン・ルーシュやアニエス・ヴェルダが行っていた手法を輸入している)。同シリーズ『日の丸』は、憲法記念日の二日前に放送された。これらの番組では女子学生が無機的に一般人に同じ質問をインタヴューしていく形式で、放送後には「マイクの暴力」として激しい批判にもさらされたが、「不特定多数」と呼ばれる人々が暮らしている日常の、現在時における不安定な生の様相を鮮やかに切り取ってもいた。
これらの番組を、「演じること」という観点から眺めたとき、そこには2種類の「俳優」がいることがわかる。一方は「インタビュアー」であり、もう一方は「通行人」である。インタビュアーは通行人の日常に非日常を投げ込むことで、一種の起爆剤の役割を果たしている。通行人は、インタビュアーから矢継ぎ早に浴びせられる「あなたはいま幸せですか」「あなたの欲しいものは何ですか」「国のために死ねますか」「最後に聞きますが、あなたはいったい誰ですか」といった質問に、ひたすらその場で即興的に答えることを余儀なくされる。途切れることのない生の現在時において、暴力的な質問により、質問された人の瞬間的な表情や言葉の選び方やうつろい自体が、一種の主人公のようにクローズアップされていく。
テレビの登場によって、リアリティを作っていく時の基準が変わっていくことを示したのがこのドキュメンタリー番組である。今野、村木、萩元は『お前はただの現在に過ぎない』という有名なテレビ論を1969年に出版した。この時期、彼らはTBSを追われ、1970年にテレビマンユニオンを設立することとなる。政治的な規制が強まる1968年前後は、大手の放送局のシステムから初期テレビがもっていた実験的な活力が失われていった時期だと考えられる。ちなみに、今野勉は、アングラ演劇の「発見の会」に戯曲を提供しており、この時期の演劇とテレビの問題意識が必ずしも遠くなかったことを思わせる。
番組の登場人物は、1950年代末に、ラジオ東京(TBS)を経てTBSテレビの世界にうつり、テレビの草創期に大きく関わった有名な3人のテレビマン、今野勉、村木良彦、萩元晴彦である。3人は1968年に、三里塚闘争の報道にかかわる問題で上層部と対立し、大手放送局であるTBSを飛び出して、日本初のテレビ制作会社「テレビマンユニオン」(1970年―)を設立したことで知られている(是枝も元テレビマンユニオンの社員であり、テレビ・ドキュメンタリーの制作からキャリアをスタートさせている)。
初期テレビの時代は、1950年代末から1960年代にかけてで、同時期の日本の演劇では、新劇の全盛時代からプレ・アングラの時期を経て、アングラの興隆に至る時期にあたる。寺山修司が天井桟敷の活動を開始するのは1967年であるが、彼はアングラ演劇をはじめる以前にラジオやテレビのドラマやドキュメンタリーの構成に積極的にかかわっていたことはよく知られている。
今野、村木、萩元の3人とも、1950年代後半に徐々に社会に浸透しつつあった新しいメディアであるテレビには、当初は疑問を持っていた。萩元は、ラジオで野球中継のように心臓外科手術の生中継を行うなど、メディア社会のリアリティにかかわる革新的な番組を制作していたが、テレビには当初は否定的だった。3人のそうした姿勢が決定的に変わるきっかけとなったのは、1959年の「ご成婚パレード」の放送である。村木はTBSで生中継を担当し、テレビカメラ設置場所の関係で、パレードを撮影できない場面で、すでに録画されたフィルムを中継にさしはさみ、お二人の生い立ちやテニスのシーンをいれた。ところが日本テレビは、パレードがまだ現れない街路の映像を延々と放送した。この生の感覚が迫力を生み、TBSは結果的に敗北したという。このとき日本テレビのプロデューサーであった牛山純一もまた、初期テレビの代表的なディレクターの一人である。
映画もテレビも映像を介するメディアだが、映画は過去が編集されたものであるのに対し、テレビは「生のもの」であり、次に何が起こるか分からない状態である。「つねに現在でありつづける状態」がテレビのリアリティの可能性であることが、3人の若手ディレクターには強烈に意識された。1966年に放送された萩元、村木がディレクターとなる「現代の主役」シリーズ『あなたは…』は、寺山修司構成の番組で、800人を超える人に街頭インタヴューで、同じ質問を繰り返した(この手法は、1960年前後のシネマ・ヴェリテにおいて、ジャン・ルーシュやアニエス・ヴェルダが行っていた手法を輸入している)。同シリーズ『日の丸』は、憲法記念日の二日前に放送された。これらの番組では女子学生が無機的に一般人に同じ質問をインタヴューしていく形式で、放送後には「マイクの暴力」として激しい批判にもさらされたが、「不特定多数」と呼ばれる人々が暮らしている日常の、現在時における不安定な生の様相を鮮やかに切り取ってもいた。
これらの番組を、「演じること」という観点から眺めたとき、そこには2種類の「俳優」がいることがわかる。一方は「インタビュアー」であり、もう一方は「通行人」である。インタビュアーは通行人の日常に非日常を投げ込むことで、一種の起爆剤の役割を果たしている。通行人は、インタビュアーから矢継ぎ早に浴びせられる「あなたはいま幸せですか」「あなたの欲しいものは何ですか」「国のために死ねますか」「最後に聞きますが、あなたはいったい誰ですか」といった質問に、ひたすらその場で即興的に答えることを余儀なくされる。途切れることのない生の現在時において、暴力的な質問により、質問された人の瞬間的な表情や言葉の選び方やうつろい自体が、一種の主人公のようにクローズアップされていく。
テレビの登場によって、リアリティを作っていく時の基準が変わっていくことを示したのがこのドキュメンタリー番組である。今野、村木、萩元は『お前はただの現在に過ぎない』という有名なテレビ論を1969年に出版した。この時期、彼らはTBSを追われ、1970年にテレビマンユニオンを設立することとなる。政治的な規制が強まる1968年前後は、大手の放送局のシステムから初期テレビがもっていた実験的な活力が失われていった時期だと考えられる。ちなみに、今野勉は、アングラ演劇の「発見の会」に戯曲を提供しており、この時期の演劇とテレビの問題意識が必ずしも遠くなかったことを思わせる。
1960年代の演劇とテレビ
初期テレビは、今日の私たちになじみのある言い方でいえば、「ドキュメンタリー」的なリアリティを新たなリアリティとして発見し、表現の可能性を模索していた。こうしたリアリティは、演劇表現の変化とまったく無関係ではないように思う。たとえば、1960年代のアンダーグラウンド演劇の代表的な傑作とされる『劇的なるものをめぐって?――白石加代子ショウ』は、スタニスラフスキー・システムに基づく俳優教育と無縁だったという意味では「素人」であった白石加代子という女優が、「演技」という行為を通じて「白石加代子が白石加代子自身になる」様相を、舞台という現場でドキュメントする、という側面をもっていたはずである。また、1960年代に流行したハプニングは、「生活と芸術の一致」を基本的な目標としてかかげているが、そうした動きと連動しつつ、後にその影響から離れていく土方巽の暗黒舞踏も、ある意味では、「命がけで突っ立っている死体」としての舞踏家が、自分自身の肉体を唯一の根拠として踊りを生成していく現場を目撃する場を組織していったとみることもできる。なにより、初期テレビと密接にかかわっていた寺山修司は、1967年以降「演劇実験室天井桟敷」において、テレビで試みた「ドキュラマ」(ドキュメンタリー+ドラマ)の発想を、「見世物小屋の復権」から「市街劇」の実践に至るまで展開していくことになる。
こうした流れのなかで、既存の演劇とくらべて明らかになっていくのは、「俳優」、それも「職業的な俳優」という存在に対する懐疑である。「ドキュメンタリー」的なリアリティとは、「一回性」のリアリティであり、寺山が市街劇『ノック』などを通じて、観客を「参加者」として巻き込み、現実と虚構の境界自体を問いなおしつつ、作り手と受け手の一回的な出会いを組織しようとした考え方は、そうしたリアリティの上に立脚していたとみることができる。また、「ドキュメンタリー」的な実況中継=一回性のリアリティが、大きな劇場性を獲得したのは、1972年に起こった「浅間山荘事件」であったと言えるかもしれない。
こうした流れのなかで、既存の演劇とくらべて明らかになっていくのは、「俳優」、それも「職業的な俳優」という存在に対する懐疑である。「ドキュメンタリー」的なリアリティとは、「一回性」のリアリティであり、寺山が市街劇『ノック』などを通じて、観客を「参加者」として巻き込み、現実と虚構の境界自体を問いなおしつつ、作り手と受け手の一回的な出会いを組織しようとした考え方は、そうしたリアリティの上に立脚していたとみることができる。また、「ドキュメンタリー」的な実況中継=一回性のリアリティが、大きな劇場性を獲得したのは、1972年に起こった「浅間山荘事件」であったと言えるかもしれない。
人間ピラミッド
こうしたリアリティと「演じること」の問題を考えていく上で、ジャン・ルーシュの映画『人間ピラミッド』(1959-61)をみてみたい。ジャン・ルーシュは人類学者出身の映像作家である。人類学は記録を映像に残していくため、映像と縁が深い学問だ。ルーシュの代表作として、ガーナの部族での悪魔払いを記録した『狂気の主人たち』(1958)やパリでの街頭インタヴューをもとにした『ある夏の記録』(1960)がある。
『人間ピラミッド』は、コートジヴォアールの首都アヴィジャンの、ある高校での生活を記録した映画である。コートジヴォアールの独立は1960年。その直前に、仕事でこの地を訪れたルーシュは、高校の同じクラスで学ぶ成績優秀な黒人と白人の生徒たちが、実は日常的にほとんど交流がないことに気付く。そこで彼は黒人と白人のそれぞれのグループに呼びかけ、「もしもお互いが交流したらどうなるか」をドラマ仕立てで実験してみることを提案する。全体のシチュエーションはルーシュが設定し、具体的な台詞は出演者の高校生が自分で書き、自分を演じるという方法で、純粋なドキュメンタリーともドラマともつかない奇妙な撮影がスタートする。
この手法は、「実験」的であり、ある意味では危険でもある。「虚構」であることを前提として、ある意味では安心して虚構の自分自身を演じているうちに、現実の自分自身がそこに流れ込んでしまうからだ。虚構の政治論議のはずが、いつのまにか、本音が暴露されてしまったりする。虚構の恋愛や友情だったはずが、本物の恋愛や友情に転化しそうになる…。実際この撮影終了後に、彼らのあいだには、本物の交友関係が生まれていった。このような手法は、これまで論じた初期テレビの革新的な担い手たちが考えていたことに通じている。また同時に、ベルトルト・ブレヒトが、「教育劇」で想定していたことにも通じている。ブレヒトは、「教育劇」を、単にできあがったフィクションを再現するのではなく、「演じる」というフィクションを導入することによって、現実のあり方を反省し、変革するための契機としようとしたのだった。
<演じること>とは、隠されたことを引き出す装置でもある。視線の対象には、引き出されたことを議論するためのしかけがあり、議論する場が生じる。観客と演じ手が同じ立場にたって議論されるようになる。<演じること>を通じてプロセスが生まれ、そこで現在が紡ぎだされていく。そこに立ち会った人がどのように変容するか、ということが、メディア時代の演劇においては重要なファクターになりうるし、演劇というメディアを、今日においてどのように使用しうるのかを考える上でも重要な視点となりうる。そうした演劇の側面は、1960年前後の映画やテレビが直面しはじめた新たなリアリティの様相を振り返ることによって、より明確なものとなるかもしれないと考えている。
『人間ピラミッド』は、コートジヴォアールの首都アヴィジャンの、ある高校での生活を記録した映画である。コートジヴォアールの独立は1960年。その直前に、仕事でこの地を訪れたルーシュは、高校の同じクラスで学ぶ成績優秀な黒人と白人の生徒たちが、実は日常的にほとんど交流がないことに気付く。そこで彼は黒人と白人のそれぞれのグループに呼びかけ、「もしもお互いが交流したらどうなるか」をドラマ仕立てで実験してみることを提案する。全体のシチュエーションはルーシュが設定し、具体的な台詞は出演者の高校生が自分で書き、自分を演じるという方法で、純粋なドキュメンタリーともドラマともつかない奇妙な撮影がスタートする。
この手法は、「実験」的であり、ある意味では危険でもある。「虚構」であることを前提として、ある意味では安心して虚構の自分自身を演じているうちに、現実の自分自身がそこに流れ込んでしまうからだ。虚構の政治論議のはずが、いつのまにか、本音が暴露されてしまったりする。虚構の恋愛や友情だったはずが、本物の恋愛や友情に転化しそうになる…。実際この撮影終了後に、彼らのあいだには、本物の交友関係が生まれていった。このような手法は、これまで論じた初期テレビの革新的な担い手たちが考えていたことに通じている。また同時に、ベルトルト・ブレヒトが、「教育劇」で想定していたことにも通じている。ブレヒトは、「教育劇」を、単にできあがったフィクションを再現するのではなく、「演じる」というフィクションを導入することによって、現実のあり方を反省し、変革するための契機としようとしたのだった。
<演じること>とは、隠されたことを引き出す装置でもある。視線の対象には、引き出されたことを議論するためのしかけがあり、議論する場が生じる。観客と演じ手が同じ立場にたって議論されるようになる。<演じること>を通じてプロセスが生まれ、そこで現在が紡ぎだされていく。そこに立ち会った人がどのように変容するか、ということが、メディア時代の演劇においては重要なファクターになりうるし、演劇というメディアを、今日においてどのように使用しうるのかを考える上でも重要な視点となりうる。そうした演劇の側面は、1960年前後の映画やテレビが直面しはじめた新たなリアリティの様相を振り返ることによって、より明確なものとなるかもしれないと考えている。
質疑応答
Q1: リアリティが変わっていく、ということはどのレベルで重要なのか?
演技のリアリティは、自明なものとして不変的に存在するものではなく、社会が何をリア
ルと考えるかによって変化しうるし、社会のリアリティが演技にフィードバックされると
いう面が確実にある(リアリズムの時代におけるスタニスラフスキー・システムの成立は、
まさにそれである)。ただ、この講座では日本の特殊性を意識し、そのリアリティの変化を、
あえて演劇ではなくテレビや映画で見た。ヨーロッパの場合、劇場芸術にステータスがあり、
文化的に安定した構造があるためにメディア社会のリアリティの構造が、リアルタイムで
演劇に反映するかどうかは状況次第である。一方で、演劇の社会的地位があいまいな日本は、
そうしたリアリティの変化が、かなりダイレクトに演劇の生産構造に影響を与えるといった
側面がある。「現代口語演劇」の成立は、まさにそうした状況の反映であるように思う。
あるいは、いまの日本の演劇の多くは、テレビに出ている俳優を見に行く、という意味で テレビのコピーとしての演劇という状況も事実としてある以上、メディア社会におけるリア リティとの相互関係という視点から演劇を考えていくことが、欧米の演劇以上に必要である し、有効であるように思われる。
あるいは、いまの日本の演劇の多くは、テレビに出ている俳優を見に行く、という意味で テレビのコピーとしての演劇という状況も事実としてある以上、メディア社会におけるリア リティとの相互関係という視点から演劇を考えていくことが、欧米の演劇以上に必要である し、有効であるように思われる。
Q2: 現代は劇場に足を運ぶ人が少ない。今後はどうなっていくのか?
たとえばドイツの市民劇は、劇場を、市民を市民化するために「教育装置」として定義し
ていた。劇場は、公共性の場として、近代における重要な位置を占めてきたが、現代のよ
うなメディア社会においては、生の劇場の公共性が占める割合は曖昧になっており、世界
的に文化的位置がゆらいでいることは否めない(劇場に限らず、「美術館」や「大学」のよ
うな制度も同じだが)。劇場を今のままに維持することに説得力はなく、新たなメディア
状況のなかで、演劇というメディアがどのように機能しうるのかを見極めることでしか、
新たな観客も生み出されないのではないか。

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.


