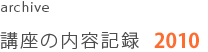


『「民衆演劇」と「公共の演劇」の構想−フランスの場合を参照しつつ』
Vol.1「大革命と演劇」
2010年11月12日(金) 19時〜21時
八木 雅子
(学習院大学大学院助教)
《所 感》
演劇は社会の変化を映し出している。フランス演劇は、革命を経て、そのパラダイムを王様から人々へと大きく転換させた。革命期に問題提起された公共(public)という考え方は現代に至るまでのフランス社会に共有されており、フランスの演劇をめぐる議論の前提にもなっている。フランスの演劇政策、文化政策の根底には、国民みんなの文化的享受の権利の実現が国の責務であるという考え方がある。
ここでいう「国」とは、フランス革命以前に人々に先んじて王様がトップダウンで作り出したものとは異なり、人々(people)の契約によって成立するものである。「国民」「国」という概念の認識が、フランスと日本ではやはり大きく異なるのだと実感させられた講座だった。文化は社会の鏡であり、文化政策にもその社会の基底にある思想が反映されている。海外の事例を学ぶことは、自らの問い返しにつながると改めて感じた。
演劇は社会の変化を映し出している。フランス演劇は、革命を経て、そのパラダイムを王様から人々へと大きく転換させた。革命期に問題提起された公共(public)という考え方は現代に至るまでのフランス社会に共有されており、フランスの演劇をめぐる議論の前提にもなっている。フランスの演劇政策、文化政策の根底には、国民みんなの文化的享受の権利の実現が国の責務であるという考え方がある。
ここでいう「国」とは、フランス革命以前に人々に先んじて王様がトップダウンで作り出したものとは異なり、人々(people)の契約によって成立するものである。「国民」「国」という概念の認識が、フランスと日本ではやはり大きく異なるのだと実感させられた講座だった。文化は社会の鏡であり、文化政策にもその社会の基底にある思想が反映されている。海外の事例を学ぶことは、自らの問い返しにつながると改めて感じた。
記録:中村美帆(東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学研究専攻博士課程)

1. publicとは何か
公共(public)とは何か。例えばpublic domainという言葉は、個人の著作権が切れて、個人の財産ではなくみんなの共有財産になった状態を言う。つまり文化は国民すべての財産だということがpublic の考え方である。文化のデモクラシーと地方分散化(分権化)、すなわち中央に集権化されている文化を地方に伝播させ、文化的環境の享受に民主主義を与え誰もが得られるようにすること、それがpublicである。そこで念頭に置かれた「国民」がより普遍化して「世界共通の・人類の」という考え方になり、世界遺産等にもつながっている。その過程で欧米中心主義の文化理解に対するアンチテーゼもあったが、今日では少なくとも文化は国民全員の財産で、そこにアクセスする権利は人権の一つという思想は共有されている。文化政策の根本原理はここに尽きると思う。
フランスにおける思想そして実際の行動としてpublicが問われ、政策で実現すべき課題として捉えられた最初の機会が革命期である。例えば、貴族から没収した財産の公開によって、ルーブル宮殿はルーブル美術館になり、みんなが美の財産・知の財産に触れられる場に変わった。一部の特権階級だけが独占してきた財産に対する権利を、そこから排除されていた人々の手に取り戻した。本日はpublicという大きな思想のもとでの革命期の演劇について見ていきたい。
フランスにおける思想そして実際の行動としてpublicが問われ、政策で実現すべき課題として捉えられた最初の機会が革命期である。例えば、貴族から没収した財産の公開によって、ルーブル宮殿はルーブル美術館になり、みんなが美の財産・知の財産に触れられる場に変わった。一部の特権階級だけが独占してきた財産に対する権利を、そこから排除されていた人々の手に取り戻した。本日はpublicという大きな思想のもとでの革命期の演劇について見ていきたい。
2. フランス旧制度下の劇場制度〜革命以前
革命前のフランスの演劇は、(1) 官許劇場による興行独占、(2) 俳優に対する否定的見方、その2点において、社会的支持を得られていたとは言い難い。
(1) 官許劇場による興行独占
18世紀初頭のフランス演劇は、①オペラ座、②テアトル・フランセ(コメディ・フランセーズ)、③テアトル・イタリアン(もともとはイタリア人劇団によるイタリア語上演)、制度上、この3つが独占していた。1789年になると官許劇場が少し増えたが、独占状態には変わりなかった。オペラ座ではオペラとバレエが、テアトル・フランセでは悲劇と喜劇が上演され、テアトル・イタリアンでは主に喜劇や歌入り芝居などが上演されていたが、これら官許劇場にはそれぞれ興行許可が与えられており、それ以外の場所では興行権を有する劇場の許可がなければできなかった。
それに対して治外法権的に存在したのがフォワールつまり市場で行われた演劇で、数カ月の市場の期間だけ例外的に上演が認められた。日本の宮芝居のように、あくまで期間限定だから官許劇場と競合しないという扱いだった。市場の芝居は当初仮設小屋で行われていたが、後に常設と同等の建物で行われるようになり、官許劇場と競合するようになった。とりわけテアトル・フランセは演劇の上演権を金銭譲渡しなかったので、市場の劇場でも演劇の上演ができない。つまり役者が互いに台詞を言って劇が進行するという上演形態が取れず、台詞の代わりにプラカードを使ったり、人形や子どもを使って裏から台詞をあてたり、歌を使ったり、「これは台詞を用いた芝居ではない」という形式をとった。18世紀になると市場の演劇はタンブル通りに進出して完全に常設化していく、さらには新たな官許劇場認可の動きが現れるなど、それまでの官許劇場の独占環境は脅かされるようになった。
一方劇作家は、このような独占状態においては、できあがった作品を官許劇場に持っていくしかなかったが、そこで受け入れられなければその作品は上演できない。また受け入れられた場合でも上演されるとはかぎらない。たとえばフランセに一度受領されてしまえば、上演されないからといってイタリアンに持ち込むことはできなくなる。また劇作家は集客に応じて報酬を受け取ることになっていたが、初演時に一定レベルの興行成績を上げられなければ劇作家はその権利を失い、たとえ再演時に大成功を収めても劇作家には報酬は支払われずに終わる。また一種の株仲間制度を土台とする前近代的制度を保持していた官許劇団は固定的な限られた俳優が中心に存在し、人材の流動性は低い。官許劇場は新興同業者だけでなく、劇作家にとっても自分たちの権利を侵害する特権的存在であったため、その不満を募らせていった。
それに対して治外法権的に存在したのがフォワールつまり市場で行われた演劇で、数カ月の市場の期間だけ例外的に上演が認められた。日本の宮芝居のように、あくまで期間限定だから官許劇場と競合しないという扱いだった。市場の芝居は当初仮設小屋で行われていたが、後に常設と同等の建物で行われるようになり、官許劇場と競合するようになった。とりわけテアトル・フランセは演劇の上演権を金銭譲渡しなかったので、市場の劇場でも演劇の上演ができない。つまり役者が互いに台詞を言って劇が進行するという上演形態が取れず、台詞の代わりにプラカードを使ったり、人形や子どもを使って裏から台詞をあてたり、歌を使ったり、「これは台詞を用いた芝居ではない」という形式をとった。18世紀になると市場の演劇はタンブル通りに進出して完全に常設化していく、さらには新たな官許劇場認可の動きが現れるなど、それまでの官許劇場の独占環境は脅かされるようになった。
一方劇作家は、このような独占状態においては、できあがった作品を官許劇場に持っていくしかなかったが、そこで受け入れられなければその作品は上演できない。また受け入れられた場合でも上演されるとはかぎらない。たとえばフランセに一度受領されてしまえば、上演されないからといってイタリアンに持ち込むことはできなくなる。また劇作家は集客に応じて報酬を受け取ることになっていたが、初演時に一定レベルの興行成績を上げられなければ劇作家はその権利を失い、たとえ再演時に大成功を収めても劇作家には報酬は支払われずに終わる。また一種の株仲間制度を土台とする前近代的制度を保持していた官許劇団は固定的な限られた俳優が中心に存在し、人材の流動性は低い。官許劇場は新興同業者だけでなく、劇作家にとっても自分たちの権利を侵害する特権的存在であったため、その不満を募らせていった。
(2) 俳優に対する否定的見方
官許劇場があったとはいえ、俳優が一般の市民とは異なるアウトローな存在だったのはフランス社会でも例外ではない。俳優はその職業として教会から破門されていたが、キリスト教社会においてそれは通常の身分制度からは外れたアウトローとなることを意味していた。革命がおこり、等しく市民権を認めた、いわゆる人権宣言が行われたが、俳優はユダヤ教徒やプロテスタント、あるいは独立した存在と認められていなかった下僕や首切り役人のような忌避される職業などと同様に、当初はその対象には含まれていなかった。ようやく俳優に市民権が認められたのは、そのおよそ4カ月後である。
市民権を得た俳優は、選挙権を手に入れ、公職につけるようになり、役人や軍人として命令を出す側に立つことができるようになったが、当時はそれに対して大きな抵抗があった。拍手を受けて生活する俳優は客やパトロンに媚を売り、従属する存在とみなす根強い蔑視があったためで、そのような人物から命令されることに耐えられないとする批判も見られた。
それでも徐々に俳優の市民権が認められるようになった背景には、革命以前から活発に議論された演劇有用論がある。演劇には価値がある、有用であるという形で、演劇擁護論が展開された。演劇がいかに民衆の教育に役立ち、民衆に有益なものかを積極的に認めることによって、演劇の存在価値が高まり、あわせて俳優の社会的地位の向上につながったと言える。
市民権を得た俳優は、選挙権を手に入れ、公職につけるようになり、役人や軍人として命令を出す側に立つことができるようになったが、当時はそれに対して大きな抵抗があった。拍手を受けて生活する俳優は客やパトロンに媚を売り、従属する存在とみなす根強い蔑視があったためで、そのような人物から命令されることに耐えられないとする批判も見られた。
それでも徐々に俳優の市民権が認められるようになった背景には、革命以前から活発に議論された演劇有用論がある。演劇には価値がある、有用であるという形で、演劇擁護論が展開された。演劇がいかに民衆の教育に役立ち、民衆に有益なものかを積極的に認めることによって、演劇の存在価値が高まり、あわせて俳優の社会的地位の向上につながったと言える。
3. 革命下の演劇
1791年に興行が自由化されると一時的に劇場の数が増えた。特権が否定されたことで、どの劇場でどの演目を上演してもいいという状況が生まれ、「俳優」も官許劇場だけに許された職業ではなくなった。
革命期に上演されていた作品は、革命政府が推奨する『ブルータス』『ウィリアム・テル』のような共和主義的なものや革命的な内容に改変された作品のほかに、モリエールやコルネイユのような古典劇の上演も多かった。またオペラ・コミックに代表される歌入り芝居は人気が高く、庶民が主役となる芝居やパロティなど、次代のメロドラマへと続く土壌も培われていった。
独占興行権もなくなり官許劇場による許認可の必要もなくなったことで上演形態の制限がなくなった。さらに革命前は、王の検閲官による戯曲の事前検閲を通らなければ上演できなかったが、革命後は基本的には検閲はなくなった。しかし次第に革命思想に合う合わないという判断を内務省や公安委員会が行うようになった。また当時は一般市民も上演中から批判合戦を繰り広げ、上演そのものを阻止する騒乱を起こしたり、パンフレット等で論戦を繰り広げたりしたため、作品がその影響を受けて、当時の革命世論に合ったものに改変されることもあった。
革命期に上演されていた作品は、革命政府が推奨する『ブルータス』『ウィリアム・テル』のような共和主義的なものや革命的な内容に改変された作品のほかに、モリエールやコルネイユのような古典劇の上演も多かった。またオペラ・コミックに代表される歌入り芝居は人気が高く、庶民が主役となる芝居やパロティなど、次代のメロドラマへと続く土壌も培われていった。
独占興行権もなくなり官許劇場による許認可の必要もなくなったことで上演形態の制限がなくなった。さらに革命前は、王の検閲官による戯曲の事前検閲を通らなければ上演できなかったが、革命後は基本的には検閲はなくなった。しかし次第に革命思想に合う合わないという判断を内務省や公安委員会が行うようになった。また当時は一般市民も上演中から批判合戦を繰り広げ、上演そのものを阻止する騒乱を起こしたり、パンフレット等で論戦を繰り広げたりしたため、作品がその影響を受けて、当時の革命世論に合ったものに改変されることもあった。
(1) 情報メディアとしての演劇(影響力の強さ)
テレビもない当時、演劇はビラやパンフレット以外の有効な情報ソースであり、その影響力の強さに演劇への関心は高かった。特に革命当初は革命思想伝播に演劇が一役買っていた。当時の劇場では、観客も受け身で観ているだけではなく、ヤジを飛ばし声を上げたりもする。その危険性から「ステッキなどの(武器になるものの)持込禁止」が掲げられるなど、劇場は論争の場でもあった。
(2)「習俗〈道徳〉の学校」〜教育手段としての演劇
革命政府は演劇のもつ影響力の強さに着目し、次第に革命思想にかなう演劇を見せることの有用性を主張、新しい国民を作るために革命に奉仕するものとして、演劇が規定されていった。影響力が強いということは、習俗を腐敗させる力も演劇は持っているわけだが、それに対しては演劇を純化すればいいという議論が展開された。
1792年頃までは革命も理想主義的で革命思想がゆるやかに伝播していけば新しい社会ができていくという楽観的な見方だった。それに対し1793年頃からは革命の理想と現実のギャップが問題になり、共和国という新しい社会にふさわしい新しい国民を作るための成人教育の有用な手段として、演劇と祭典は特に注目された。
1792年頃までは革命も理想主義的で革命思想がゆるやかに伝播していけば新しい社会ができていくという楽観的な見方だった。それに対し1793年頃からは革命の理想と現実のギャップが問題になり、共和国という新しい社会にふさわしい新しい国民を作るための成人教育の有用な手段として、演劇と祭典は特に注目された。
(3) 市民の祭り(革命祭典)
祭典はルソーが掲げた一つの理想であり、老若男女区別なく皆が集まって一つの想いと一つの時間を共有し、平等と多様性の空間の中での一体化を可能にするものだった。今で言う市民参加の理想に近い。演劇のように見る人とやる人が分化しないという意味でも、理想形として言及された。
さまざまな祭典が試みられたが、既存の全ての束縛や差異を超えて一つの国民という一体感を感じさせるほどの熱狂に至ったのは、革命勃発から1年後の1790年7月14日にパリで行われた全国連盟祭だけだった。連盟祭は、現在革命記念日にシャンゼリゼで行われる軍事パレードと近い内容で、革命に関わった連盟兵が一堂に会して革命の興奮を思い起こす、いわば革命の追体験の場だった。
勃発から1年経ち、少し冷静になったころの革命の祭典である連盟祭は、一つの理想を体現している。理念系としてはギリシアやローマの思想を受け継ぎ、市民が一堂に集って演劇に触れられる空間を目指していた。フランスの民衆演劇の出発点には、ギリシア・ローマへの憧憬、市民がみんな一つの空間で演劇を観られるというユートピアのイメージがある。現実には困難だったとはいえ、フランスの民衆演劇は、革命期の思想や革命期の一体感を、理想形としてずっと抱えてきた。1790年の連盟祭以降、連盟祭は毎年行われたが、90年の興奮は二度と戻ることはなかった。革命政府は革命の理想を体現するものとして、さらに「理性の祭典」そして「最高存在の祭典」を行ったが、革命の追体験と国民の一体化への試みは失敗する一方で、理想としての連盟祭の伝説化が進んだ。
このような祭典による革命の追体験と革命による新しい国民の創成、そして一体化への試みは、同じく革命によって成立した共産圏の国々で展開された行事とも類似している。革命期には演劇的要素の強いものもあったが、演劇的要素が強い場合、観衆はしかし必ずしも意図した方向へ導かれない、むしろ意図しない要素が付加されてしまいかねない。行進や革命歌のような単純な歌の合唱、マスゲームは一体感を高めるのにより効果的である。したがって演劇的要素は後退していった。
さまざまな祭典が試みられたが、既存の全ての束縛や差異を超えて一つの国民という一体感を感じさせるほどの熱狂に至ったのは、革命勃発から1年後の1790年7月14日にパリで行われた全国連盟祭だけだった。連盟祭は、現在革命記念日にシャンゼリゼで行われる軍事パレードと近い内容で、革命に関わった連盟兵が一堂に会して革命の興奮を思い起こす、いわば革命の追体験の場だった。
勃発から1年経ち、少し冷静になったころの革命の祭典である連盟祭は、一つの理想を体現している。理念系としてはギリシアやローマの思想を受け継ぎ、市民が一堂に集って演劇に触れられる空間を目指していた。フランスの民衆演劇の出発点には、ギリシア・ローマへの憧憬、市民がみんな一つの空間で演劇を観られるというユートピアのイメージがある。現実には困難だったとはいえ、フランスの民衆演劇は、革命期の思想や革命期の一体感を、理想形としてずっと抱えてきた。1790年の連盟祭以降、連盟祭は毎年行われたが、90年の興奮は二度と戻ることはなかった。革命政府は革命の理想を体現するものとして、さらに「理性の祭典」そして「最高存在の祭典」を行ったが、革命の追体験と国民の一体化への試みは失敗する一方で、理想としての連盟祭の伝説化が進んだ。
このような祭典による革命の追体験と革命による新しい国民の創成、そして一体化への試みは、同じく革命によって成立した共産圏の国々で展開された行事とも類似している。革命期には演劇的要素の強いものもあったが、演劇的要素が強い場合、観衆はしかし必ずしも意図した方向へ導かれない、むしろ意図しない要素が付加されてしまいかねない。行進や革命歌のような単純な歌の合唱、マスゲームは一体感を高めるのにより効果的である。したがって演劇的要素は後退していった。
4. まとめ
革命期のフランスの思想として、ルソーの一般意思、かみ砕いていえば国=共和国の考え方として、自分の意志で契約をして社会と結びついている、憲法等に承認を与える契約によって国民になっているという考え方が前提にある。フランスで国民といったときには、国民国家(nation)という民族的な帰属ではなく、「民衆(people)」という枠組みのない存在を考えている。日本語の「国民」とはニュアンスが異なる。
革命期が以降の演劇政策、文化政策、ひいては政治全般に与えた影響とは、根本にpublicという考え方をおくことだ。そのpublicのために政策を行う対象領域に演劇も含まれた。演劇を含めた芸術の享受の権利、知的財産の享受の権利について、フランスではずっと国民の権利の実現を担保するのは国の責務だと考えてきた。
そもそも議論がなされない日本とは異なり、フランスでは演劇を否定する議論も繰り返される中でそれに対抗して公的な場で演劇について議論し続けてきた。演劇関係者だけでなく、一般の思想家や文筆家や法律家、知識階級が真剣に議論していた。大衆にとっても演劇は身近なものであり、演劇有用論は業界の泣き言ではなく一般社会の大きなトピックとして語られていた。フランスにおいては、演劇の必要性の議論は、時代を超えて繰り返し主張されることが求められてきたのである。
日本で助成金問題を語るときにしばしば陥りがちなのは、「いいものを作っているんだから金をくれ」という作り手の論理である。それに対し、「享受すべき人が享受できない状況を改善するために補助してくれ」「一般市民の享受権を守るため」という論理で説明されるのがフランスである。その前提としてよいものを作る作り手の権利は尊重されるので、クリエイションにお金をかけないということに対して批判はなされる。
そういう文化政策が有効かどうか、例えば一般市民に還元されたかどうかを評価するのは、数量換算できないので非常に難しい。それでも調査は行われていて、例えば劇場に行く機会が増えたかどうか、集客率で計算している。しかし客が集まればいいという単純な話ではなく、劇場に行く機会がどれだけ増えるかが重要だ。
ヨーロッパの文化政策を参照するときに、補助金が多いのは王侯貴族のパトロネーゼがルーツだといわれることが多いが、だから今日も支援されているという単純な話ではない。publicという考え方によって主体の転換が起きた。王様から人々へと主体が変わったから今日の文化政策がある。革命以前と革命後では、演劇が誰のものか、何のためのものかという考え方について、大きな変化が起きたのだ。
革命期が以降の演劇政策、文化政策、ひいては政治全般に与えた影響とは、根本にpublicという考え方をおくことだ。そのpublicのために政策を行う対象領域に演劇も含まれた。演劇を含めた芸術の享受の権利、知的財産の享受の権利について、フランスではずっと国民の権利の実現を担保するのは国の責務だと考えてきた。
そもそも議論がなされない日本とは異なり、フランスでは演劇を否定する議論も繰り返される中でそれに対抗して公的な場で演劇について議論し続けてきた。演劇関係者だけでなく、一般の思想家や文筆家や法律家、知識階級が真剣に議論していた。大衆にとっても演劇は身近なものであり、演劇有用論は業界の泣き言ではなく一般社会の大きなトピックとして語られていた。フランスにおいては、演劇の必要性の議論は、時代を超えて繰り返し主張されることが求められてきたのである。
日本で助成金問題を語るときにしばしば陥りがちなのは、「いいものを作っているんだから金をくれ」という作り手の論理である。それに対し、「享受すべき人が享受できない状況を改善するために補助してくれ」「一般市民の享受権を守るため」という論理で説明されるのがフランスである。その前提としてよいものを作る作り手の権利は尊重されるので、クリエイションにお金をかけないということに対して批判はなされる。
そういう文化政策が有効かどうか、例えば一般市民に還元されたかどうかを評価するのは、数量換算できないので非常に難しい。それでも調査は行われていて、例えば劇場に行く機会が増えたかどうか、集客率で計算している。しかし客が集まればいいという単純な話ではなく、劇場に行く機会がどれだけ増えるかが重要だ。
ヨーロッパの文化政策を参照するときに、補助金が多いのは王侯貴族のパトロネーゼがルーツだといわれることが多いが、だから今日も支援されているという単純な話ではない。publicという考え方によって主体の転換が起きた。王様から人々へと主体が変わったから今日の文化政策がある。革命以前と革命後では、演劇が誰のものか、何のためのものかという考え方について、大きな変化が起きたのだ。

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.


