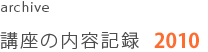


『ドキュメンタリー演劇とは何か』
Vol.3「ドキュメンタリーという手法」
2010年11月11日(水) 19時〜21時
谷岡 健彦
(東京工業大学准教授)
《所 感》
ドキュメンタリーは、分類の問題ではなく、手法の問題として思考することが重要である。演劇において何が虚構で何が真実かといった劇の本質に肉薄する重要な考察が、本講座において展開された。その手法とはドキュメンタリーにおいては、舞台で表現する以前に取材する人とされる人の関係性作りが舞台作品の根幹になっているという点であり、本講座において詳細に分析されている。
今年、フェスティバルトーキョーで上演された『HIROSHIMA-HAPCHEON:二つの都市をめぐる展覧会』(演出:松田正隆)は、俳優たちが展示された舞台である。俳優たちは、広島と広島で被爆した5万人もの韓国人の出身地であったハプチョンに赴き、取材した体験を演技で再現、報告する。その手法は、あまりに大きなかなしみの前に身動きが取れずにいる私たちに、現在の認識のレベルである局所的な思い出を共有することから関係性を構築しうることを示した。 方法と主題はいかに絡み合い、展開していくのか。本講座で行われた手法の分析は、演劇の理論的考察の礎となるものである。
ドキュメンタリーは、分類の問題ではなく、手法の問題として思考することが重要である。演劇において何が虚構で何が真実かといった劇の本質に肉薄する重要な考察が、本講座において展開された。その手法とはドキュメンタリーにおいては、舞台で表現する以前に取材する人とされる人の関係性作りが舞台作品の根幹になっているという点であり、本講座において詳細に分析されている。
今年、フェスティバルトーキョーで上演された『HIROSHIMA-HAPCHEON:二つの都市をめぐる展覧会』(演出:松田正隆)は、俳優たちが展示された舞台である。俳優たちは、広島と広島で被爆した5万人もの韓国人の出身地であったハプチョンに赴き、取材した体験を演技で再現、報告する。その手法は、あまりに大きなかなしみの前に身動きが取れずにいる私たちに、現在の認識のレベルである局所的な思い出を共有することから関係性を構築しうることを示した。 方法と主題はいかに絡み合い、展開していくのか。本講座で行われた手法の分析は、演劇の理論的考察の礎となるものである。
記録:塩田典子(早稲田大学大学院文学研究科芸術学演劇映像専攻日本演劇修士課程修了)

1. 写生とドキュメンタリー
1年ほど前から俳句を始めた。自分のような初心者は、先生や先輩から「写生を心がけなさい」、「頭の中だけで俳句を作ってはいけない」とよく言われる。「写生」とは、「現実をよく見て写し取ること」だが、これは「ドキュメンタリー」とどこか重なると考えている。
俳句の実作者であり、評論も書く仁平勝は「写生」について次のように述べている。「たぶん、俳人たちはあまり気づいていないが、近代俳句における写生とは、じつは取合せに新鮮さを求める方法意識から出てきたものだ」(「おとなの文学」、『俳句研究』夏の号)。仁平によると、写生とはあくまで方法の上での革新であり、現実をよく見ること自体は目的ではなく、良い俳句を作るための方法だという。 「写生」と「取合せ」について、俳人の岸本尚毅が実際に詠んだ句を例に考えてみたい。
俳句の実作者であり、評論も書く仁平勝は「写生」について次のように述べている。「たぶん、俳人たちはあまり気づいていないが、近代俳句における写生とは、じつは取合せに新鮮さを求める方法意識から出てきたものだ」(「おとなの文学」、『俳句研究』夏の号)。仁平によると、写生とはあくまで方法の上での革新であり、現実をよく見ること自体は目的ではなく、良い俳句を作るための方法だという。 「写生」と「取合せ」について、俳人の岸本尚毅が実際に詠んだ句を例に考えてみたい。
「雨だれの向かうは雨や×××××」
下の5文字を隠して引用した。最初の12文字だけで情景が頭に浮かんでくる、とても上手な句である。おそらく部屋の中にいて、軒先に大きな雨だれがあり、その向こうにしとしとと雨が降っているのだろう。これがこの句で詠まれていることの一つである。では「×××××」の部分にはどんな言葉が入るだろうか。
俳句は17文字しかないため、一つか二つのことしか詠めない。二つのことを「取合せ」て詠むことで、詩的情緒を生む。例えば、「雨」から想起して「濃紫陽花」(こあじさい)を取合せたとする。綺麗な句ではあるが、良い句だとは評価されないだろう。季節が夏であることしか伝わらず、世界がそれ以上に広がらない。次に、意表をついた語を入れてみる。「雨だれの向かうは雨や雪女」。これでは奇抜すぎて訳がわからない句になってしまう。
岸本が取合せたのは「蟻地獄」だ。まず、場所が明確になってくる。雨を眺めている人間がいる部屋は、高層マンションではなく、お寺かどこか縁の下のある建物だろうと情景が見えてきて、句の世界が広がっていく。また、「地獄」という言葉で、日常的な情景の中にちょっとした凄みを加えることもできる。当たり前のものでもなく、奇を衒ったものでもなく、ほどよい距離のものを取合せている。俳句は、頭の中だけで作ると、月並みか奇想天外なものになってしまう。現実をよく見ていないと新鮮な取合せは出てこない。写生のねらいは、詩の情緒がいちばん深まる取合せを見つけてくることにある。
では、演劇において「取合せ」とは何だろうか。劇作家や演出家が組み立ててゆくものすべて、つまり、物語の筋立て、人物や状況の設定、およびその見せ方などがそうだと言える。演劇の実作者が注意を払うところと、俳人が取合せで注意を払うところはある意味で似ている。月並みにも奇想天外なものにもならない新鮮さを獲得するための手法がドキュメンタリーなのではないかと考える。
本講座では、ドキュメンタリー演劇を、このように現実を描く上での方法、方法意識として考えてみたい。現実を描いていればドキュメンタリーというわけではなく、反対にドキュメンタリーでなければ、現実を描けないわけでもない。現実を描くには様々な方法があり、その一つがドキュメンタリーである。
俳句は17文字しかないため、一つか二つのことしか詠めない。二つのことを「取合せ」て詠むことで、詩的情緒を生む。例えば、「雨」から想起して「濃紫陽花」(こあじさい)を取合せたとする。綺麗な句ではあるが、良い句だとは評価されないだろう。季節が夏であることしか伝わらず、世界がそれ以上に広がらない。次に、意表をついた語を入れてみる。「雨だれの向かうは雨や雪女」。これでは奇抜すぎて訳がわからない句になってしまう。
岸本が取合せたのは「蟻地獄」だ。まず、場所が明確になってくる。雨を眺めている人間がいる部屋は、高層マンションではなく、お寺かどこか縁の下のある建物だろうと情景が見えてきて、句の世界が広がっていく。また、「地獄」という言葉で、日常的な情景の中にちょっとした凄みを加えることもできる。当たり前のものでもなく、奇を衒ったものでもなく、ほどよい距離のものを取合せている。俳句は、頭の中だけで作ると、月並みか奇想天外なものになってしまう。現実をよく見ていないと新鮮な取合せは出てこない。写生のねらいは、詩の情緒がいちばん深まる取合せを見つけてくることにある。
では、演劇において「取合せ」とは何だろうか。劇作家や演出家が組み立ててゆくものすべて、つまり、物語の筋立て、人物や状況の設定、およびその見せ方などがそうだと言える。演劇の実作者が注意を払うところと、俳人が取合せで注意を払うところはある意味で似ている。月並みにも奇想天外なものにもならない新鮮さを獲得するための手法がドキュメンタリーなのではないかと考える。
本講座では、ドキュメンタリー演劇を、このように現実を描く上での方法、方法意識として考えてみたい。現実を描いていればドキュメンタリーというわけではなく、反対にドキュメンタリーでなければ、現実を描けないわけでもない。現実を描くには様々な方法があり、その一つがドキュメンタリーである。
2. 英国におけるドキュメンタリー演劇
イギリスにおけるドキュメンタリー演劇は、英語でそのまま“documentary theatre”と呼ばれる。しかし最近は、インタヴューして出てきた言葉をそのまま使う作品が多いため、“verbatim theatre”という言葉も広く使われている。“verbatim”というのは「字義通りの」「一言一句忠実な」という意味で、取材テープに録音された言葉に忠実だということだ。
イギリスでドキュメンタリー演劇が広く注目を集めるようになったのは、1990年代の後半から2000年代に入ってからだ。もちろんさかのぼれば、1930年代からドキュメンタリー演劇は存在する。しかしイギリスには1968年まで上演台本の検閲があり、事前に宮内大臣へ台本を提出しなければならなかったため、時事的な題材を扱いづらかった。検閲撤廃後の70年代にはアートへの助成金も増え、優れた政治劇が創られるようになる。この時期から活躍しはじめたのが、劇作家のデヴィッド・エドガー(David Edgar)やデヴィッド・ヘアー(David Hare)で、彼らは、戦後のイギリスという国家の歩みを辿り、現在のイギリスはどのような状況にあるのかを思考する大規模な作品を創作していく。
デヴィッド・ヘアーの二つの作品に注目したい。ヘアーは1968年以降に演劇活動をスタートさせ、90年代前半に、Racing Demon(1990)、Murmuring Judges(1991)、The Absence of War(1993)の三部作を執筆している。
最後のThe Absence of Warは、三部作の中で最も現実の事件に肉薄した作品で、1992年に行われた総選挙での労働党の敗北を描いている。1979年に保守党のマーガレット・サッチャーが首相の座に就くが90年に退陣に追い込まれる。次の首相メイジャーは、2年後に総選挙を行うが、勝算があると思われた労働党は敗北を喫す。ヘアーは、総選挙時の労働党の選挙対策本部などを徹底的にリサーチし、党大会の様子や党首のスピーチをリアルに舞台上に作り上げた。
しかしヘアーはこの作品をドキュメンタリー演劇としては提示しなかった。フィクションや想像の要素を入れ、台詞も書き直している。また、当時の労働党党首ニール・キノック(Neil Kinnock)を、ジョージ・ジョーンズ(George Jones)という名前に変えている。
このような変更を加えたことに対して、ヘアーは「本当のストーリーではなく、出来合いのストーリーを語ることに何の意義があるのか、よく分からないからだ」と述べている。ここでいうストーリーとは、たんに「物語」という意味ではなく、劇の核心、劇作家の伝えたいことという意味で受け取ってほしい。「出来合いのストーリー」とは、勝つチャンスのあった労働党が負けたという周知の事実である。「本当のストーリー」とは、人間がいかに確信をもって誤った選択をしてしまうのか、90年代における社会主義とは何かといったことだ。ヘアーは現実から一歩離れて、現象の下に流れている別のレベルのドラマを語ろうとした。
現代日本の同系統の作品として、永井愛『歌わせたい男たち』(2005)が挙げられる。これは、都立高校の卒業式における君が代斉唱時不起立問題を主題にした大変すぐれた作品である。着任したての音楽教師、不起立を主張する教師、どうしても君が代を歌って欲しい校長の3人がドラマの軸となっている。永井愛は、この作品を書くにあたって、君が代不起立での処分取り消しを求めた裁判を傍聴し、綿密な取材を行っている。校長の台詞の一部には、裁判での証言が“verbatim”に使われている。
とはいえ、この作品もフィクションとして提示されている。たとえば、不起立を主張する教師は社会科担当と設定されているが、現実の都立高校で不起立を貫いている根津公子さんは、家庭科の教師である。「写生」をして、現実をよく見ると、思わぬ事実(家庭科の教員が不起立を貫いている)が見えてくるが、これをそのまま劇に仕立てようとすると、人物像が複雑になり、話の核が分散してしまう。政治に関心が高そうだというイメージのある社会科教師という設定にすることで、観客への説明の手間を省き、手際よくウェルメイドのコメディに仕上げている。
しかし単純化したせいで、失ったものもある。『歌わせたい男たち』は、フィクションであることが見えることで、「まさか現実のことではないだろう」、「きっとカリカチュアされているのだろう」と、観客に安心感を与えてしまう。また、フィクション化する過程で何かが抜け落ちていく可能性もある。本当に起きたことだという重みを伝えるには、別の語り口や表現方法を用いる必要があろう。
ヘアーが2003年に発表したThe Permanent Wayは、このような問題意識のもとにThe Absence of Warとは異なる手法で作られている。本作は、イギリスの国鉄民営化と、その後に続発した鉄道事故を描いているが、創作にあたって俳優による鉄道事故関係者(民営化に関わった人、鉄道会社の社長、事故で一命を取り留めた人、事故で家族を失った人、事故の原因を調査した人など)のインタヴューが行われた。そのさい、ヘアーと演出家はレコーダーの使用を禁じ、取材相手を注意深く観察し、どのような口調で、どのような身ぶりを交えて発言していたかを克明にメモし、記憶するよう指示した。俳優が集めてきた言葉を、ヘアーが上演台本へとまとめ、俳優は取材相手の言葉や表情などを極力正確に写し取って演じた。“verbatim”といっても、まず俳優の、次にヘアーの取捨選択を経るため、厳密な意味では一言一句ではないが、まずは主観を捨てて、素材として集められた言葉に寄り添うという方法がとられた点に注意しておこう。
本作は、インタヴューの言葉をもとにしたモノローグを積み重ねながら進行していく劇だが、ヘアーによると、たんに事実を並べた劇ではなく、ここにも「ストーリー」があるという。それは、犠牲者の遺族と生存者との間に生じる葛藤であり、これは当初予想もしていなかった主題だった。ヘアーは、意外性こそ優れたドキュメンタリーのしるしとしているが、他者の言葉に誠実に耳を傾けることによって思いもかけないストーリーが浮かび上がってきたのである。
イギリスでドキュメンタリー演劇が広く注目を集めるようになったのは、1990年代の後半から2000年代に入ってからだ。もちろんさかのぼれば、1930年代からドキュメンタリー演劇は存在する。しかしイギリスには1968年まで上演台本の検閲があり、事前に宮内大臣へ台本を提出しなければならなかったため、時事的な題材を扱いづらかった。検閲撤廃後の70年代にはアートへの助成金も増え、優れた政治劇が創られるようになる。この時期から活躍しはじめたのが、劇作家のデヴィッド・エドガー(David Edgar)やデヴィッド・ヘアー(David Hare)で、彼らは、戦後のイギリスという国家の歩みを辿り、現在のイギリスはどのような状況にあるのかを思考する大規模な作品を創作していく。
デヴィッド・ヘアーの二つの作品に注目したい。ヘアーは1968年以降に演劇活動をスタートさせ、90年代前半に、Racing Demon(1990)、Murmuring Judges(1991)、The Absence of War(1993)の三部作を執筆している。
最後のThe Absence of Warは、三部作の中で最も現実の事件に肉薄した作品で、1992年に行われた総選挙での労働党の敗北を描いている。1979年に保守党のマーガレット・サッチャーが首相の座に就くが90年に退陣に追い込まれる。次の首相メイジャーは、2年後に総選挙を行うが、勝算があると思われた労働党は敗北を喫す。ヘアーは、総選挙時の労働党の選挙対策本部などを徹底的にリサーチし、党大会の様子や党首のスピーチをリアルに舞台上に作り上げた。
しかしヘアーはこの作品をドキュメンタリー演劇としては提示しなかった。フィクションや想像の要素を入れ、台詞も書き直している。また、当時の労働党党首ニール・キノック(Neil Kinnock)を、ジョージ・ジョーンズ(George Jones)という名前に変えている。
このような変更を加えたことに対して、ヘアーは「本当のストーリーではなく、出来合いのストーリーを語ることに何の意義があるのか、よく分からないからだ」と述べている。ここでいうストーリーとは、たんに「物語」という意味ではなく、劇の核心、劇作家の伝えたいことという意味で受け取ってほしい。「出来合いのストーリー」とは、勝つチャンスのあった労働党が負けたという周知の事実である。「本当のストーリー」とは、人間がいかに確信をもって誤った選択をしてしまうのか、90年代における社会主義とは何かといったことだ。ヘアーは現実から一歩離れて、現象の下に流れている別のレベルのドラマを語ろうとした。
現代日本の同系統の作品として、永井愛『歌わせたい男たち』(2005)が挙げられる。これは、都立高校の卒業式における君が代斉唱時不起立問題を主題にした大変すぐれた作品である。着任したての音楽教師、不起立を主張する教師、どうしても君が代を歌って欲しい校長の3人がドラマの軸となっている。永井愛は、この作品を書くにあたって、君が代不起立での処分取り消しを求めた裁判を傍聴し、綿密な取材を行っている。校長の台詞の一部には、裁判での証言が“verbatim”に使われている。
とはいえ、この作品もフィクションとして提示されている。たとえば、不起立を主張する教師は社会科担当と設定されているが、現実の都立高校で不起立を貫いている根津公子さんは、家庭科の教師である。「写生」をして、現実をよく見ると、思わぬ事実(家庭科の教員が不起立を貫いている)が見えてくるが、これをそのまま劇に仕立てようとすると、人物像が複雑になり、話の核が分散してしまう。政治に関心が高そうだというイメージのある社会科教師という設定にすることで、観客への説明の手間を省き、手際よくウェルメイドのコメディに仕上げている。
しかし単純化したせいで、失ったものもある。『歌わせたい男たち』は、フィクションであることが見えることで、「まさか現実のことではないだろう」、「きっとカリカチュアされているのだろう」と、観客に安心感を与えてしまう。また、フィクション化する過程で何かが抜け落ちていく可能性もある。本当に起きたことだという重みを伝えるには、別の語り口や表現方法を用いる必要があろう。
ヘアーが2003年に発表したThe Permanent Wayは、このような問題意識のもとにThe Absence of Warとは異なる手法で作られている。本作は、イギリスの国鉄民営化と、その後に続発した鉄道事故を描いているが、創作にあたって俳優による鉄道事故関係者(民営化に関わった人、鉄道会社の社長、事故で一命を取り留めた人、事故で家族を失った人、事故の原因を調査した人など)のインタヴューが行われた。そのさい、ヘアーと演出家はレコーダーの使用を禁じ、取材相手を注意深く観察し、どのような口調で、どのような身ぶりを交えて発言していたかを克明にメモし、記憶するよう指示した。俳優が集めてきた言葉を、ヘアーが上演台本へとまとめ、俳優は取材相手の言葉や表情などを極力正確に写し取って演じた。“verbatim”といっても、まず俳優の、次にヘアーの取捨選択を経るため、厳密な意味では一言一句ではないが、まずは主観を捨てて、素材として集められた言葉に寄り添うという方法がとられた点に注意しておこう。
本作は、インタヴューの言葉をもとにしたモノローグを積み重ねながら進行していく劇だが、ヘアーによると、たんに事実を並べた劇ではなく、ここにも「ストーリー」があるという。それは、犠牲者の遺族と生存者との間に生じる葛藤であり、これは当初予想もしていなかった主題だった。ヘアーは、意外性こそ優れたドキュメンタリーのしるしとしているが、他者の言葉に誠実に耳を傾けることによって思いもかけないストーリーが浮かび上がってきたのである。
3.スコットランド国立劇場の Black Watch (2006)
作 Gregory Burke(1968-) 演出 John Tiffany 演出補 Steven Hoggett
作 Gregory Burke(1968-) 演出 John Tiffany 演出補 Steven Hoggett
次にスコットランド国立劇場が2006年に創ったBlack Watchという作品を見ていきたい。「ブラック・ウォッチ」とは、日本で「スコットランド高地連隊」と訳される部隊の名称であり、イギリス陸軍の中で最も精強をうたわれた連隊である。この連隊は2004年にイラクのファルージャに派遣され、アメリカ海兵隊と共同作戦を取ったさい、現地で自爆攻撃に遇い兵士3人を失った。この作品は、その時現場にいた兵士たちへのインタヴューをもとにつくられている。
この作品の興味深いところは、劇作家が兵士たちにインタヴューを行う場面自体が作中に織り込まれ、ドキュメンタリー演劇を創るさいの困難も描かれているところだ。例えば、レコーダーを手にした作家にイラクでの経験について尋ねられた兵士は、「イラクがどんなところか知りたければ、バグダッドに行けばいいじゃないか」と敵意を向ける。また、兵士がマイクを意識して、インタヴュアーの期待に合わせた受け答えをする場面もあるし、さらには兵士から、「劇作家としての自分の名前を高めるために俺たちを利用しているのだろう」と詰め寄られる場面もある。このように、インタヴューが上手くいかないことを描く場面が随所に挿入され、そう簡単に人間は真実を話すものではないことが示される。
インタヴューを困難にしている原因のひとつに、劇中に登場する劇作家が中産階級出身だということが挙げられる。本作を書いた劇作家グレゴリー・バークは、「無神経な中産階級の劇作家」という虚構の人物を創り上げたと述べており、作中の劇作家と兵士たちの階級の違いは、話される言葉遣いに端的に表現されている。なお、この作家はバーク本人ではない。実際にバークが行ったインタヴューは、パブで兵士たちと一緒に酒を飲み、彼らから聞いた言葉をトイレに立ったときにメモするという方法で行われており、無神経にレコーダーを置いて質問するようなことはしていない。またバークは労働者階級出身で、親戚にブラック・ウォッチの兵士がいたこともあり、かなりの程度兵士たちの信頼を得ていた。
本作には虚構の部分も含まれているが、広い意味での「ドキュメンタリー演劇」に入るだろう。フィクションの部分とバークが丁寧に拾い上げた実際の言葉は、本当に起こったことだという重みをきちんと観客に伝えられるだけの真正さを生み出し、この劇の力強さとなっている。
この作品の興味深いところは、劇作家が兵士たちにインタヴューを行う場面自体が作中に織り込まれ、ドキュメンタリー演劇を創るさいの困難も描かれているところだ。例えば、レコーダーを手にした作家にイラクでの経験について尋ねられた兵士は、「イラクがどんなところか知りたければ、バグダッドに行けばいいじゃないか」と敵意を向ける。また、兵士がマイクを意識して、インタヴュアーの期待に合わせた受け答えをする場面もあるし、さらには兵士から、「劇作家としての自分の名前を高めるために俺たちを利用しているのだろう」と詰め寄られる場面もある。このように、インタヴューが上手くいかないことを描く場面が随所に挿入され、そう簡単に人間は真実を話すものではないことが示される。
インタヴューを困難にしている原因のひとつに、劇中に登場する劇作家が中産階級出身だということが挙げられる。本作を書いた劇作家グレゴリー・バークは、「無神経な中産階級の劇作家」という虚構の人物を創り上げたと述べており、作中の劇作家と兵士たちの階級の違いは、話される言葉遣いに端的に表現されている。なお、この作家はバーク本人ではない。実際にバークが行ったインタヴューは、パブで兵士たちと一緒に酒を飲み、彼らから聞いた言葉をトイレに立ったときにメモするという方法で行われており、無神経にレコーダーを置いて質問するようなことはしていない。またバークは労働者階級出身で、親戚にブラック・ウォッチの兵士がいたこともあり、かなりの程度兵士たちの信頼を得ていた。
本作には虚構の部分も含まれているが、広い意味での「ドキュメンタリー演劇」に入るだろう。フィクションの部分とバークが丁寧に拾い上げた実際の言葉は、本当に起こったことだという重みをきちんと観客に伝えられるだけの真正さを生み出し、この劇の力強さとなっている。

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.


