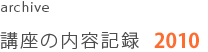


『ドキュメンタリー演劇とは何か』
Vol.2「ドイツにおけるドキュメンタリー演劇、その背景と歴史:リミニ・プロトコル(と)の仕事を手がかりに」
2010年10月28日(木) 19時〜21時
萩原 健
(明治大学国際日本学部専任講師)
《所 感》
「パフォーマンスとしてのレクチャーをめざす」という講師の言葉通り、豊富な映像を通して歴史的経緯を紐解きながら、実際に自らが関わった制作の現場体験を交えてドキュメンタリー演劇の本質に迫ろうとする本レクチャーは、2時間という時間の長さを感じさせないものであった。ドイツのドキュメンタリー演劇には、近過去と同時代に対する強い問題意識が伝統的にあったが、2000年代の新しい動きにはメディアテクノロジーの発展と「現実」の捉え方の変化が関与しているとの指摘は実感できる。新たに問われているのは、グローバル化が進む社会の意識構造そのものの変化なのである。講師の言うように、この新たなドキュメンタリー演劇はかつての声高な批判ではなく、「当事者」として参加することで自分自身に「現実」とは何かを問う試みといえよう。「演劇」の可能性はその枠組そのものを問うことにあるとよく言われるが、その実例として、今回のレクチャーは大変示唆的であった。
「パフォーマンスとしてのレクチャーをめざす」という講師の言葉通り、豊富な映像を通して歴史的経緯を紐解きながら、実際に自らが関わった制作の現場体験を交えてドキュメンタリー演劇の本質に迫ろうとする本レクチャーは、2時間という時間の長さを感じさせないものであった。ドイツのドキュメンタリー演劇には、近過去と同時代に対する強い問題意識が伝統的にあったが、2000年代の新しい動きにはメディアテクノロジーの発展と「現実」の捉え方の変化が関与しているとの指摘は実感できる。新たに問われているのは、グローバル化が進む社会の意識構造そのものの変化なのである。講師の言うように、この新たなドキュメンタリー演劇はかつての声高な批判ではなく、「当事者」として参加することで自分自身に「現実」とは何かを問う試みといえよう。「演劇」の可能性はその枠組そのものを問うことにあるとよく言われるが、その実例として、今回のレクチャーは大変示唆的であった。
記録:柴田隆子(学習院大学大学院人文科学研究科博士後期課程在学)

0. イントロダクション
近年注目されている〈ドキュメンタリー演劇〉と呼ばれるもののうちには、戯曲や劇場、ひいては俳優といった既成の枠組みを離れてリアリティーを追求するものがしばしばある。その代表格がドイツのリミニ・プロトコルの作品群だろう。ただ、彼らの作品は突然生まれたわけではなく、ドイツにはそれ以前に、ドキュメンタリー的な演劇を生む背景や歴史があった。本レクチャーでは、サブタイトルが示すように、リミニ・プロトコルの日本公演で通訳および字幕翻訳・制作・操作を務めた講師自身の経験に基づく情報を織り交ぜつつ、ドイツの演劇におけるドキュメンタリー的な演劇の背景と歴史について考察する。
リミニ・プロトコルは三人の演出家をコア・メンバーとするグループで、その詳しい制作方法については後述するが、彼らの狙いは、メンバーのダニエル・ヴェツェル(Daniel Wetzel)が『カール・マルクス:資本論、第一巻 東京ヴァージョン』(2009)公演時のインタヴューで語ったところによると、「現場に居合わせた人みんなでいっしょに考える場所」の創造であり、同じくメンバーのヘルガルド・ハウグ(Helgard Haug)によれば、「〈遊び〉の可能性を発見し観客と新しい関係をつくる」ことだという。こうした理念の点で少なからず共通する先行例として、たとえばアメリカのリヴィング・シアター(Living Theater)が思い起こされるが、まさに同劇団の演出家、ジュディス・マリーナ(Judith Malina)を招いて2006年にベルリーンのドイツ芸術アカデミーで開かれたシンポジウム、「ジュディス・マリーナ〜政治演劇のパイオニア」にヴェツェルはパネリストの一人として参加している。そして、マリーナはここで、彼女の恩師であり、1940年代に亡命してニューヨークの演劇学校〈ドラマティック・ワークショップ〉を率いていた演出家、エルヴィーン・ピスカートア(Erwin Piscator)からの影響を強調しているが、このピスカートアこそ、ドイツのドキュメンタリー(的)演劇を語る上で避けて通ることのできない人物である。その仕事は1920年代に始まる。
リミニ・プロトコルは三人の演出家をコア・メンバーとするグループで、その詳しい制作方法については後述するが、彼らの狙いは、メンバーのダニエル・ヴェツェル(Daniel Wetzel)が『カール・マルクス:資本論、第一巻 東京ヴァージョン』(2009)公演時のインタヴューで語ったところによると、「現場に居合わせた人みんなでいっしょに考える場所」の創造であり、同じくメンバーのヘルガルド・ハウグ(Helgard Haug)によれば、「〈遊び〉の可能性を発見し観客と新しい関係をつくる」ことだという。こうした理念の点で少なからず共通する先行例として、たとえばアメリカのリヴィング・シアター(Living Theater)が思い起こされるが、まさに同劇団の演出家、ジュディス・マリーナ(Judith Malina)を招いて2006年にベルリーンのドイツ芸術アカデミーで開かれたシンポジウム、「ジュディス・マリーナ〜政治演劇のパイオニア」にヴェツェルはパネリストの一人として参加している。そして、マリーナはここで、彼女の恩師であり、1940年代に亡命してニューヨークの演劇学校〈ドラマティック・ワークショップ〉を率いていた演出家、エルヴィーン・ピスカートア(Erwin Piscator)からの影響を強調しているが、このピスカートアこそ、ドイツのドキュメンタリー(的)演劇を語る上で避けて通ることのできない人物である。その仕事は1920年代に始まる。
1. 1920年代のドイツ
1920年代のドイツでは、第一次世界大戦(1914-18)や、その後に成立した初の民主国家であるワイマール共和国の問題が演劇において多く描かれた。特に20年代末、政治的なテーマを扱う〈時事劇(ZeitstÜck〉が盛んに書かれたが、なかでもエルンスト・トラー(Ernst Toller)の『どっこい、おれたちは生きている! Hoppla, wir leben!』(1927)が有名である。トラーは第一次世界大戦後に革命家として活動し、大逆罪で逮捕拘留された。その後、すっかり変わってしまった世間への驚きを自伝的な作品として描き、『ボイラーの火を消せ Feuer aus den Kesseln』(1930)でも第一次世界大戦とドイツ革命を描いている。同様にフリードリヒ・ヴォルフ(Friedrich Wolf)は『カタロの水兵たち Die Matrosen von Cattaro』(1930)でドイツ海軍の蜂起をテーマにしているが、ヴォルフの作品には他に、堕胎法と貧困の関係を問題にした『青酸カリ Cyankali』(1929)や、貧困層における中国革命を扱った『タイ・ヤンは目覚める Tai Yang erwacht』(1930)などの作品がある。
時事劇のテーマは、ブライアン・バートン(Brian Barton)『記録演劇 Das Dokumentartheater』(1987、「ドキュメンタリー演劇」の訳も可)によれば、大きく三つ、「戦争と革命」「裁判」「社会問題」がある。「戦争と革命」を描いたトラーやヴォルフの作品の他、「裁判」のテーマではクレデ(Carl Credé)の『刑法218条 §218』(1929)、「社会問題」では青少年の厚生の問題を扱ったランペル(Peter Martin Lampel)の『感化院の暴動 Revolte im Erziehungshaus』(1930)などが挙げられる。
こうした作品を好んで演出したのが、第一次世界大戦に従軍後、革命思想に心酔した演出家、ピスカートアである。『どっこい、おれたちは生きている!』の演出では、三階建ての舞台装置を組み、中央をはさんで左右に三階に区切られた小舞台の前面に紗幕が下りる仕掛けを作り、そこにいわば〈現実の断片〉として、第一次世界大戦時の映像や、同時代のベルリーンの街の様子などの映像を投影した。『タイ・ヤンは目覚める』の演出では、経済的な理由から(1929年に世界恐慌)そこまで大掛かりな装置は実現できなかったものの、幟に統計やスローガンを描くことで、〈現実〉を舞台に持ち込もうと試みた。その後、ナチスの台頭を受けてニューヨークに亡命した彼は、当地に演劇学校を開いたが、これが〈ドラマティック・ワークショップ〉で、テネシー・ウィリアムズ、アーサー・ミラー、マーロン・ブランド、トニー・カーチスらを輩出している。そして教え子の一人、マリーナは先述の2006年のシンポジウムで、演劇は俳優の自己主張の場ではなく、何かをコミュニケートするもの、伝え渡すものだということをピスカートアが教えてくれた、と述べている。虚構ではなく、〈現実〉すなわち観衆の実際の生活世界を常に主眼に置いていたピスカートアの取り組みを裏付ける発言だろう。
ピスカートアが先駆となり、その後、職業俳優ではなく、労働者を主な担い手として発展したアジプロ演劇は、近年になって評価されるようになったが、当時は、労働者の集会所や酒場で口上・寸劇・演奏などの形態が入り混じって上演されたため、いわゆる演劇とは似て非なるものと考えられていた。制作方法も、戯曲を制作の出発点にする従来の手法とは異なっていた。まず〈アジプロ隊〉と呼ばれる団体の素人俳優が、同じ労働者階級の人々に取材し、インタビューの記録をつくる。次にそれを会議にかけ、劇作家も加えて、寸劇に仕立てていく、というものであった。これは確かに現実の出来事の〈再現〉ではあるが、同じ労働者階級によって演じられたという点で、限りなく現実の出来事に近いものが上演で示されたといえる。なお、当時、労働者演劇の研究のためドイツに渡った千田是也が、劇作家・演出家・俳優であるヴァンゲンハイムの率いるアジプロ隊の集団制作に参加していたことが知られている。
時事劇のテーマは、ブライアン・バートン(Brian Barton)『記録演劇 Das Dokumentartheater』(1987、「ドキュメンタリー演劇」の訳も可)によれば、大きく三つ、「戦争と革命」「裁判」「社会問題」がある。「戦争と革命」を描いたトラーやヴォルフの作品の他、「裁判」のテーマではクレデ(Carl Credé)の『刑法218条 §218』(1929)、「社会問題」では青少年の厚生の問題を扱ったランペル(Peter Martin Lampel)の『感化院の暴動 Revolte im Erziehungshaus』(1930)などが挙げられる。
こうした作品を好んで演出したのが、第一次世界大戦に従軍後、革命思想に心酔した演出家、ピスカートアである。『どっこい、おれたちは生きている!』の演出では、三階建ての舞台装置を組み、中央をはさんで左右に三階に区切られた小舞台の前面に紗幕が下りる仕掛けを作り、そこにいわば〈現実の断片〉として、第一次世界大戦時の映像や、同時代のベルリーンの街の様子などの映像を投影した。『タイ・ヤンは目覚める』の演出では、経済的な理由から(1929年に世界恐慌)そこまで大掛かりな装置は実現できなかったものの、幟に統計やスローガンを描くことで、〈現実〉を舞台に持ち込もうと試みた。その後、ナチスの台頭を受けてニューヨークに亡命した彼は、当地に演劇学校を開いたが、これが〈ドラマティック・ワークショップ〉で、テネシー・ウィリアムズ、アーサー・ミラー、マーロン・ブランド、トニー・カーチスらを輩出している。そして教え子の一人、マリーナは先述の2006年のシンポジウムで、演劇は俳優の自己主張の場ではなく、何かをコミュニケートするもの、伝え渡すものだということをピスカートアが教えてくれた、と述べている。虚構ではなく、〈現実〉すなわち観衆の実際の生活世界を常に主眼に置いていたピスカートアの取り組みを裏付ける発言だろう。
ピスカートアが先駆となり、その後、職業俳優ではなく、労働者を主な担い手として発展したアジプロ演劇は、近年になって評価されるようになったが、当時は、労働者の集会所や酒場で口上・寸劇・演奏などの形態が入り混じって上演されたため、いわゆる演劇とは似て非なるものと考えられていた。制作方法も、戯曲を制作の出発点にする従来の手法とは異なっていた。まず〈アジプロ隊〉と呼ばれる団体の素人俳優が、同じ労働者階級の人々に取材し、インタビューの記録をつくる。次にそれを会議にかけ、劇作家も加えて、寸劇に仕立てていく、というものであった。これは確かに現実の出来事の〈再現〉ではあるが、同じ労働者階級によって演じられたという点で、限りなく現実の出来事に近いものが上演で示されたといえる。なお、当時、労働者演劇の研究のためドイツに渡った千田是也が、劇作家・演出家・俳優であるヴァンゲンハイムの率いるアジプロ隊の集団制作に参加していたことが知られている。
2. 1960年代の西ドイツ
その後、アジプロ隊による演劇はナチスによる弾圧を受けて消滅、同様のドキュメンタリー的な演劇がドイツに現れるのは1960年代になってからのことである。これが西ドイツ(当時)で主に制作された〈記録演劇 Dokumentartheater〉と呼ばれる演劇で、さきのバートンはそのテーマを以下の六つに分類する。①ロルフ・ホーホフート(Rolf Hochhuth)の『神の代理人 Der Stellvertreter』(1962)やペーター・ヴァイス(Peter Weiss)の『追究 Die Ermittlung』(1965)に描かれたような「第三帝国による支配と暴力」、②英国首相チャーチルの無差別爆撃を問題にした同じホーホフートの『兵士たち Die Soldaten』(1967)にある「戦争とモラル」の問題、③ハイナー・キップハルト(Heinar Kipphardt)『オッペンハイマー事件 In der Sache J. Robert Oppenheimer』(1964)での「核兵器時代の科学者の責任」、④ヴァイス『ヴェトナム討論 Vietnam-Diskurs』(1968)で問題とされた「帝国主義に対する抵抗」、⑤マックス・フォン・デア・グリューン(Max von der Grü
n)『非常事態 又は 街頭演劇がやってくる Notstand oder Das Straßentheater kommt』(1969)のように既存の劇場の外で上演されることもあった「西ドイツの憲法と民主主義」のテーマ、そして⑥ドルスト(Tankred Dorst)『トラー Toller』(1968)にみるような「革命の可能性」である。
こうしたテーマの背景には、近い過去にナチス・ドイツ、同時代にベルリーンの壁の建設やキューバ危機に象徴される東西の冷戦、原水爆実験を始めとする核開発といった社会状況が挙げられる。〈ドキュメンタリー〉の概念が演劇において前景に出てくるのはこの時代からだが、その先駆けとなったのがホーホフートの『神の代理人』である。第二次大戦中のローマ法王、ピウス12世を主人公にしたこの作品は、法王がナチス・ドイツのユダヤ人迫害を批判しなかったことを問題にし、現実主義者の法王に対して、フィクションの理想主義者の神父をカウンターパートにし、その対立を描いている。
ドキュメンタリー演劇のモデルとして、バートンはこうした「古典的な範型でのドキュメント」のほか、「叙事演劇のアダプション」と「世界史(的)プロセスへの介入」を挙げる。前者の例とされるキップハルト『オッペンハイマー事件』は、原爆を開発した科学者が告発される経緯、および〈国家〉と〈個人の研究の自由〉との葛藤を描いたもので、ブレヒトの『ガリレイの生涯』に通じる構造をもつ。「世界史(的)プロセスへの介入」とは、作品を上演することによって同時代の社会現象に影響を与えうることを意味する。たとえばヴァイスの『追究』は、アウシュヴィッツの問題を、当時まさに行われていたアウシュヴィッツ裁判での証言という形式で描き出し、これが東西ドイツを問わず、十数の劇場で同時上演されたことで、少なからぬ影響が同時代のドイツ社会に及んだ。そして『神の代理人』『オッペンハイマー事件』『追究』の3作品をいち早く見出し、演出したのもまたピスカートアであった。
こうしたテーマの背景には、近い過去にナチス・ドイツ、同時代にベルリーンの壁の建設やキューバ危機に象徴される東西の冷戦、原水爆実験を始めとする核開発といった社会状況が挙げられる。〈ドキュメンタリー〉の概念が演劇において前景に出てくるのはこの時代からだが、その先駆けとなったのがホーホフートの『神の代理人』である。第二次大戦中のローマ法王、ピウス12世を主人公にしたこの作品は、法王がナチス・ドイツのユダヤ人迫害を批判しなかったことを問題にし、現実主義者の法王に対して、フィクションの理想主義者の神父をカウンターパートにし、その対立を描いている。
ドキュメンタリー演劇のモデルとして、バートンはこうした「古典的な範型でのドキュメント」のほか、「叙事演劇のアダプション」と「世界史(的)プロセスへの介入」を挙げる。前者の例とされるキップハルト『オッペンハイマー事件』は、原爆を開発した科学者が告発される経緯、および〈国家〉と〈個人の研究の自由〉との葛藤を描いたもので、ブレヒトの『ガリレイの生涯』に通じる構造をもつ。「世界史(的)プロセスへの介入」とは、作品を上演することによって同時代の社会現象に影響を与えうることを意味する。たとえばヴァイスの『追究』は、アウシュヴィッツの問題を、当時まさに行われていたアウシュヴィッツ裁判での証言という形式で描き出し、これが東西ドイツを問わず、十数の劇場で同時上演されたことで、少なからぬ影響が同時代のドイツ社会に及んだ。そして『神の代理人』『オッペンハイマー事件』『追究』の3作品をいち早く見出し、演出したのもまたピスカートアであった。
3. 2000年代のドイツのドキュメンタリー演劇
記録演劇の波はしかし、まもなく現れた、シャウビューネの一連の演出家たちに代表される1970年代の若手の創り手の台頭とともに引いていく。そして再びドキュメンタリー演劇という言葉がしばしば口にされるようになったのが、近年、つまり2000年代である。
この時期に注目を集めたものとして、たとえばアンドレス・ファイエル(Andres Veiel)の『キック Der Kick』がある。この作品は、2002年にマスコミの耳目を集めた旧東独のネオナチ少年による殺人事件を題材に、マスコミの報道姿勢への疑問から独自にインタビューを重ねて制作され、舞台、映画、小説のヴァージョンで発表されている。背景には、近い過去として東西ドイツの分断、同時代の社会状況として若年者の失業やネオナチなどの問題があり、その意味で、これまでのドキュメンタリーの流れを汲むものである。ただし、インタビューを集めたという意味でアジプロ演劇的な要素があるが、職業俳優によって演じられたため、現実の出来事と上演との距離が大きい作品といえる。
一方、このようなシリアスな問題意識を正攻法で処理するアプローチと異なり、同じ2000年代には、まったくタッチの異なる新たなドキュメンタリー演劇が生まれていることが注目される。その例として挙げられるのがリミニ・プロトコルやクリス・コンデック(Chris Kondek)である。内容的にユーモアを感じさせるもので、職業俳優よりもむしろ、作品のテーマとなる事実に関わる当事者本人が俳優となって演じ、またそのテーマについて、受け手である観客が同じ時空間でともに考えることが目指されている。たとえばコンデックの『デッド・キャット・バウンス Dead Cat Bounce』は、舞台に、株式市場という、リアルタイムで展開する劇場外の出来事を接続したものだが(これが可能になった背景として2000年代の通信技術の発達があることは見逃せない)、観客を実際に株の売り買いに参加させることで、観客が当事者化する事態も生じている。
同様、リミニ・プロトコルの場合でも、虚構の役を誰かに演じてもらうことはない。そこでは、フィクションの出来事が示されるのではなく、扇田昭彦の言を借りると「当事者本人が自分の過去の行為と体験を、事実に即して語る」のである。たとえば日本での公演『カール・マルクス:資本論、第一巻 東京ヴァージョン』(2009.2)では、8人のドイツヴァージョンの出演者に加え、更に日本の当事者とされる4人が追加されたが、選出の基準となったのは、『資本論』に通じたエキスパートであること、あるいは『資本論』に書かれた内容とその人物の生き様が重なることであり、キャスティングのためのインタビューの内容が、同時に作品の内容につながっていった(なおドイツヴァージョンの制作ではおよそ100人がインタビューを受けたという)。『Cargo Tokyo-Yokohama』(2009.11)では、パフォーマーであるトラックの運転手は就職情報誌を通じて募集された。ヨーロッパヴァージョンでの、〈ブルガリア人のドライバー〉による〈国境越え〉という2つの要素を加えるために、ブラジル人のコミュニティーにも募集がかけられた(そこには日系ブラジル人の雇用問題も含みこまれている)。テクストは毎日変わり、英語とドイツ語で書かれた台詞テクストと、ト書きとタイムスケジュールを兼ねる構成表が、日本語に翻訳され(ブラジル人ドライバーのために一部ローマ字表記)、翌日の稽古の時間までに演出家の手元に戻された。こうしてみると、作品作りの手法は1920年代のアジプロ演劇のそれに限りなく近いが、準備の周到さの点ではそうであっても、作り手の政治的主張を押し付けず、受け手に主体的に考えさせるという点では異なる。
この時期に注目を集めたものとして、たとえばアンドレス・ファイエル(Andres Veiel)の『キック Der Kick』がある。この作品は、2002年にマスコミの耳目を集めた旧東独のネオナチ少年による殺人事件を題材に、マスコミの報道姿勢への疑問から独自にインタビューを重ねて制作され、舞台、映画、小説のヴァージョンで発表されている。背景には、近い過去として東西ドイツの分断、同時代の社会状況として若年者の失業やネオナチなどの問題があり、その意味で、これまでのドキュメンタリーの流れを汲むものである。ただし、インタビューを集めたという意味でアジプロ演劇的な要素があるが、職業俳優によって演じられたため、現実の出来事と上演との距離が大きい作品といえる。
一方、このようなシリアスな問題意識を正攻法で処理するアプローチと異なり、同じ2000年代には、まったくタッチの異なる新たなドキュメンタリー演劇が生まれていることが注目される。その例として挙げられるのがリミニ・プロトコルやクリス・コンデック(Chris Kondek)である。内容的にユーモアを感じさせるもので、職業俳優よりもむしろ、作品のテーマとなる事実に関わる当事者本人が俳優となって演じ、またそのテーマについて、受け手である観客が同じ時空間でともに考えることが目指されている。たとえばコンデックの『デッド・キャット・バウンス Dead Cat Bounce』は、舞台に、株式市場という、リアルタイムで展開する劇場外の出来事を接続したものだが(これが可能になった背景として2000年代の通信技術の発達があることは見逃せない)、観客を実際に株の売り買いに参加させることで、観客が当事者化する事態も生じている。
同様、リミニ・プロトコルの場合でも、虚構の役を誰かに演じてもらうことはない。そこでは、フィクションの出来事が示されるのではなく、扇田昭彦の言を借りると「当事者本人が自分の過去の行為と体験を、事実に即して語る」のである。たとえば日本での公演『カール・マルクス:資本論、第一巻 東京ヴァージョン』(2009.2)では、8人のドイツヴァージョンの出演者に加え、更に日本の当事者とされる4人が追加されたが、選出の基準となったのは、『資本論』に通じたエキスパートであること、あるいは『資本論』に書かれた内容とその人物の生き様が重なることであり、キャスティングのためのインタビューの内容が、同時に作品の内容につながっていった(なおドイツヴァージョンの制作ではおよそ100人がインタビューを受けたという)。『Cargo Tokyo-Yokohama』(2009.11)では、パフォーマーであるトラックの運転手は就職情報誌を通じて募集された。ヨーロッパヴァージョンでの、〈ブルガリア人のドライバー〉による〈国境越え〉という2つの要素を加えるために、ブラジル人のコミュニティーにも募集がかけられた(そこには日系ブラジル人の雇用問題も含みこまれている)。テクストは毎日変わり、英語とドイツ語で書かれた台詞テクストと、ト書きとタイムスケジュールを兼ねる構成表が、日本語に翻訳され(ブラジル人ドライバーのために一部ローマ字表記)、翌日の稽古の時間までに演出家の手元に戻された。こうしてみると、作品作りの手法は1920年代のアジプロ演劇のそれに限りなく近いが、準備の周到さの点ではそうであっても、作り手の政治的主張を押し付けず、受け手に主体的に考えさせるという点では異なる。
4. ドキュメンタリー演劇の今後
以上、1920年代のあと、60年代、そして2000年代と、ドイツにおいては40年周期でドキュメンタリー演劇の波が、またその背景となる、近過去や同時代社会に対する強い問題意識の波が訪れている。このことは、ちょうどその合間を埋めるように、1940年代の第二次世界大戦やナチス・ドイツによる支配、1980年代の冷戦の終焉や東西ドイツの統一という大きな事件があったことと無関係ではない。だから、今後、ひょっとすると2020年代にドイツで再び歴史的な事件があり、2040年代のドイツにまた新たなドキュメンタリー演劇が現われるかもしれない。
また、2000年代に登場した一連の新たなタッチのドキュメンタリー演劇は、同時代の世界各国の演劇人同士、また彼らと市井の人々との交流を促して、今後、新しいメディアテクノロジーを用いた、更なるドキュメンタリー演劇が生み出されていくことが推測される。そして、リミニ・プロトコルの作品に代表されるような、演劇、パフォーマンス、アートというようなカテゴライズの難しい作品は、ドイツに限らず、生まれてきている。そこでは創り手が意図するにせよしないにせよ、繰り返し〈演劇〉という枠組みの再考が促されるに違いない。こうした作品をサポートするには、制作スタッフにも、交渉先の多様化など、これまでになかったような制作プロセスに付随する状況に対する柔軟さが求められることになるだろう。
また、2000年代に登場した一連の新たなタッチのドキュメンタリー演劇は、同時代の世界各国の演劇人同士、また彼らと市井の人々との交流を促して、今後、新しいメディアテクノロジーを用いた、更なるドキュメンタリー演劇が生み出されていくことが推測される。そして、リミニ・プロトコルの作品に代表されるような、演劇、パフォーマンス、アートというようなカテゴライズの難しい作品は、ドイツに限らず、生まれてきている。そこでは創り手が意図するにせよしないにせよ、繰り返し〈演劇〉という枠組みの再考が促されるに違いない。こうした作品をサポートするには、制作スタッフにも、交渉先の多様化など、これまでになかったような制作プロセスに付随する状況に対する柔軟さが求められることになるだろう。

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.


