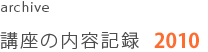


『ドキュメンタリー演劇とは何か』
Vol.1「演劇における〈ドキュメンタリー的〉なもの―その方法と可能性をめぐって」
2010年10月10日(日) 13時〜15時
森山 直人
(演劇批評家)
《所 感》
本レクチャーは、ドキュメンタリー映画の歴史を概観することによりドキュメンタリー映画と演劇の結びつきを捉え、「演劇における<ドキュメンタリー的>なもの」とは何かを考察していくものであった。その際、「関係性」という言葉が重要なキーワードとなっていた。ドキュメンタリー映画における作り手と被写体の関係性と、演劇における俳優と観客の関係性は類似するものがあり、両者が互いにどのように関係を構築していくのかが作品の出来に深く関わっている。
「演劇」という言葉の指す範囲が拡張し続けているなかで、「ドキュメンタリー演劇」とは何なのか、そもそも「演劇」自体をどう捉えていけばよいのか、あるいは、何が「虚構」で何が「現実」なのかを考える重要な手がかりが得られたレクチャーであった。しかし、結局「演劇」が捉えどころのないものであるということに変わりはなく、逆に捉えどころのない曖昧なものであるからこそ、そこに「演劇」の無限の可能性が見出せるのではないかと感じた。
本レクチャーは、ドキュメンタリー映画の歴史を概観することによりドキュメンタリー映画と演劇の結びつきを捉え、「演劇における<ドキュメンタリー的>なもの」とは何かを考察していくものであった。その際、「関係性」という言葉が重要なキーワードとなっていた。ドキュメンタリー映画における作り手と被写体の関係性と、演劇における俳優と観客の関係性は類似するものがあり、両者が互いにどのように関係を構築していくのかが作品の出来に深く関わっている。
「演劇」という言葉の指す範囲が拡張し続けているなかで、「ドキュメンタリー演劇」とは何なのか、そもそも「演劇」自体をどう捉えていけばよいのか、あるいは、何が「虚構」で何が「現実」なのかを考える重要な手がかりが得られたレクチャーであった。しかし、結局「演劇」が捉えどころのないものであるということに変わりはなく、逆に捉えどころのない曖昧なものであるからこそ、そこに「演劇」の無限の可能性が見出せるのではないかと感じた。
記録:園部友里恵(東京大学大学院教育学研究科修士課程在学)

1. 「ドキュメンタリー演劇」の問題
近年、「ドキュメンタリー演劇」という言葉を耳にする機会が増えた。本レクチャーのタイトルは、「ドキュメンタリー演劇」を、「演劇における<ドキュメンタリー的>なもの」という言葉にあえて言い換えている。そこには、「ドキュメンタリー演劇」、すなわち「ドキュメンタリー」と「演劇」の問題がある。この問題は、19世紀の後半から20世紀全体に渡り、演劇と映像メディアが作り出すイメージの問題に直結してくる。この問題は管見の限りではきちんとしたアプローチで論じられているものはあまりなく、今後きちんと論じられるべき問題である。本レクチャーにおいて、「演劇における<ドキュメンタリー的>なもの」に対して、決定的な体系や結論めいたものを示すことはできない。そこで、どのようにこの問題を考えるようになったのかというところから話を進めることにする。そうすることでこの問題の本質的な部分に触れ得るかもしれない。
2. ドキュメンタリー映画と演劇との結びつき
本レクチャーにおいては、「演劇における<ドキュメンタリー的>なもの」についてドキュメンタリー映画を切り口に考えていく。というのも、ドキュメンタリー映画との出会いをきっかけに<ドキュメンタリー的なもの>と演劇の結びつきを、他でもない私自身が考え始めたためである。ドキュメンタリー映画を観る中で演劇の問題と重なって見えてきたのは、ドキュメンタリーのフィクション性という問題である。佐藤真や森達也らドキュメンタリー映画作家は、今まで存在していた「ドキュメンタリーは真実を映す」という立場に対し、「ドキュメンタリーはフィクションである」という立場をとった。つまり、ドキュメンタリーを、客観的真実を映し出すものではなく、何らかのフィクションが混じるものとして想定するのである。その根拠の一つは、編集、すなわち作者の編集を経て1本のフィルムに仕立て上げられること、もう一つにはカメラの存在、すなわちフレームの内側には真実の痕跡を映すかもしれないが外側にあるものは何一つ映し出していないということが挙げられる。
また演技の問題がある。ここで言う「演技」とは、プロの俳優が決められた台詞を喋るという意味のものではない。被写体がカメラに対して示す反応は、作り手と被写体の関係性によって異なり、その関係性によって被写体がカメラという存在をどう捉えるかも異なる。具体例として、以下の2つの例が挙げられる。
また演技の問題がある。ここで言う「演技」とは、プロの俳優が決められた台詞を喋るという意味のものではない。被写体がカメラに対して示す反応は、作り手と被写体の関係性によって異なり、その関係性によって被写体がカメラという存在をどう捉えるかも異なる。具体例として、以下の2つの例が挙げられる。
①被写体がカメラを意識しなくなるまで作り手との関係性を構築した例
羽仁進『教室の子どもたち』(ドキュメンタリー映画)
この作品は、学校における子どもの日常的な様子を描いたもの。この撮影のために、羽仁らは毎日学校に通って子どもたちと仲良くなり、カメラを隠すなどの工夫を施した。子どもたちがカメラの存在を忘れた時、すなわち、作り手という存在への意識がなくなった時に出てくる生き生きとした表情を撮影した。
この作品は、学校における子どもの日常的な様子を描いたもの。この撮影のために、羽仁らは毎日学校に通って子どもたちと仲良くなり、カメラを隠すなどの工夫を施した。子どもたちがカメラの存在を忘れた時、すなわち、作り手という存在への意識がなくなった時に出てくる生き生きとした表情を撮影した。
②被写体にあえてカメラを意識させて撮影した例
大島渚『忘れられた皇軍』(テレビドキュメンタリー番組)
この作品は、第2次世界大戦中に日本軍に従軍した在日朝鮮人の戦後補償の問題を扱っている。戦後補償を求める盲目の人物が、涙を流しながらカメラに向かって勢いよく自分の心情を訴える場面がある。完全にカメラを意識しながら喋っており、そこには作り手が撮影を進めるにつれて被写体もカメラを意識し、心情がエスカレートしていくという両者の関係性が生じている。
この作品は、第2次世界大戦中に日本軍に従軍した在日朝鮮人の戦後補償の問題を扱っている。戦後補償を求める盲目の人物が、涙を流しながらカメラに向かって勢いよく自分の心情を訴える場面がある。完全にカメラを意識しながら喋っており、そこには作り手が撮影を進めるにつれて被写体もカメラを意識し、心情がエスカレートしていくという両者の関係性が生じている。
3. ドキュメンタリー映画における作家の主体性と被写体との関係性
大島の映画論で最も重要なのは「作家の主体性」である。「作家の主体性」とは、被写体である対象は、作り手がどのように関わるかで変容するため、作家が対象にどのように関わるかが決まってはじめて対象が決まるという理論である。言い換えると、作り手と被写体の関係の構築の際には、そこにカメラが存在するために、作り手は主体たらざるを得ないと論じている。
一方、ドキュメンタリー映画に対しての劇映画には、「俳優はカメラが存在しないようにふるまわなければならない」という一つの原則がある。このような劇映画の構造は、19世紀型の劇場であるプロセニアム型舞台が持っているイデオロギーと関わっている。プロセニアム型舞台は、客席と舞台上は別世界であり、行き来ができないものという発想に基づく。俳優と観客が関係しないことで1つのフィクションを成立させる。
大島が活躍した1950年代後半の映画界には大きな転機があった。それは手持ちカメラの誕生と同時録音が可能になったことである。それまでの劇映画全盛期は、撮影所で次々に劇映画を量産していた。機材が一般に入手が困難な時代において、撮影所は重要な場所として機能していた。しかし撮影機材と録音機材が劇的に軽くなることで、手持ちカメラと録音機を現場に持ち込み、その場で起こっていることを撮影することができるようになった。
反撮影所的なシステムの登場と同時に新たな問題も浮上した。それは、作り手すなわち撮影する主体自身が、観客の前に現前してしまうという問題である。「今、ここに作りつつある自分とは何者なのか」ということを作り手が考えなければならなくなったのである。
一方、ドキュメンタリー映画に対しての劇映画には、「俳優はカメラが存在しないようにふるまわなければならない」という一つの原則がある。このような劇映画の構造は、19世紀型の劇場であるプロセニアム型舞台が持っているイデオロギーと関わっている。プロセニアム型舞台は、客席と舞台上は別世界であり、行き来ができないものという発想に基づく。俳優と観客が関係しないことで1つのフィクションを成立させる。
大島が活躍した1950年代後半の映画界には大きな転機があった。それは手持ちカメラの誕生と同時録音が可能になったことである。それまでの劇映画全盛期は、撮影所で次々に劇映画を量産していた。機材が一般に入手が困難な時代において、撮影所は重要な場所として機能していた。しかし撮影機材と録音機材が劇的に軽くなることで、手持ちカメラと録音機を現場に持ち込み、その場で起こっていることを撮影することができるようになった。
反撮影所的なシステムの登場と同時に新たな問題も浮上した。それは、作り手すなわち撮影する主体自身が、観客の前に現前してしまうという問題である。「今、ここに作りつつある自分とは何者なのか」ということを作り手が考えなければならなくなったのである。
4. 演劇における俳優と観客の関係性
この問題と非常に近しいところにあるのが、1960年代の演劇、すなわち反リアリズム演劇である。1960年代の演劇は、観客がそこにいるけれどもいないことにするというリアリズムの基本的なスタイルに対し、「誰に見られているのか」ということを重視した。観客との関係性を問うていく中で、主体性が問われることになる。我々は、この1960年代の演劇の問題を現在も引きずっている。現在、「演劇における<ドキュメンタリー的>なもの」がクローズアップされる起源はこのような1960年代の演劇界の動きにある。
近年、「演劇に立ち会う」という表現を用いることがある。この表現には、観客は単に観るのではなく、俳優の前に立つ、立ち会う、目撃するという意味が含まれている。このような俳優と観客との関係を意識した時、演劇のドキュメンタリー性が始まっているのではないか。つまり今までの議論を踏まえると、ドキュメンタリー映画における「カメラの前に現前する被写体、被写体の前に現前するカメラ」は、演劇における「観客の前に現前する俳優、俳優の前に現前する観客」に置き換えられる。観客は舞台上で起こっていることを遠目から観ることはできないし、また俳優も観客と全く無関係に舞台上だけで完結した1つの世界を緻密に組み上げるだけでは駄目だとなった時、演劇における一種のドキュメンタリー性が明らかになってくる。
現在、我々は、演劇を観る時、目の前に役者がいるいうことを抵抗なく受け入れられる環境にある。しかし、完全に俳優がそこにいることを忘れている可能性もある。つまり、演劇がみせる世界に完全に入ってしまえば、イリュージョンという俳優の存在を忘れる現象が起こる。これは演劇の本質的なあり方かもしれない。にもかかわらず俳優は必ず観客の前に現われてくる。例えば、俳優が魅力的だった場合、俳優の魅力と同時に演劇の世界に没頭するというように、俳優が目の前にいるということを意識しながらイリュージョンが起こる場合もある。このように、演劇における俳優と観客の関係性は多様であり、このことが演劇を捉えどころのないものにする要因の1つではないか。
近年、「演劇に立ち会う」という表現を用いることがある。この表現には、観客は単に観るのではなく、俳優の前に立つ、立ち会う、目撃するという意味が含まれている。このような俳優と観客との関係を意識した時、演劇のドキュメンタリー性が始まっているのではないか。つまり今までの議論を踏まえると、ドキュメンタリー映画における「カメラの前に現前する被写体、被写体の前に現前するカメラ」は、演劇における「観客の前に現前する俳優、俳優の前に現前する観客」に置き換えられる。観客は舞台上で起こっていることを遠目から観ることはできないし、また俳優も観客と全く無関係に舞台上だけで完結した1つの世界を緻密に組み上げるだけでは駄目だとなった時、演劇における一種のドキュメンタリー性が明らかになってくる。
現在、我々は、演劇を観る時、目の前に役者がいるいうことを抵抗なく受け入れられる環境にある。しかし、完全に俳優がそこにいることを忘れている可能性もある。つまり、演劇がみせる世界に完全に入ってしまえば、イリュージョンという俳優の存在を忘れる現象が起こる。これは演劇の本質的なあり方かもしれない。にもかかわらず俳優は必ず観客の前に現われてくる。例えば、俳優が魅力的だった場合、俳優の魅力と同時に演劇の世界に没頭するというように、俳優が目の前にいるということを意識しながらイリュージョンが起こる場合もある。このように、演劇における俳優と観客の関係性は多様であり、このことが演劇を捉えどころのないものにする要因の1つではないか。
5. ドキュメンタリー性の問題
今までの話を整理すると、ドキュメンタリー性にはいくつかの問題がある。
①「生成―変化」の問題
何かがそこで生じ変化していくという、まさに目の前に立ちあがってくる「生成―変化」の問題がある。この目の前という言葉には、ニュートラルな自分とニュートラルな誰かではなく、まさにそこに関係をもってしまった両者の間に起こることを描き出すという意味が含まれている。また、演劇の場合、作品そのもの以上に、稽古場が様々な「<ドキュメンタリー的>なもの」の「生成―変化」が起こり得る重要な場所であると言えるかもしれない。
② 報告(報道)の問題
ドキュメンタリー性とは、今ここで起こっていることを知らない人に報告するというジャーナリスティックな機能がある。1920年代後半から30年代にかけて、プロパガンダの道具として演劇が積極的に活用されたことからも演劇と報告(報道)は関係していることがわかる。例えば、「アジプロ演劇」は、今流にいえば「情報弱者」に対し、今世の中で起こっていることを演劇で伝える目的で行われていた。
①「生成―変化」の問題
何かがそこで生じ変化していくという、まさに目の前に立ちあがってくる「生成―変化」の問題がある。この目の前という言葉には、ニュートラルな自分とニュートラルな誰かではなく、まさにそこに関係をもってしまった両者の間に起こることを描き出すという意味が含まれている。また、演劇の場合、作品そのもの以上に、稽古場が様々な「<ドキュメンタリー的>なもの」の「生成―変化」が起こり得る重要な場所であると言えるかもしれない。
② 報告(報道)の問題
ドキュメンタリー性とは、今ここで起こっていることを知らない人に報告するというジャーナリスティックな機能がある。1920年代後半から30年代にかけて、プロパガンダの道具として演劇が積極的に活用されたことからも演劇と報告(報道)は関係していることがわかる。例えば、「アジプロ演劇」は、今流にいえば「情報弱者」に対し、今世の中で起こっていることを演劇で伝える目的で行われていた。
6. 「演劇における<ドキュメンタリー的>なもの」と間接性
ドキュメンタリー映画がプロパガンダや左翼思想と関わっていたことは、記録演劇やベルトルト・ブレヒトの演劇論とつながっている。このことを示す最も有名なものの一つにペーター・ヴァイス『追究』がある。この作品の上演権は特定の劇場ではなく上演したい劇場全てに渡され幾つかの劇場で同時上演されたが、これを翻訳した岩淵達治によれば、この作品で興味深いのは何かを演じるということに距離をとったという点である。そこには間接性ということが関係している。直接的に何かを描くということに演劇の存在価値があるという考え方をされるが、ラジオドラマ等のようにダイレクトに入ってくるとあまりにも生々しすぎる場合がある。「演劇における<ドキュメンタリー的>なもの」は、間接的(ブレヒト的に言えば「考えるスペースを残す」)であるからこそ、力を発揮するということがある。間接的であること、あるいは別の立場から間接性を考えるための方法の1つに、虚構(フィクション)を現実世界に導入するということがある。その例として、ジャン・ルーシュ監督『人間ピラミッド』が挙げられる。ルーシュは、独立直前のコートジヴォアールの首都アビジャンで、黒人と白人が会話をしないという問題を抱える高校で、黒人と白人が友達になるというドラマの創作を提案し、それを記録した。このドラマ創作の過程を経ることで、生徒たちは最終的には本当に仲良くなった。ここで起こったことは、虚構と現実がある瞬間に飛んでしまうということである。この作品は完全に演劇的な文脈、つまりブレヒトの「教育劇」(あるシチュエーションを様々な人に演じさせることを通じて、何かを学ばせ、社会を変革していくことを目指す手法)を踏まえている。
最近の「演劇における<ドキュメンタリー的>なもの」においても、現実の中にフィクションを持ち込むことによってどういう波紋が生じるかということを模索するものが多いように思う。いずれにしても、「演劇における<ドキュメンタリー的>なもの」という問題では、映像と演劇の本質的な違いと、本質的な接点を同時に考えなければならない。この未開拓の分野を今後開拓していくことが必要である。
最近の「演劇における<ドキュメンタリー的>なもの」においても、現実の中にフィクションを持ち込むことによってどういう波紋が生じるかということを模索するものが多いように思う。いずれにしても、「演劇における<ドキュメンタリー的>なもの」という問題では、映像と演劇の本質的な違いと、本質的な接点を同時に考えなければならない。この未開拓の分野を今後開拓していくことが必要である。

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.


