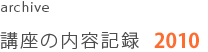


『ブレヒトにおける演劇と教育』
Vol.3「ブレヒト教育演劇論の継承」
2010年7月8日(木) 19時〜21時
中島 裕昭
(東京学芸大学 演劇分野教授)
《所 感》
ブレヒトというと、単純に「メタ構造」を思い浮かべてしまうが、『ブレヒトにおける演劇と教育』の第3回目の今回は、そのようなメタ構造を使ったブレヒトの教育劇が、当時のベルリンでいかに必要であったか、またそれがドイツの演劇教育を考えるうえで、どのように影響を与え、継承されていったかが、解りやすく説明された。ブレヒトの、社会的な問題を演じることで考えるという方法論は、被抑圧者のための演劇やTheatre in Education(T.I.E.)、PETAなど、様々な国や団体を経由して日本にもたくさん入ってきている。そういった意味では継承は至るところで行なわれているといえるだろう。これを機会に、日本で今後どのようにブレヒトが継承され、発展していくのかに注意を向けていきたいと思った。その政治性から、ブレヒトの教育劇は過去のものと思っている人にはぜひ出席してもらいたかった、非常に充実した内容であった。
ブレヒトというと、単純に「メタ構造」を思い浮かべてしまうが、『ブレヒトにおける演劇と教育』の第3回目の今回は、そのようなメタ構造を使ったブレヒトの教育劇が、当時のベルリンでいかに必要であったか、またそれがドイツの演劇教育を考えるうえで、どのように影響を与え、継承されていったかが、解りやすく説明された。ブレヒトの、社会的な問題を演じることで考えるという方法論は、被抑圧者のための演劇やTheatre in Education(T.I.E.)、PETAなど、様々な国や団体を経由して日本にもたくさん入ってきている。そういった意味では継承は至るところで行なわれているといえるだろう。これを機会に、日本で今後どのようにブレヒトが継承され、発展していくのかに注意を向けていきたいと思った。その政治性から、ブレヒトの教育劇は過去のものと思っている人にはぜひ出席してもらいたかった、非常に充実した内容であった。
記録:和泉聡子(東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学研究専攻修士課程)

1.ブレヒトの教育演劇の理論的定義
a) 政治的な態度決定、社会的行動の選択のための学習教材となるべき演劇。
b) 提供者と受容者の区別をせず、取り上げられるテーマの関係者によって演じられ、観られる。
b) 提供者と受容者の区別をせず、取り上げられるテーマの関係者によって演じられ、観られる。
ブレヒトは「観る」こと自体を完全に否定していたわけではない。演じることによって考え、観て感じて議論して、また考え演じるという様な一連のプロセスの中で「観る」ということは想定しているが、観るだけの人、ただの観客は否定しているのである。
上記a)b)の定義は、理論的にはこの様に説明できるというものであるが、それは同じブレヒトの「叙事的演劇」にも繋がっていく考え方であり、それを「教育演劇」と厳密に線引きすることは困難である。しかしブレヒトが自ら「教育演劇」と名付けて考えていた、一群の作品がある。そこには、上記の理論的なものだけでは整理し切れない、もう少し具体的な内容があるので次に紹介する。
2.実際に制作されたブレヒト教育劇作品の具体的特性
a) 政治教育を目的とする、小規模の音楽劇(コーラスを用いている)
b) 行動の選択という問題設定と選択肢の意味・結果を、簡素かつ明白に提示
c) 組織の行動目標を優先し、その中での個人の犠牲を肯定している
d) 作品中の出来事に対する判断のためにメタ構造が設定されている
e) 実演における参加者の組織化(ただ観るだけの人を作らない)
b) 行動の選択という問題設定と選択肢の意味・結果を、簡素かつ明白に提示
c) 組織の行動目標を優先し、その中での個人の犠牲を肯定している
d) 作品中の出来事に対する判断のためにメタ構造が設定されている
e) 実演における参加者の組織化(ただ観るだけの人を作らない)
ここでいっている教育とは一般教育ではなく、明らかに政治教育である。政治的な判断をしてほしいということが前提としてあり、選択して行動することが、実際の社会の中での政治に繋がっていく。そのようなことを目的として教育演劇が生まれていく中で、音楽家たちの要請もあり、コーラスが入れられるようになった。ある舞台の上で行なわれている出来事に対して、外から判断できるようにする構造(メタ構造)が設定されていて、音楽、特にコーラスがその役割を果たしている場合が多い。
シリーズ初回でも音楽や歌と場面の関係についてのご質問があったのでひとつ例を挙げておく。『三文オペラ』の結婚式の場面で花嫁が歌う「海賊ジェニーの歌」という歌である。
歌詞の内容:波止場の汚い食堂で皿洗いとして働いているジェニーは、男にも相手にされず、つまらない毎日だが、実は海賊の一味である。いつか仲間が海からやってきて、ジェニーに「誰を殺そうか」と尋ねると、彼女は「みんな殺して」と答える。
結婚式にはふさわしくない内容の歌詞で「社会の中で現在人々が何を期待しているのか」が幸せなはずの花嫁の口から出てくるアンバランス感がある。祝いの場面なのに、それは見掛けだけで、実は社会状況が転覆してしまうかもしれないというような感覚に当時は共感が集まっていた。
前回実際に戯曲を読んでみて、ブレヒトの教育劇では、戯曲の構造についてはよく考えられているが、実際に演じてみる際に、演じ手がどのように解釈し、自分の中で内面化し、演技として凝縮していくかということに関して、あまりブレヒトは考えていないのではないか?という参加者からのコメントがあった。戯曲だけを読むと、技巧的、人工的なスタイルで書かれているのでそういう感想をもつだろう。戯曲の中では論理的に解りやすく問題が設定され、選択肢が2つ用意されているが、登場人物たちが何を感じ、何に葛藤していたのか、など様々な感情や思考の推移がテキストの中からは読み取れない。それが書かれていないけれども、そこを感じ、考えないと演じられないようになっている。それを感じ考え演じることで、参加している人にとっての自己理解や状況理解を促すことができる。ブレヒトには、そこを感じ、考え、話し合ってほしいという狙いがある。
ブレヒトはその当時、個の犠牲を肯定していた。もちろん完全に個を否定している訳ではないという議論も当然あるし、ブレヒトが自ら「教育劇」としている作品の中にはこの部分が曖昧な作品もあるが、少なくとも、教育劇中の問題設定の中で、一度は個人の犠牲を肯定する内容を選択肢として提示した上で、考えてもらうという構造になっている。ブレヒトは当時、あの政治状況の中で、個性の否定について、それを新しいものとしてポジティブに考えていて、それがどういう場面であったら肯定的に考えられるのかを模索し、提起していた。
この様な具体的特性は、1930年代のベルリンで活動していたブレヒトにはその必要性が切にあった。その後亡命したブレヒトは、ただ戯曲を書き溜めることしかできなかったし、帰国後は、ベルリーナ・アンサンブルで「教育劇」とは離れた作品を創ることになった。結果的に教育劇はある一定の時期にしか書かれなかったことになり、完全に自分が納得できるように上演できたのかは議論が分かれるところである。
シリーズ初回でも音楽や歌と場面の関係についてのご質問があったのでひとつ例を挙げておく。『三文オペラ』の結婚式の場面で花嫁が歌う「海賊ジェニーの歌」という歌である。
歌詞の内容:波止場の汚い食堂で皿洗いとして働いているジェニーは、男にも相手にされず、つまらない毎日だが、実は海賊の一味である。いつか仲間が海からやってきて、ジェニーに「誰を殺そうか」と尋ねると、彼女は「みんな殺して」と答える。
結婚式にはふさわしくない内容の歌詞で「社会の中で現在人々が何を期待しているのか」が幸せなはずの花嫁の口から出てくるアンバランス感がある。祝いの場面なのに、それは見掛けだけで、実は社会状況が転覆してしまうかもしれないというような感覚に当時は共感が集まっていた。
前回実際に戯曲を読んでみて、ブレヒトの教育劇では、戯曲の構造についてはよく考えられているが、実際に演じてみる際に、演じ手がどのように解釈し、自分の中で内面化し、演技として凝縮していくかということに関して、あまりブレヒトは考えていないのではないか?という参加者からのコメントがあった。戯曲だけを読むと、技巧的、人工的なスタイルで書かれているのでそういう感想をもつだろう。戯曲の中では論理的に解りやすく問題が設定され、選択肢が2つ用意されているが、登場人物たちが何を感じ、何に葛藤していたのか、など様々な感情や思考の推移がテキストの中からは読み取れない。それが書かれていないけれども、そこを感じ、考えないと演じられないようになっている。それを感じ考え演じることで、参加している人にとっての自己理解や状況理解を促すことができる。ブレヒトには、そこを感じ、考え、話し合ってほしいという狙いがある。
ブレヒトはその当時、個の犠牲を肯定していた。もちろん完全に個を否定している訳ではないという議論も当然あるし、ブレヒトが自ら「教育劇」としている作品の中にはこの部分が曖昧な作品もあるが、少なくとも、教育劇中の問題設定の中で、一度は個人の犠牲を肯定する内容を選択肢として提示した上で、考えてもらうという構造になっている。ブレヒトは当時、あの政治状況の中で、個性の否定について、それを新しいものとしてポジティブに考えていて、それがどういう場面であったら肯定的に考えられるのかを模索し、提起していた。
この様な具体的特性は、1930年代のベルリンで活動していたブレヒトにはその必要性が切にあった。その後亡命したブレヒトは、ただ戯曲を書き溜めることしかできなかったし、帰国後は、ベルリーナ・アンサンブルで「教育劇」とは離れた作品を創ることになった。結果的に教育劇はある一定の時期にしか書かれなかったことになり、完全に自分が納得できるように上演できたのかは議論が分かれるところである。
3.ブレヒト教育劇に対する批判点
a) 強固な政治イデオロギー(社会主義、反ファシズムという政治目標)
b) 個性の否定と、それに賛成する宗教イデオロギー的色合い
c) ブレヒト自身による『処置』という作品の上演禁止(変化していく社会への対応)
d) 東西冷戦状況における旧西ドイツでの反共産主義とブレヒトへの警戒感
e)「観客」を想定しない演劇形式の困難さ(娯楽作品として楽しむことの否定)
f) 芸術作品に既定の(1つの)答え・選択肢・強いメッセージを盛り込むことの困難さ
b) 個性の否定と、それに賛成する宗教イデオロギー的色合い
c) ブレヒト自身による『処置』という作品の上演禁止(変化していく社会への対応)
d) 東西冷戦状況における旧西ドイツでの反共産主義とブレヒトへの警戒感
e)「観客」を想定しない演劇形式の困難さ(娯楽作品として楽しむことの否定)
f) 芸術作品に既定の(1つの)答え・選択肢・強いメッセージを盛り込むことの困難さ
教育劇の理論については、1970年代までは議論がなされず、「教育劇」はブレヒトの全作品の中でも過激な、異端的な作品としてその評価は低かった。1970年代になり、教育劇の理論が再構築され受容されるようになっても、その政治性などから、結局、ブレヒトの教育劇は一般化するには至らなかった。
4.ドイツにおける演劇教育の基本コンセプトの1つとしてのブレヒト教育劇
まず、ドイツの演劇教育について、その特色を概観する。
a)演劇と教育をつなぐ複数の拠点、基盤の厚さ
(各地の劇場、社会教育施設、キリスト教会、演劇教育学会、児童青少年演劇協会、全国演劇教育連盟などがそれぞれ活発に活動)
b)学校教育の中に取り入れられた科目としての演劇
(1997年に1つの州から開始され、徐々に全国へ広がる。対応して大学における教科教員養成が開始される。2000年以降、地域の劇場と学校の提携が進み、2010年までに大学入学試験科目にという目標が設定されている。)
c)1970年代からのブレヒトの理論を出発点にした、教育劇の研究
(ブレヒト教育劇理論の再構成と具体化。演ずることによる、内的モデルの再編成と行動様式の学習についての研究)
d)ヨーロッパに亡命してきたアウグスト・ボアールの仕事が与えた、多大な影響
(各地の劇場、社会教育施設、キリスト教会、演劇教育学会、児童青少年演劇協会、全国演劇教育連盟などがそれぞれ活発に活動)
b)学校教育の中に取り入れられた科目としての演劇
(1997年に1つの州から開始され、徐々に全国へ広がる。対応して大学における教科教員養成が開始される。2000年以降、地域の劇場と学校の提携が進み、2010年までに大学入学試験科目にという目標が設定されている。)
c)1970年代からのブレヒトの理論を出発点にした、教育劇の研究
(ブレヒト教育劇理論の再構成と具体化。演ずることによる、内的モデルの再編成と行動様式の学習についての研究)
d)ヨーロッパに亡命してきたアウグスト・ボアールの仕事が与えた、多大な影響
ドイツ演劇教育学会の中心的研究者であるゲルト・コッホが、2008年にまとめたところによると、ドイツの演劇教育におけるブレヒトの遺産は、1)芸術家が同時に教育者であるということの自己認識、2)芸術を基盤とした、民主的な経験学習の考え方の提示、3)「遊び」を人類学的な文脈から社会科学的な文脈へ変えたこと、の3点だという。そしてブレヒトは、今日のドイツ演劇教育のニーズに併せた形で、今後も継承されていくであろう。
5.ブレヒト教育劇の継承可能性
前述の様に、ドイツにはもともと芸術教育の伝統があるので、演劇と教育の結びつきにも深い理解があり、その理論の前提にブレヒトがあることは間違いない。しかしその政治性には違和感があり、今ではブレヒトの教育劇の政治性については、研究者と一部の実践者のみが注目していて、一般的にはそれとは距離がおかれている
a)演劇実践が学習活動になり得るということの明確な意識
ただ観るのではなく、演ずることによって、自分自身の経験や他者との関係、社会的状況をよりよく理解し、行動についての選択や、社会的態度を更新することができるというのは、ドイツでは既に自明のこととなっている。しかしそれはブレヒト以前にはみられなかった。ブレヒト以後、ドイツでは演じて学ぶということが共有化されている。それはブレヒトの継承のひとつであろう。またそのためにブレヒトが用いた、簡素で、双方向に開いている、演劇の形式も広く継承されているといえる。
ただ観るのではなく、演ずることによって、自分自身の経験や他者との関係、社会的状況をよりよく理解し、行動についての選択や、社会的態度を更新することができるというのは、ドイツでは既に自明のこととなっている。しかしそれはブレヒト以前にはみられなかった。ブレヒト以後、ドイツでは演じて学ぶということが共有化されている。それはブレヒトの継承のひとつであろう。またそのためにブレヒトが用いた、簡素で、双方向に開いている、演劇の形式も広く継承されているといえる。
b)選択肢を選ぶことよりも、選択肢を作ることに重点
当時のブレヒトにとっては緊急性の高い問題だったことは推測できるが、現代では、個人が否定されていることには抵抗感がある。現在は、個性の死と組織という単純な二項対立では考えられない。そこでブレヒトの教育劇にあった「少数の政治的なものとして選択肢が提示され、その中から選ぶ事を求める」という構造よりも、むしろ参加者で選択肢を作るということに重点がおかれているだろう。創作過程への参加によって問題を発見し、状況を判断し、自身の感情や意見を整理できる。そして共同作業の中で、選択肢を作って演じていくことで得られる学びは大きい。それは、観客はただ観る者ではなく、関与し、介入すべき者であるという位置付けにおいて、広い意味でブレヒトを継承していることになろう。
ブレヒトの書いた教育劇をそのまま演じることがブレヒトの継承ではなく、ブレヒトが行なったように、参加者が問題を発見し、新しく選択肢を作ってやってみることが、ブレヒトの継承といえるであろう。
当時のブレヒトにとっては緊急性の高い問題だったことは推測できるが、現代では、個人が否定されていることには抵抗感がある。現在は、個性の死と組織という単純な二項対立では考えられない。そこでブレヒトの教育劇にあった「少数の政治的なものとして選択肢が提示され、その中から選ぶ事を求める」という構造よりも、むしろ参加者で選択肢を作るということに重点がおかれているだろう。創作過程への参加によって問題を発見し、状況を判断し、自身の感情や意見を整理できる。そして共同作業の中で、選択肢を作って演じていくことで得られる学びは大きい。それは、観客はただ観る者ではなく、関与し、介入すべき者であるという位置付けにおいて、広い意味でブレヒトを継承していることになろう。
ブレヒトの書いた教育劇をそのまま演じることがブレヒトの継承ではなく、ブレヒトが行なったように、参加者が問題を発見し、新しく選択肢を作ってやってみることが、ブレヒトの継承といえるであろう。
質疑応答
C1 (参加者): 教育的な面を含む演劇に、我々がまだ価値を見出せていないのではないか。芸術は芸術であり、社会からは自律しているべきという考え方が演劇人だけでなく、観客の方にもあるのでは。
A1 (臨席のボアール研究者 里見実氏):
芸術が社会に対して自律していると考えることこそ社会的であろう。社会をどう考えるかの問題だ。社会はあらかじめ存在するもので、その社会の中に組み込まれて、芸術もある機能を果たしている。社会に適応しながらそういう機能を果たしていればいるほど、芸術家は自分が自律しているという意識を持つことができる。古代も現代も、そういう芸術と社会の関係が支配的であろう。しかしブレヒトとのかかわりで芸術と社会をみていくと、社会をどう作っていくのかということが重要である。芝居を1本作ることは、社会を作ることである。制作過程での社会をどう構築していくかということと、舞台と観衆との間で作られる関係もまた社会を作ることである。社会を、存在するものではなく、作るものとして捉えている。そのイメージを抜きにはブレヒトは語れない。
C2 (参加者):選択する力、判断する力を付けるという目的は理解したが、それを話し合いではなく、演劇でやる必要性は、主体と客体がどんどん入れ替わることが可能という点なのだろうか。
A2 (臨席のボアール研究者 里見実氏):
興味深いことに、スタニスラフスキーとブレヒトは同時期に受容されることが非常に多い。登場人物を造形するため、自分自身ではない人間を演じるためにスタニスラフスキーのシステムを使い、今度はそこから出て、外から客観的に見ていくためにブレヒトの方法を使う。ワークショップは、その2つの往復運動である。それは社会問題を考える上では非常に有効だろうが、効果を挙げるためには、1週間くらい時間をかけたワークショップにする必要があるだろう。
A2 (講師):同感である。現代の日本でのワークショップ体制は、講師を1人呼んで半日行なうというのが主流だろうが、それでは変容するところまでは行かないだろう。
A2 (講師):同感である。現代の日本でのワークショップ体制は、講師を1人呼んで半日行なうというのが主流だろうが、それでは変容するところまでは行かないだろう。

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.


