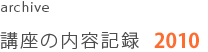


『ブレヒトにおける演劇と教育』
Vol.2「ブレヒト教育演劇の『教育』内容」
2010年7月1日(木) 19時〜21時
中島 裕昭
(東京学芸大学教育学部 音楽・演劇講座 演劇分野教授)
《所 感》
ブレヒトの「教育劇」はよく耳にするものの、実際にどういったものが「教育劇」と呼ばれているのか、そこでの「教育」とはどういう意味なのか、正直なところ、よくわかっていなかった。今回の講義では「教育劇」とみなされている作品『イエスマン/ノーマン』を実際に声に出して読んでみる機会を得た。さらに「教育劇」が書かれた背景を知ることで、少しは具体的に「教育劇」をイメージすることができたように思う。それと同時に、「教育劇」の実践の難しさも垣間見た。演劇としての面白さと教育の両立は、簡単ではないのだろう。
しかし、学び考えることもまた面白い行為であると私は思う。現代にも通じる「教育劇」の可能性を諦めてしまうには、まだ早い。そんなことを感じた2時間であった。
ブレヒトの「教育劇」はよく耳にするものの、実際にどういったものが「教育劇」と呼ばれているのか、そこでの「教育」とはどういう意味なのか、正直なところ、よくわかっていなかった。今回の講義では「教育劇」とみなされている作品『イエスマン/ノーマン』を実際に声に出して読んでみる機会を得た。さらに「教育劇」が書かれた背景を知ることで、少しは具体的に「教育劇」をイメージすることができたように思う。それと同時に、「教育劇」の実践の難しさも垣間見た。演劇としての面白さと教育の両立は、簡単ではないのだろう。
しかし、学び考えることもまた面白い行為であると私は思う。現代にも通じる「教育劇」の可能性を諦めてしまうには、まだ早い。そんなことを感じた2時間であった。
記録:福西千砂都(東京学芸大学大学院教育学研究科博士前期課程修了)

1.ブレヒトの教育劇作品
前回の講座終了後「教育劇は誰によってどのように区分、分類されているのか」という質問が寄せられた。これは難しい問題である。ブレヒトが教育劇と呼んでいるものは以下の通りだ。
『リンドバーグ(たち)の飛行。少年少女のためのラジオ教育劇』
『(了解についてのバーデン)教育劇』
『イエスマン。学校オペラ』
『処置。教育劇』
『例外と原則。教育劇』
『ホラティ人とクリアティ人。教育劇』
『(了解についてのバーデン)教育劇』
『イエスマン。学校オペラ』
『処置。教育劇』
『例外と原則。教育劇』
『ホラティ人とクリアティ人。教育劇』
『イエスマン。学校オペラ』以外は、タイトルの中に「教育劇」と入っている。
今日は『イエスマン/ノーマン』を受講者に読んでもらうが、ブレヒトはこれを教育劇と呼んでいない。しかし『イエスマン/ノーマン』も教育劇としてよいだろうと言われている。その理由についても考えたい。
今日は『イエスマン/ノーマン』を受講者に読んでもらうが、ブレヒトはこれを教育劇と呼んでいない。しかし『イエスマン/ノーマン』も教育劇としてよいだろうと言われている。その理由についても考えたい。
2.ブレヒトの教育劇
ブレヒトは教育劇を「政治的な態度決定、社会的行動の選択のための学習教材となるべき演劇。提供者と受容者の区別をせず、取り上げられるテーマの関係者によって演じられ、観られる」とまとめている。ではこの理念がどこまで実現、実行されたのだろうか。
極論だが、最近はブレヒトの教育劇は理念として存在するだけで、ブレヒトによって実現はされていないという意見がある。また、試行錯誤して積み上げられたもので、体系的に考えられたものではないので、教育劇という定義そのものが不可能であるとも言われている。このように曖昧な教育劇をどう捉え、更に、どのように現在に再利用できるのかが一番の問題である。今の演劇教育やWSの中で、ブレヒトはどのように位置付いているのだろうか。
教育劇はドイツ語で“Lehrstück”と記される。これは、ブレヒトが関係者とともにつくりあげた造語である。“Stück”は芝居や音楽の単位である「曲」のような意味であり、“Lehr”は、学ぶというようなことに関係して使われる。“Lehrstück”は、日本語の「市街劇」や「テント劇」といった感覚に近い、教育や学習という語と劇を組み合わせた造語である。このようなドイツ語の語感をそのまま残した場合「教訓劇」と訳すのが日本語の感覚と一番近い。しかし、演劇関係者は「教訓」という言葉を嫌う。学校くさい、面白くないといった印象があるのだろう。このような「教訓=すでに決まったメッセージがあって、それを伝達する」というイメージは、ブレヒトの考えた内容とは異なるため、「教育劇」と訳されている。他には「教材劇」という訳もある。
極論だが、最近はブレヒトの教育劇は理念として存在するだけで、ブレヒトによって実現はされていないという意見がある。また、試行錯誤して積み上げられたもので、体系的に考えられたものではないので、教育劇という定義そのものが不可能であるとも言われている。このように曖昧な教育劇をどう捉え、更に、どのように現在に再利用できるのかが一番の問題である。今の演劇教育やWSの中で、ブレヒトはどのように位置付いているのだろうか。
教育劇はドイツ語で“Lehrstück”と記される。これは、ブレヒトが関係者とともにつくりあげた造語である。“Stück”は芝居や音楽の単位である「曲」のような意味であり、“Lehr”は、学ぶというようなことに関係して使われる。“Lehrstück”は、日本語の「市街劇」や「テント劇」といった感覚に近い、教育や学習という語と劇を組み合わせた造語である。このようなドイツ語の語感をそのまま残した場合「教訓劇」と訳すのが日本語の感覚と一番近い。しかし、演劇関係者は「教訓」という言葉を嫌う。学校くさい、面白くないといった印象があるのだろう。このような「教訓=すでに決まったメッセージがあって、それを伝達する」というイメージは、ブレヒトの考えた内容とは異なるため、「教育劇」と訳されている。他には「教材劇」という訳もある。
3.ブレヒト教育劇の直接の契機
次に、ブレヒトが“Lehrstück”(教育劇)を考え始めた直接の契機について述べる。
まず、前回も話した通り「三文オペラ」があまりにも娯楽的に享受されたことへの反省が考えられる。さらに、最近の研究では、もっと具体的な契機として、音楽との出会いが注目されている。その出会いの舞台となったのが、「バーデン・バーデン音楽祭」である。この音楽祭は、パウル・ヒンデミットなどが、現代音楽を紹介するためにつくったものだ。
当時のドイツでは、クラシックの歴史の上で生みだされた新しい音楽が観客に受け入れられないでいた。この状況を打破するにはどうすればいいか。新しい技術や需要形態を模索した結果、「実用音楽」に辿り着く。1920年頃のアメリカで、エリック・サティが行った「家具の音楽」すなわち「日常生活の中でじゃまにならない音楽」といった工夫が、ドイツの特にウィーン楽派の人々にも伝わったのだ。彼らは、自分たちの音楽が日常とかけ離れていないことを証明するために、素人でもできる音楽を模索した。より生活に近いところに音楽をもっていきたいという切実な思いから、彼らはこの音楽祭を行っていたのである。
さらに、ヒンデミットらはラジオという新しいメディアを使っての音楽享受を考えていた。ブレヒトは特に、このラジオに注目しており、聴取者参加型のラジオを放送したりした。
こういった活動を行う音楽家たちの依頼で、ブレヒトは『リンドバーグたちの飛行』を書いた。これは、1929年7月にバーデン・バーデンで初演されている。
このように、ブレヒトの作品は社会主義的な背景ばかりではなく、周囲の音楽家たちからの影響を大きく受けたと考えられる。もちろんブレヒトの中に社会のなかでの演劇の意味という問題意識があったために、他の芸術家からの働きかけに積極的に応じたという側面もある。
さらに、ブレヒト教育劇の共通の重要なテーマである個人の価値に対する評価の問題がある。これは、どんな役割も交換可能であり、どんな人間も交換可能であるという考えで、唯一無二のものとしての個人の価値を徹底的に否定したものである。つまり、物事の成果は共同体全体に還元され、個人はそのための犠牲を引き受ける、とも言える考え方である。
以上のような要素から、ブレヒトの教育劇はつくられていった。
また、ブレヒトの教育劇の直接の契機となったのは、大西洋横断に成功したリンドバークの手記『われわれふたり』(We;Wir Zwei)である。タイトルにある「われわれ」とはリンドバーグと飛行機のことである。大西洋横断の成功は、リンドバークひとりの力ではなく、飛行機をつくる技術や、その技術者、整備者たちの力でもある。このリンドバーグひとりの英雄性を否定した考え方にブレヒトは興味を抱いた。
このような背景を考えると、ブレヒトの教育劇の理念が、各作品にどこまで反映されているかが怪しいことが分かる。実用音楽や個人の否定、当時の最新技術(ラジオ)など、当時の時代性は現代の活用にはつながらない。しかし、教育劇の持つ枠組みは利用できると考える。
まず、前回も話した通り「三文オペラ」があまりにも娯楽的に享受されたことへの反省が考えられる。さらに、最近の研究では、もっと具体的な契機として、音楽との出会いが注目されている。その出会いの舞台となったのが、「バーデン・バーデン音楽祭」である。この音楽祭は、パウル・ヒンデミットなどが、現代音楽を紹介するためにつくったものだ。
当時のドイツでは、クラシックの歴史の上で生みだされた新しい音楽が観客に受け入れられないでいた。この状況を打破するにはどうすればいいか。新しい技術や需要形態を模索した結果、「実用音楽」に辿り着く。1920年頃のアメリカで、エリック・サティが行った「家具の音楽」すなわち「日常生活の中でじゃまにならない音楽」といった工夫が、ドイツの特にウィーン楽派の人々にも伝わったのだ。彼らは、自分たちの音楽が日常とかけ離れていないことを証明するために、素人でもできる音楽を模索した。より生活に近いところに音楽をもっていきたいという切実な思いから、彼らはこの音楽祭を行っていたのである。
さらに、ヒンデミットらはラジオという新しいメディアを使っての音楽享受を考えていた。ブレヒトは特に、このラジオに注目しており、聴取者参加型のラジオを放送したりした。
こういった活動を行う音楽家たちの依頼で、ブレヒトは『リンドバーグたちの飛行』を書いた。これは、1929年7月にバーデン・バーデンで初演されている。
このように、ブレヒトの作品は社会主義的な背景ばかりではなく、周囲の音楽家たちからの影響を大きく受けたと考えられる。もちろんブレヒトの中に社会のなかでの演劇の意味という問題意識があったために、他の芸術家からの働きかけに積極的に応じたという側面もある。
さらに、ブレヒト教育劇の共通の重要なテーマである個人の価値に対する評価の問題がある。これは、どんな役割も交換可能であり、どんな人間も交換可能であるという考えで、唯一無二のものとしての個人の価値を徹底的に否定したものである。つまり、物事の成果は共同体全体に還元され、個人はそのための犠牲を引き受ける、とも言える考え方である。
以上のような要素から、ブレヒトの教育劇はつくられていった。
また、ブレヒトの教育劇の直接の契機となったのは、大西洋横断に成功したリンドバークの手記『われわれふたり』(We;Wir Zwei)である。タイトルにある「われわれ」とはリンドバーグと飛行機のことである。大西洋横断の成功は、リンドバークひとりの力ではなく、飛行機をつくる技術や、その技術者、整備者たちの力でもある。このリンドバーグひとりの英雄性を否定した考え方にブレヒトは興味を抱いた。
このような背景を考えると、ブレヒトの教育劇の理念が、各作品にどこまで反映されているかが怪しいことが分かる。実用音楽や個人の否定、当時の最新技術(ラジオ)など、当時の時代性は現代の活用にはつながらない。しかし、教育劇の持つ枠組みは利用できると考える。
4.『イエスマン』初版と『イエスマン/ノーマン』
『イエスマン/ノーマン』は日本の能『谷行』をもとにしている。
1921年にA.ウェイリーが『谷行』の英訳を出版し、1929年12月にはエリーザベト・ハウプトマンがその英訳をさらに独訳した。ブレヒトはその頃『リンドバーグの飛行』『教育劇』を初演していたが(1929年7月)、1930年のベルリン新音楽祭の題材として、三文オペラの作曲家クルト・ヴァイルが『谷行』を「学校オペラ」とすることを提案したのである。主人公が少年であり、形式がコンパクト、展開も短く、装置なども含めて簡単に済むところが「学校オペラ」にふさわしいと考えられたのだろう。
1930年4月には『イエスマン』初版がほぼ完成し、音楽雑誌に発表された。同年5月から6月には、ベルリン教育授業センターで生徒たちによって公演され、さらに6月にはベルリン・ノイケルン区のギムナジウムにて公演された。このギムナジウムでは『イエスマン』初版に関して学生による討論が行われ、この討論を受けて1931年末、『イエスマン/ノーマン』に改作される。『イエスマン/ノーマン』は『イエスマン』第二版と『ノーマン』の二作品から成るが、これらを別々に上演することをブレヒトは禁止している。
このようにして、『イエスマン/ノーマン』はつくられた。しかし当時のベルリンでは上演されなかったようで、1951年のリヴィング・シアターが初演であると言われている。一方『イエスマン』初版は1930年から32年にかけて、とくに音楽教育とのつながりの中で多く上演されている。
1921年にA.ウェイリーが『谷行』の英訳を出版し、1929年12月にはエリーザベト・ハウプトマンがその英訳をさらに独訳した。ブレヒトはその頃『リンドバーグの飛行』『教育劇』を初演していたが(1929年7月)、1930年のベルリン新音楽祭の題材として、三文オペラの作曲家クルト・ヴァイルが『谷行』を「学校オペラ」とすることを提案したのである。主人公が少年であり、形式がコンパクト、展開も短く、装置なども含めて簡単に済むところが「学校オペラ」にふさわしいと考えられたのだろう。
1930年4月には『イエスマン』初版がほぼ完成し、音楽雑誌に発表された。同年5月から6月には、ベルリン教育授業センターで生徒たちによって公演され、さらに6月にはベルリン・ノイケルン区のギムナジウムにて公演された。このギムナジウムでは『イエスマン』初版に関して学生による討論が行われ、この討論を受けて1931年末、『イエスマン/ノーマン』に改作される。『イエスマン/ノーマン』は『イエスマン』第二版と『ノーマン』の二作品から成るが、これらを別々に上演することをブレヒトは禁止している。
このようにして、『イエスマン/ノーマン』はつくられた。しかし当時のベルリンでは上演されなかったようで、1951年のリヴィング・シアターが初演であると言われている。一方『イエスマン』初版は1930年から32年にかけて、とくに音楽教育とのつながりの中で多く上演されている。
・映像資料:能『谷行』(金剛流)
・グループに分かれてハウプトマンの独訳『谷行』と『イエスマン』初版を音読。
さらに、『イエスマン/ノーマン』(岩淵達治訳)を各自で黙読する。
・独訳『谷行』、『イエスマン』初版、『イエスマン/ノーマン』の違いについて、グループで意見交換。
・グループに分かれてハウプトマンの独訳『谷行』と『イエスマン』初版を音読。
さらに、『イエスマン/ノーマン』(岩淵達治訳)を各自で黙読する。
・独訳『谷行』、『イエスマン』初版、『イエスマン/ノーマン』の違いについて、グループで意見交換。
能の『谷行』と、独訳『谷行』、『イエスマン』初版、『イエスマン/ノーマン』では少年が山に行く理由や、谷に落とされる理由が違っている。
例えば、能の『谷行』では“修験道の修行”という宗教的な理由によって少年は山に入り、そこで体調を崩してしまう。修験道の“大法”によって修行中の病は禁忌とされているために、谷に落とされる。
独訳『谷行』では、少年は母の病気快癒を祈念しての“山修行”のために山に入り、やはり体調を崩したことが山修行の“大法”にふれるとして谷に落とされる。
一方、『イエスマン』初版では、少年が山に入るのは“研究旅行”のためである。そして、体調を崩した少年が谷底に落とされるのは“病気の者を背負っては狭い尾根を渡れないため”という実際的な理由が説明されている。
ここで、参加者から「研究旅行とは何なのか」という疑問が出された。同じ疑問がベルリンのギムナジウムの学生による討論の際にも発せられている。その結果、『イエスマン/ノーマン』の『イエスマン』第二版では、街で疫病が流行っているので薬を取りにいく、すなわち“街(共同体)を救うため”という必然性が追加されている。
そして『ノーマン』では、少年は素直に“しきたり”を受け入れない。街に帰ろうと言い、“しきたり”に反発する。ただし『ノーマン』では少年が山に入るのは、ただ“研究旅行”のためである。街(共同体)を救うという役目はなくなっている。
このように『谷行』や『イエスマン』初版、『イエスマン/ノーマン』では、細かな前提事項や事情が異なっている。
例えば、能の『谷行』では“修験道の修行”という宗教的な理由によって少年は山に入り、そこで体調を崩してしまう。修験道の“大法”によって修行中の病は禁忌とされているために、谷に落とされる。
独訳『谷行』では、少年は母の病気快癒を祈念しての“山修行”のために山に入り、やはり体調を崩したことが山修行の“大法”にふれるとして谷に落とされる。
一方、『イエスマン』初版では、少年が山に入るのは“研究旅行”のためである。そして、体調を崩した少年が谷底に落とされるのは“病気の者を背負っては狭い尾根を渡れないため”という実際的な理由が説明されている。
ここで、参加者から「研究旅行とは何なのか」という疑問が出された。同じ疑問がベルリンのギムナジウムの学生による討論の際にも発せられている。その結果、『イエスマン/ノーマン』の『イエスマン』第二版では、街で疫病が流行っているので薬を取りにいく、すなわち“街(共同体)を救うため”という必然性が追加されている。
そして『ノーマン』では、少年は素直に“しきたり”を受け入れない。街に帰ろうと言い、“しきたり”に反発する。ただし『ノーマン』では少年が山に入るのは、ただ“研究旅行”のためである。街(共同体)を救うという役目はなくなっている。
このように『谷行』や『イエスマン』初版、『イエスマン/ノーマン』では、細かな前提事項や事情が異なっている。
5.クルト・ヴァイルが提案した「学校オペラ」の意図
クルト・ヴァイルは政治的に強い意志を持っていたわけではなく、新しい音楽に関して熱心に活動していた。彼のあげた「学校オペラ」の趣旨は以下の三点である。
- (次の世代の)作曲家が、オペラの新しい基礎を学習するため
- 今までのような華美なものでなくいわゆる「小さなオペラ」、「単純で、不自然さのない」オペラの作り方を学習するため
- 「簡単にまねて歌えるという意味で子ども用ということではなく、慎重に、場合によっては長い時間をかけて学ぶ、それもまずは音楽的なことを学ぶとしても、同じ程度以上に精神的なことも学ぶために学校で用いられるように」
特に3が興味深い。教育劇というと簡素な形式と可動性が前面に出ていると考えられるが、ヴァイルは、音楽教育に関して、ゆっくりと時間をかけて取り組むことに意味があると考えているのだ。
ヴァイルは『イエスマン』初版の初演時のパンフレットで、「音楽の教育的効果は、子どもたちが音楽という回り道をしながら、ある考え方について集中的に取り組むことができる、という点にある」と述べている。
ヴァイルは『イエスマン』初版の初演時のパンフレットで、「音楽の教育的効果は、子どもたちが音楽という回り道をしながら、ある考え方について集中的に取り組むことができる、という点にある」と述べている。
6.ブレヒトの劇作上の主旨
ブレヒトは、舞台を日常に応用していくべきであり、舞台から思考し、改革したいと考えた。しかしそれは困難である。舞台にどうしても付随するさまざまな条件が、近代的な教育の理念とはぴったりとは一致しないためだ。ブレヒトは、演劇の実践者として、演劇としておもしろくすることと、日常に応用し教育を考えていくことが単純には結びつかないことに、初期の段階から気づいていたように見える。ただし、演劇という芸術メディアがおかれている歴史的条件が、当時と今日では異なることを無視するわけにはいかない。ブレヒトにとっても、ある時期には、演劇が政治教育のメディアでありうる可能性があったのだと思う。
7.ハイナー・ミュラー『教育劇との決別』
最後に、ハイナー・ミュラーがシュタインヴェークへ書いた手紙を紹介する(『教育劇との決別』1977年1月4日)。ハイナー・ミュラーは『ハムレットマシーン』で有名だが、過去に教育劇を書いていた。シュタインヴェークはブレヒトの初期の研究者である。
手紙には、次の革命的状況が来ない限り、教育劇は使えない。政治的選択を突きつけられない限り、教育劇はあまり意味がない。いまの状況が大きく変化するような時間がたたない限り、役にたたないだろう、と言ったことが記されている。
ただし、この手紙が書かれたのは1977年、東西ドイツの時代である。西側は政治の時代の末期であり、社会的な活動が健全なものでなくなっていた。一方で、東ドイツの社会主義にも未来はなく、ミュラーは、書けるものはもうないと思っていた時期であったことを念頭に置いてほしい。
次回は、現在における教育劇の使用価値について、教育劇をどのように活用できるのかを考える。
手紙には、次の革命的状況が来ない限り、教育劇は使えない。政治的選択を突きつけられない限り、教育劇はあまり意味がない。いまの状況が大きく変化するような時間がたたない限り、役にたたないだろう、と言ったことが記されている。
ただし、この手紙が書かれたのは1977年、東西ドイツの時代である。西側は政治の時代の末期であり、社会的な活動が健全なものでなくなっていた。一方で、東ドイツの社会主義にも未来はなく、ミュラーは、書けるものはもうないと思っていた時期であったことを念頭に置いてほしい。
次回は、現在における教育劇の使用価値について、教育劇をどのように活用できるのかを考える。

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.


