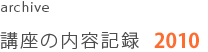


『ブレヒトにおける演劇と教育』
Vol.1「ブレヒトが『教育』に近づいた経緯」
2010年6月24日(木) 19時〜21時
中島 裕昭
(東京学芸大学)
《所 感》
ブレヒトの演劇理論書は本人が書いたものや、さまざまな演劇人が書いたものが存在するが、なかなか難解な点が多く、「叙事的演劇」「異化効果」など、言葉が独り歩きしている感がぬぐえなかったように思われる。
本レクチャーはそうした中で「コミュニケーション構造のメタレベル」という構造を導入して、さまざまなタームの説明を行ったことで、ブレヒト演劇理論をわかりやすくすることを積極的に試みていたことで、とても新鮮なものであった。また「叙事的」という言葉と「演劇」という言葉の結び付きがいかにヨーロッパ演劇で画期的であったかということも言及されており、ブレヒトの演劇が従来の「ドラマ的形式」とどのように異なるかが改めて明らかになったと考えられる。
ブレヒトの演劇理論書は本人が書いたものや、さまざまな演劇人が書いたものが存在するが、なかなか難解な点が多く、「叙事的演劇」「異化効果」など、言葉が独り歩きしている感がぬぐえなかったように思われる。
本レクチャーはそうした中で「コミュニケーション構造のメタレベル」という構造を導入して、さまざまなタームの説明を行ったことで、ブレヒト演劇理論をわかりやすくすることを積極的に試みていたことで、とても新鮮なものであった。また「叙事的」という言葉と「演劇」という言葉の結び付きがいかにヨーロッパ演劇で画期的であったかということも言及されており、ブレヒトの演劇が従来の「ドラマ的形式」とどのように異なるかが改めて明らかになったと考えられる。
記録:梅原宏司(立教大学講師・早稲田大学演劇博物館GCOEグローバル特別研究生)

1.ブレヒトが「教育」に近づいた経緯
ブレヒトの生涯と演劇論の展開は、以下の4期に分けられる。
- 初期:〜1926年、ブレヒトが本格的にマルクス主義の学習を開始するまで。
- ベルリン期:〜1933年、「叙事的演劇」の理論を先鋭化させ「教育劇」を開発する。この時期がブレヒトにとって最も理論的な時期であり、最も問題となる時期でもある。ブレヒトの理論は、彼を理解する俳優や劇団、観客などの関係者によって発展させられた。
- 亡命期:〜1949年、ナチの政権奪取により亡命、戯曲執筆を中心とする。この時期は俳優や劇団、観客などの関係者に恵まれず、そのため戯曲や映画シナリオの執筆に専念したので、オリジナルの大作が多い。
- 東ベルリン期:〜1956年、ベルリーナ・アンサンブルを指導。この時期は再び俳優や劇団、観客などの関係者に恵まれ、また国家から特権扱いをされて一見成功した演劇人のように見える時期であった。また戯曲では、他の作家の作品を改作したものが多い。
(1) ブレヒト劇におけるコミュニケーション構造とは何か?
まず、舞台で示される出来事・登場人物についてのメタレベルを設定する。このメタレベルは、コーラスや審判者など、また演劇を構成する演技・音楽などによって設定され、出来事と観客との間に距離を置き、観客と出来事の同一化・情緒化を切断し拒否する効果を持つ。
そして、現実世界の中での同様の出来事・言動に対する観客の態度決定を求める。
そして、現実世界の中での同様の出来事・言動に対する観客の態度決定を求める。
(2) ブレヒト演劇において求められる「異化効果」、「社会的身ぶり」とは何か?
異化効果とは、舞台で示される出来事・登場人物の言動の社会的身ぶりを意識させることである。
社会的身ぶりとは、ある人物が一定の歴史的条件の下で社会的に達成しようとしている意図、ある出来事が社会の中で持つ歴史的な意味を示すものである。
より詳しくは、佐和田他編『演劇学のキーワード』(ぺりかん社、2007年)の丸本隆の記事(191ページより)を参照してほしい。
社会的身ぶりとは、ある人物が一定の歴史的条件の下で社会的に達成しようとしている意図、ある出来事が社会の中で持つ歴史的な意味を示すものである。
より詳しくは、佐和田他編『演劇学のキーワード』(ぺりかん社、2007年)の丸本隆の記事(191ページより)を参照してほしい。
2.ブレヒト演劇論の展開
ドラマ的(劇的)演劇と叙事的演劇の対比
ヨーロッパの文芸理論ではアリストテレスの分類に基づき、伝統的に「叙事的」「劇的」「叙情的」の3分類が存在していた。「叙事的」というのは演劇に使われる分類ではなく、ホメロスなどの叙事詩について使われるものであった。したがって「叙事的演劇」という言葉自体が、すでにヨーロッパの文芸理論の伝統から逸脱する試みだったのである。
ブレヒトが自分で書いた演劇理論にはさまざまなものがあるが、『今日の世界は演劇によって再現できるか』(千田是也訳、白水社)に主なものが入っている。その中でも『「マハゴニー市の興亡」についての注』では、「劇的(ドラマ的)形式」と「叙事的形式」を二項対立的にキーワードで説明している。
ブレヒトが自分で書いた演劇理論にはさまざまなものがあるが、『今日の世界は演劇によって再現できるか』(千田是也訳、白水社)に主なものが入っている。その中でも『「マハゴニー市の興亡」についての注』では、「劇的(ドラマ的)形式」と「叙事的形式」を二項対立的にキーワードで説明している。
(1)「ドラマ的形式」による演劇のコミュニケーション構造
ドラマ的形式は、何よりも「舞台と観客による共同の表象」を重視する。ここではブレヒトが標的にした自然主義演劇について考えてみる。
舞台は観客と「第4の壁」によって仕切られ、完結した世界が演じられている。そのため舞台は統一感があるものとなる。また、終演後に観客が劇場の外へ出ていけば、劇場で上演されていた出来事は、すでに観客とは関係ないものとなる。
観客は舞台の上で演じられる世界の中へ感情移入し、追体験する。ここで「舞台と観客による共同の表象」が仮定される。
また、観客の舞台の表象や感情移入は、実際には個々に違うはずであるが、観客は全体として一つの共同体として想定され、同じ表象や感情移入を行うと想定される。
舞台は観客と「第4の壁」によって仕切られ、完結した世界が演じられている。そのため舞台は統一感があるものとなる。また、終演後に観客が劇場の外へ出ていけば、劇場で上演されていた出来事は、すでに観客とは関係ないものとなる。
観客は舞台の上で演じられる世界の中へ感情移入し、追体験する。ここで「舞台と観客による共同の表象」が仮定される。
また、観客の舞台の表象や感情移入は、実際には個々に違うはずであるが、観客は全体として一つの共同体として想定され、同じ表象や感情移入を行うと想定される。
(2)「叙事的形式」による演劇のコミュニケーション構造
叙事的形式は、ドラマ的形式が目的とする観客の感情移入・追体験を排する。
演技者のセリフや演技・音楽・美術は、出来事から距離をとり、社会的・歴史的文脈の中で出来事をコメントするものとして作用する。このことをブレヒトは、交通事故の状況を当事者が説明し再現する行為に例えている。こうした場合、当事者は状況についての「判断」を行いながら説明・再現を行い、また事故そのものから距離をとって、それぞれの状況にコメントすることによって説明がなされる。
例えば、クルト・ヴァイル作曲の『三文オペラ』などでは、「コメントする音楽」の手法として、ロマンチックな詞を、こっけいなメロディで歌うなどの手法を用いている。さまざまなズレをいろいろな形で用いるのである。パウル・デッサウ作曲の『コーカサスの白墨の輪』も、コメントする音楽の典型である。
統一感がある「ドラマ的形式」に対して、モンタージュ手法などが多用され、冷めた感じの作品となる。また、舞台と観客を区切る「第4の壁」は極力排除される。この発想の中には、アジアの演劇から得られたものもある。ブレヒトは京劇の梅蘭芳などからインスパイアされ、京劇・歌舞伎などの演技を、ヨーロッパのドラマ的形式とは異なる「異化的」なものと考えた。これを論じたのが「中国の俳優術における異化効果」である。また歌舞伎の観客の掛け声なども「第4の壁」を壊すものとしてとらえられた。これには先例があり、ブレヒトの先輩であるラインハルトは歌舞伎の花道を作って上演している。
また、観客は劇場の外に出ても、舞台で提示された問題について考え、議論することを求められる。これは個々の観客が個々の表象を持ち、個々の意見を持つことを前提としているからである。観客が自分の意見を持ちやすくするため、リラックスして舞台に臨むことが求められる。その一例が、劇場での喫煙の奨励である(これには飲食や喫煙を容認した歌舞伎の影響も考えられる)。
ブレヒトは舞台で問題を提示するが、問題についての自身の明確な答えを出さない。これはブレヒト以前のハウプトマンらの社会劇が、問題への答えを明確に出していること(「女性がすべきこと」を明示しているなど)と大きな違いである。こうした観客の答えが作劇にフィードバックすることもある。教育劇の『イエスマンとノーマン』は、最初『イエスマン』だけだったのだが、学校で上演したら観客から異論が出てきたので、『ノーマン』の部分を加えた。だから舞台を見て決まった答えが出てくることは、ブレヒトにとっては本意ではないのである。
演技者のセリフや演技・音楽・美術は、出来事から距離をとり、社会的・歴史的文脈の中で出来事をコメントするものとして作用する。このことをブレヒトは、交通事故の状況を当事者が説明し再現する行為に例えている。こうした場合、当事者は状況についての「判断」を行いながら説明・再現を行い、また事故そのものから距離をとって、それぞれの状況にコメントすることによって説明がなされる。
例えば、クルト・ヴァイル作曲の『三文オペラ』などでは、「コメントする音楽」の手法として、ロマンチックな詞を、こっけいなメロディで歌うなどの手法を用いている。さまざまなズレをいろいろな形で用いるのである。パウル・デッサウ作曲の『コーカサスの白墨の輪』も、コメントする音楽の典型である。
統一感がある「ドラマ的形式」に対して、モンタージュ手法などが多用され、冷めた感じの作品となる。また、舞台と観客を区切る「第4の壁」は極力排除される。この発想の中には、アジアの演劇から得られたものもある。ブレヒトは京劇の梅蘭芳などからインスパイアされ、京劇・歌舞伎などの演技を、ヨーロッパのドラマ的形式とは異なる「異化的」なものと考えた。これを論じたのが「中国の俳優術における異化効果」である。また歌舞伎の観客の掛け声なども「第4の壁」を壊すものとしてとらえられた。これには先例があり、ブレヒトの先輩であるラインハルトは歌舞伎の花道を作って上演している。
また、観客は劇場の外に出ても、舞台で提示された問題について考え、議論することを求められる。これは個々の観客が個々の表象を持ち、個々の意見を持つことを前提としているからである。観客が自分の意見を持ちやすくするため、リラックスして舞台に臨むことが求められる。その一例が、劇場での喫煙の奨励である(これには飲食や喫煙を容認した歌舞伎の影響も考えられる)。
ブレヒトは舞台で問題を提示するが、問題についての自身の明確な答えを出さない。これはブレヒト以前のハウプトマンらの社会劇が、問題への答えを明確に出していること(「女性がすべきこと」を明示しているなど)と大きな違いである。こうした観客の答えが作劇にフィードバックすることもある。教育劇の『イエスマンとノーマン』は、最初『イエスマン』だけだったのだが、学校で上演したら観客から異論が出てきたので、『ノーマン』の部分を加えた。だから舞台を見て決まった答えが出てくることは、ブレヒトにとっては本意ではないのである。
(3)「教育劇」のコミュニケーション構造
「教育劇」の「教育」とは、人を育てるという、教育の最も広義の意味を持っている。ブレヒトはそうした教育によって、人々が出来事への賛否を決定し、政治的態度を明確にすることを求めた。現在の日本などではそうした状況は想定しにくいが、アウグスト・ボアールなどの実践にはそうした政治的前提が維持されている。
「出来事をコメントする」のは「叙事的形式」と同じであるが、明確な問題設定がなされ、またコーラスや審判者などが、出来事についての「裁判」などの仮想の議論の場を設定しリードする。
コーラスは、そもそもギリシャ悲劇にもメタレベルとして存在したものであり、その後のドラマ的形式にも内包されていたものだが、ブレヒトは再度メタレベルを見えるようにしたのである。
また、「単純に見る人としての観客」を拒否し、一緒に関与する「観客」(ステークホルダーともいえる)を想定している。そもそも教育劇は、工場や学校で、ステークホルダーとしての観客とともに作られたものであった。そのため観客から縁遠い主題は取り上げられなかった。また、後の観客に縁遠いと考えられた題材の教育劇は再上演されなかった。例えば、『処置』はブレヒトによって上演が禁止されたが、これは主題が共産党の話なので、共産党関係者以外には意味がないということが禁止理由の中に入っている(他にも理由があるが)。
ところが、ステークホルダーと時間をかけて教育劇を作っていく機会は、亡命期にはなくなってしまった。それを「失われた応用演劇の基盤」としてとらえることができる。
これに対し、教育劇のようにステークホルダーだけで作ることがない普通の叙事的演劇は、外部の人々を想定するので、いろいろなことを作品に書きこまなければならないため、後世の演出家による再解釈がしやすくなる。例えば叙事的演劇の典型例の一つ、『アルトゥロ・ウイの興隆』は、テキストではヒトラーの政治的役割が強調されているが、ベルリーナ・アンサンブルのハイナー・ミュラーは、ヒトラーのカリスマ的魅力の危険を、役者の肉体によって強調して成功した。
ただし、今日の日本でも、ステークホルダーと作っていくような、応用演劇としての教育劇のニーズは存在すると考えられる。構造的に選択を迫られる問題はいつでも存在するからである(普天間基地問題、ダム建設問題など)。その中でステークホルダーの行動や考えをシミュレーションすることは意味がある。社会問題だけでなくても、個人的な問題についてそのような手法で考えることは意味があるはずである。
「出来事をコメントする」のは「叙事的形式」と同じであるが、明確な問題設定がなされ、またコーラスや審判者などが、出来事についての「裁判」などの仮想の議論の場を設定しリードする。
コーラスは、そもそもギリシャ悲劇にもメタレベルとして存在したものであり、その後のドラマ的形式にも内包されていたものだが、ブレヒトは再度メタレベルを見えるようにしたのである。
また、「単純に見る人としての観客」を拒否し、一緒に関与する「観客」(ステークホルダーともいえる)を想定している。そもそも教育劇は、工場や学校で、ステークホルダーとしての観客とともに作られたものであった。そのため観客から縁遠い主題は取り上げられなかった。また、後の観客に縁遠いと考えられた題材の教育劇は再上演されなかった。例えば、『処置』はブレヒトによって上演が禁止されたが、これは主題が共産党の話なので、共産党関係者以外には意味がないということが禁止理由の中に入っている(他にも理由があるが)。
ところが、ステークホルダーと時間をかけて教育劇を作っていく機会は、亡命期にはなくなってしまった。それを「失われた応用演劇の基盤」としてとらえることができる。
これに対し、教育劇のようにステークホルダーだけで作ることがない普通の叙事的演劇は、外部の人々を想定するので、いろいろなことを作品に書きこまなければならないため、後世の演出家による再解釈がしやすくなる。例えば叙事的演劇の典型例の一つ、『アルトゥロ・ウイの興隆』は、テキストではヒトラーの政治的役割が強調されているが、ベルリーナ・アンサンブルのハイナー・ミュラーは、ヒトラーのカリスマ的魅力の危険を、役者の肉体によって強調して成功した。
ただし、今日の日本でも、ステークホルダーと作っていくような、応用演劇としての教育劇のニーズは存在すると考えられる。構造的に選択を迫られる問題はいつでも存在するからである(普天間基地問題、ダム建設問題など)。その中でステークホルダーの行動や考えをシミュレーションすることは意味がある。社会問題だけでなくても、個人的な問題についてそのような手法で考えることは意味があるはずである。
質疑応答
Q1: 映画の方が演劇より忘我的になりやすいと思うのだが、なぜ彼は映画『クーレ・ヴァンペ』を作ったのか?
ブレヒトと映画は縁が深い。台本やシノプシスをたくさん作っている。また映画理論家のベラ・バラージュらともつきあいがあった。
そもそも、自然主義の演劇は観客を観客組織の会員として組織した。自然主義演劇は多くの会員に対する事実上のマスメディアだった。
その役割を、後に複製可能な映画が担った。『戦艦ポチョムキン』などの作品は政治集会でも上映された。ブレヒトの友人ヴァルター・ベンヤミンは映画の魅力を、マスメディアとしての大衆の操作可能性に見た。今はビデオやDVDを個人で見るような状態が出現し、メディアの受容形態が変わっている。
ただ、ブレヒトが関わった映画の『クーレ・ヴァンペ』や『三文オペラ』、『死刑執行人もまた死す』は、どれもブレヒトの個人的な考えが全面的に受け入れられたわけではなく、その点についてのブレヒト自身の「不完全燃焼」が伺える。
そもそも、自然主義の演劇は観客を観客組織の会員として組織した。自然主義演劇は多くの会員に対する事実上のマスメディアだった。
その役割を、後に複製可能な映画が担った。『戦艦ポチョムキン』などの作品は政治集会でも上映された。ブレヒトの友人ヴァルター・ベンヤミンは映画の魅力を、マスメディアとしての大衆の操作可能性に見た。今はビデオやDVDを個人で見るような状態が出現し、メディアの受容形態が変わっている。
ただ、ブレヒトが関わった映画の『クーレ・ヴァンペ』や『三文オペラ』、『死刑執行人もまた死す』は、どれもブレヒトの個人的な考えが全面的に受け入れられたわけではなく、その点についてのブレヒト自身の「不完全燃焼」が伺える。
Q2: Q1の方とは反対に、映画の方が異化効果を出せるという考え方もある。ゴダールやストローブ=ユイレ、フォン=トリアーなど、ブレヒト的と評される監督もいる。そうした映画のモンタージュ手法と異化効果の関係はどう思うか?
緊密なドラマに対して、叙事的な形式はいろいろな要素が盛り込める。それがモンタージュである。小説でもいろいろな実験がなされている(ドス・パソスの、新聞記事的文章や小説的内容を並列する手法など)。ブレヒトはモンタージュ・映画編集にいろいろな可能性を感じていたと思う。
ただ、映画作品は作品がパッケージ化されて出てくるということがあり、まとまりが出てきてしまうと思う。映画史でいうと、初期の方がいろいろな試みがあったと思う。
ストローブ=ユイレはブレヒトの『ユリウス・カエサル氏の商売』を映画化している。構造的には非常に面白いが、映画の全体的なまとまりでいったら、ブレヒト的な効果が出ているかどうかの評価は難しい。個人的な判断としては原作の方が、ブレヒト的効果がよく出ていると思う。
ただ、映画作品は作品がパッケージ化されて出てくるということがあり、まとまりが出てきてしまうと思う。映画史でいうと、初期の方がいろいろな試みがあったと思う。
ストローブ=ユイレはブレヒトの『ユリウス・カエサル氏の商売』を映画化している。構造的には非常に面白いが、映画の全体的なまとまりでいったら、ブレヒト的な効果が出ているかどうかの評価は難しい。個人的な判断としては原作の方が、ブレヒト的効果がよく出ていると思う。

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.


