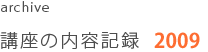


『ワークショップ論 ― 演劇ワークショップの力』
Vol.7「演劇ワークショップの実践報告とそこからみえてくる可能性
〜水俣、そしてアチェ(インドネシア)での経験を中心に」
〜水俣、そしてアチェ(インドネシア)での経験を中心に」
2010年1月24日(日) 13時〜15時
花崎 攝
(演劇デザインギルド)
《所 感》
今回は2006年の水俣病公式確認50年事業でのワークショップと、アチェでのワークショップの試みの報告である。両方とも、極めて複雑な地元社会の人間関係の中で、どのように参加者を募り、よりよいワークショップができるかということに非常に苦心している。水俣での経験は、政治と演劇活動の関係を考えざるを得ない経験であり、障がい者との経験でもある。彼らは、選択の余地なく良くも悪くも異なった経験をしているため視点も違い、一般には必ずしも知られていない制度のもとで生きている。彼らと協働作業することは、非常に学ぶところが多く、考えされられる。一方、そこでコミュニケーションの仕方を工夫する必要があった。またアチェでは、参加者の暮らす地域の地図を作っているうちに、内戦時の記憶が鮮明によみがえってくるという経験もあった。内戦時の記憶を分かち合うことで、大人の都合で敵味方に分断されていた子どもたちが、ともに内戦の被害者であったことが確認され、和解のための貴重な糧となった。
記録者は、こうした複雑な地元社会の中に飛び込んで行った演劇人の役割というところに非常に関心を抱いた。現在の日本では、演劇人と呼ばれる人々は圧倒的に大都市に偏っている。そうした演劇の社会的役割を再考するのに、水俣とアチェの経験は役立つと考えさせられた。
今回は2006年の水俣病公式確認50年事業でのワークショップと、アチェでのワークショップの試みの報告である。両方とも、極めて複雑な地元社会の人間関係の中で、どのように参加者を募り、よりよいワークショップができるかということに非常に苦心している。水俣での経験は、政治と演劇活動の関係を考えざるを得ない経験であり、障がい者との経験でもある。彼らは、選択の余地なく良くも悪くも異なった経験をしているため視点も違い、一般には必ずしも知られていない制度のもとで生きている。彼らと協働作業することは、非常に学ぶところが多く、考えされられる。一方、そこでコミュニケーションの仕方を工夫する必要があった。またアチェでは、参加者の暮らす地域の地図を作っているうちに、内戦時の記憶が鮮明によみがえってくるという経験もあった。内戦時の記憶を分かち合うことで、大人の都合で敵味方に分断されていた子どもたちが、ともに内戦の被害者であったことが確認され、和解のための貴重な糧となった。
記録者は、こうした複雑な地元社会の中に飛び込んで行った演劇人の役割というところに非常に関心を抱いた。現在の日本では、演劇人と呼ばれる人々は圧倒的に大都市に偏っている。そうした演劇の社会的役割を再考するのに、水俣とアチェの経験は役立つと考えさせられた。
記録:梅原宏司(早稲田大学演劇博物館GCOE特別研究員)

はじめに、アチェの事情を説明しておきたい。アチェは3年計画で毎年おこなう予定だったが、3年目の2009年11月にスマトラ島地震の影響、その後発生した外国人襲撃事件で計画が延期になっている。この講座を企画した当時は、事業全体の報告を予定していたが、事業が完結していない。了解したうえで、お聞きいただきたい。

1.2006年の水俣病公式確認50年事業でのワークショップ
実施概要
ワークショップ実施時期:2006年4月〜10月
創作舞台の発表:10月14日(土)
ワークショップ実施場所:もやい館、公民館等
創作舞台の発表:水俣市文化会館
実施主体 主催:水俣病公式確認50年事業実行委員会
共催:水俣市教育委員会
製作:演劇デザインギルド
ワークショップ実施時期:2006年4月〜10月
創作舞台の発表:10月14日(土)
ワークショップ実施場所:もやい館、公民館等
創作舞台の発表:水俣市文化会館
実施主体 主催:水俣病公式確認50年事業実行委員会
共催:水俣市教育委員会
製作:演劇デザインギルド
実施計画
プレ・ワークショップ(2回)
第一期 交流期間(第1回〜第6回)
第二期 取材と構成台本つくり(第7回〜第8回)
第三期 稽古準備期間(第9回〜リハーサル)
舞台発表(10月14日・水俣市文化会館)
ビデオ上映会とふりかえり
(計ワークショップ19回、出前ワークショップ9回 *プレ・ワークショップを除く。)
プレ・ワークショップ(2回)
第一期 交流期間(第1回〜第6回)
第二期 取材と構成台本つくり(第7回〜第8回)
第三期 稽古準備期間(第9回〜リハーサル)
舞台発表(10月14日・水俣市文化会館)
ビデオ上映会とふりかえり
(計ワークショップ19回、出前ワークショップ9回 *プレ・ワークショップを除く。)
主催の実行委員会が水俣市内の49団体の代表者からなるもの(網羅的)であった。
この中に4つの部会があり、その「地域福祉部会」の事業としてワークショップが行われた。私たちの担当した「創作舞台芸術」以外に40〜50の事業が行われていた。
予算は、環境省、熊本県、水俣市が出資した。
部会内部にはさまざまな利害関係の絡み合いがあったため、事業の方向性をめぐって「事業目的」「事業目標」「事業内容」など官僚的な文章がいくつも定められ、その文言をめぐる綱引きが続いた。政治的なかけひきの直中に放り込まれた感があった。
この中に4つの部会があり、その「地域福祉部会」の事業としてワークショップが行われた。私たちの担当した「創作舞台芸術」以外に40〜50の事業が行われていた。
予算は、環境省、熊本県、水俣市が出資した。
部会内部にはさまざまな利害関係の絡み合いがあったため、事業の方向性をめぐって「事業目的」「事業目標」「事業内容」など官僚的な文章がいくつも定められ、その文言をめぐる綱引きが続いた。政治的なかけひきの直中に放り込まれた感があった。
(熊本県のテレビ局のニュースビデオを見る)
「普通に来てたら舞台に上がることになっちゃった」(ワークショップ参加者・小学生)
本番1か月前、構成台本の検討会において、「何を伝えたいのかわからない」「もっと障がい者のことを入れてほしい」という意見が出された。
最終的に、水俣病を学ぶ孫と多くを語りたがらないお菓子屋夫婦の話から始まり、参加者の記憶や願いをつづる公演となった。
本番1か月前、構成台本の検討会において、「何を伝えたいのかわからない」「もっと障がい者のことを入れてほしい」という意見が出された。
最終的に、水俣病を学ぶ孫と多くを語りたがらないお菓子屋夫婦の話から始まり、参加者の記憶や願いをつづる公演となった。
水俣病は現在も続いている問題である。1995年政治的和解が不十分ながら一応なされる。これは患者の高齢化が一因をなしているが、その後の関西訴訟でチッソだけでなく国の責任を最高裁が認めたことが契機になり、補償をめぐる訴えが再燃した。現在、新しく7,000人以上が患者認定申請している。
また現在進行中のチッソ分社化(補償目的と営利目的の会社に分ける)問題もある。患者が死に絶えたら問題はすべて封印し、なかったことになり、チッソの営利部門は何食わぬ顔をして存続する姿勢である。
また現在進行中のチッソ分社化(補償目的と営利目的の会社に分ける)問題もある。患者が死に絶えたら問題はすべて封印し、なかったことになり、チッソの営利部門は何食わぬ顔をして存続する姿勢である。
そんななか、今につづく深刻な被害の一つは、地域住民の人間関係が壊れていることである。水俣市は人口が3万人を割り、市として存続が危うい状態である。地域最大企業チッソの存在がまちの屋台骨を支えてきた現実があり、「チッソにはなるべく文句を言ってくれるな」という住民の声がある。また水俣病に関わりたくない市民も多い。これには水俣市全体に関わる『水俣病』の風評被害も反映している。
これに対して、患者・支援者はチッソに誠実な対応を求めている。しかし、患者にも認定・未認定・新申請患者の間でコンフリクトがあり、支援者でも地元支援者(チッソに関係ある人とそうでない人)、「よそ者」と呼ばれる地元出身でない支援者、地域外の支援者の間にもさまざまな立場、関係があり、一枚岩ではない。
こうしたコンフリクトは、一朝一夕で水に流すことはできない。そこで、いかに人間関係の再生を目指すのかが重要な課題になる。
これに対して、患者・支援者はチッソに誠実な対応を求めている。しかし、患者にも認定・未認定・新申請患者の間でコンフリクトがあり、支援者でも地元支援者(チッソに関係ある人とそうでない人)、「よそ者」と呼ばれる地元出身でない支援者、地域外の支援者の間にもさまざまな立場、関係があり、一枚岩ではない。
こうしたコンフリクトは、一朝一夕で水に流すことはできない。そこで、いかに人間関係の再生を目指すのかが重要な課題になる。
また、マスコミは、水俣病への注目度は高いが(「脳性麻痺」の中に水俣病患者がいる可能性があるが、科学的に未解明であり、中には自ら水俣病と名乗りたくない人もいる)、市内の水俣病以外の障がい者(施設・団体)については注目度が低い。年金等、社会保障の仕組みの違い、そこから生まれる経済格差などもからんで、関係者の間にわだかまりもある。その結果、水俣病当事者とそれ以外の障がい者は交流できていない。
こうした複雑な状況が、ワークショップの設定テーマ、「聴き、聴き合う」、「今までに出会ったことのない人に、出会ったことのない仕方で出会う」、および以下の実施計画の背景要因だった。
こうした複雑な状況が、ワークショップの設定テーマ、「聴き、聴き合う」、「今までに出会ったことのない人に、出会ったことのない仕方で出会う」、および以下の実施計画の背景要因だった。
まず、常駐スタッフ(福原忠彦さん。半年地元で暮らす)を置くことを決める。しかし、予算ねん出が大変困難だった。
福原は、他の施設をきめこまかく回った。これは、患者以外のワークショップ参加者がほとんどいなかったことが原因だが、その背景には「どうせ水俣病に回収され、利用されちゃうんでしょ…」という施設関係者の思いもあった。
直接「水俣病」という文言をいれずに、音楽家港大尋氏とともにおこなった「失われた「うた」を求めて〜水俣50年のうた探し〜」によるアサヒ・アート・フェスへの参加も、圧倒的に不足していた予算の補てんと、より広い人たちとの関係づくり、および地元の歌、伝統芸能にフォーカスすることで、「水俣病」だけに偏った地域イメージの払しょくの一助として役立った。
福原は、他の施設をきめこまかく回った。これは、患者以外のワークショップ参加者がほとんどいなかったことが原因だが、その背景には「どうせ水俣病に回収され、利用されちゃうんでしょ…」という施設関係者の思いもあった。
直接「水俣病」という文言をいれずに、音楽家港大尋氏とともにおこなった「失われた「うた」を求めて〜水俣50年のうた探し〜」によるアサヒ・アート・フェスへの参加も、圧倒的に不足していた予算の補てんと、より広い人たちとの関係づくり、および地元の歌、伝統芸能にフォーカスすることで、「水俣病」だけに偏った地域イメージの払しょくの一助として役立った。

ワークショップは以下のような過程で行われた。
第1期(交流期間)…町歩きなどをする=チッソが文化活動に熱心だった(大リーガー、バレエ団、大相撲などを呼ぶ)記録を発見する。患者は車移動が多いので、町の人にとっても患者にとっても、まちを歩くことは新鮮な経験だった。
また患者はみな仕事をしたいので、仕事についての話と夢を演劇にした(旅行の添乗員など)
また患者はみな仕事をしたいので、仕事についての話と夢を演劇にした(旅行の添乗員など)
第2期(取材期間)…患者は聞きとられてばかりなので、彼らが聞きたいことを聞いてほしいという思いがあったため、そのようなプログラムを組んだ。ワークショップに参加していない人の声も舞台に反映させたいという思いもあった。
また、ワークショップ期間を通じて、出前ワークショップを行った。10分、15分、30分という、考えられない短さで、内容はマッサージや体を使ったゲームなどだった。これは、水俣では、顔見知りになり、信頼関係をつくることが非常に重要だからだ。、出前(押しかけ?!)ワークショップで参加をよびかけ、事業の周知、広報を目指した。それは福原の努力によるところがとても大きく、効果も大きかった。
また、ワークショップ期間を通じて、出前ワークショップを行った。10分、15分、30分という、考えられない短さで、内容はマッサージや体を使ったゲームなどだった。これは、水俣では、顔見知りになり、信頼関係をつくることが非常に重要だからだ。、出前(押しかけ?!)ワークショップで参加をよびかけ、事業の周知、広報を目指した。それは福原の努力によるところがとても大きく、効果も大きかった。
ワークショップ後半、第3期(稽古期間)に入る頃からデザインギルドは「プロの演劇人」という立場を、あえて鮮明にしていった。これは、デザインギルドを呼んだ支援者のコーディネーターが「患者の苦しみを舞台で表現してほしい」という考えであったが、患者の「多様なひとたちと交流したい」「悲劇の主人公でない自分を表現したい」「『患者』であることだけに疲れた」という声を聞き、「水俣病の水俣」でなく「水俣病を包括した水俣」を表現したいと考えたためである。
こうして、意図的にデザインギルドが「プロ」という権力行使を行うことで、参加者の意思を尊重し、ギルドの判断を貫徹することにし、台本も花崎たちの責任で作った。
ライブペインティングについては、ある障がい者施設の入所者たちが福原と仲良くなり、参加を希望したのだが、施設側が難色を示し、結局その施設が前々日に舞台への参加を決めたので、そうした参加形態を取った。ここでも、障害者が個人の判断で自らの行動を決められない現実を垣間見ることとなった。
さまざまな混乱もあった。例えば、最初にデザインギルドを呼んだコーディネーターが、水俣病のみにフォーカスした舞台が実現しないとわかると、別の劇団を呼んで、もう一つの公演上演を行った(出演者も重なった)のである。この動きも、水俣病をめぐる長い歴史のなかでの複雑な人間関係、力関係の一つの表れである。
○主な成果
小中高生…水俣病が市内のことと思えなかったのが、理解を深められた。
水俣病とそれ以外の障がい当事者が共同作業できた(現状では、施設・支援者はそうでない)
資料館(外部の人が来る)以外のところで、市内の人が患者の声を聴く機会ができた。
水俣病とそれ以外の障がい当事者が共同作業できた(現状では、施設・支援者はそうでない)
資料館(外部の人が来る)以外のところで、市内の人が患者の声を聴く機会ができた。
○ふりかえり
○その後…
ワークショップの参加者有志によって「水俣ば生きる会」が結成された。患者、障害者、一般市民を含む、水俣ではめずらしい立場の違う人たちが集うグループである。一方、東京では、患者のひとりが上京したことがきっかけとなり、「世田谷水俣交流実行委員会」(自立生活を行う世田谷の障がい者と水俣病患者の交流の場・水俣の患者に「自立生活」という第三の道を示したいという思いがある)ができる。この交流は今でも続いている。
これらの活動は、演劇ワークショップが一過性の活動に終わらず、地域の暮らしや人間関係をかえていく力になりうるという考えに基づいておこなっている。
これらの活動は、演劇ワークショップが一過性の活動に終わらず、地域の暮らしや人間関係をかえていく力になりうるという考えに基づいておこなっている。
2.アチェの子どもたちと創る演劇ワークショップ
事業概要
主催:国際交流基金
共催:コミュニタス・ティカール・パンダン (Komunitas Tikar Pandan)
主催:国際交流基金
共催:コミュニタス・ティカール・パンダン (Komunitas Tikar Pandan)
事業概要
主催:国際交流基金
共催:コミュニタス・ティカール・パンダン (Komunitas Tikar Pandan)
主催:国際交流基金
共催:コミュニタス・ティカール・パンダン (Komunitas Tikar Pandan)
第1回 アチェの子どもたちと創る演劇ワークショップ
アグス・ヌール・アマル(アチェ人ストーリーテラー、俳優)
当初の事業目的は、内戦によって被害を受けた子どもたちの精神的なケアをめざすことであった。が、しかし、精神的なケアをおこなうには、心理学の専門家等との共同作業が必要であり、また継続的なケアが欠かせない。短期間しか滞在できない私たちには責任が取りにくい。そのため、現地のカウンターパートとも協議し、現地の状況の推移も加味し、その都度、修正しながら進行している。現在は、現地の復興を担う、とくに文化的な活動を推進しうる人材育成に、その目的がシフトしてきている。
このワークショップでは、事業開始時に出会うことのできた、現地のカウンターパート、コミュニタス・ティカール・パンダン(NGO)と、俳優アグス・ヌール・アマルが重要な役割を果たしている。
このワークショップでは、事業開始時に出会うことのできた、現地のカウンターパート、コミュニタス・ティカール・パンダン(NGO)と、俳優アグス・ヌール・アマルが重要な役割を果たしている。
第1回
参加した子どもたちは、GAM地域や国軍地域など背景のちがう3か所から集まっているので最初は表情が硬かった。また村を出ることが初めての子もおり、付き添いの人に同行してもらった。この付き添いの人々が重要だった。
カウンターパートのスタッフが、入れ替わり立ち替わりいっぱいいた。日本的な感覚からすると、役割のはっきりしない人もいたのだが、緊張している参加者の子どもたちをリラックスさせてくれたり、さまざまなコミュニケーションを取る手助けになった。
Jポップの松浦亜弥の振り付けもやった(現地で人気があった)。
ワークショップは、演劇だけでなく、美術、音楽、ダンス、また地元の伝統芸能も含めておこない、「10年後のアチェを考える」というテーマで演劇をつくり発表した。
カウンターパートのスタッフが、入れ替わり立ち替わりいっぱいいた。日本的な感覚からすると、役割のはっきりしない人もいたのだが、緊張している参加者の子どもたちをリラックスさせてくれたり、さまざまなコミュニケーションを取る手助けになった。
Jポップの松浦亜弥の振り付けもやった(現地で人気があった)。
ワークショップは、演劇だけでなく、美術、音楽、ダンス、また地元の伝統芸能も含めておこない、「10年後のアチェを考える」というテーマで演劇をつくり発表した。
第2回 アチェ子ども会議
第1回目の参加者に再び集まってもらった。背景のちがう参加者相互のより深い相互理解とネットワークづくりに主眼をおき、地元のアーティストの協力を得てミニ文化祭を実施した。
まず、見学地(タケゴン)で地図づくりの実習をおこない、次に自分たちの村の地図作り…第1回では「敵味方」から「相互理解」へという意図を持っていったが、参加者の不安が強くて深く踏み込むことができなかった
まず、見学地(タケゴン)で地図づくりの実習をおこない、次に自分たちの村の地図作り…第1回では「敵味方」から「相互理解」へという意図を持っていったが、参加者の不安が強くて深く踏み込むことができなかった
⇒第2回で地図を作ると、詳細な内戦の記憶・経験が噴出してきた。地図を媒介とすること
で、客観的な描写がなされ、個人的な感情の噴出がおこっても、語り手が自らを支える
よすがとなった。地図の持つ有効性と可能性に、進行役自ら改めて驚く出来事だった。
アチェにおける日本人である進行役の役割とその可能性については、内戦に直接の利害関係をもたない第三者であるがゆえに、平和構築のきっかけ作りができるのではないかと考えている。人間不信があったので「表現が、受け入れられること、伝わるのだと実感することをめざす」ということが重要だった。
第3回は、状況もさらに変化してきているので、カウンターパートと協議して再考する予定。いまのところ、地図を使った運営を行いたいと考えている。
第3回は、状況もさらに変化してきているので、カウンターパートと協議して再考する予定。いまのところ、地図を使った運営を行いたいと考えている。
質疑応答
Q1: 水俣で常駐スタッフを務めた福原さんはどんなバックグラウンドなのか?
立教大学の如月小春の授業で演劇ワークショップを、水俣キャンプに参加した友人の影響で水俣病について考えるようになった。世田谷でスタッフとしてワークショップをしたときに花崎と知り合い、水俣病公式確認50年事業に参加することになった。
Q2: アチェで子どもたちが作った作品のモデルなどは、情報があったのか?
地元のアマチュア劇団からの情報はあった。また、参加者のなかには、イスラム学校で
寄宿生活している子がおり、学校できなかった演劇をつくりたいという情熱があった。
Q3: 我々が考える以上にそうした作品を作ることは危ない橋を渡ることもありうると思うが?
大人たちは「子どもたちはすごい、我々にはできない」と言っていた。
Q4: やはり文化祭という文脈があってできたのではないか?
語りの文化が盛んだった地方であるが、大人は間接直接に内戦に関与していたので祭りなど
失われた文化的な行事等をにわかに復興するのが難しいと聞いている。内戦に駆りだされ
なかった子どもたち(青少年)がイニシアティブをとれば可能になるかもしれない。
また、地域で子どもたちの声を表現する手段として演劇を使ってほしいという希望も ある。子どもたちは本格的な文化祭を目指したがっているので、文化的オーガナイザーを 養成したいというのが我々の願いである。
また、地域で子どもたちの声を表現する手段として演劇を使ってほしいという希望も ある。子どもたちは本格的な文化祭を目指したがっているので、文化的オーガナイザーを 養成したいというのが我々の願いである。
Q5: 障がい者を対象としたワークショップで新しい発見は?
私たちとは良くも悪くも違う経験をしているから視点も違うこと、健常者が知らない制度の
もとで生きていること、コミュニケーションの仕方に工夫がある。単純に健常者と障がい
者が平等だとは思わないが、対等にできるとは思っている。
違っている視点を持つことの強みやエネルギーの集中発揮の仕方、人に合わせられない ことが意見表明として有効に働くこともある。
健常者とおこなうときと、違うとはあまり思わないが、障がい者との方が気づくことは 多いかな?
違っている視点を持つことの強みやエネルギーの集中発揮の仕方、人に合わせられない ことが意見表明として有効に働くこともある。
健常者とおこなうときと、違うとはあまり思わないが、障がい者との方が気づくことは 多いかな?
Q6: 地図を作ることへの抵抗はあったか?また、カウンターパートが地図を重視する理由は?
抵抗感はなかったが、地元には地図そのものもなかった(軍事的な理由もある)。
カウンターパートがグループワークをうまくやってくれた。
今のアチェの切実な課題の一つは自分たちの手で経済的復興を達成することで、作物 の流通がうまくいっていないことなどがあり、地図が必要で、歴史の聞き取りにも役に 立っている。
カウンターパートがグループワークをうまくやってくれた。
今のアチェの切実な課題の一つは自分たちの手で経済的復興を達成することで、作物 の流通がうまくいっていないことなどがあり、地図が必要で、歴史の聞き取りにも役に 立っている。
Q7: 地図を作る時紙の上に書くのは抵抗があるケースがある。修正もきかないので、地面の上の
方がうまくいくことも多い。アチェの場合は、紙に書くことによって記憶を呼び覚まされる
ケースだったのではないか?地図を通して見ている(それで開発をやってしまう)
政府・軍・企業の世界と、人々が生活している景観は違う。また山間部に行くと、地図を 見てはじめて気づくこともある。
政府・軍・企業の世界と、人々が生活している景観は違う。また山間部に行くと、地図を 見てはじめて気づくこともある。
(花崎・里見) 子どもにとって地図はとても新鮮なものである。

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.


