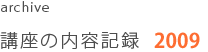


『ワークショップ論 ― 演劇ワークショップの力』
Vol.3「アウグスト・ボアール『試みの演劇』の成立背景
―ラテンアメリカ民衆演劇運動とブレヒト受容―」
―ラテンアメリカ民衆演劇運動とブレヒト受容―」
2009年12月20日(日) 13時〜15時
里見 実
(國學院大學非常勤講師)
《所 感》
アウグスト・ボアールは、ラテンアメリカの民衆演劇運動、そこから始まったワークショップの先駆け的な存在である。初期のボアールはそれを「試みの演劇」と呼んでいた、ふだんの生活に遍在する「抑圧」を意識化・対象化すること、また演劇において固定化されている「演者⇔観客」という関係を壊して、観客がアクター(行為者)として能動的に舞台に介入し、ドラマの流れを変えることを目指した演劇的実験である。ボアールの「試みの演劇」にとりわけ大きな影響を及ぼしているのは、ブレヒトの「教育劇」の思想と方法である。「教育」という言葉の意味の転換、「教師⇔生徒」という権力関係の脱構築という点ではパウロ・フレイレの教育論の影響も大きい。
こうしたボアールの業績は、ヨーロッパでのスタニスラフスキーやブレヒトの受容とはまた違ったものであり、それぞれの比較も今後重要になるのではないかと考えさせられた。
アウグスト・ボアールは、ラテンアメリカの民衆演劇運動、そこから始まったワークショップの先駆け的な存在である。初期のボアールはそれを「試みの演劇」と呼んでいた、ふだんの生活に遍在する「抑圧」を意識化・対象化すること、また演劇において固定化されている「演者⇔観客」という関係を壊して、観客がアクター(行為者)として能動的に舞台に介入し、ドラマの流れを変えることを目指した演劇的実験である。ボアールの「試みの演劇」にとりわけ大きな影響を及ぼしているのは、ブレヒトの「教育劇」の思想と方法である。「教育」という言葉の意味の転換、「教師⇔生徒」という権力関係の脱構築という点ではパウロ・フレイレの教育論の影響も大きい。
こうしたボアールの業績は、ヨーロッパでのスタニスラフスキーやブレヒトの受容とはまた違ったものであり、それぞれの比較も今後重要になるのではないかと考えさせられた。
記録:梅原宏司(早稲田大学演劇博物館GCOE特別研究員)

はじめに
「ボアール・ワークショップ」というものはよく聞くし中心的な役割を果たしていることはよくわかっているが、その仕事の具体的な内容はあまり知られていないようである。
一つにはテクストに触れる機会がない(かなりの本が絶版・品切れになっている)ためと思われる。彼の思想と方法を知るにはまずはテクストに触れるのがいちばん手っとり早いのだが。
ボアールの文章は平明で面白い(面白すぎる?)のですぐに入っていける。里見訳の『被抑圧者の演劇』は仏訳からの重訳であった。この本でボアールは世界的に広く知られるようになった。現在は彼の方法の集大成ともいえる『職業俳優とそうではない人々のための演劇ゲーム集』を訳している。
一つにはテクストに触れる機会がない(かなりの本が絶版・品切れになっている)ためと思われる。彼の思想と方法を知るにはまずはテクストに触れるのがいちばん手っとり早いのだが。
ボアールの文章は平明で面白い(面白すぎる?)のですぐに入っていける。里見訳の『被抑圧者の演劇』は仏訳からの重訳であった。この本でボアールは世界的に広く知られるようになった。現在は彼の方法の集大成ともいえる『職業俳優とそうではない人々のための演劇ゲーム集』を訳している。
1.ボアールの歩み―フレイレらとの関係で―
『被抑圧者の演劇』と『被抑圧者の教育学』(パウロ・フレイレ)とは題名からも分かるように強く結び付いている。実際ボアールはフレイレらとともに50年―60年代初頭のブライジル民衆文化運動に参加していたが、フレイレの方は1964年のブラジルのクーデタで国外追放になり、そのためにかえって活動の場は世界的にひろがっていった。亡命中に書かれた『被抑圧者の教育学』(1969)は母語のポルトガル語版は出版できず、スペイン語版がイリイチなどの手で地下出版され、それが英訳されて世界的なベストセラーになっていく。
一方ボアールは軍事政権下のブラジルでも粘り強い活動をつづけるが、71年、ついに彼も国外追放になり、『被抑圧者の演劇』が1975年、ブエノスアイレスで出版される。この本もアルゼンチンでも軍政下で禁書となり、主として英訳と仏訳で知られるようになった(上述したとおり、里見は仏訳で知ることになった)。
ボアールとフレイレの仕事を結んでいるのがブラジル民衆文化運動だが、それは文字文化と非文字文化のとのインターフェイスで成立した文化運動といってよいだろう。16〜17世紀のヨーロッパ文化(ラブレー、セルバンテス、シェイクスピア)は、文字文化と非文字・身体的(民衆)文化とのぶつかり合い(インターフェイス)の中で文字文化が新たな生命力を獲得するにいたった古典的な事例だが、フレイレ・ボアールの活動はそれとよく似た軌跡をたどっている。
フレイレは識字教育者として知られているのだが、彼が目指していたのは狭い意味での「識字」ではない。それは「世界を読み」「自らの歴史を書き直す」運動であり、人々が相互の語り(対話)、造型的・音楽的・身体的(演劇的)表現を通して世界と人間にたいする自らの関わり方そのものを変革していく「自由のための文化行動」なのである。
私自身は久保覚たちと「民衆文化研究会」(ロシア・アヴァンギャルド、イギリス民衆芸術運動、ブレヒト、韓国のパンソリやマダン劇、PETAの運動など、世界各地の民衆文化運動を領域横断的に学ぶサークル)に参加しており、ボアールの仕事もその中で紹介した。この会は一方でブレヒトの教育劇やマダン劇なども試演していて、その流れの中で黒テントの人たちと81年からPETA方式のワークショップに取り組むことになった。
民衆文化研究会の報告や討議内容は「伝統と現代」1982年1・3月合併号(特集「民衆文化への視点」)、機関紙「解纜」1−2号、1980年代のまだ月刊だった時代の「新日本文学」にその一部が掲載されている。
一方ボアールは軍事政権下のブラジルでも粘り強い活動をつづけるが、71年、ついに彼も国外追放になり、『被抑圧者の演劇』が1975年、ブエノスアイレスで出版される。この本もアルゼンチンでも軍政下で禁書となり、主として英訳と仏訳で知られるようになった(上述したとおり、里見は仏訳で知ることになった)。
ボアールとフレイレの仕事を結んでいるのがブラジル民衆文化運動だが、それは文字文化と非文字文化のとのインターフェイスで成立した文化運動といってよいだろう。16〜17世紀のヨーロッパ文化(ラブレー、セルバンテス、シェイクスピア)は、文字文化と非文字・身体的(民衆)文化とのぶつかり合い(インターフェイス)の中で文字文化が新たな生命力を獲得するにいたった古典的な事例だが、フレイレ・ボアールの活動はそれとよく似た軌跡をたどっている。
フレイレは識字教育者として知られているのだが、彼が目指していたのは狭い意味での「識字」ではない。それは「世界を読み」「自らの歴史を書き直す」運動であり、人々が相互の語り(対話)、造型的・音楽的・身体的(演劇的)表現を通して世界と人間にたいする自らの関わり方そのものを変革していく「自由のための文化行動」なのである。
私自身は久保覚たちと「民衆文化研究会」(ロシア・アヴァンギャルド、イギリス民衆芸術運動、ブレヒト、韓国のパンソリやマダン劇、PETAの運動など、世界各地の民衆文化運動を領域横断的に学ぶサークル)に参加しており、ボアールの仕事もその中で紹介した。この会は一方でブレヒトの教育劇やマダン劇なども試演していて、その流れの中で黒テントの人たちと81年からPETA方式のワークショップに取り組むことになった。
民衆文化研究会の報告や討議内容は「伝統と現代」1982年1・3月合併号(特集「民衆文化への視点」)、機関紙「解纜」1−2号、1980年代のまだ月刊だった時代の「新日本文学」にその一部が掲載されている。
2.ボアールのテーマと方法―「被抑圧者」とはだれか?―
「被抑圧者」とは何か?
労働者、農民、先住民がただちに想像されるが、実際には同じ労働者の中でも抑圧・被抑圧があり、また家族(男女・大人と子供)、医者と患者といったふだんは意識されない権力関係が存在する。抑圧的な関係性に馴染んでしまうと、人間はかぎりなく他者を(他者とともに自分をも)非人間化していくことになる。ボアールはこの関係を対象化して問題化する道具として演劇を考えるのである。
教師と生徒の関係は「抑圧」の典型例ともいえる。「すべてを知っている」教師が「何も知らない」生徒に一方的に知識を注入する権威主義的な関係(学校関係)をフレイレは問題化する。このような関係性の下では生徒は自前の思考を放棄した受動的な存在となり、かりに教師の伝える知識やメッセージがどのように価値の高いものであったとしても、それは結果的に死物になっていく。出来合いの知識をたんに受容するだけでは「知る」という行為は成立しない。自分が置かれている状況にたいする驚きや問いから出発し、他者との対話を通して自らの思考を鍛え上げていくことが、知るという行為であり、学ぶという行為であるはずだ。こうしたフレイレの思想はブレヒトやボアールの演劇観とも通底するものだろう。
「状況を発見する」手がかりとして、フレイレは「コード表示」と呼ばれる絵や写真を多用する。自分たちの生活の一場面を映したものであるが、その絵や写真を「読み」、問題化することから対話が生まれ、深まっていくのである。ボアールの場合は、それが劇の場面として提示されることになるのだが、彼が好んで使うのは彫像演劇という手法である。あたかも一枚の写真のごとく、ある場面が静止した状態で示される。動きをいったん止めること、出来事の流れを中断することで状況が異化され、見る者たちの「介入」が触発されることになる。
「ストップ!」というかけ声でおこなわれる「中断」がボアールの場合は重要な位置をしめている。ボアールのもっとも代表的なテクニックは「討論劇」で、観客が舞台に向けて「ストップ」をかけ、登場人物になりかわって劇の流れをかえていくというセッションなのであるが、介入可能な瞬間を発見し、行為することが観客の役割になっていく。そのまま放っておけば劇はずるずると悲劇的な結末に終わっていくわけである。
こうした彫像演劇や討論劇の手法は、シェイクスピアの戯曲でよく使われる劇中劇の方法とも通ずるものだろう。自らの状況を劇中劇という「鏡」もしくは「額縁」の中に入れて対象化することから、劇の新しい展開が生まれてくるわけだが、討論劇では観客がストップをかけて舞台の俳優になりかわり、ドラマを変えるための行動を試行錯誤的に探索する。
「観客が行為することを禁じられた観客として存在すること」、それが最大の抑圧なのだ、と、ボアールはくりかえし述べている。被抑圧者の演劇とは、ひとくちでいえば、観客がたんなる観客であることをやめて行為(演技)する人間、見ることと行為することの間をたえず往還するスペクト・アクターに転じていくための演劇的な手立てなのである。
労働者、農民、先住民がただちに想像されるが、実際には同じ労働者の中でも抑圧・被抑圧があり、また家族(男女・大人と子供)、医者と患者といったふだんは意識されない権力関係が存在する。抑圧的な関係性に馴染んでしまうと、人間はかぎりなく他者を(他者とともに自分をも)非人間化していくことになる。ボアールはこの関係を対象化して問題化する道具として演劇を考えるのである。
教師と生徒の関係は「抑圧」の典型例ともいえる。「すべてを知っている」教師が「何も知らない」生徒に一方的に知識を注入する権威主義的な関係(学校関係)をフレイレは問題化する。このような関係性の下では生徒は自前の思考を放棄した受動的な存在となり、かりに教師の伝える知識やメッセージがどのように価値の高いものであったとしても、それは結果的に死物になっていく。出来合いの知識をたんに受容するだけでは「知る」という行為は成立しない。自分が置かれている状況にたいする驚きや問いから出発し、他者との対話を通して自らの思考を鍛え上げていくことが、知るという行為であり、学ぶという行為であるはずだ。こうしたフレイレの思想はブレヒトやボアールの演劇観とも通底するものだろう。
「状況を発見する」手がかりとして、フレイレは「コード表示」と呼ばれる絵や写真を多用する。自分たちの生活の一場面を映したものであるが、その絵や写真を「読み」、問題化することから対話が生まれ、深まっていくのである。ボアールの場合は、それが劇の場面として提示されることになるのだが、彼が好んで使うのは彫像演劇という手法である。あたかも一枚の写真のごとく、ある場面が静止した状態で示される。動きをいったん止めること、出来事の流れを中断することで状況が異化され、見る者たちの「介入」が触発されることになる。
「ストップ!」というかけ声でおこなわれる「中断」がボアールの場合は重要な位置をしめている。ボアールのもっとも代表的なテクニックは「討論劇」で、観客が舞台に向けて「ストップ」をかけ、登場人物になりかわって劇の流れをかえていくというセッションなのであるが、介入可能な瞬間を発見し、行為することが観客の役割になっていく。そのまま放っておけば劇はずるずると悲劇的な結末に終わっていくわけである。
こうした彫像演劇や討論劇の手法は、シェイクスピアの戯曲でよく使われる劇中劇の方法とも通ずるものだろう。自らの状況を劇中劇という「鏡」もしくは「額縁」の中に入れて対象化することから、劇の新しい展開が生まれてくるわけだが、討論劇では観客がストップをかけて舞台の俳優になりかわり、ドラマを変えるための行動を試行錯誤的に探索する。
「観客が行為することを禁じられた観客として存在すること」、それが最大の抑圧なのだ、と、ボアールはくりかえし述べている。被抑圧者の演劇とは、ひとくちでいえば、観客がたんなる観客であることをやめて行為(演技)する人間、見ることと行為することの間をたえず往還するスペクト・アクターに転じていくための演劇的な手立てなのである。
3.ボアールの劇場活動―「対象化」のための演劇―
ボアールはワークショップで人々とともに創作するという活動を行ったが、60年代はサンパウロのアリーナ劇場の芸術監督であり、ミュージカルから古典劇まで広範な作品を多様なしかたで手掛けて多くのヒット作を送り出してきたブラジルきってのポピュラーな劇場演出家という側面も持っている。『彼らはタキシードを着ない』(ストライキが題材のリアリズム劇)、『ズンビ』(黒人奴隷反乱)、『ティラデンテス』(歯医者、独立運動のリーダー)などがボアールのヒット作である。ミュージカル的な作品からは「ズンビ」など数々のポップスが出てくる。
青年演出家としてのボアールがとりくんだ最初の課題は俳優と役を癒着させないこと、そこに距離を置くことであった。つまり、演ずるということは自分を演ずることではない、ということだ。
当時のラテンアメリカ演劇はスターシステムによって支配されていた。スターシステムにおいては、スターはどの作品でもスターその人である。他者を演ずるためには、自分の身体の動きを分析し、相対化して「他者」(役)の感情・動きを自分のものにする必要がある。これは正統的スタニスラフスキーシステムの方法である。
『ズンビ』『ティラデンテス』では、同じ役を多数の役者が入れ替わり演じている。これは、役を「社会的仮面」と考えるところから採用された方法だが、こうしたところにもブレヒトの影響が現れている。
ブレヒトの教育劇では、コーラスから代わる代わる役者が出てくる手法が採用されている。演ずるものが何事かを学ぶという考えに基づいており、役者たちが役を入れ替えながら、その行為を吟味し、矛盾や対立を深化していくというものだ。『処置』、『イエスマン・ノーマン』などだが、その後のブレヒトの劇場作品にもこの考え方は引き継がれている。
ブレヒトのこれらの作品は「教育劇」と呼ばれているが、いわゆる「教育」を目指したものではない。劇で人を「教育」するという発想ではなく、劇を「学習材」として位置づけていた。実験と批判的思考のための検討素材なのだ。実際ブレヒトはその存命中、『処置』の上演を許さなかった。観客に「見せる」ためのスペクタクルではなく、演ずる者自身が学ぶための素材であると考えていたからだ。
フレイレのいう「コード表示」や「意識化」を演劇的に方法化していく過程でボアールがどのようにスタニスラフスキーやブレヒトを読み解いてきたかを見ていくと非常に興味深い。
青年演出家としてのボアールがとりくんだ最初の課題は俳優と役を癒着させないこと、そこに距離を置くことであった。つまり、演ずるということは自分を演ずることではない、ということだ。
当時のラテンアメリカ演劇はスターシステムによって支配されていた。スターシステムにおいては、スターはどの作品でもスターその人である。他者を演ずるためには、自分の身体の動きを分析し、相対化して「他者」(役)の感情・動きを自分のものにする必要がある。これは正統的スタニスラフスキーシステムの方法である。
『ズンビ』『ティラデンテス』では、同じ役を多数の役者が入れ替わり演じている。これは、役を「社会的仮面」と考えるところから採用された方法だが、こうしたところにもブレヒトの影響が現れている。
ブレヒトの教育劇では、コーラスから代わる代わる役者が出てくる手法が採用されている。演ずるものが何事かを学ぶという考えに基づいており、役者たちが役を入れ替えながら、その行為を吟味し、矛盾や対立を深化していくというものだ。『処置』、『イエスマン・ノーマン』などだが、その後のブレヒトの劇場作品にもこの考え方は引き継がれている。
ブレヒトのこれらの作品は「教育劇」と呼ばれているが、いわゆる「教育」を目指したものではない。劇で人を「教育」するという発想ではなく、劇を「学習材」として位置づけていた。実験と批判的思考のための検討素材なのだ。実際ブレヒトはその存命中、『処置』の上演を許さなかった。観客に「見せる」ためのスペクタクルではなく、演ずる者自身が学ぶための素材であると考えていたからだ。
フレイレのいう「コード表示」や「意識化」を演劇的に方法化していく過程でボアールがどのようにスタニスラフスキーやブレヒトを読み解いてきたかを見ていくと非常に興味深い。
4.ディスカッション
高尾:
ボアールの亡命後、彼はパリに行き、ブラジル帰国後に政治に入っていくが、
その帰国後のことがよくわからない。
里見:
自分にもよくわからない。ヨーロッパ時代の活動については『被抑圧者の演劇 第2巻』
や『ストップ!セ・マジーク』があり、「討論劇」以外に「見えない演劇」などもかな
りおこなっていた。自分は昔、ポンピドゥーセンターの前で移民とフランス人が移民の
問題をめぐって激しい口論をしている場面にぶつかった。所用をすませてもう一度通り
かかったら、いくつもの人の輪ができて、議論が白熱していた。あれはボアールたちの
仕業だったに違いない。役者が尋常でなくうまかった。80年代のパリ近辺ではボアール
は隠れたブームだったようで、熱く彼の仕事について語る人にぼくも何人か出会ってい
る。また、ヨーロッパに移ってからは、ラテンアメリカでは拒否していたセラピー(心理
的)要素がかなり入ってくる。
帰国後、労働者党(PT)に入り、「立法演劇」(法制定演劇)を行うようになる。 2002年に『俳優と非俳優たちのためのエクササイズとゲーム集』の英語版がでて、 これは旧版と『ストップ』などを集大成した大著だが、ブラジル帰国後の経験についても 若干は書かれている。晩年のブラジルでの仕事についてはあまりよく知らないので、 今日の辻さんの話が楽しみだ。
帰国後、労働者党(PT)に入り、「立法演劇」(法制定演劇)を行うようになる。 2002年に『俳優と非俳優たちのためのエクササイズとゲーム集』の英語版がでて、 これは旧版と『ストップ』などを集大成した大著だが、ブラジル帰国後の経験についても 若干は書かれている。晩年のブラジルでの仕事についてはあまりよく知らないので、 今日の辻さんの話が楽しみだ。
5.「ワークショップ」という言葉の意味 ―ヒストリー・ワークショップとの関連で―
ボアールは「試みの演劇」を標榜していたが、「試み」にはスペイン語では「稽古」の意味もある。これはブレヒトの「試み」という概念の影響もあるだろう。ブレヒトは稽古場の経験やそこでの作業者たちの関係性を非常に重要視した。ワークショップにも「試みの演劇」という言葉にも、けいこ場の経験を公開するという問題意識が強く込められていると思う。
「試みの演劇」というのは、公演を準備する稽古場のプロセスを公開し、公衆とそれを共有するというコンセプトだ。1930年代のイギリス労働者演劇で提唱された「演劇ワークショップ」と共通する。
ボアールの場合はもっと徹底していて、彼がラテンアメリカでおこなった「試みの演劇」はそもそも公演(ショウ)を目的とする「稽古」ではなかった。「公演」を目的としない稽古であった。私たちが「ワークショップ」というときも、その力点は公演よりも稽古の経験の方に置かれているといってよいのではないかと思う。ヨーロッパに移ってからのボアールはショウにも大きな比重をかけるようになったが、その場合のショウは観衆の介入によって変更されるべき「たたき台」として提示されるわけだから、それもまた一種の「稽古」、観衆が現実生活の中でおこなう本番の行為のための準備なのである。ボアール自身が関わっているわけではないが、彼の方法を用いておこなわれたアフリカのレソトの討論劇がそのありようをたいへん典型的に示しているので、関連資料をお配りしよう。
「試みの演劇」というのは、公演を準備する稽古場のプロセスを公開し、公衆とそれを共有するというコンセプトだ。1930年代のイギリス労働者演劇で提唱された「演劇ワークショップ」と共通する。
ボアールの場合はもっと徹底していて、彼がラテンアメリカでおこなった「試みの演劇」はそもそも公演(ショウ)を目的とする「稽古」ではなかった。「公演」を目的としない稽古であった。私たちが「ワークショップ」というときも、その力点は公演よりも稽古の経験の方に置かれているといってよいのではないかと思う。ヨーロッパに移ってからのボアールはショウにも大きな比重をかけるようになったが、その場合のショウは観衆の介入によって変更されるべき「たたき台」として提示されるわけだから、それもまた一種の「稽古」、観衆が現実生活の中でおこなう本番の行為のための準備なのである。ボアール自身が関わっているわけではないが、彼の方法を用いておこなわれたアフリカのレソトの討論劇がそのありようをたいへん典型的に示しているので、関連資料をお配りしよう。
(資料配布)
稽古場や仕事場の経験の共有というワークショップの思想はイギリスでは歴史ワークショップの運動として活かされている。市民とプロフェッショナルな歴史家が共同で第一次資料にもとづいて地域の歴史を掘り起こしていくワークショップで1980年代以降、数々の成果をhistory workshop series として公刊している。普通には、「歴史」はもっぱら歴史家によって記述された「物語」として読者に提供され、史料から過去を復元していくその過程は、市民のものにはなっていない。だが歴史研究のほんとうの醍醐味は、歴史家のこの舞台裏の経験にこそあるのではないか。それを歴史家と人々が共有しよう、という考え方である。歴史ワークショップの成果は書物だけではなく、たとえば地元のモリス自動車の歴史のように、映像として作品化されたものもあり、これはBBCによって放映された。イギリス・ドキュメンタリー運動の伝統が、現在もこういう形で生きているのかもしれない。世田谷の「地域の物語」のワークショップとこうしたイギリスのワークショップ運動とはかなり通じ合うものがあるのではないだろうか。
舞台のショウを見せるだけでなく、舞台裏の作業の現場に人々を招き、そこで経験を共有するという演劇ワークショップの思想は、このように演劇プロパーにとどまらない広がりをもっている。パウロ・フレイレは『被抑圧者の教育学』で、講義以前の「準備」の過程と講義そのものがまったく別々な行為として二元化してしまっているのが権威主義型教師の特徴だと指摘している。舞台裏の「研究」は学生の立ち入ってはならない聖域になってしまっているのである。
「ワークショップ」とか、フランス語の「アトリエ」という言葉には、労働の再生を求める19世紀のヨーロッパ労働者運動の夢が込められている。その底に流れているのは、ウイリアム・モリスやフランスサンディカリストたちが追求した「仕事場の哲学」だろう。モリスが芸術というとき、それはほとんど労働と同義であって、芸術とはつまりは私たちの仕事の作法を変えていく「術」なのだ。
舞台のショウを見せるだけでなく、舞台裏の作業の現場に人々を招き、そこで経験を共有するという演劇ワークショップの思想は、このように演劇プロパーにとどまらない広がりをもっている。パウロ・フレイレは『被抑圧者の教育学』で、講義以前の「準備」の過程と講義そのものがまったく別々な行為として二元化してしまっているのが権威主義型教師の特徴だと指摘している。舞台裏の「研究」は学生の立ち入ってはならない聖域になってしまっているのである。
「ワークショップ」とか、フランス語の「アトリエ」という言葉には、労働の再生を求める19世紀のヨーロッパ労働者運動の夢が込められている。その底に流れているのは、ウイリアム・モリスやフランスサンディカリストたちが追求した「仕事場の哲学」だろう。モリスが芸術というとき、それはほとんど労働と同義であって、芸術とはつまりは私たちの仕事の作法を変えていく「術」なのだ。
質疑応答
Q1: 世田谷PTのこんどの上演される『ヘンリー三世』でもポストトークがおこなわれるようだ。
ポストトークで、演劇の作者が種明かししているようなものは、 ワークショップと同じようにとらえてよいのか?
ポストトークで、演劇の作者が種明かししているようなものは、 ワークショップと同じようにとらえてよいのか?
ボアールの場合は作品を完結したものとは考えていない。ショウは観衆によって作り
替えられるものとしてある。公演後のポストトークやワークショップを重視したのは
フランスの太陽劇団で、これはラテンアメリカにも大きな影響を及ぼしている。
プレトークもおこなわれている。コロンビアの劇団ラ・カンデラリアでは舞台稽古 の段階で当事者を招待し、劇の内容を叩いてもらうことがある(例えばテーマがスト リートチルドレンなら、彼らを招待して、演劇の内容との乖離を突いてもらうなど)。
ラテンアメリカ社会の中では演劇は非常な重みを持っている。演劇という形式で問題 を提起し、討議するということはアリーナ劇団以外にも、さまざまな劇団がおこなって いた。社会運動の中にも演劇は深く根づいている。
プレトークもおこなわれている。コロンビアの劇団ラ・カンデラリアでは舞台稽古 の段階で当事者を招待し、劇の内容を叩いてもらうことがある(例えばテーマがスト リートチルドレンなら、彼らを招待して、演劇の内容との乖離を突いてもらうなど)。
ラテンアメリカ社会の中では演劇は非常な重みを持っている。演劇という形式で問題 を提起し、討議するということはアリーナ劇団以外にも、さまざまな劇団がおこなって いた。社会運動の中にも演劇は深く根づいている。
Q2: 「観客」という役割の否定、作品を完結したものとしてみない「運動」としてとらえる
のはボアールの特徴なのか、ラテンアメリカのものなのか?
ラテンアメリカの特徴といってよいだろう。ただそれぞれの劇団や個人によってスタイ
ルは違う。ボアールのようにアウトリーチを重要視する人もいるし、あくまでも劇場の
仕事に中心を置く人もいる。コロンビアのラ・カンデラリアのサンティアゴ・ガルシア
はその一例である。劇場での作品行為を通して人々と出会う、新しい観衆を創造する、
という問題意識がサンティアゴにはかなり強烈に見られるように思う。非常に実験的な
作品を観衆にぶつけて、しかも若い多くの観客層を劇場に引き付けることに成功してい
る。綿密な調査と即興演技を重ねて一つの作品を2年かけてつくっているが、それを何
百回、作品によっては1,500回も上演できているというから驚きだ。
例えば、『デ・カオスとデカ・カオス』(カカオ貴族とカオス理論の語呂合わせ)という 作品がある。エリート階級の自壊のプロセスを10の非連続場面で描きながら、秩序の揺 らぎが拡大していく様相をイメージ化している。カオス理論やフラクタル幾何学から 示唆を得て構想されたものらしいが、こうした先端的な問題意識に支えられた集団制作 作品が広範な人々によって受け入れられているわけである。とその一方で、ペルーのユ ヤチカニ劇団のように各地のカーニバルやイベントに参加し、そこで学んだ伝承をとり こんで作品を制作している劇団もある。
例えば、『デ・カオスとデカ・カオス』(カカオ貴族とカオス理論の語呂合わせ)という 作品がある。エリート階級の自壊のプロセスを10の非連続場面で描きながら、秩序の揺 らぎが拡大していく様相をイメージ化している。カオス理論やフラクタル幾何学から 示唆を得て構想されたものらしいが、こうした先端的な問題意識に支えられた集団制作 作品が広範な人々によって受け入れられているわけである。とその一方で、ペルーのユ ヤチカニ劇団のように各地のカーニバルやイベントに参加し、そこで学んだ伝承をとり こんで作品を制作している劇団もある。
Q2: 劇場がないからか?
自分の劇場をもっている劇団は少ない。カンデラリアの場合は自分の劇場をもっていて、
他の劇団にも貸している。食堂もあり、俳優たちの生活拠点にもなっているようだ。
資金も資材もないという「貧しさ」がラテンアメリカの演劇を美学的にも条件づけている。
「何もない舞台」で焦点化されるのは俳優の身体だ。フィリピンのPETAでも初期の
ギドデたちは「持たざる者の美学」を提唱していて、実際、それは大きな可能性を発揮
したといえるだろう。他方でラテンアメリカの民衆演劇には祝祭的な華やかさを重視す
る面があり、ユヤチカニも仮面や衣装の制作に大きな力を注いでいる。
Q3: スタニスラフスキーに対するボアールの読み方はどのようなものか?アリストテレス型の
「同化」読み方を否定しているボアールがなぜスタニスラフスキーに関心を持つのか?
ラテンアメリカの現代演劇はスタニスラフスキー受容とともに始まったといえるくらい、
その影響は大きい。ボアールの場合もそうだ。役を役者から自立したものととらえるとき
に、その役づくりの基礎になるのはスタニスラフスキーの方法であるからだ。
ボアールは、役への感情移入という方向で役づくりを考えていたようだが、ある時期から 読み方が変わっていく。役と役の相互関係、そして役の内的葛藤のダイナミクスから劇を 作ろうとした段階になって、読み方が変わっていくように思う。
ボアールは、役への感情移入という方向で役づくりを考えていたようだが、ある時期から 読み方が変わっていく。役と役の相互関係、そして役の内的葛藤のダイナミクスから劇を 作ろうとした段階になって、読み方が変わっていくように思う。
Q4: スタニスラフスキーとブレヒトの「分析」という共通点はどうか?
ラテンアメリカではスタニスラフスキーとブレヒトとはほとんど同時的に入っていて両者
を対立すると考えている人はあまりいない。ラテンアメリカきってのブレヒティアンである
サンティアゴ・ガルシアもそうだ。ボアールはある時期からスタニスラフスキーに距離を
置くようになるが、離反しているわけではない。彼のエクササイズの中にはスタニスラフ
スキー的なものが多く含まれている。このあたりのことは、自分の宿題として今後もう少し
きちんと見ていきたいと思っている。

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.


