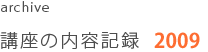


『ワークショップ論 ― 演劇ワークショップの力』
Vol.2「演劇とワークショップ」
2009年12月13日(日) 18時45分〜20時45分
熊谷 保宏
(日本大学芸術学部准教授)
《所 感》
第1回の後に休憩をはさんで連続開催された第2回ワークショップ論では、演劇とワークショップに関心を絞った、より具体的な講義となった。言葉だけでなく、豊富な画像イメージから想起される感覚的な学びの経験でもあった。
演劇の歴史が、ワークショップの発見から得た刺激は重要だった。シアターゲームの体系は、ワークショップ的な場を構成する手法への関心と方法論の発展をもたらした。ワークショップを通して演劇の手法が芸術や娯楽以外の目的にも応用できることが分かり、そのような活動が「応用演劇」と名付けられるに至った。こうした動きは単純な連続ではなく、世界各地で同時多発的に起こっている。
演劇の側からみれば、ワークショップはギリシャ古代劇の昔から劇場での「上演」が基本だった演劇実践の社会的な形式を拡張する場であった。一方ワークショップの側からは、参加体験を通じて発見を得るにあたり演劇の手法が極めて有効だったという見方もできる。ともに手法としては非常に強力であり、その危険性は十分考慮しなければならない。
第1回の後に休憩をはさんで連続開催された第2回ワークショップ論では、演劇とワークショップに関心を絞った、より具体的な講義となった。言葉だけでなく、豊富な画像イメージから想起される感覚的な学びの経験でもあった。
演劇の歴史が、ワークショップの発見から得た刺激は重要だった。シアターゲームの体系は、ワークショップ的な場を構成する手法への関心と方法論の発展をもたらした。ワークショップを通して演劇の手法が芸術や娯楽以外の目的にも応用できることが分かり、そのような活動が「応用演劇」と名付けられるに至った。こうした動きは単純な連続ではなく、世界各地で同時多発的に起こっている。
演劇の側からみれば、ワークショップはギリシャ古代劇の昔から劇場での「上演」が基本だった演劇実践の社会的な形式を拡張する場であった。一方ワークショップの側からは、参加体験を通じて発見を得るにあたり演劇の手法が極めて有効だったという見方もできる。ともに手法としては非常に強力であり、その危険性は十分考慮しなければならない。
記録:中村美帆(東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学研究専攻博士課程)

はじめに
ワークショップは、それ自体で取り上げるに値するテーマ、問題 (matter) なのか。英語圏では単体で、すなわち主題として取り上げられることはまずない。‘workshop’をタイトルに掲げた本も日本では増えている一方、それぞれの分野・領域によって込めている意味も違ってきている。ワークショップと演劇をめぐる歴史的な整理が必要だ。
1.ワークショップの原像:原初的イメージを作った人々と時代
1−1 ワークショップの語義
ワークショップの意味するところは多義的である。
<ワークショップの2つ意味と訳語>
-
古い意味:もの作りの場(空間的な意味合い)
例:サンタクロースの仕事部屋
サンタの家は居住部分と夏の間にプレゼントを作る仕事部屋で構成される。
物理的・空間的意味でのワークショップ(仕事部屋、空間) - 新しい意味:人の集い(時間的な意味合い)
例:みんなでスライドを観ている会議室
新しい技術の勉強会、濃い議論ができるディスカッションの場、集まりの光景
時間的概念としてのワークショップ(集い)
演劇では、前者の「作りの場」という意味でワークショップという言葉を用い始めたが、実態としては後者の「集い」という性格も強く、次第に後者が前者を凌駕していったといいう経緯がある。そう考えると、今日のワークショップ概念の形成にあたり演劇の果たした役割は大きい。
日本でのワークショップ普及の一つのきっかけになったのが中野民雄『ワークショップ』(岩波新書、2001年)である。そのワークショップの歴史、系統図(同書16頁:元の出典は、兵庫教育大学大学院平成8年度修士論文「ワークショップの課題と展望−合意形成と身体解放の視点から−」高田研、1996年である)中に挙げられていながら本文では触れられていない演劇の系譜、ジョージ・ピエール・ベイカーの活動からワークショップと演劇をめぐる歴史を辿り始めたい
1−2 ジョージ・ピエール・ベイカー
ジョージ・ピエール・ベイカーは、20世紀前半のハーバード大学の演劇研究者であり教師である。ベイカーというカリスマ教師に憧れ演劇を志す若きエリートたちが、ベイカーの英語クラス (“English 47”)で戯曲制作の授業を受けるべく全米各地からボストンに集まってきた。書いた戯曲を上演したいという希望が高まったが、授業制度の中では難しかったために、授業とは別に新しい場を別途設けることになった。その場に与えられた名称がワークショップ (“47 Workshop”)だったのである。このワークショップは活発な創作・上演活動を展開し、演劇界の注目するところとなった。
これが新しい意味でのワークショップの最も古い事例である。たいへん生産性の高い場で、ユージン・オニール、フィリップ・バリー(『フィラデルフィア物語』原作)、シドニー・ハワード(『風と共に去りぬ』脚本)など、その後のアメリカの演劇界・映画界を背負って立つ人材をこの「ワークショップ」が輩出し、それよりさらに多くの演劇教育者を輩出した。大学での演劇教育に可能性を感じた若者が、就職先の大学に演劇のクラスや当時としては画期的な演劇科を立ち上げた。それが今日のアメリカの、演劇教育に支えられた演劇文化の礎となっている。アメリカの大学の半分には演劇科がある。その出発点がベイカーのワークショップであったということだ。
これが新しい意味でのワークショップの最も古い事例である。たいへん生産性の高い場で、ユージン・オニール、フィリップ・バリー(『フィラデルフィア物語』原作)、シドニー・ハワード(『風と共に去りぬ』脚本)など、その後のアメリカの演劇界・映画界を背負って立つ人材をこの「ワークショップ」が輩出し、それよりさらに多くの演劇教育者を輩出した。大学での演劇教育に可能性を感じた若者が、就職先の大学に演劇のクラスや当時としては画期的な演劇科を立ち上げた。それが今日のアメリカの、演劇教育に支えられた演劇文化の礎となっている。アメリカの大学の半分には演劇科がある。その出発点がベイカーのワークショップであったということだ。
1−3 ロシア・アバンギャルド、そしてブレヒト
ほぼ同時期にみられたワークショップの展開としては、ロシア・アバンギャルドにおけるそれがある。代表的人物はフセヴォロド・エミリエヴィッチ・メイエルホリドだ。彼のつくった革新的な演技術・俳優術「ビオメカニカ」を生んだのは1920年代初めに設立された国立演劇工房(ワークショップ)である。その前身はロシア革命前にメイエルホリドが個人で立ち上げていた演劇スタジオであった。
メイエルホリドの代表作『ミステリヤ・ブッフ』の作者マヤコフスキーもワークショップの開拓者だ。詩人・劇作家であり、芸術左翼前線LEF(Left Front of the art)の主要メンバーだったマヤコフスキーは、のちにLEFを離脱して芸術革命前線REF(Revolution Front of the art) を結成した。その際マヤコフスキーはこの新団体をワークショップとして動かそう(団体だけれどワークショップ的な活動こそ実態とする)としたのである。LEF時代から作っていた雑誌のように言論の場を担うだけでもなく、議論するだけでもなく、作品を作り人材を輩出する場としてREFを構想した。残念ながらうまくいかなかったらしくあまり資料も残っていないが、おそらく積極的な活動を展開していたことは推察される。想像するに、とにかく新しいことをすべく熱い議論を重ね、作品のアイディアを出し、試作や試行を繰り返していたのではないか。 いずれにせよ、メイエルホリドのワークショップもマヤコフスキーのそれも、現代のワークショップでイメージされるような生温い感じのものではなかったと思われる。目指していたのは芸術のまったく新しい表現であり、まったく新しい芸術であり、それを生み出す場としてワークショップと言う名前が選ばれた。それ以外の名称が考えられなかったというのは重要な点だ。
当時のロシア演劇はアバンギャルド以外もワークショップ的な要素が強い。スタニフラフスキーも不遇だった一時期に学校兼実験的な場である「第一スタジオ」で若手相手に活動をしていた。そこからスタニフラフスキー・メソッドが生まれてきたことを考えると、ここもワークショップ的な場だったのではないかと思う。
ちなみにオックスフォード英語辞典(OED、語源も含めた包括的記述が特徴)では、ワークショップは新旧両方の意味で掲載されている。新しい方の意味は演劇、マヤコフスキーのワークショップが発祥ではないかと書かれている。また、マックス・ラインハルトがアメリカにわたって最初に手掛けた演劇の研究所が「ラインハルト・ワークショップ」だったとも書かれている。OEDにはワークショップに関して計5つの用例が掲載されているが、その大半が演劇で占められていることは興味深い。
今一人、ベルトルト・ブレヒトも忘れてはならない。ワークショップという言葉を重用してはいないものの、ある意味では誰よりも何よりもワークショップ的なる精神を体現した人のように思える。創作スタイルも多分に協同的で、そのような協同的な場を創造的に維持していた。彼の仕事部屋にはつねに作家や評論家が入り浸り、議論に明け暮れ、そんな議論の中から作品たちも形をなしていった。そんな仕事部屋と、彼が実験的な演出・演技を追求し続けた稽古場は、いずれも「ワークショップ」と呼びうるものだ。その後のワークショップ史にも影響を与えた(与え続けている)点もブレヒトの特徴であろう。
メイエルホリドの代表作『ミステリヤ・ブッフ』の作者マヤコフスキーもワークショップの開拓者だ。詩人・劇作家であり、芸術左翼前線LEF(Left Front of the art)の主要メンバーだったマヤコフスキーは、のちにLEFを離脱して芸術革命前線REF(Revolution Front of the art) を結成した。その際マヤコフスキーはこの新団体をワークショップとして動かそう(団体だけれどワークショップ的な活動こそ実態とする)としたのである。LEF時代から作っていた雑誌のように言論の場を担うだけでもなく、議論するだけでもなく、作品を作り人材を輩出する場としてREFを構想した。残念ながらうまくいかなかったらしくあまり資料も残っていないが、おそらく積極的な活動を展開していたことは推察される。想像するに、とにかく新しいことをすべく熱い議論を重ね、作品のアイディアを出し、試作や試行を繰り返していたのではないか。 いずれにせよ、メイエルホリドのワークショップもマヤコフスキーのそれも、現代のワークショップでイメージされるような生温い感じのものではなかったと思われる。目指していたのは芸術のまったく新しい表現であり、まったく新しい芸術であり、それを生み出す場としてワークショップと言う名前が選ばれた。それ以外の名称が考えられなかったというのは重要な点だ。
当時のロシア演劇はアバンギャルド以外もワークショップ的な要素が強い。スタニフラフスキーも不遇だった一時期に学校兼実験的な場である「第一スタジオ」で若手相手に活動をしていた。そこからスタニフラフスキー・メソッドが生まれてきたことを考えると、ここもワークショップ的な場だったのではないかと思う。
ちなみにオックスフォード英語辞典(OED、語源も含めた包括的記述が特徴)では、ワークショップは新旧両方の意味で掲載されている。新しい方の意味は演劇、マヤコフスキーのワークショップが発祥ではないかと書かれている。また、マックス・ラインハルトがアメリカにわたって最初に手掛けた演劇の研究所が「ラインハルト・ワークショップ」だったとも書かれている。OEDにはワークショップに関して計5つの用例が掲載されているが、その大半が演劇で占められていることは興味深い。
今一人、ベルトルト・ブレヒトも忘れてはならない。ワークショップという言葉を重用してはいないものの、ある意味では誰よりも何よりもワークショップ的なる精神を体現した人のように思える。創作スタイルも多分に協同的で、そのような協同的な場を創造的に維持していた。彼の仕事部屋にはつねに作家や評論家が入り浸り、議論に明け暮れ、そんな議論の中から作品たちも形をなしていった。そんな仕事部屋と、彼が実験的な演出・演技を追求し続けた稽古場は、いずれも「ワークショップ」と呼びうるものだ。その後のワークショップ史にも影響を与えた(与え続けている)点もブレヒトの特徴であろう。
1−4 小括:ワークショップ原像イメージの独断と偏見に基づく印象
ここまでワークショップの原像イメージを作った演劇人を概観してきたが、共通して言えるのは圧倒的なカリスマであり、多分に絶対君主的で面々であったということだ。初期のワークショップは今日の民主的なイメージとは対称的な、独裁的なそれであったように思えるのである。その生産性に重きを置く場の成り立ちも、今日のワークショップとは対称的とみるべきであろう。
2.シアターゲーム:ワークショップの近代化
次にワークショップの近代化について、シアターゲームというものを通じて考えたい。
演劇ワークショップ、あるいは演劇ワークショップのためのゲームをシアターゲームという。シアターゲームが生まれてきたのは1960-1970年代で、そのフォーマットが整えられてきたのは1970年代以降であることを考えると、1980年代以降に盛り返してきた今日のワークショップの隆盛にシアターゲームの果たした役割を考えないわけにはゆかない。
演劇ワークショップ、あるいは演劇ワークショップのためのゲームをシアターゲームという。シアターゲームが生まれてきたのは1960-1970年代で、そのフォーマットが整えられてきたのは1970年代以降であることを考えると、1980年代以降に盛り返してきた今日のワークショップの隆盛にシアターゲームの果たした役割を考えないわけにはゆかない。
2−1 モレノ
シアターゲームの話に先立ちモレノという人物の功績について確認しておきたい。
精神科医のヤコブ・L・モレノは、メイエルホリドやブレヒトと同時期から演劇ワークショップ的な実践をしていたが、その中身は彼らとはまったく異なるものであった。
精神科医のヤコブ・L・モレノは、メイエルホリドやブレヒトと同時期から演劇ワークショップ的な実践をしていたが、その中身は彼らとはまったく異なるものであった。
<初期ワークショップと現在のワークショップの違い>
構造性(時間配分、はじめ・なか・おわり、導入・展開・帰結)への意識
→その原点がモレノの活動にある
シアターゲームの存在
→その原点がモレノの活動にある
モレノはブタペストで生まれ、ウィーンで学び、後にアメリカに移住した精神科医で、心理療法としての「サイコドラマ(心理劇)」を作った人として知られている。モレノのサイコドラマには、多分に今日のワークショップに通じる要素がある。演劇だけれど目的が芸術とは違うところ(治療)にあるという点では、今日の応用演劇の最も重要な原点といえる。そして今日のワークショップに通じる構造性を有する。
サイコドラマのセッションは3部分から構成される。ウォームアップ、ドラマ(アクション部分)、シェアリング(振り返り)である。このような構造性は、メイエルホリドらのワークショップにはおそらくなかった類のものだ。目的と構造性の持ち込み、そしてそれを本の形で書きあらわして残したのが、今日のワークショップにつながるモレノの功績である。
サイコドラマのセッションは3部分から構成される。ウォームアップ、ドラマ(アクション部分)、シェアリング(振り返り)である。このような構造性は、メイエルホリドらのワークショップにはおそらくなかった類のものだ。目的と構造性の持ち込み、そしてそれを本の形で書きあらわして残したのが、今日のワークショップにつながるモレノの功績である。
2−2 ヴァイオラ・スポーリン
次にシアターゲームの創設者と言われるヴァイオラ・スポーリンを取り上げたい。1960年代後半に活躍したスポーリンは、もともとソーシャル・ワーカーとしてシカゴのスラム地区でセツルメント活動に従事していた。スラムにはお金がないから子どもの遊具を用意できない。子どもが身体と創造力を使って遊ぶにはどうしたらいいか?
と考えたのがシアターゲームと言われている。彼女自身がこしらえたというより彼女がシステム化したといった方がより正確かもしれない。
1963年にスポーリンの著作『Improvisation for the Theater』が出版された意義は大きい。活字出版されることで、はるかに広い世界に向けた確実な伝達が可能になった。シアターゲームはスポ ーリンの出版により近代化を遂げたともいえる。
アメリカでは本人の活動とあいまってかなりの範囲で普及したし、国際的にも十数カ国語に訳されて読まれた。演劇関係者の共通言語となりつつあったにもかかわらず、日本では長いあいだ訳されず、数年前に部分訳で出版されたところである。なお日本ではボアールのゲーム集も翻訳されていない。
1963年にスポーリンの著作『Improvisation for the Theater』が出版された意義は大きい。活字出版されることで、はるかに広い世界に向けた確実な伝達が可能になった。シアターゲームはスポ ーリンの出版により近代化を遂げたともいえる。
アメリカでは本人の活動とあいまってかなりの範囲で普及したし、国際的にも十数カ国語に訳されて読まれた。演劇関係者の共通言語となりつつあったにもかかわらず、日本では長いあいだ訳されず、数年前に部分訳で出版されたところである。なお日本ではボアールのゲーム集も翻訳されていない。
2−3 アウグスト・ボアール(詳細は次回)
1931年生まれのボアールは、識字教育に取り組んだパウロ・フレイレと前述のブレヒトに影響を受け、1970年代に独自の演劇手法を構築して展開した。今年(2009年)5月の訃報は世界的なニュースとなった。
1974年に出版されたボアール著『被抑圧者の演劇』の中心的なテーゼは「観客というのは悪いことばだ」というものである。観客であっても舞台の上に介入する権利がある。進行を止め、舞台の世界を変えることができる。このことを実現するためには観客は俳優へと変身しなければならないわけだが、それは簡単なことではない。演劇を観たこともない人々には、役を演じる前段階が必要だった。そこでボアールはゲームを徹底的に研究した。その成果が、1975年に出版された『Games for Actors & Non-Actors(俳優と非俳優のためのゲーム集)』である。先のスポーリンの著作と合わせて、現代ワークショップの2大ゲーム本である。
この本をみると、ボアールの被抑圧者の演劇をゲームがいかに支えているかがよくわかる。ボアール自身のゲームの意味付けは、被抑圧者の演劇(TO)の「武器庫」(Arsenal of TO)というほど重要なものだった。武器庫から状況に応じて武器を取り出し新しい戦略を作る。ボアールの理解にあたっては、彼が実にゲームのマスターだったという点を忘れてはならないように思う。
1974年に出版されたボアール著『被抑圧者の演劇』の中心的なテーゼは「観客というのは悪いことばだ」というものである。観客であっても舞台の上に介入する権利がある。進行を止め、舞台の世界を変えることができる。このことを実現するためには観客は俳優へと変身しなければならないわけだが、それは簡単なことではない。演劇を観たこともない人々には、役を演じる前段階が必要だった。そこでボアールはゲームを徹底的に研究した。その成果が、1975年に出版された『Games for Actors & Non-Actors(俳優と非俳優のためのゲーム集)』である。先のスポーリンの著作と合わせて、現代ワークショップの2大ゲーム本である。
この本をみると、ボアールの被抑圧者の演劇をゲームがいかに支えているかがよくわかる。ボアール自身のゲームの意味付けは、被抑圧者の演劇(TO)の「武器庫」(Arsenal of TO)というほど重要なものだった。武器庫から状況に応じて武器を取り出し新しい戦略を作る。ボアールの理解にあたっては、彼が実にゲームのマスターだったという点を忘れてはならないように思う。
2−4 日本における初期的なワークショップ
ボアールの『被抑圧者の演劇』の、より世界的な背景として、1970-1980年代に第3世界で同時多発した民衆的な文化運動がある。冷戦構造の中で深刻化する南北問題を背景に、民衆が自分たちの状況をとらえなおすツールとして文化、演劇に注目した。道具や電気がなくてもできる演劇は、手近な、使える道具となりうる。ボアールの活動はその南米バージョンで、他にもアフリカの「開発のための演劇」、韓国のマダン劇、フィリピン演劇協会(PETA)などの事例がある。
日本では、こと演劇に限っては、PETA が大きな影響を持った。1980年代に PETA のワークショップを経験した演劇人たちにより、その体系的なワークショップの方法論が熱心に紹介されたからである。
PETAは1960年代後半頃に始まったフィリピンの演劇団体・文化団体である。歴史的な経緯からワークショップに力を入れ、独特の方法論を育み、1970年代後半にはかなり洗練されたシステムになっていた。PETAがまとめたワークショップのマニュアル(BITAW:Basic Integrated Theatre Arts Workshop)は、かなり洗練された内容だった。ボアールとスポーリンの著作がゲーム本だったのに対し、BITAWは周到に体系化されたワークショップマニュアルだった。
日本において、そのようなワークショップが早くから紹介されたことの意味は大きい。PETA 的なワークショップは長らく主流だったからである。
日本では、こと演劇に限っては、PETA が大きな影響を持った。1980年代に PETA のワークショップを経験した演劇人たちにより、その体系的なワークショップの方法論が熱心に紹介されたからである。
PETAは1960年代後半頃に始まったフィリピンの演劇団体・文化団体である。歴史的な経緯からワークショップに力を入れ、独特の方法論を育み、1970年代後半にはかなり洗練されたシステムになっていた。PETAがまとめたワークショップのマニュアル(BITAW:Basic Integrated Theatre Arts Workshop)は、かなり洗練された内容だった。ボアールとスポーリンの著作がゲーム本だったのに対し、BITAWは周到に体系化されたワークショップマニュアルだった。
日本において、そのようなワークショップが早くから紹介されたことの意味は大きい。PETA 的なワークショップは長らく主流だったからである。
3.応用演劇について
続いて、現代においてワークショップを考える場合に無視できない概念である「応用演劇」というものについて概観しておきたい。
3−1 ジョエル・プロトキンによる応用演劇の定義
1980年代から言葉としての Applied theatre (drama)はあったような気がするが、積極的な定義が今なお難しい言葉でもある。こうした問題について、解消とまではいかないが暫定的に解決したのが、ジョエル・プロトキンであった。
プロトキンは、後に応用演劇と呼ばれるような数々の現場でフィールドワークを行い、1997年にウェブサイト「Applied & Interactive Theatre Guide」を立ち上げた。応用演劇的なものを体で捕まえて考察し、応用演劇の主な柱として、次の4つの領域を挙げている。
プロトキンは、後に応用演劇と呼ばれるような数々の現場でフィールドワークを行い、1997年にウェブサイト「Applied & Interactive Theatre Guide」を立ち上げた。応用演劇的なものを体で捕まえて考察し、応用演劇の主な柱として、次の4つの領域を挙げている。
<応用演劇の4つの柱>
・therapy ・politics ・education ・spirituality
・therapy ・politics ・education ・spirituality
プロトキンの発見で面白いのは、この4つの領域のどこにおいても現場で活躍する実践家は、自分たちは「○○である」というアイデンティファイ・自己規定を拒否しているということだ。「therapy と言えるかはさておき少なくともspiritualityではない」というふうに、積極的な定義を避け、他の活動と比較して自分たちは「○○ではない」というスタンスなのである。
そうした分析を踏まえて、プロトキンは「消極的定義」という方法を考え出した。つまり演劇の2大主要目的である芸術と娯楽を除いたもの、芸術・娯楽「以外」の目的で用いられる演劇が「応用演劇である」という定義である。この応用演劇の消極的定義はうまく機能し、そのおかげで自由になった面がある。プロトキンもこの消極的定義を得て研究を進めた。それが次に紹介する応用演劇の9つの分野分けである。
そうした分析を踏まえて、プロトキンは「消極的定義」という方法を考え出した。つまり演劇の2大主要目的である芸術と娯楽を除いたもの、芸術・娯楽「以外」の目的で用いられる演劇が「応用演劇である」という定義である。この応用演劇の消極的定義はうまく機能し、そのおかげで自由になった面がある。プロトキンもこの消極的定義を得て研究を進めた。それが次に紹介する応用演劇の9つの分野分けである。
3−2 プロトキンによる9分野と日本での実践
以下、プロトキンによる9つの分野分けと日本での実践について簡単にみていきたい。
Psychodrama:サイコドラマ(心理劇)
モレノが構築し、今日でも行われている演劇をもちいた心理療法。
日本でも戦後間もなく紹介された。基本的には医療領域における治療目的の実践が主流で あったが、日本心理劇学会などはのちにみるドラマセラピーやプレイバックシアターなどへ も間口を広げている。
モレノが構築し、今日でも行われている演劇をもちいた心理療法。
日本でも戦後間もなく紹介された。基本的には医療領域における治療目的の実践が主流で あったが、日本心理劇学会などはのちにみるドラマセラピーやプレイバックシアターなどへ も間口を広げている。
Theatre for Development:開発のための演劇
1970年代に生まれ近年も盛んなアフリカ特有のコミュニティ・シアターで、地域の問題を 演劇を使って考えるものである。日本でこの名称を掲げてやっている人はもちろんいない。
1970年代に生まれ近年も盛んなアフリカ特有のコミュニティ・シアターで、地域の問題を 演劇を使って考えるものである。日本でこの名称を掲げてやっている人はもちろんいない。
Drama Therapy:ドラマセラピー
セラピーである点でサイコドラマにも近いが、実践領域はいわゆる治療に限定されてはいな い。方法論においてもいろいろなものを幅広く採用している。日本でも複数の流派で活動が 行われており、応用演劇の中では一般に普及している方だといえる。
セラピーである点でサイコドラマにも近いが、実践領域はいわゆる治療に限定されてはいな い。方法論においてもいろいろなものを幅広く採用している。日本でも複数の流派で活動が 行われており、応用演劇の中では一般に普及している方だといえる。
Grassroots Theatre:草の根演劇
グラスルーツなスタンスで、政治的なステートメントを演劇でおこなう運動。1960年代か らアメリカで活動しているラディカルなパフォーマンス集団ブレッド&パペットシアター などは有名。日本では、ジャンルというほどの運動はないだろう。
グラスルーツなスタンスで、政治的なステートメントを演劇でおこなう運動。1960年代か らアメリカで活動しているラディカルなパフォーマンス集団ブレッド&パペットシアター などは有名。日本では、ジャンルというほどの運動はないだろう。
Theatre of the Oppressed:被抑圧者のための演劇
先に紹介したボアールによる。日本では概念としては普及し、やっている人や方法論を利用 している人は多い。ただし「被抑圧者の演劇」という名称を前面に出して実践している人は いないのではないか。
先に紹介したボアールによる。日本では概念としては普及し、やっている人や方法論を利用 している人は多い。ただし「被抑圧者の演劇」という名称を前面に出して実践している人は いないのではないか。
Workplace Role Training:職業的な役割訓練
職業的な訓練としてロールプレイを用いる方法。さまざまな展開があり、方法論も進化を 続けている。日本でも企業研修等の機会にロールプレイがおこなわれることは多い。演劇的 手法としては、もっとも普及したものといえるであろう。
職業的な訓練としてロールプレイを用いる方法。さまざまな展開があり、方法論も進化を 続けている。日本でも企業研修等の機会にロールプレイがおこなわれることは多い。演劇的 手法としては、もっとも普及したものといえるであろう。
Playback Theatre:プレイバックシアター
ドラマセラピーの一種であるとも考えられるが、こちらは具体的なフォーマットをもつ独自 の様式であり、独自のコミュニティを形成している。参加者から語ってもらった思い出を 俳優たちが即興で演じる。日本でも複数の陣営が継続的に活動をし、規模も全国的になって いて、一定の普及をしていると言える。
ドラマセラピーの一種であるとも考えられるが、こちらは具体的なフォーマットをもつ独自 の様式であり、独自のコミュニティを形成している。参加者から語ってもらった思い出を 俳優たちが即興で演じる。日本でも複数の陣営が継続的に活動をし、規模も全国的になって いて、一定の普及をしていると言える。
Theatre in Education (TIE):シアターインエデュケーション
1960年代のイギリスに端を発する具体的な方法論を持った演劇教育である。演劇形式に 仕立てられた教科の教材を俳優チームのリードのもと、学習者の参加を促しつつ、展開する。 いわゆる演劇を教える狭義の演劇教育ではない、演劇による教育である。
日本でも演劇教育という枠組みは一定の認知をうけていると思うが、TIEのような具体的な モデルが一定の運動として普及するようなことはなかった。
1960年代のイギリスに端を発する具体的な方法論を持った演劇教育である。演劇形式に 仕立てられた教科の教材を俳優チームのリードのもと、学習者の参加を促しつつ、展開する。 いわゆる演劇を教える狭義の演劇教育ではない、演劇による教育である。
日本でも演劇教育という枠組みは一定の認知をうけていると思うが、TIEのような具体的な モデルが一定の運動として普及するようなことはなかった。
3−3 日本の応用演劇の状況
プロトキンの9分野から日本の応用演劇の状況をみると、日本で盛り上がっていないものは、第3世界にルーツを持つような社会変革系の動き、それが近年特に停滞気味という印象を持つ。日本で残っているのは、心理系・自己啓発系ではないか。問題状況を社会的に変えていくというより、個人に足りないものを演劇で救済する、癒していくタイプのものが広まっているという印象を受ける。
日本ならではの活発な応用演劇のあり方として「Drama for communication」と呼べる傾向がある。日本におけるワークショップはことごとくコミュニケーションのための応用演劇になっているのではないか。特に漫然と演劇ワークショップと呼ばれるものはその傾向が強いように思う。
応用演劇を「主な活動形態がワークショップである演劇」とみることもできる。演劇の歴史においては、ギリシャ演劇以降基本的に劇場での上演を行ってきたわけだが、20世紀になってそうではない形式を発見した。1920-30年代のアバンギャルドたちは、上演以外のワークショップ活動も行いつつ、ターミナルとしてのシアターは維持していた。それに対し1980年代以降にでてきた応用演劇は、活動の最終形態がワークショップであるというのが特徴である。
日本ならではの活発な応用演劇のあり方として「Drama for communication」と呼べる傾向がある。日本におけるワークショップはことごとくコミュニケーションのための応用演劇になっているのではないか。特に漫然と演劇ワークショップと呼ばれるものはその傾向が強いように思う。
応用演劇を「主な活動形態がワークショップである演劇」とみることもできる。演劇の歴史においては、ギリシャ演劇以降基本的に劇場での上演を行ってきたわけだが、20世紀になってそうではない形式を発見した。1920-30年代のアバンギャルドたちは、上演以外のワークショップ活動も行いつつ、ターミナルとしてのシアターは維持していた。それに対し1980年代以降にでてきた応用演劇は、活動の最終形態がワークショップであるというのが特徴である。
4.さいごに
ワークショップとは何か。現実としては、その場をもつ側の自己定義しだいである。用意する側が「これはワークショップである」と言った時点でワークショップになる。そういう人たちは「ワークショップ」に積極的な意味を見出しているのだろうから、それでいいとも思うが、そのような現実がもたらしている混乱もあるのではないかというのが、ここでの問題意識だ。
たとえば、悪質な自己啓発セミナーまがいの「ワークショップ」もあるのではないか。それは、見た目はワークショップっぽくあったとしても、いわゆるワークショップとは原理が違うはずである。
自己啓発セミナーとは何か。たとえば医学的な診療や心理的なカウンセリングは、現実の世界とは違う非日常空間を、その枠組みとして明確に設定する。そこは実験・治療空間であるから、現実とは異なる。それに対し、自己啓発セミナーは枠組みが不明である。セミナーという「今、ここ」の場があたかも社会の現場でもあるような設定がされ、「今、ここ」で人間が変われないとあなたは変われないという強迫的な要素をはらむ。
問題はワークショップの枠組みである。ある種の、おそらくは枠組みが不明な演劇ワークショップが、悪質な自己啓発セミナーに近づいてしまうような可能性は否定できない。特に曖昧な「コミュニケーションのための演劇」の場合、ここでやれれば社会でもうまくやれるという前提をともなっているのではないか。この前提がすなわち枠組みである。ワークショップのより安定した社会的認知のためにも、その「枠組み」について、今後、多くの議論が必要であろう。
演劇とワークショップの歴史を振り返ってきた。100年のあいだに大きな変化があったように思う。特にワークショップの原像は、今の演劇ワークショップとは根本的に異なる強度をもつものであった。今日のワークショップは、はるかにゆるいイメージだ。1960年代から1970年代にかけてシステムとして確立されたワークショップは、強めの社会的な問題意識を背景にしていた。しかし今日の日本の現状では、社会的問題意識は停滞して、非常に個人的・自己啓発的なものの普及が目立つ。現在いささか曖昧なまま放置されているワークショップの「枠組み」についてもよく考えるべき時期であろう。その際の有効な隣接概念が「応用演劇」だと思うのである。
たとえば、悪質な自己啓発セミナーまがいの「ワークショップ」もあるのではないか。それは、見た目はワークショップっぽくあったとしても、いわゆるワークショップとは原理が違うはずである。
自己啓発セミナーとは何か。たとえば医学的な診療や心理的なカウンセリングは、現実の世界とは違う非日常空間を、その枠組みとして明確に設定する。そこは実験・治療空間であるから、現実とは異なる。それに対し、自己啓発セミナーは枠組みが不明である。セミナーという「今、ここ」の場があたかも社会の現場でもあるような設定がされ、「今、ここ」で人間が変われないとあなたは変われないという強迫的な要素をはらむ。
問題はワークショップの枠組みである。ある種の、おそらくは枠組みが不明な演劇ワークショップが、悪質な自己啓発セミナーに近づいてしまうような可能性は否定できない。特に曖昧な「コミュニケーションのための演劇」の場合、ここでやれれば社会でもうまくやれるという前提をともなっているのではないか。この前提がすなわち枠組みである。ワークショップのより安定した社会的認知のためにも、その「枠組み」について、今後、多くの議論が必要であろう。
演劇とワークショップの歴史を振り返ってきた。100年のあいだに大きな変化があったように思う。特にワークショップの原像は、今の演劇ワークショップとは根本的に異なる強度をもつものであった。今日のワークショップは、はるかにゆるいイメージだ。1960年代から1970年代にかけてシステムとして確立されたワークショップは、強めの社会的な問題意識を背景にしていた。しかし今日の日本の現状では、社会的問題意識は停滞して、非常に個人的・自己啓発的なものの普及が目立つ。現在いささか曖昧なまま放置されているワークショップの「枠組み」についてもよく考えるべき時期であろう。その際の有効な隣接概念が「応用演劇」だと思うのである。

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.


