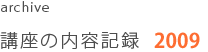


『ワークショップ論 ― 演劇ワークショップの力』
Vol.1「ワークショップ概説―理論と広がり」
2009年12月13日(日) 16時〜18時
高尾 隆
(東京学芸大学芸術・スポーツ科学系音楽・演劇講座演劇分野特任准教授)
《概 要》
ワークショップ論シリーズの1回目は、ワークショップとは何かを明確に定義するのではなく、 受講生も参加してワークショップという概念をめぐる問題意識をあぶり出し、論点を整理した 見取り図を共有するものだった。結果として、プラグマティズムに端を発して実践と理論の 往復を目指してきた歴史的経緯と、もっぱらコミュニケーションと結びつけて語られる今日の ワークショップへの関心とその背景にある社会状況、2つの切り口からワークショップを考える 内容となった。
ワークショップを思考の対象として主題化する営み自体が海外では例を見ないというが、 ならばワークショップの手法を取り入れてワークショップを考察するという行為も、かなり 珍しいものだろう。今回はそれが講座という場でレクチャー形式で行われたが、ではワーク ショップについてのレクチャーを文字で記録することができるか?という逆説はどこまで 解消できているだろうか。読み手の判断を仰ぐばかりである。
ワークショップ論シリーズの1回目は、ワークショップとは何かを明確に定義するのではなく、 受講生も参加してワークショップという概念をめぐる問題意識をあぶり出し、論点を整理した 見取り図を共有するものだった。結果として、プラグマティズムに端を発して実践と理論の 往復を目指してきた歴史的経緯と、もっぱらコミュニケーションと結びつけて語られる今日の ワークショップへの関心とその背景にある社会状況、2つの切り口からワークショップを考える 内容となった。
ワークショップを思考の対象として主題化する営み自体が海外では例を見ないというが、 ならばワークショップの手法を取り入れてワークショップを考察するという行為も、かなり 珍しいものだろう。今回はそれが講座という場でレクチャー形式で行われたが、ではワーク ショップについてのレクチャーを文字で記録することができるか?という逆説はどこまで 解消できているだろうか。読み手の判断を仰ぐばかりである。
記録:中村美帆(東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学研究専攻博士課程)

はじめに
この講義はワークショップ論シリーズの第1回になる。第1回だけでワークショップが
分かるわけがない(笑)。シリーズが終わるときになって、何か分かるかもしれないし
それでも分からないかもしれないが、まずはワークショップの問題が浮かび上がるように
するのが、今日の趣旨である。
そもそも、ワークショップについてレクチャーをする行為自体、非常に逆説的である。 せっかくワークショップのことを考えるので、ワークショップ的なやり方を取り入れて いきたい。だから今日はみなさんの考えや疑問を聞きながらオーダーメイドで講義を 作っていきたい。
そもそも、ワークショップについてレクチャーをする行為自体、非常に逆説的である。 せっかくワークショップのことを考えるので、ワークショップ的なやり方を取り入れて いきたい。だから今日はみなさんの考えや疑問を聞きながらオーダーメイドで講義を 作っていきたい。
1.アイスブレイク:3枚のカードのワーク
1−1 ワークの進行
《ワークの進行の記録》
赤青緑の3種類のカードを参加者にそれぞれ1枚ずつ配布する。
赤青緑の3種類のカードを参加者にそれぞれ1枚ずつ配布する。
赤:私とワークショップの関わり
ワークショップと自分の関わりの自己紹介を記入
青:ワークショップのイメージ
ワークショップのイメージ、あるいは私が考えるワークショップの定義など
緑:ワークショップについての疑問
普段接しているワークショップを少し離れたところから改めて考えてみる
例:「ワークショップは何故このようなやり方になっているんだろう?」
ワークショップと自分の関わりの自己紹介を記入
青:ワークショップのイメージ
ワークショップのイメージ、あるいは私が考えるワークショップの定義など
緑:ワークショップについての疑問
普段接しているワークショップを少し離れたところから改めて考えてみる
例:「ワークショップは何故このようなやり方になっているんだろう?」
以上の色ごとのテーマ分けに従って、各自配布されたカードに所要時間10分程度で記入する。
まとまった文章である必要はなく、箇条書き・キーワード・図でもいい。記入途中に受講生に
確認の上で、「隣の人が何を描いたか、ちらちらみてもいい」ことを公認する宣言が講師から出される。
3枚のカードができたら、全員席を離れて、教室内を移動しながら出会った人とカードを交換していく。 赤いカードは赤いカード同士で交換し、交換したカードを読み、また他の人と違うカードを交換し、 それを読む。この作業を通して各々のカードが書き手の手を離れてばらばらに教室をめぐることになり、 交換したカードを読むことで、いろんな人の考えを知ることができるようになる。
約15分程度のカード交換中には、「全とっかえ(手持ちの3枚を全部一度に交換する)」、「ばば抜き」 といった新しい交換方法が教室の中で自然に開発されていった。最終的に時間が来たところで交換を やめ、そのとき持っていたカードを手に各自席に戻り、授業再開となる。使用したカードは講義終了後に 任意で提出してもらい、今後の参考資料として活用する。
3枚のカードができたら、全員席を離れて、教室内を移動しながら出会った人とカードを交換していく。 赤いカードは赤いカード同士で交換し、交換したカードを読み、また他の人と違うカードを交換し、 それを読む。この作業を通して各々のカードが書き手の手を離れてばらばらに教室をめぐることになり、 交換したカードを読むことで、いろんな人の考えを知ることができるようになる。
約15分程度のカード交換中には、「全とっかえ(手持ちの3枚を全部一度に交換する)」、「ばば抜き」 といった新しい交換方法が教室の中で自然に開発されていった。最終的に時間が来たところで交換を やめ、そのとき持っていたカードを手に各自席に戻り、授業再開となる。使用したカードは講義終了後に 任意で提出してもらい、今後の参考資料として活用する。
1−2 講師によるワークの振り返り
もしこれが演劇ワークショップのファシリテーターだったら、3色で色ごとにチームに分かれて、
そのテーマで演劇を作るワークショップをやると思う。こんなふうにワークショップは、ちょっとした
アイスブレイクから始まることが多い。そもそもなぜアイスブレイクが必要かという問いも、
ワークショップの問題の一つといえる。
ワークショップのすべてをわかっているわけではないので、今日の講義は答えの定まらない仮説の 段階の内容となる。きっかけとなる話ではあるが、それがすべて正しいと思わないでほしい。むしろ 講義の内容に対し、それは面白い/それは違うという意見が出てくる方が、ワークショップらしくて嬉しい。
今回のワークでカードからは、ワークショップの問題が大きく2つに分かれて浮かび上がってくる。 1つが、ワークショップの歴史の問題、そもそも何故生まれてきたのだろうという問いである。 もう1つが、ワークショップの現在に関する問題である。何故今日こんなにワークショップが広まって きたのか、その過程でワークショップの意味、過程はどのように拡大してきたのか。それはいいことか、 それとも悪いことか。今後はどうなっていくか。今日はこの2つの問題について考えていることを講義したい。
ワークショップのすべてをわかっているわけではないので、今日の講義は答えの定まらない仮説の 段階の内容となる。きっかけとなる話ではあるが、それがすべて正しいと思わないでほしい。むしろ 講義の内容に対し、それは面白い/それは違うという意見が出てくる方が、ワークショップらしくて嬉しい。
今回のワークでカードからは、ワークショップの問題が大きく2つに分かれて浮かび上がってくる。 1つが、ワークショップの歴史の問題、そもそも何故生まれてきたのだろうという問いである。 もう1つが、ワークショップの現在に関する問題である。何故今日こんなにワークショップが広まって きたのか、その過程でワークショップの意味、過程はどのように拡大してきたのか。それはいいことか、 それとも悪いことか。今後はどうなっていくか。今日はこの2つの問題について考えていることを講義したい。
2.ワークショップの歴史
古くからワークショップのようなコミュニケーションの形はあるが、それにワークショップと
いう名前が与えられたのは、ここ100年前後だと思う。それ以前は日常世界にあって、意識も
されず概念化されなかった。意識して捉えてワークショップという名前と形を与えたのが100年
くらい前になる。何人かのキーパーソンが、日常生活から切り離してワークショップの今の
形を規定した。名札の使用(ワークショップネーム)、ふりかえり、アイスブレイク…ワーク
ショップの特徴と言われる諸要素は、歴史的にみると、起源があり理由があることがわかる。
ワークショップの歴史の語り始めは、プラグマティズムから始めたい。おおざっぱにいうと「役に 立つ考えこそがいい考え、役に立つ思想こそがいい思想」という考え方である。もう少し現実の 社会をよくしていく、現実の社会に適応できる思想のかたちを目指した運動である。
ワークショップの歴史の語り始めは、プラグマティズムから始めたい。おおざっぱにいうと「役に 立つ考えこそがいい考え、役に立つ思想こそがいい思想」という考え方である。もう少し現実の 社会をよくしていく、現実の社会に適応できる思想のかたちを目指した運動である。
2−1 ジョン・デューイ
ジョン・デューイ(1859-1952)のプラグマティズムは、ワークショップの考え方に大きな影響を
与えた。ワークショップは20世紀初めに世界で同時多発的に生じた現象で、何か特定の起源がある
というわけではないが、その際にデューイの理論が骨組みとして重要だった。デューイが『思考の
方法(How We Think)』という本の中で述べているreflective thinking(反省的思考あるいは
省察的思考)という考え方がある。何かを考えながら振り返るというものだ。日本語の反省という
言葉には悪いイメージがあるので、省察的思考と言った方がそこから自由になれるかもしれない。
デューイは社会科学者が実験室をもつことの必要性を説いた。理論をただ作っただけでは役に立つ とは限らない。考えているだけなので本当にうまく働くかどうかわからないからだ。まず現場に もっていかないと現場を変えることはできない。実際にデューイが作ったシカゴ大学に実験学校は、 考えたアイディアを実際にやってみる場として機能し、理論と現場の往復が可能となった。 反省的思考は4つのサイクルからできている。
デューイは社会科学者が実験室をもつことの必要性を説いた。理論をただ作っただけでは役に立つ とは限らない。考えているだけなので本当にうまく働くかどうかわからないからだ。まず現場に もっていかないと現場を変えることはできない。実際にデューイが作ったシカゴ大学に実験学校は、 考えたアイディアを実際にやってみる場として機能し、理論と現場の往復が可能となった。 反省的思考は4つのサイクルからできている。
- 理 論
考えて理論を作る。アイディアレベルからもう少し固まった理論的なものまで含む。 - 実 行
理論だけでは何も変わらない。実際に考えてやってみるプロセスが重要。ここでのプロセスは実際の現場でも実験でも両方可。 - 観 察
やりっぱなしではなく、やったことで何が起きたか観察する段階が重要。まさにそこで起きていることを、いろんなレベルで観察する。 - 省 察
観察して終わりではなく、観察を元に自分たちがやったことはどうだったのか、理論の通りだったか違ったか、 違ったとしたらなぜなのか、考える。そうして得られたものを生かして理論を改善する。
この4サイクルによって理論が高められ、現場の実践も高められていく。サイクルが螺旋階段のように
スパイラルとなって向上していくイメージである。デューイの理想は、この向上のスパイラルが回って
いけば社会はどんどん良くなるという、ある種楽観的な見方だった。そのため進歩史観という批判もある。
ワークショップにおいては、実践にこのサイクルをあてはめるとわかりやすくなる。
ワークショップにおいては、実践にこのサイクルをあてはめるとわかりやすくなる。
- 事前打ち合わせ
参加者に何をしてほしいのか、自分たちは何をしたいのかを考える。
参加者に遊んでほしいのか、探究してほしいのか、身につけてほしいのかを考える。 - プランを作ってワークショップで実践
- おわったら振り返り
参加者の振り返りとファシリテーターの振り返りの両方がある。
うまくいかないときは何をしたいかはっきりしていなかったときが多い。 - 上記1〜3を生かしてワークショップの方法を改善していく
このようなデューイの考え方を背景に、実践レベルでは、世界各地でいろんな現象が生じた。
イギリスの労働者演劇でのジョアン・リトルウッドのシアターワークショップや、ワーク
ショップという名称は使っていないとはいえロシア・アバンギャルドやパリのダダイズムのような
芸術運動も、今日のワークショップに関係のある動きとして挙げられる。その後心理系の運動へと、
この文脈は続いていく。
2−2 カール・ロジャーズとクルト・レヴィン
カール・ロジャーズ(1902-1987)は心理学者で、日本ではカウンセリングの文脈で知られている。
ロジャーズが作ったのが「来談者中心療法」である。これは、カウンセラーが働きかけるのではなく、
ひたすら来談者に語ってもらい能動的に傾聴するものだ。とにかく聞いているうちに来談者が
いつのまにか何かを見つけるというスタイルである。晩年のロジャーズはグループワークに関心を
持っていた。彼が「エンカウンター(出会い)」と呼んだ実践はある種の社会実験であり、人が
ただ集まって5日間過ごす環境を設定し、そこで何が起こるか、日常から切り離された非日常空間で
どのような関係が構築されるか、ひたすら観察するものである。その日常との切り離しにおいて、
よりピュアな関係性構築のために、ワークショップネームの名札を使ったのではないか、と仮説
として考えている。
エンカウンターはアメリカで大流行したが、それを発展させたのがクルト・レヴィン (1890-1947) である。彼の実践は「Tグループ」と呼ばれていた。背景には東洋的なもの、スピリチュアルなもの への関心もあった。
しかし、ここまでのワークショップ隆盛はいったん収束することになる。それが何故かを考えることは、 今のワークショップにとっても重要である。
エンカウンターはアメリカで大流行したが、それを発展させたのがクルト・レヴィン (1890-1947) である。彼の実践は「Tグループ」と呼ばれていた。背景には東洋的なもの、スピリチュアルなもの への関心もあった。
しかし、ここまでのワークショップ隆盛はいったん収束することになる。それが何故かを考えることは、 今のワークショップにとっても重要である。
2−3 PDCA(Plan,Do,Check,Act)サイクル
ワークショップのサイクルによく似たPDCA(Plan,Do,Check,Act)サイクルは、産業工学の文脈で
登場した考え方だった。この考え方を使うと、改善を重ねて無駄を排除することで、極力まで
効率化を推し進めることができた。ただしこの考え方はあくまで経営者側の見方で、労働する側は
どんどんPDCAサイクルに飲み込まれ、労働から疎外されていくことになった。突き詰めることで
袋小路にはまってしまった。
日本では、ワークショップの手法をビジネスの文脈での問題解決に活用することが多かった。特に 問題のある社員を参加させて性格改善を目指す研修として機能していた。1960年頃に登場したSTと 呼ばれる感受性訓練の研修は、エンカウンターの手法に近い内容だった。しかし本来のエン カウンターは集まったところで自由に話し合うというものだったのに対し、ここでは企業のニーズの 高まりから個人の内面向上の研修という側面が強まった。その結果、ファシリテーターがどんどん その人の内面に攻め込んでいく過激なグループセミナーのようなものも行われるようになった。 その結果、精神病院に運ばれたり自殺したりする人も出てしまい、危険性がクローズアップされた。
ワークショップの流れは、ここで一回断絶することになる。やってみて考えようと楽観的に思って いたが、実践の危険性を経験した。逆に理論をきちんと考えることの重要性が見えてきた。
日本では、ワークショップの手法をビジネスの文脈での問題解決に活用することが多かった。特に 問題のある社員を参加させて性格改善を目指す研修として機能していた。1960年頃に登場したSTと 呼ばれる感受性訓練の研修は、エンカウンターの手法に近い内容だった。しかし本来のエン カウンターは集まったところで自由に話し合うというものだったのに対し、ここでは企業のニーズの 高まりから個人の内面向上の研修という側面が強まった。その結果、ファシリテーターがどんどん その人の内面に攻め込んでいく過激なグループセミナーのようなものも行われるようになった。 その結果、精神病院に運ばれたり自殺したりする人も出てしまい、危険性がクローズアップされた。
ワークショップの流れは、ここで一回断絶することになる。やってみて考えようと楽観的に思って いたが、実践の危険性を経験した。逆に理論をきちんと考えることの重要性が見えてきた。
3.ワークショップの現在
一度盛り上がりを見せた後に断絶したワークショップが、1980年代にもう一度盛り上がってきたのが、
現在につながる流れとなる。一番大きな背景は、近代的なものへの閉塞感だった。近代システムの
機能不全が見え始めたのがこの頃になる。芸術においては社会の価値観を変革しようとする運動は
20世紀初頭から起こっていたが、それ以外の社会においても近代の閉塞感が見え始めた。
近代的なものの最たる例が教育と官僚だが、この2つの分野が今ワークショップの考え方に一番
関心を持っているのも象徴的である。
3−1 教育と地方自治体
1980年代頃には、佐藤学が指摘した「学びからの逃走」、学校暴力、いじめ、不登校(当時の表現は
登校拒否)といった問題が生じていた。いい学校、いい大学に行けば幸せになれるという
学歴のレールが壊れ始めていた。そのため管理体制を強化して問題を解決することはできず、
管理とは逆の発想になるワークショップ的なものに注目が集まった。
また地方自治体行政においても住民とかけ離れたハコモノ行政に対する批判が噴出した時期で、 行政が自分たちの仕事を正当化するために住民を巻き込んで参加型で物事を進める必要が生じていた。
そうした社会的なニーズに対し、それをバックアップする考え方・理論の登場があったのが この時代である。但し注意するべきは、教育と官僚という最も近代的な存在は、近代的な ものの延命のために敢えて自分の中に異物を注入しているということだ。注入にあたって毒は 抜きさって、うまく延命を図ろうとしている。
また地方自治体行政においても住民とかけ離れたハコモノ行政に対する批判が噴出した時期で、 行政が自分たちの仕事を正当化するために住民を巻き込んで参加型で物事を進める必要が生じていた。
そうした社会的なニーズに対し、それをバックアップする考え方・理論の登場があったのが この時代である。但し注意するべきは、教育と官僚という最も近代的な存在は、近代的な ものの延命のために敢えて自分の中に異物を注入しているということだ。注入にあたって毒は 抜きさって、うまく延命を図ろうとしている。
3−2 関係に対する関心
もうひとつ1980年代の特徴が「関係に対する関心」である。近代社会の「個」中心、「個」が
集まって社会を形成するという考え方から、関係性へと関心が移っていったのがこの頃である。
何を話していても結局「コミュニケーションの問題」と言われるのはその最たる例である。
演劇ではベケットがラディカルにそれをやってみせた。
例えば教育では、個人の学習による知識の蓄積ではなく、関係性を通した学びへと関心が シフトしている。ビジネスの世界でも、人材育成や組織づくりに参加型の手法が続出している。 まちづくりの分野で市民の参加型でのまちづくりが叫ばれ、公共劇場が中心となったまちづくりの 仕事が登場したのもこの頃である。芸術においても、ワークショップ誕生当初の頃と同様に、 1人の天才アーティストに従ってものをつくることの行き詰まりから、いろんな人が関わって コラボレーションでものを作る方向へと関心が移っていた。宗教やスピリチュアリティの世界でも 同様で、イギリスの演劇教育の発祥が中世のキリスト教会劇だということもかかわっている。 そこでは神秘体験の継承するために、淡々と事実を伝えるのではなく、神秘体験の驚きや感動を 疑似的に伝える必要があった。そのために演劇の手法を使い、観劇によって疑似体験化していた。 そうしたルーツを踏まえて今日の宗教は、説教や書物という一方的な既存の伝え方ではなく、 参加的なあり方に関心を示している。このように、ありとあらゆる領域でワークショップ型の活動、 参加的なものが増えてきている。
例えば教育では、個人の学習による知識の蓄積ではなく、関係性を通した学びへと関心が シフトしている。ビジネスの世界でも、人材育成や組織づくりに参加型の手法が続出している。 まちづくりの分野で市民の参加型でのまちづくりが叫ばれ、公共劇場が中心となったまちづくりの 仕事が登場したのもこの頃である。芸術においても、ワークショップ誕生当初の頃と同様に、 1人の天才アーティストに従ってものをつくることの行き詰まりから、いろんな人が関わって コラボレーションでものを作る方向へと関心が移っていた。宗教やスピリチュアリティの世界でも 同様で、イギリスの演劇教育の発祥が中世のキリスト教会劇だということもかかわっている。 そこでは神秘体験の継承するために、淡々と事実を伝えるのではなく、神秘体験の驚きや感動を 疑似的に伝える必要があった。そのために演劇の手法を使い、観劇によって疑似体験化していた。 そうしたルーツを踏まえて今日の宗教は、説教や書物という一方的な既存の伝え方ではなく、 参加的なあり方に関心を示している。このように、ありとあらゆる領域でワークショップ型の活動、 参加的なものが増えてきている。
3−3 海外でのワークショップ
では今日、世界レベルではワークショップについてどのような議論が行われているだろうか。
仮説だがかなりラディカルな問題提起として指摘したいのは、日本以外ではワークショップと
いう言葉を使っていない!?ということだ。海外の視点からは、日本で「ワークショップ論」と
いう言葉を使って講座が行われていること自体、面白い現象に見えるという。
今演劇の国際学会で「ワークショップ」というタイトルはほとんどみない。 applied theatre/drama、日本語で言うなら演劇の手法を社会に生かす応用演劇という 言い方が多い。それ以外に劇場で行われているものについてはeducational program 呼ばれることが多い。また実際に何か一緒に仕事をしようという場合に、単にprojectと呼んでいる。
日本ではこれまで学ぶというと一方通行の講座が伝統的だった。まったく新しい ワークショップというかたちを導入するにあたり、それが何かをよく考える必要が あった。そこで単なるメソッドではなく、方法論(メソドロジー)として、その方法を 取り入れる考え方からとらえようとしたのが日本的だった。日本という文脈で新しいものが 入ってきたときには、違和感を含めて概念化して考えざるを得ないところがある。
たとえば現在のイギリスでは、これまで教育学部で演劇教育をやっていた ひとがどんどん演劇学部に移っているという現象がある。drama educationと 言っていた人がapplied dramaと言い出し、学校教育への応用だけでなく 刑務所での活動やビジネスへの応用を模索し始めた。実際の活動の質は変わらなくても、 名前を鞍替えすることで活動の幅は広がる。現実的に言えば、お金も集めやすくなる。
このような現実を踏まえたときにどうすればいいのか、考え方としては2つある。
ワークショップはもう時代遅れと判断し、applied dramaに移行していく
その場合ワークショップという言葉は10年後にはなくなっているだろう
方法は残っても方法論として残らず、今日のように主題化されることもないだろう
方法論としてワークショップの概念化を可能にした現代日本の特殊な状況を活かすワークショップを掲げて議論を続ける
日本で理論を鍛えて世界に発信する可能性もある
まだ個人的な答えは出ていないが、(2)の可能性はあると思っている。日本をはじめとする 東アジアではコミュニケーションや表現の問題を取り出して考える土壌ができている。 ワークショップという視点からコミュニケーションや表現の問題を考え、ワークショップ概念を 豊かにし、それを海外に発信する可能性はありうるかもしれない。ワークショップの未来には、 複数の可能性が広がっている。
今演劇の国際学会で「ワークショップ」というタイトルはほとんどみない。 applied theatre/drama、日本語で言うなら演劇の手法を社会に生かす応用演劇という 言い方が多い。それ以外に劇場で行われているものについてはeducational program 呼ばれることが多い。また実際に何か一緒に仕事をしようという場合に、単にprojectと呼んでいる。
日本ではこれまで学ぶというと一方通行の講座が伝統的だった。まったく新しい ワークショップというかたちを導入するにあたり、それが何かをよく考える必要が あった。そこで単なるメソッドではなく、方法論(メソドロジー)として、その方法を 取り入れる考え方からとらえようとしたのが日本的だった。日本という文脈で新しいものが 入ってきたときには、違和感を含めて概念化して考えざるを得ないところがある。
たとえば現在のイギリスでは、これまで教育学部で演劇教育をやっていた ひとがどんどん演劇学部に移っているという現象がある。drama educationと 言っていた人がapplied dramaと言い出し、学校教育への応用だけでなく 刑務所での活動やビジネスへの応用を模索し始めた。実際の活動の質は変わらなくても、 名前を鞍替えすることで活動の幅は広がる。現実的に言えば、お金も集めやすくなる。
このような現実を踏まえたときにどうすればいいのか、考え方としては2つある。
ワークショップはもう時代遅れと判断し、applied dramaに移行していく
その場合ワークショップという言葉は10年後にはなくなっているだろう
方法は残っても方法論として残らず、今日のように主題化されることもないだろう
方法論としてワークショップの概念化を可能にした現代日本の特殊な状況を活かすワークショップを掲げて議論を続ける
日本で理論を鍛えて世界に発信する可能性もある
まだ個人的な答えは出ていないが、(2)の可能性はあると思っている。日本をはじめとする 東アジアではコミュニケーションや表現の問題を取り出して考える土壌ができている。 ワークショップという視点からコミュニケーションや表現の問題を考え、ワークショップ概念を 豊かにし、それを海外に発信する可能性はありうるかもしれない。ワークショップの未来には、 複数の可能性が広がっている。
4.質疑応答から"膨らまし"
Q1: 様々なワークショップの広がりの中で、高尾さんがインプロに拘っている理由は?
普段の活動はインプロ、即興演劇をやっている。もともとは上演が主で、お客さんからもらった
キーワードで5−10分、あるいは1時間の即興芝居をつくる。そういう営みが、ある時期から
ワークショップとして盛んになってきた。私の場合は出会った順序としてインプロが先なので、
後からワークショップという概念で理論づけしているかたちになる。
自分自身が楽しくてやっているインプロが、ただやっているだけで衝突を引き起こす。プロの 俳優ではない人を集めてやっていることが専門性を乗り越える行為に見えたり、みんなで世界を 作っていく即興的コラボレーションの要素が従来のものの見方とちがったり、そういう事態が 日常的に生じている。その境界線を乗り越えるにあたり、芸術を作ること、調べたものを 発表すること、教育をすること、全部がごちゃまぜで必要になる。そうした実践を通じて、 演劇と社会の関わりを考えている。
最近気になっているのは、フェミニズムの考え方をきちんと取り入れたいということだ。 効率性や集客性といったこれまで男性的な原理が強すぎた専門性とは違うところに価値をあてていきたい。
自分自身が楽しくてやっているインプロが、ただやっているだけで衝突を引き起こす。プロの 俳優ではない人を集めてやっていることが専門性を乗り越える行為に見えたり、みんなで世界を 作っていく即興的コラボレーションの要素が従来のものの見方とちがったり、そういう事態が 日常的に生じている。その境界線を乗り越えるにあたり、芸術を作ること、調べたものを 発表すること、教育をすること、全部がごちゃまぜで必要になる。そうした実践を通じて、 演劇と社会の関わりを考えている。
最近気になっているのは、フェミニズムの考え方をきちんと取り入れたいということだ。 効率性や集客性といったこれまで男性的な原理が強すぎた専門性とは違うところに価値をあてていきたい。
Q2: ワークショップが60年代で1度断絶して80年代に復活する間の歴史的状況とは?
2つのレベルがあったと思う。60年代に活躍していた人がどこに行ったのかというレベルと、
運動がどうなったかというレベルである。
人が消えていなくなったわけではなく、人は常にそこにいた。名前を変えて実質的には あまり変わらない活動をやっていた。名前を変えた例として、「自己啓発セミナー」を 挙げておく。そうやって名前を変えて、新しい潮流に乗ろうとする。一方の参加する側も 新しい潮流に乗りたくて新しい名前に惹かれてやってくる。本質的にやっていることは そんなに変わらないが、商売としてやる場合は、新しいものを適宜取り入れる必要がある。 鞍替えして生き延びたりする。
運動としては、効率化、科学的なものに基づいて実践を組み立てるという動きはあった。 素人がぐるぐる考えていることろから抜け出したいという欲求があった。理論作りは専門家に 任せて、現場は専門家が作った素晴らしい理論の実践に徹するという分化が考えられたりもした。
人が消えていなくなったわけではなく、人は常にそこにいた。名前を変えて実質的には あまり変わらない活動をやっていた。名前を変えた例として、「自己啓発セミナー」を 挙げておく。そうやって名前を変えて、新しい潮流に乗ろうとする。一方の参加する側も 新しい潮流に乗りたくて新しい名前に惹かれてやってくる。本質的にやっていることは そんなに変わらないが、商売としてやる場合は、新しいものを適宜取り入れる必要がある。 鞍替えして生き延びたりする。
運動としては、効率化、科学的なものに基づいて実践を組み立てるという動きはあった。 素人がぐるぐる考えていることろから抜け出したいという欲求があった。理論作りは専門家に 任せて、現場は専門家が作った素晴らしい理論の実践に徹するという分化が考えられたりもした。

*Q2からの広がり:聴衆参加のミニ・ディスカッション(敬称略)
里見 実
(第3回講師・國學院大學非常勤講師)
流れを2つ、紹介したい。まずは1980年に民衆文化研究会の活動が始まったことである。そこでは、
フィリピンから帰ってきたワークショップ経験者の堀田さんや黒テント、韓国から帰ってきた
研究者や活動家が持ち帰ったマダン劇(広場で自分たちの問題を演じる演劇)、ラテンアメリカの
アウグスト・ボアール、様々な演劇の活動を取り上げていた。
もうひとつの流れが過去を振り返る研究の成果である。ロシア・アバンギャルドなど、ワーク ショップにつながる過去を振り返る研究が出始め、膨大な蓄積の存在が一気に見えてきた時期でもあった。
当時は、世界同時多発的に同じような動きが起きていた。我々は興奮状態でワークショップをやっていた。 美術の領域でも教師が中心になってかなり早くから美術ワークショップという言葉を使ってやっており、 音楽も同様の状況だった。そういう動きが一気に視野に入ってきたのは80年代初めだが、視野に入ってきたと いうことは70年代にもずっと行われていたということである。
そこで再発見されたものは多かった。ウィリアム・モリスのワークショップや、モリスが意識していた 中世の職人たちの仕事の仕方、中世の職人の仕事の仕方の再発見・再創造があった。それがワーク ショップという言葉につながる。
今でも僕自身はワークショップという言葉に愛着がある。日本語に馴染まないため訳語を考えた時期も あるが、ワークショップという言葉でいこうと腹をくくったのは、やはりworkshop、フランス語で いえばアトリエだと思ったからだ。だからワークショップは仕事の仕方を変えていくことであり、 特別な場所での実験とは思っていなかった。我々の仕事の仕方を変えていくこと。限定された場を 超えて外にはみ出していく運動的な性質のものだと考えていたし、そうしたいと思っていた。
企業の中でもいろいろな実践があったと思うが、そういうことについては当時の僕らは全く考えていなかった。 企業社会の論理とはもうちょっと違った労働のスタイルの話だと考えていた。
もうひとつの流れが過去を振り返る研究の成果である。ロシア・アバンギャルドなど、ワーク ショップにつながる過去を振り返る研究が出始め、膨大な蓄積の存在が一気に見えてきた時期でもあった。
当時は、世界同時多発的に同じような動きが起きていた。我々は興奮状態でワークショップをやっていた。 美術の領域でも教師が中心になってかなり早くから美術ワークショップという言葉を使ってやっており、 音楽も同様の状況だった。そういう動きが一気に視野に入ってきたのは80年代初めだが、視野に入ってきたと いうことは70年代にもずっと行われていたということである。
そこで再発見されたものは多かった。ウィリアム・モリスのワークショップや、モリスが意識していた 中世の職人たちの仕事の仕方、中世の職人の仕事の仕方の再発見・再創造があった。それがワーク ショップという言葉につながる。
今でも僕自身はワークショップという言葉に愛着がある。日本語に馴染まないため訳語を考えた時期も あるが、ワークショップという言葉でいこうと腹をくくったのは、やはりworkshop、フランス語で いえばアトリエだと思ったからだ。だからワークショップは仕事の仕方を変えていくことであり、 特別な場所での実験とは思っていなかった。我々の仕事の仕方を変えていくこと。限定された場を 超えて外にはみ出していく運動的な性質のものだと考えていたし、そうしたいと思っていた。
企業の中でもいろいろな実践があったと思うが、そういうことについては当時の僕らは全く考えていなかった。 企業社会の論理とはもうちょっと違った労働のスタイルの話だと考えていた。
高尾:
今の議論にインスパイアされて1つ発言したい。
自分自身の研究のスタイルとして、質的研究を行っている。演劇教育に関する質的な研究は、 演劇を作ることと教育することが混じり合い全部が重なり合っている。だから研究を論文に する行為そのものへの批判的問題意識も感じている。
研究者が研究対象から略奪しているコロニアルな研究スタイルに問題意識を持ち、研究成果を 研究対象に返さないといけないと考えたときに、最後の表現形式として論文という形式が 果たして適切なのか。論文ではなく、映像を採用したり戯曲にして上演するパフォーマンス・ エスノグラフィーも必要になってくる。ここまで来ると研究活動と表現活動が相当重なり合う。 更に、例えば研究成果を演劇にして一緒に上演したり、一緒に関わって何かやったりすることは、 学び、教育にもつながる。こんなかたちで、研究と教育と芸術のクロスオーバーが起こる。
そういうクロスオーバーが発生している今日、社会の中で大人たちが何をしているか。 一例として「third place」という考え方がある。家庭でも職場でもないもう1つのサードプレイスを 持っていることが、その人の仕事や人生の質を高めるというものだ。それをワークショップという やり方でやっているところもあり、そうではないものもある。具体的には、地域密着型の新しい 学びのかたちであるシブヤ大学の活動などが挙げられる。そこで問われているのは大人の学びであり、 大人が働く、というのはどういうことかを問い直す営みである。
自分自身の研究のスタイルとして、質的研究を行っている。演劇教育に関する質的な研究は、 演劇を作ることと教育することが混じり合い全部が重なり合っている。だから研究を論文に する行為そのものへの批判的問題意識も感じている。
研究者が研究対象から略奪しているコロニアルな研究スタイルに問題意識を持ち、研究成果を 研究対象に返さないといけないと考えたときに、最後の表現形式として論文という形式が 果たして適切なのか。論文ではなく、映像を採用したり戯曲にして上演するパフォーマンス・ エスノグラフィーも必要になってくる。ここまで来ると研究活動と表現活動が相当重なり合う。 更に、例えば研究成果を演劇にして一緒に上演したり、一緒に関わって何かやったりすることは、 学び、教育にもつながる。こんなかたちで、研究と教育と芸術のクロスオーバーが起こる。
そういうクロスオーバーが発生している今日、社会の中で大人たちが何をしているか。 一例として「third place」という考え方がある。家庭でも職場でもないもう1つのサードプレイスを 持っていることが、その人の仕事や人生の質を高めるというものだ。それをワークショップという やり方でやっているところもあり、そうではないものもある。具体的には、地域密着型の新しい 学びのかたちであるシブヤ大学の活動などが挙げられる。そこで問われているのは大人の学びであり、 大人が働く、というのはどういうことかを問い直す営みである。

花崎 攝
(第7回講師・演劇デザインギルド)
実践者の立場から、学校、特に小中学校に、先生が教えるのではないかたちでの活動が入って
きていることが指摘できる。一方大学はどうだろうか。
学校は軍隊や官僚のように近代の根幹をなすシステムである。学校の中には強固なヒエラルキーがある。 ピラミッドが揺るぎなく存在する学校の中では、ワークショップの方法で非日常的な空間を作り日常を 断ち切った自分としてそこに現れるということが実際には不可能である。生徒も先生も誰も信じていない。 ただ非日常空間に自分として現れることが本当に可能だとは思っていない一方で、現実の閉塞感は 感じていて、それに代わるものとしてワークショップが求められるニーズがある。そういう状況で、 コミュニケーションとか便利な言葉で中身は問われないままに、表現することが「能力を高める」と いう言い方で求められている。
そうした行為に意味がないとは思わないけれど、ものすごく大きな矛盾を抱えたまま進行しているとは思っている。
学校は軍隊や官僚のように近代の根幹をなすシステムである。学校の中には強固なヒエラルキーがある。 ピラミッドが揺るぎなく存在する学校の中では、ワークショップの方法で非日常的な空間を作り日常を 断ち切った自分としてそこに現れるということが実際には不可能である。生徒も先生も誰も信じていない。 ただ非日常空間に自分として現れることが本当に可能だとは思っていない一方で、現実の閉塞感は 感じていて、それに代わるものとしてワークショップが求められるニーズがある。そういう状況で、 コミュニケーションとか便利な言葉で中身は問われないままに、表現することが「能力を高める」と いう言い方で求められている。
そうした行為に意味がないとは思わないけれど、ものすごく大きな矛盾を抱えたまま進行しているとは思っている。
高尾:
まさに延命のために毒を抜いて導入している状況といえる。落語の「目黒の秋刀魚」のように、
学校がワークショップを取り入れるときにおなかを壊しそうなものは全部抜いて取り入れた結果、
不味いものになってしまっていないかという問題意識はある。
ファシリテーションの観点から言うと、例えばロバート・チェンバース『参加型ワークショップ』(日本 語訳は2004年出版)では、fasipulationについて論じている。ワークショップでは、リーダーが一方的に 知識を授けるのではなく、ファシリテーターがお互いに関わり合う学びの場を促進する。facilitation(促進 する、促す)というとやさしい言い方だが、ファシリテーターは仕切りのリーダーとしては絶対的で、 ファシリテーターがこうやろうといったときに他の参加者は厭だとは言いにくくなる。そういう状況を 皮肉ってfasipulation(参考:manipulate:誘導する)という言い方をしている。
学校教育の現場では、どうしてもfasipulationが多くなる。そこでは、もともと学校がやろうとしている ことは変えないで、形だけをとりいれやすいものに変えようとしている。それはメソッドとしてのワーク ショップではあるけれど、メソドロジーではないと思う。
土井隆義さんの若者文化の研究では、現代の若者のコミュニケーションの変化について、コミュニケー ションの2つのレベルから論じている。まず1つが親密圏のコミュニケーション、もう1つが公共圏の コミュニケーションだ。親密圏は、家族や友達、利益抜きのコミュニケーションで、もう1つが公共圏、 学校の先生や駅の人やお店の人、社会的なコミュニケーションである。従来のイメージでは、親密圏は 素の自分のままで喧嘩もできるし仲直りもできる空間、一方の公共圏では思ったまま感じたままでは いけなくて適切な接し方があるというのが子どもの世界観だった。それが今日では逆転しているのでは ないかというのが土井さんの研究の指摘である。つまり親密圏での傷つけ合いにものすごく敏感に なっていて、その都度その都度空気を読んで自分がその親密圏で生き延びるための役割を演じている。 それで疲れてしまって公共圏で気を回す余裕がなく、公共圏では自分をさらけ出してくつろいでしまう。
ここではコミュニケーションの意味を精査して使う必要がある。今の若者がコミュニケーション能力が 落ちているのではなく、むしろコミュニケーション能力が異常に高いのではないか。だから苦しく なっているというものの見方ができる。親密圏にあたる学校でワークショップをやることは2重の演技を 要求していることになる。
ファシリテーションの観点から言うと、例えばロバート・チェンバース『参加型ワークショップ』(日本 語訳は2004年出版)では、fasipulationについて論じている。ワークショップでは、リーダーが一方的に 知識を授けるのではなく、ファシリテーターがお互いに関わり合う学びの場を促進する。facilitation(促進 する、促す)というとやさしい言い方だが、ファシリテーターは仕切りのリーダーとしては絶対的で、 ファシリテーターがこうやろうといったときに他の参加者は厭だとは言いにくくなる。そういう状況を 皮肉ってfasipulation(参考:manipulate:誘導する)という言い方をしている。
学校教育の現場では、どうしてもfasipulationが多くなる。そこでは、もともと学校がやろうとしている ことは変えないで、形だけをとりいれやすいものに変えようとしている。それはメソッドとしてのワーク ショップではあるけれど、メソドロジーではないと思う。
土井隆義さんの若者文化の研究では、現代の若者のコミュニケーションの変化について、コミュニケー ションの2つのレベルから論じている。まず1つが親密圏のコミュニケーション、もう1つが公共圏の コミュニケーションだ。親密圏は、家族や友達、利益抜きのコミュニケーションで、もう1つが公共圏、 学校の先生や駅の人やお店の人、社会的なコミュニケーションである。従来のイメージでは、親密圏は 素の自分のままで喧嘩もできるし仲直りもできる空間、一方の公共圏では思ったまま感じたままでは いけなくて適切な接し方があるというのが子どもの世界観だった。それが今日では逆転しているのでは ないかというのが土井さんの研究の指摘である。つまり親密圏での傷つけ合いにものすごく敏感に なっていて、その都度その都度空気を読んで自分がその親密圏で生き延びるための役割を演じている。 それで疲れてしまって公共圏で気を回す余裕がなく、公共圏では自分をさらけ出してくつろいでしまう。
ここではコミュニケーションの意味を精査して使う必要がある。今の若者がコミュニケーション能力が 落ちているのではなく、むしろコミュニケーション能力が異常に高いのではないか。だから苦しく なっているというものの見方ができる。親密圏にあたる学校でワークショップをやることは2重の演技を 要求していることになる。

熊谷 保宏
(第2回講師・日本大学芸術学部准教授)
演劇のワークショップとして持っていく場面とは別に、演劇の現場そのものもワークショップであると
いうことができる。うまく利用しているともいえるし、適当に使い分けているともいえる。
ワークショップにおいては、身の回りにある言葉を方便で使い分けていた。それがある時点から、 想像の現場と社会を切り結ぶ原理のようなものがでてきて一変してしまった。そうした流れの中で 現代においてワークショップにどのような有効性があるのか。すべてがコミュニケーションという 言葉に回収されてしまっている状況に問題意識はある。
ワークショップにおいては、身の回りにある言葉を方便で使い分けていた。それがある時点から、 想像の現場と社会を切り結ぶ原理のようなものがでてきて一変してしまった。そうした流れの中で 現代においてワークショップにどのような有効性があるのか。すべてがコミュニケーションという 言葉に回収されてしまっている状況に問題意識はある。

Q3: 演劇の事例をベースとしたワークショップの将来像が中心だったが、他の分野は?
2007年に香港で開催された演劇教育の国際学会のシンポジウムで、国際演劇教育連盟・国際音楽教育連盟・
国際美術教育連盟の会長が鼎談する機会があった。その際に音楽教育連盟の会長が今の問題として指摘したのが
コミュニケーションである。そこでは、言葉を使わない異文化理解、他者理解、コミュニケーションを
学ぶものとして音楽教育の可能性を指摘していた。このように、音楽教育と言ったときに、音楽の技術を
伝えることよりも音楽を通したコミュニケーションに力点を置く研究が増えている。芸術を
コミュニケーション、表現のツールとして学ぶという動きはあると言っていいと思う。
コミュニケーションという概念は、宮崎駿の「千と千尋の神隠し」に出てくるキャラクター「カオナシ」の ようなもので、何でもどんどん飲み込んで肥えていくけれど、肥えていけばいくほど自分が何者かわからなく なっていく。言説の政治、言葉での戦い合い、言葉を作って言説を語ることで実態ができていくポストモダンの 思想に典型的な状況かもしれない。
これまでも私たちは言葉を作ることでやりたいことをやってきた。80年代の「国際人」、それから「個性」と いう言葉も何でもからめ捕れる便利な言葉だった。「コミュニケーション」も、そういう風にみんなが使う 便利な言葉になりつつある。
実際に「コミュニケーション教育」といったときに、アジアの研究者とヨーロッパの研究者で言うことが 違ったりする。香港の研究者が「学校教育で窮屈な子どもに自由にできるコミュニケーションの場を」と いえば、フィンランドの研究者が「子どもに社会性をもたせるために挨拶等のコミュニケーションを学んで ほしい」という。いろんな意味の違いがある中で、言説を鍛えることが必要になっている。例えば「豊かな心」と いったときに実際には何が育っているか。それを表現する言説を作らなければならない。
コミュニケーションという概念は、宮崎駿の「千と千尋の神隠し」に出てくるキャラクター「カオナシ」の ようなもので、何でもどんどん飲み込んで肥えていくけれど、肥えていけばいくほど自分が何者かわからなく なっていく。言説の政治、言葉での戦い合い、言葉を作って言説を語ることで実態ができていくポストモダンの 思想に典型的な状況かもしれない。
これまでも私たちは言葉を作ることでやりたいことをやってきた。80年代の「国際人」、それから「個性」と いう言葉も何でもからめ捕れる便利な言葉だった。「コミュニケーション」も、そういう風にみんなが使う 便利な言葉になりつつある。
実際に「コミュニケーション教育」といったときに、アジアの研究者とヨーロッパの研究者で言うことが 違ったりする。香港の研究者が「学校教育で窮屈な子どもに自由にできるコミュニケーションの場を」と いえば、フィンランドの研究者が「子どもに社会性をもたせるために挨拶等のコミュニケーションを学んで ほしい」という。いろんな意味の違いがある中で、言説を鍛えることが必要になっている。例えば「豊かな心」と いったときに実際には何が育っているか。それを表現する言説を作らなければならない。

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.


