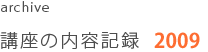


シリーズ講座『舞台芸術の現在』
Vol.4「〈マルチメディア的〉アメリカ」
2009年10月28日(水) 19時〜21時
内野 儀
(東京大学大学院総合文化研究科教授)
《所 感》
マルチメディアとは何か。そもそも演劇は視覚、聴覚に接触するマルチメディアであり、それをあえてマルチメディア的舞台芸術と呼ぶのは、記録された動画が舞台に用いられている場合をいう。メディアという概念の特性、舞台芸術と技術との関係を解きほぐし、ニック・ケイの文章を参照しながら、メディアの増殖性、輻輳性、回帰性について解説した。またヴィデオテクノロジーが発達するにつれて、現代美術と舞台芸術がジャンル横断しながら変容していく過程の検証を行った。1965年以降ヴィデオテクノロジーが一般化したが、舞台に記録映像を用いる当初の意義は、メディアという媒介性を舞台に持ち込むことで、パフォーマーの現前性をより明確にするという試みであった。
グローバリゼーション下、さまざまな技術が日常化し必要不可欠となっている今日、舞台芸術という対話の場において、より違和感のない感情の伝達方法とは何か。舞台は現実に対応するメディアとしての機能をいかに果たしうるのか。舞台表現の根源的方法に立ち戻り、現在活躍するアメリカの舞台芸術の分析を行った、数多くの、とても貴重な示唆をいただいた講座であった。
マルチメディアとは何か。そもそも演劇は視覚、聴覚に接触するマルチメディアであり、それをあえてマルチメディア的舞台芸術と呼ぶのは、記録された動画が舞台に用いられている場合をいう。メディアという概念の特性、舞台芸術と技術との関係を解きほぐし、ニック・ケイの文章を参照しながら、メディアの増殖性、輻輳性、回帰性について解説した。またヴィデオテクノロジーが発達するにつれて、現代美術と舞台芸術がジャンル横断しながら変容していく過程の検証を行った。1965年以降ヴィデオテクノロジーが一般化したが、舞台に記録映像を用いる当初の意義は、メディアという媒介性を舞台に持ち込むことで、パフォーマーの現前性をより明確にするという試みであった。
グローバリゼーション下、さまざまな技術が日常化し必要不可欠となっている今日、舞台芸術という対話の場において、より違和感のない感情の伝達方法とは何か。舞台は現実に対応するメディアとしての機能をいかに果たしうるのか。舞台表現の根源的方法に立ち戻り、現在活躍するアメリカの舞台芸術の分析を行った、数多くの、とても貴重な示唆をいただいた講座であった。
記録:塩田典子(早稲田大学大学院文学研究科芸術学(演劇映像)専攻修士課程修了)

1.はじめに
今日、いわゆるマルチメディア的演劇、上演が主流であるかどうかはともあれ、ある先鋭的な思想の問題とリンクしながら進んできている。戦後絶えず行われてきたそのような活動が、日本ではアメリカのコピーライトの意識が高いせいか手に入りにくく、なかなか映像で紹介されなかった。本講座ではウースターグループなどいくつかの事例を、思想的問題とともに語り起していきたい。
2.マルチメディア
<メディアという問題>
- 視覚性と記録を可能にする媒体としてのメディア (フィルム→映画→ヴィデオという展開)
- 声のメディアとしてのラジオ
- インターネット
90年代以降ゼロ年代に入り、アーティストの関心にのぼる
<マルチメディアとは何か?>
演劇はそもそも、知覚と聴覚に関わる複数のメディアが同時に存在するマルチメディアであるという前提がある。
あえて、マルチメディアという言葉を使うのは、記録メディアとしての映像、ライヴ中継も可能なテレビに加えて、ヴィデオテクノロジーとの関係が意識されるようになってからマルチメディアという言葉がでてきたのではないか?
アメリカの場合、演劇と映画という表現形式において、20世紀初頭以降それぞれの居場所を考えながら、マーケットの奪い合い、俳優の奪い合い、技術者の奪い合いにおいてかろうじて調整してきたという歴史がある。
あえて、マルチメディアという言葉を使うのは、記録メディアとしての映像、ライヴ中継も可能なテレビに加えて、ヴィデオテクノロジーとの関係が意識されるようになってからマルチメディアという言葉がでてきたのではないか?
アメリカの場合、演劇と映画という表現形式において、20世紀初頭以降それぞれの居場所を考えながら、マーケットの奪い合い、俳優の奪い合い、技術者の奪い合いにおいてかろうじて調整してきたという歴史がある。
2−1. メディアにおける二項対立
テクノロジー一般という概念、テクノロジーという還元的な概念を敵視するという長い伝統が西洋にはあり、日本にもいろいろなところにあるが、それはほとんど内面化されたイデオロギーとしてさまざまな時代環境の中で、さまざまな影響を舞台芸術に与えてきたと言える。ここではその問題をあえて単純化して考えたい。
「ライヴ性」対「記録」されたもの
「一回性」対「再現可能性」
「直接性」対「媒介性」
(直接的コミュニケーション)(媒介的コミュニケーション)
「本物」対「コピー」
「一回性」対「再現可能性」
「直接性」対「媒介性」
(直接的コミュニケーション)(媒介的コミュニケーション)
「本物」対「コピー」
「本物性」と「偽物性」はヴィトンのバックを考えると分りやすい。本物のヴィトンのバックは色んな種類の本物があって、別にコピーも存在する。本物、偽物はどちらも複数であり、実は重なりあうようなそれぞれの関係がある。
「劇場では、生のパフォーマンスが展開してそれが今ここで生起する一回性のものだが、映画やテレビでは何度も再現可能であるし、映画はフィルムに記録された原理的にいうと映像のスクリーンという平面に投射された光りの束にすぎない」(アントナン・アルトー)という言葉があるが、原理的にはこのようなものである。
テレビはたとえそれがライヴであっても、モニターという平面に映る一種の媒介的映像に過ぎず、テレビもこのようなドット(点)であるにすぎない。テレビ上の身体は、平面に投射されたイメージにすぎないのである。これに対して舞台芸術は目の前、同じ空間に俳優、ダンサーがおり、ある意味での本物性がある。舞台芸術側からすると、舞台芸術の方が偉く、映画・テレビの側からすれば舞台芸術のライヴ性への良心の呵責のようなものがある。それゆえ、舞台芸術の方が市場価値が高いということになる。マーケッタビリティが高いというのは単に儲かるということを指すのではなく、文化的価値が高く、生の舞台に接しなければならないといった教育や言説はそこから導かれてくる。
「直接性」については原理的に奇妙であり、特に演劇については、俳優は事前に書かれたセリフを喋っているので劇作家の単なる媒介であると理念としては言える。また、ダンサーについては、私は直接的直感的に今ここで踊っているんだと言われれば仕方がないが、『白鳥の湖』といった作品を踊る場合はやはり物語の人物を演じているということになる。物語の人物がどこにいるのかというと、そこにはなくてどこか別のところから来ていると言うことになる。
「劇場では、生のパフォーマンスが展開してそれが今ここで生起する一回性のものだが、映画やテレビでは何度も再現可能であるし、映画はフィルムに記録された原理的にいうと映像のスクリーンという平面に投射された光りの束にすぎない」(アントナン・アルトー)という言葉があるが、原理的にはこのようなものである。
テレビはたとえそれがライヴであっても、モニターという平面に映る一種の媒介的映像に過ぎず、テレビもこのようなドット(点)であるにすぎない。テレビ上の身体は、平面に投射されたイメージにすぎないのである。これに対して舞台芸術は目の前、同じ空間に俳優、ダンサーがおり、ある意味での本物性がある。舞台芸術側からすると、舞台芸術の方が偉く、映画・テレビの側からすれば舞台芸術のライヴ性への良心の呵責のようなものがある。それゆえ、舞台芸術の方が市場価値が高いということになる。マーケッタビリティが高いというのは単に儲かるということを指すのではなく、文化的価値が高く、生の舞台に接しなければならないといった教育や言説はそこから導かれてくる。
「直接性」については原理的に奇妙であり、特に演劇については、俳優は事前に書かれたセリフを喋っているので劇作家の単なる媒介であると理念としては言える。また、ダンサーについては、私は直接的直感的に今ここで踊っているんだと言われれば仕方がないが、『白鳥の湖』といった作品を踊る場合はやはり物語の人物を演じているということになる。物語の人物がどこにいるのかというと、そこにはなくてどこか別のところから来ていると言うことになる。
2−2. 舞台芸術と技術
照明、音響を考えればわかるように、テクノロジーは舞台芸術に長い間関係してきた。アメリカでは19世紀の終わりから20世紀にかけて、電気照明が劇場で使用されるようにりな、それが可能となったことから、さまざまな劇場表現が可能となった。
照明:ランプの光り→ガス照明→電気照明
音響:生演奏→リールテープ→カセットテープ→CD→MD→ファイル
音響:生演奏→リールテープ→カセットテープ→CD→MD→ファイル
<シェイクスピアの時代>
シェイクスピアの時代には、「鳥が鳴いた。もうすぐ夜明けだ」というように、ま昼に太陽の光りの下で上演していた時代は、セリフによって時間や場所を観客に説明してきた。舞台には簡単な装置しかなく、日の光りの照明しか使えなかった。しかしそのような設備の不足は作家にとっては有利な面が多かった。言葉だけで時間、場面を変化させることができ、その結果シェイクスピアの舞台では、数多くのシーンが存在したのである。
したがって、メディア芸術に対する拒否反応が舞台芸術側にあるが、舞台芸術のライヴ性、直接性を損なわないかぎりはあまり、考えられてこなかった。
したがって、メディア芸術に対する拒否反応が舞台芸術側にあるが、舞台芸術のライヴ性、直接性を損なわないかぎりはあまり、考えられてこなかった。
<マルチメディア芸術>
一般にマルチメディアという場合、素材ないし表現手段に映像、つまり動画のメディアが加わっていると、そう呼ばれることがある。フィルム映像を舞台芸術に導入した事例は映画の初頭から随分あり、戦後だけで見てもかなり早い時期から映像作家とのコラボレーションとよべるようなものを行ってきた。
<ヴィデオテクノロジーの影響>
舞台芸術に大きな転換をもたらしたのは、ヴィデオというメディアが創られて、ヴィデオテクノロジーが瞬く間に発展、普及したことである。1965年にソニーがヴィデオの録画機材を発売した。時代時代を画する時期には必ずそこに介在したテクノロジーがあるといったのはフレドリック・ジェイムソンというアメリカの研究者であり批評家であるが、彼がポストモダンと言われる時代状況を徴候的に示すテクノロジーはヴィデオであると言ったと記憶している。
時代を画するメディアテクノロジーとは、その登場によって、人間の認識や知覚が揺らぐことを意味する。つまり、ここでいう人間は知覚する主体としての人間であるが、存在様式、主体、あるいは主体化と関わる実在性や、身体がそこにある、あるいは人間がそこに存在しているというような事柄自体が揺らぐことを意味するのである。また、視覚性から記憶、認知の問題に至るまで複雑かつ哲学的な領域でもあるポストモダンにおける人間存在の地殻変動的事態をヴィデオが徴候的にもたらしているとも言える。
時代を画するメディアテクノロジーとは、その登場によって、人間の認識や知覚が揺らぐことを意味する。つまり、ここでいう人間は知覚する主体としての人間であるが、存在様式、主体、あるいは主体化と関わる実在性や、身体がそこにある、あるいは人間がそこに存在しているというような事柄自体が揺らぐことを意味するのである。また、視覚性から記憶、認知の問題に至るまで複雑かつ哲学的な領域でもあるポストモダンにおける人間存在の地殻変動的事態をヴィデオが徴候的にもたらしているとも言える。
<メディア技術の進化>
第二次世界大戦後のいわゆる現代美術の分野で、ヴィデオアートという固有のジャンルが生みだされる。ヴィデオを使うことによって今までの美術の文脈の中で出し得ない、新しい領域が切り開かれてくる。美術の場合は分りやすいのは、動かなかった絵が動くのであるから大きな違いがあるからである。
最初に現代美術からはじまって、それが次第に舞台芸術に浸食してくる。大きな機械でこわごわと録画を行っていた時代から、β/VHSの家庭用ヴィデオ機器になり、それがあっという間に古くなってDVDが生れ、今やYouTubeがネットを席巻していることからも分るようにメディア環境の急速な変化がある。ヴィデオテクノロジー誕生後30年程の展開と現代美術から舞台芸術への流れはパラレルに進んでいる。
最初に現代美術からはじまって、それが次第に舞台芸術に浸食してくる。大きな機械でこわごわと録画を行っていた時代から、β/VHSの家庭用ヴィデオ機器になり、それがあっという間に古くなってDVDが生れ、今やYouTubeがネットを席巻していることからも分るようにメディア環境の急速な変化がある。ヴィデオテクノロジー誕生後30年程の展開と現代美術から舞台芸術への流れはパラレルに進んでいる。
<マルチメディア時代の舞台芸術>
日本におけるマルチメディア芸術
- ダムタイプ『S/N』(1995)
台があって、下に大きなスクリーンがある。パフォーマーは基本的に台の上におり、 下のスクリーンにはさまざまな映像や、ライヴで行われていることが大写しにされている。
- サイモン・マクバーニー『エレファント・バニッシュ』(2003)
メディア芸術を取り入れた代表的な舞台作品。映像の使い方、俳優は必ずマイクを 通して喋るという、メディアに取り囲まれた身体と村上春樹の言語との親近性が マクバーニーによって描かれた舞台である。
3.ニック・ケイ『マルチメディア:ヴィデオ、インスタレーション、パフォーマンス』(2007)
イギリスのエクセター大学の先生がアメリカの現代美術と演劇について書いた本。
3−1. イントロダクション(引用1)
- マルチメディア芸術の「収斂化」
マルチメディアによって拡散された表現が、一方でアーティストの意志において、 ある種の強度を持つこと。 - マルチメディア芸術の「逆流=拡散」
拡散した表現が、ビルダーズ・アソシエイションのように物語へ、回帰する方向へ 進んでいく。20世紀終わり頃から、ある種かき消されてきたものが回帰してくる。 - 本の構成(取り上げているアーティスト)
第一章「ヴィデオの時間、パフォーマンスの時間」
ナム・ジュン・パイク、ジョン・ケージ、フラクサス、ブルース・ナウマン、 ダン・グレアム、ジョン・ジョナス 第二章「ヴィデオの空間、パフォーマンスの空間」
ビト・アコンチ、スタジオアズユーロ、ピロティ・ウェスト、ゲイリー・ヒル 第三章「複数化するメディア」
ウースターグループ、ジョン・ジェスラン、ビルダーズ・アソシエイション
3−2. メディアテクノロジーを使用した試み
この書物でまず注目しなければならないのは、テレビ、ヴィデオのテクノロジーが単に既存の芸術様式(絵画であれ演劇であれ)、その形式的既存性を補完する形でメディアが導入されたのではなく、約束事、因習性を破壊したり乗り越えたりするというようなジャンル横断的ないしは越境的な試みを求めていたなかでヴィデオテクノロジーが注目されたということである。
つまり、現代の我々が現代の感覚では、既存の演劇において俳優が喋って、物語がそこで上演されるという形式に違和感を持った時に、ヴィデオを使ったら何か違うものができるのではないかという発想の転換である。今のアーティストの感性、世界観、自分の考えているものと、既存の表現形式が齟齬をきたしてくる。その時、それをどうするか、という問題である。
一方ではヴィデオアートが出てきて、美術において身体が問題化されるようになり、アクションペインティングやパフォーマンスアートというジャンルの成立に向っていく。
つまり、現代の我々が現代の感覚では、既存の演劇において俳優が喋って、物語がそこで上演されるという形式に違和感を持った時に、ヴィデオを使ったら何か違うものができるのではないかという発想の転換である。今のアーティストの感性、世界観、自分の考えているものと、既存の表現形式が齟齬をきたしてくる。その時、それをどうするか、という問題である。
一方ではヴィデオアートが出てきて、美術において身体が問題化されるようになり、アクションペインティングやパフォーマンスアートというジャンルの成立に向っていく。
3−3. 美術におけるマルチメディア芸術
戦後アメリカ美術においては、オブジェクトつまり物としてそこにあるものとして動かない作品と観者の静的な作品受容の関係が変化する。少なくともこの作品は今見ている私が死んでも生き残る、時間を超越していることが前提とされたが、そうい美術作品の概念そのものを問いなおしたものが、この本ではナム・ジュン・パイク、ジョン・ケージが最初だと述べている。
(引用1)で完結に書かれていた、そこでしか生起していないもの(音楽は基本的にそうであるが)と芸術がどのように連携しているかはある種の逆説をはらむ。ある種の永続性や不変性を希求するオブジェとしての芸術作品と、その場で生まれては消えてしまう音楽との連携はどう行うのか。それを試みた世代において、時間という従来の美術にとっては関係ないはずだった要素、概念がテレビやヴィデオテクノロジー、ライヴパフォーマンスとしばしばパラドキシカルな関係をとおして問題化されたという流れがある。
(引用1)で完結に書かれていた、そこでしか生起していないもの(音楽は基本的にそうであるが)と芸術がどのように連携しているかはある種の逆説をはらむ。ある種の永続性や不変性を希求するオブジェとしての芸術作品と、その場で生まれては消えてしまう音楽との連携はどう行うのか。それを試みた世代において、時間という従来の美術にとっては関係ないはずだった要素、概念がテレビやヴィデオテクノロジー、ライヴパフォーマンスとしばしばパラドキシカルな関係をとおして問題化されたという流れがある。
- Vertical Roll (1972) ジョン・ジョナス
同時期に、時間だけではなく空間性が問題化される流れもある。ジョン・ジョナスの作品Vertical Rollは、基本的に単一チャンネルの(モニターが一つ置かれた)ヴィデオ作品である。72年当時は一つのモニターを置くことも大変であり、複数のモニターを置けるような時代ではなかった。展示と同じ年に行われた「有機はちみつの垂直な転がり」と、ジョナス自身のマルチメディアのライヴパフォーマンスのプロセスで作った映像を後で、作品として提出している。ところがライヴパフォーマンス自身がそれとは又別のドキュメンタリービデオ作品となっている。そういう極めて複雑な、つまり作品とは何か、それが唯一絶対のアウラを放っているわけではなくて、そのヴィデオそのものが別のものを撮っているにすぎず、ではその何か別のものがオリジナルなのかというと、それがまた何か別のものを参照しているというそういうような形で、相互参照的な、インターテクスチュアルに作品概念がジョナスの中では機能しているという例を紹介している。
これは従来の美術とは異なっている。美術には絵画のフレームのように作品の枠というものがあり、これが全部であるということが明白であった。しかしこのジョナスの芸術作品を経験するということは、そこに付帯としての作品というものが逆に呼び込まれていくような形になる。もちろんそうしたものはコンセプチュアルであって、立体的にはなんの意味もないという意見もあるが、少なくともそういう概念装置の中で作品が構想され作られている。
さらに重要なことは、作品が消えてしまうということである。そもそも、行われたパフォーマンス、オリジナルに、ヴィデオ作品ではアクセスできない。観者であった美術鑑賞者は今や演劇の観客的になり、さらにはそれ以上にパフォーマンスの要素ともなり、主体的に作品空間にフィジカルにとり込まれてしまう。 - 美術と観者との関係性の変化
ヴィデオインスタレーションにおいては、見る人、見られる人という関係が崩れていく。
今までの美術体験においては、好きな時に見ることを止められるが、ヴィデオ作品がたとえば、3分50秒であった場合、全部見なくてはいけないのではないか、ということがある。全部見なくてはいけないとすると、それは従来無かった演劇的な束縛である。観者が意識的身体的に、動かされており、同じ作品を見ても人によって見た作品が異なってくるということが起きてくる。
3−4. パフォーマンスの現前性
(引用2)
引用文にある1970年代半ば以降は、ヴィデオ録画の家庭用機器が販売されてから10年程経過している。絵画であればその作品の存在は美術館の中にあると言えるが、映像はどこにあるか? という問いには、テレビという箱の中にあるとは言えない。映像が撮られた場所がどこかにあって、その場所であるということしか我々は分らない。
次の段階として、さまざまな演劇を巡る主題である、俳優の現前、プレゼンスとは何なのか、アクションとは何がどこで起きているのか、何を表象しているのか、ライヴで行われていることと、その外にあるかもしれないテキスト、言語、それを媒介するようなさまざまなメディアというようなものを誰がどう知覚しているのかという問題がある。
次の段階として、さまざまな演劇を巡る主題である、俳優の現前、プレゼンスとは何なのか、アクションとは何がどこで起きているのか、何を表象しているのか、ライヴで行われていることと、その外にあるかもしれないテキスト、言語、それを媒介するようなさまざまなメディアというようなものを誰がどう知覚しているのかという問題がある。
(引用3)
- パフォーマーの現前性批判
演劇史においてよく知られた前提であるが、俳優がそこにいることが、演劇のかけがね、それでこそライヴだということを、「それは本当か?」と疑問に付したのがポストモダンである。そのことが脱構築的思考、つまりいわゆる初期デリダの思想と関係しており、デリダというフランスの哲学者が哲学史に根源的な批判を加えたことと、俳優がそこに立っているということを無根拠にもう認められないということが関係しているという。俳優が立っているということが誰もが理解すべき絶対的な事実であるということ自体が疑われるという知覚、認識の問題がここで述べられている。 - メディアによる変形と逆流
マルチメディア演劇は、媒介性、メディエーションという問題と取り組むことでメディアによって変形させられる。ウースターグループのHOUSE/LIGHTSでは、ケイト・フォークという俳優がいて、その俳優はそこにいるが、その場にいる姿が映像で生中継される。また、編集担当者は上演中に、映像をさまざまに加工し、記録映像を介入させる。その舞台はライヴではあるが、ライヴではなく、大きな枠組みではそれ自体ライヴであるが、その場で映像の切り替えなどのコンピューターの操作等が行われる中、そこで何が起きているのかに関心が寄せられていく。パフォーマーはその中で、ある特権的な地位を舞台上に占めており、いわば意味の源泉である。つまり、パフォーマーが権威的にそこに存在しないと、我々は説得されないわけである。
ニック・ケイは通常の意味におけるパフォーマーの「場所」「権威」がもはや壊滅的な状態にあると述べている。(俳優がある役柄を演じることで持つ、無条件に存在した「場所」「権威」が失効した)しかし、このHOUSE/LIGHTSにおいて逆流し、変形したものによって、パフォーマーの「現前性」が再召還され、「場所」「権威」が再び保証されるとしている。
ケイト・フォークはファウストという役を演じており、もう一つは1965年のカルト映画『オルガの恥辱の家』のオルガという役も同時に演じている。「そこにいるのは誰ですか?」と聞いたら、私はケイト・フォークであり、オルガであり、ファウストであるという、そのような存在になっているのである。そこでやはり、ケイト・フォークという身体が呼び出されて、そこで現前性が問題化されているのではないか。やはりライヴであるということが結局のところ重要なのではないか、という意識のパラドクスが起きている。つまり、そこで起きていることが複数化、複雑化しているにも関わらず、ある種今までの演劇と結局同じことが起きてはいないか、ということが最後に問題になってくるのである。 - 演劇というメディアの輻輳性
演劇は観客へのアプローチ方法やチャンネルが複数化しているにも関わらず、輻輳しつつも収束に向うメディア、パフォーマンスである。いろいろなことがいろいろなところで同時多発的に行われていて、何を見ても聞いてもいいし、どの物語に耳を傾けてもいいという舞台があったとして、それは困難な舞台であるけれども、ある種の収束に向うということである。収束とは、さまざまな要素それ自体をある種の全体として受入れるということである。
舞台でさまざまなことが行われていても、われわれはやはり話している人を見ていることが多い。ところが、5人一度に話したらどうするのか? 最初はとまどっても、5人一度に話しているということ自体をそのものとして受入れるということが起きている。 - 日本における俳優の現前性
日本において、パフォーマーの「権威」「場所」は壊滅状態にあるのか?ハムレットの役を演じている人が「生きるべきか死ぬべきか」という場面を演じている時に「お前はハムレットではなくて野村萬斎だろう」と言ったら、「権威」「場所」は保証されない。つまり権威というのは、彼が野村萬斎だということはみんな知っているけれども、野村萬斎がハムレットを演じているという約束事を受入れることによってが生じる。そのことが、上演を可能にしているわけである。そういう伝統的な方法は壊滅的な状態になっているとケイはいうが、この認識が日本にはない。少しならあるかと思うが、つまり演劇を観たことがない人に『ハムレット』を見せ、その人が野村萬斎を見て、「NHKの日本語で遊ぼうのお兄ちゃんだ」と発言したら、これは表象のシステムが壊れているということになる。子どもであれば許されるが、大人がこのように言い、ふざけるな、と出て行ったらこれは演劇のシステムが崩壊しているということになる。俳優が登場人物を透明に表象するというシステムは、理論的には壊れているとされている。
<マルチメディアの投入>
演劇におけるマルチメディアの投入は、既存の形式を変えようという前提を持った人による、新しい可能性の模索や、もっと演劇を豊かにという発想ではなかった。マルチメディアの投入は、元来、演劇とは何かという根源的な問い、つまりライヴ性あるいは媒介性という問題や俳優の現前性との関係で行われてきた。つまり映像を入れたら舞台表現がより豊かになるとか、若い人は映像に慣れているから見栄えをよくしておこうといった、単に美学的手段だったわけではない。
しかし、近年の日本におけるマルチメディアの投入はライヴのアクションを補完すればいい方で、たいていは背景をなしているに過ぎないのではないか。
しかし、近年の日本におけるマルチメディアの投入はライヴのアクションを補完すればいい方で、たいていは背景をなしているに過ぎないのではないか。
(映像資料と解説)
4. HOUSE/LIGHTS (1992) THE WOOSTER GROUP
- THE WOOSTER GROUP
リチャード・シェクナーが率いていたパフォーマンスグループに属していた若手アーティストが1976年に活動を開始し、グループに所属しつつ、自分たちだけで活動を行う時に使用していた団体名である。80年にシェクナーが辞めたことを契機にグループ自体がウースターグループと改名し、エリザベス・ルコントが芸術監督となる。 - HOUSE/LIGHTS (1992)
この作品は、アメリカにおいて60年代前衛のロールモデル的な存在であるガートルート・スタイン(1874-1946)という作家のDoctor Faustus Lights the Lights(ファウスト博士が灯りに火をともす)(1938)という前衛的なオペラのリブレットと、『オルガの恥辱の家』(1964)というカルト映画の二つの作品をもとに制作されている。ウースターグループは難解で知られるが、この作品はNYタイムズが「難しくないから、みんな観にいこう。楽しいよ」という劇評を寄せた。「難解」は、ここでは「つまらない」と同義的に使用しているが、それだけではないということである。 この舞台は一人芝居的な様相を呈しているが、種々雑多な要素が彼女の身体イメージを構成している。彼女が座り、下のモニターに生中継される身体があるが、そうしたものを中心に極めてノイジーに舞台は展開する。ノイジーとはしまりがない、だらしないという意味ではなく、反対に舞台は精密に、かつデタラメに進んでいく。
この作品の特徴は、徹底してオリジナルのものが何もない、全部どこかの何かのイメージを借りてきているということである。ではオリジナルのものは何かというと、瞬間に生起するイメージがある種のオリジナリティと言える。劇中流れるアナウンスも50年代の映画から引用である。映画の引用場面『オルガの屈辱の家』では、映画とまったく同じ身ぶりを再現している。重要なのは、映画的な抑揚やメロドラマ的な濃さのようなものがなく、極めて内容がなくかつ文脈もなく、何もないということである。
映像が先になったり舞台が先になったり、引用される映画と舞台の進行がシンクロしないで何となく関係しているという状態で進んでいく。音響効果で三味線が鳴っていたが、こういう極めて雑多な物がある意図に基づいて配置されるというよりは、直感的なものだと思われる。このように、イメージが切断し断片化されているという中において、しかし、そこにケイト・フォークがいるのである。彼女は誰かよく分らない存在となっていく。あれは一体誰なのかという問がなかなか成立しないのである。舞台上のケイト・フォークのアイデンティティが分らない。ケイト・フォークだとは言えないだろうが、ケイト・フォークである、という構成になっている。
5.SNOW (2000), FireFall (2009) John Jesurun
- ジョン・ジェスラン(1951_)
80年代アンダーグラウンドのNYクラブシーン出身であり、イェール大学で彫刻の修士号を取得し、最初はテレビ局に勤務していた。東京大学で客員教授、京都造形芸術大学で教授をつとめ、日本とも縁がある作家である。
80年代当初は『空虚な月の中のチャン』というテレビ番組を演劇で行うという作品を上演していた。2日で台本を書いて、すぐ上演するというテレビ的な発想であり、70程作品を上演した。ヴィデオテクノロジーを多用するプロセスにおいて、ある極点に達した作品がSNOW (2000)である。 - SNOW (2000)
観客は四方を囲まれた中央の部屋に座っている。上に4つのモニターがある。客席を囲んだその周りが廊下になっており、そこで俳優が演技を行う。観客は実際の俳優を、モニターを通してのみ観ることになる。22のカメラが観客席の周囲いろいろな場所に配置されていて、そこから伝達される映像と、ライヴ映像だけではなく記録済みの映像をスイッチングで選択しながら流す。その混ぜ合わされた4つのモニター画面しか観客には見えない。
オープニングはオリエンタリズムの映像をわざと流している。物語の内容は、基本的にテレビ局のどたばた劇である。観客には、今モニターに映っている映像と後ろを走り回る足音が聞える。人の気配や、俳優がマイクに向って喋る声の、マイクからではない地声が洩れ聞えてくる。そういう、自分では見えないところで何か演劇が起っているという環境を描いている。この作品が可能となるのは、カメラが小さくなったというテクノロジーが大きく関わり、固定カメラと人の動きにつれて動くカメラを適宜配していて、極めて精密にどこのシーンでどこのカメラが何を捉えているか、その映像に何をかぶせるかが構想されている。この作品は、一般的な意味において普通のセリフ劇であり、そこでは会話があり、観客はそれが距離をおいてしか聞えない。実はそれこそが、我々のメディア環境そのものであり、テレビ局の裏側は事実我々には見えないのであり、我々は背景を気配としてだけ観ているものに感じているという作品である。 - FireFall (2009) John Jesurun (引用4)
この作品は、瞬間的に認知可能な映像、誰もがすぐ気がつくような断片を多用しており、その断片が実は関係しあい、何かのメッセージではないかということを匂わせている。みんなでウェブサイトを作成しているが、途中で外部からの介入があり、話が困惑するというような進行である。
6. SUPERVISION (2005) Continuous City (2008) The Builders Association
最後に取り上げるのが、ウースターグループに所属していたマリアンヌ・ウィームスが1994年に結成したビルダーズ・アソシエイションである。
ニック・ケイはまず、メディアを複数化する、multiplyするのがウースターグループで、メディアを使った表現一つ一つが何かの変形であり、生の表現も含め、そういうさまざまな電子機器による細工を使ってライヴではものすごくいろいろなことが同時に起きている。それが増殖する(させる)、“multipluingmedia”であると述べている。
次にジョン・ジェスランについて、輻輳化、“convergence”というタイトルで、ある種の収束をみせていると書いている。ジェスランの場合はメディアを使用しているが、言語作家、テキスト作家であるという側面がかなり強く、それを聞かせたいというのが大きい。先ほどの映像の中でもありがちな会話をしている中で、突然神話的なイメージが呼び出されて来る。ジェスランはテキストを単なるテレビ局の人たちのために使うのはではなく、やはりテキストはテキストの、言語には言語の、ないしは声には声の、あるいは生の声には生の声の、そうした言語的特性にある種の中心性を置いているのである。
そして、ビルダーズ・アソシエイションでは、物語が回帰してくる。
ニック・ケイはまず、メディアを複数化する、multiplyするのがウースターグループで、メディアを使った表現一つ一つが何かの変形であり、生の表現も含め、そういうさまざまな電子機器による細工を使ってライヴではものすごくいろいろなことが同時に起きている。それが増殖する(させる)、“multipluingmedia”であると述べている。
次にジョン・ジェスランについて、輻輳化、“convergence”というタイトルで、ある種の収束をみせていると書いている。ジェスランの場合はメディアを使用しているが、言語作家、テキスト作家であるという側面がかなり強く、それを聞かせたいというのが大きい。先ほどの映像の中でもありがちな会話をしている中で、突然神話的なイメージが呼び出されて来る。ジェスランはテキストを単なるテレビ局の人たちのために使うのはではなく、やはりテキストはテキストの、言語には言語の、ないしは声には声の、あるいは生の声には生の声の、そうした言語的特性にある種の中心性を置いているのである。
そして、ビルダーズ・アソシエイションでは、物語が回帰してくる。
- SUPERVISION (2005) (引用5)
NYタイムズは、「ストーリーそのものは実にチープで今更だ」と劇評で述べており、その通りだと思うが、ただこの作品を観れば分るように非常に凝った映像で、あれが生の人間なのか映像の影なのか、判別し難い程の上演時の空間そのものは非常に面白いものである。
ハリウッド映画の宣伝を思わせる映像は、舞台前面にオペレーターが座り、コンピューターをその場で操作しており、生の舞台においては、その映像の技術力で圧倒される作品である。 - Continuous City 『流動都市』(2008) (引用5)
SUPERVISIONより落ちついた作品で、何年かかけて行っているプロジェクトである。グローバリゼーションの中で世界を旅する家族がお互いに連絡を絶やさないようにするという、比較的直線的な物語が語られる。そこでは、ソーシャル・ネットワーキング、ヴィデオ・チャットやブログを使いながら、インターネットの経験によって家族がばらばらになりながらも電子機器でつながっているというような、ある種回帰してくる物語が展開している。 - グローバリゼーションと演劇
グローバリゼーションの現状に芸術はどのような対応が可能か。もうすぐ来日するドイツ語系スイスのリミニ・プロトコルという集団がCall Cuttaというパフォーマンスを行った。そのパフォーマンスは、観客はドイツやスイスで重役室のようなところに通される。そこで電話を使って話している相手が、実は非常に遠いところにいるというものである。コールセンターは、たとえばアメリカでパソコンが壊れて修理依頼の電話をするとアメリカにいるアメリカ人と話しているつもりが実は相手はインドにいる、というような構造を持っている。日本でも中国を経由してそういうことが起っている。それを主題にしたパフォーマンスで、コールセンターにいるカルカッタの人とずっと携帯の国際電話でしゃべるというもので、いろいろ質問され、最後は歌を歌えと指示を与えられる。この作品は、「本当の距離」の伝達であるが、グローバリゼーションをどう演劇で表現していくか、あるいはグローバリゼーションで問題になっていることに直接的間接的にどのように答えていくかは、非常に困難である。『流動都市』では、その現状を描いただけではないか。また、日本でこのビルダーズ・アソシエイションのように高い技術を持つ人は演劇の分野におらず、企業で高い給料をもらっているのではないか。
1995年のステラークのパフォーマンスで、体中に電極をつけて、カナダでコンピューターを操作し、オーストラリアにいるステラークの筋肉をぴくぴくさせるというものがあった。オーストラリアにいるステラークがカナダにいる人に身体的に操作される。インターネットが出始めた当時は、「そうだよね。つながっているんだ」という意識が顕在化することが面白かった。
現在、インターネットを基盤とした文化表現はとても多様であり、インターネット環境は我々の日常となった。そこで、演劇が今後この現状にどのように関わっていけるかという問題は、考えられてしかるべきである。

[映像資料]
HOUSE/LIGHTS (1992) THE WOOSTER GROUP
SNOW (2000) John Jesurun
FireFall (2009) John Jesurun
SUPERVISION (2005) The Builders Association
Continuous City (2008) The Builders Association
References:
Kaye,Nick. Multi-Media:Video,Installation,Performance.(London:Routledge,2007)
Blankenship,Mark.“Online, Onstage: Interfacing with the world” New York Times, Nov. 18 2008.
Genzlinger,Neil.“A Triptych of Fables About the Too-Much-Information Era”New York Times Dec.2,2005
La Rocco Claudia.“Playing with Fire Walls:The Laptops Take Center Stage.”New York Times Feb.9,2009.
HOUSE/LIGHTS (1992) THE WOOSTER GROUP
SNOW (2000) John Jesurun
FireFall (2009) John Jesurun
SUPERVISION (2005) The Builders Association
Continuous City (2008) The Builders Association
References:
Kaye,Nick. Multi-Media:Video,Installation,Performance.(London:Routledge,2007)
Blankenship,Mark.“Online, Onstage: Interfacing with the world” New York Times, Nov. 18 2008.
Genzlinger,Neil.“A Triptych of Fables About the Too-Much-Information Era”New York Times Dec.2,2005
La Rocco Claudia.“Playing with Fire Walls:The Laptops Take Center Stage.”New York Times Feb.9,2009.

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.


