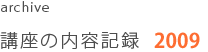


シリーズ講座『舞台芸術の現在』
Vol.2「グローバリゼーションの時代における演劇的抵抗と実践」
2009年10月2日(金) 19時〜21時
鴻 英良
(演劇批評家)
《所 感》
演劇とともに思考する。現在の日本において、この実現性はアプリオリであるのか。
この問いへの回答は、否定的であった。しかし、停滞状態にある現実に対して、かすかな抵抗は可能だと言うものだった。ソ連崩壊後加速したグローバリゼーションの時代に現れた苦境に人はいかにして立ち向かうことができるのか。本講座は、氏が演劇を考えるうえでの軸として参照する、閉塞した状態に対するブレヒト的抵抗(F・ジェイムソン)を基に、観客が演劇をみるという行為の中にある意識的能動的な参加とは何かを問うものであった。日本における実践としてモレキュラーシアター、ポルトBの上演形式を検証し、9.11以降ブッシュ政権下において格闘のうえ死に至ったS・ソンタグ(がんによる病死)への追悼として行われたM・アブラモビッチのパフォーマンス作品Thomas Lips、ベルギーの植民地であったルワンダで起った大虐殺を取り上げた9時間にわたる舞台『ルワンダ94』で国際的に物議をかもしたグルポフ(ベルギー)の今後の活動を、海外の重要な事例として提示した。
資本主義下で遂行される暴力の可視化、その具体的な演劇的抵抗と実践を解説した氏によって、演劇とともに思考することの未来への詩片が示されたのである。
演劇とともに思考する。現在の日本において、この実現性はアプリオリであるのか。
この問いへの回答は、否定的であった。しかし、停滞状態にある現実に対して、かすかな抵抗は可能だと言うものだった。ソ連崩壊後加速したグローバリゼーションの時代に現れた苦境に人はいかにして立ち向かうことができるのか。本講座は、氏が演劇を考えるうえでの軸として参照する、閉塞した状態に対するブレヒト的抵抗(F・ジェイムソン)を基に、観客が演劇をみるという行為の中にある意識的能動的な参加とは何かを問うものであった。日本における実践としてモレキュラーシアター、ポルトBの上演形式を検証し、9.11以降ブッシュ政権下において格闘のうえ死に至ったS・ソンタグ(がんによる病死)への追悼として行われたM・アブラモビッチのパフォーマンス作品Thomas Lips、ベルギーの植民地であったルワンダで起った大虐殺を取り上げた9時間にわたる舞台『ルワンダ94』で国際的に物議をかもしたグルポフ(ベルギー)の今後の活動を、海外の重要な事例として提示した。
資本主義下で遂行される暴力の可視化、その具体的な演劇的抵抗と実践を解説した氏によって、演劇とともに思考することの未来への詩片が示されたのである。
記録:塩田典子(早稲田大学大学院文学研究科芸術学(演劇映像)専攻修士課程修了)

1.はじめに
舞台芸術の現在という問題について、個別的に考えていこうとする場合、例えばフランス、アメリカなどの舞台を中心にして話すというやり方もありますが、私はむしろ、舞台芸術の展開の中でどのようなことが起っているのか、その見取り図を全体として構想しなければならないと思っているのです。そうしたことを考える時、僕は演劇批評家なので、僕にはいくつかの参照軸があります。何かが起こっているとき、それがどのような意味を持つのか、あるいは、何かを観ている時に、それがどのような意味を持っているのかを考えていこうとするとき、参照事項として何かがないと、そうしたものについて考えていくのが難しいのです。
2.演劇を考える軸
2−1. 後期アングラ小劇場とその時代
こうした問題について具体的に話していく前に、個人的なことをちょっとだけいいますと、私が演劇を見始めたのは1970年代の終わりなので、日本におけるアングラ、小劇場運動が、最後の輝きを見せていた頃でした。そのころ、演劇は現実と激しい緊張関係を持ち、演劇的な活動そのものが現実と密接に関連していました。演劇が現在と切り結んでいく瞬間について考えることが、つまり、1977、78年から82、83年にかけて、寺山修司、鈴木忠志、唐十郎たちが何を考えていたのか、そしてそれがその時代とどういう関係にあったのかというようなことを考えることが、私がいま演劇とともに何かを考えたり、構想したりするときの一つの軸になります。
2−2. カントールとマニフェスト
その後、演劇にかなり興味を持ち、海外の演出家の作品に会う機会ができ、そのようなときに僕が経験したこと、それがもう一つの軸です。1982年、利賀村の演劇祭で、日本にやってきたポーランドの演出家タデウシュ・カントール(1915?1990)の作品を観たあと、彼の書いた膨大な演劇論、彼自身の一連のマニフェスト文を読みました。彼の舞台を観つつマニフェストを翻訳していく中で、この演出家が何を考えていたのかということにコミットしていく形で私の演劇観が形成されていきました。
2−3. ジェイムソンによる『ブレヒトと方法』
最近、三つ目の新たな軸として、今日お配りした資料にあるF・ジェイムソン(1934-)というアメリカの批評家が加わりました。ジェイムソンの有名な本としては、Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism(1991)があり、そこでは資本主義生産様式の後期において、文化的戦略というのはどういう風になされているのか、ということについて書かれています。その彼が1998年『ブレヒトと方法』を書きました。私はその本がなぜこの時期に書かれたのかを考えてみました。1997、98年には、文化的諸問題に関わらず、いろいろな政治的経済的な領野で、誰もがグローバリゼーションということを語りはじめた。世界はグローバル化している。そのことによって、我々の生活はどう変わってきたのか、それだけではなくアーティストたちはどういう表現をするようになってきたのか、ということが熱心に語られるようになりました。グローバリゼーション時代の演劇がどうなっているのかという関心が、90年代の終わりくらいから出てきて、2000年くらいから、グローバリゼーションとアート、芸術、演劇というような話が盛んに議論されるようになりました。
ちょうどその頃、『ブレヒトと方法』という本が書かれたのですが、そのなかに彼がなぜブレヒト(1898?1956)を今問題にするのかを書いた一節があります。ここでのポイントは、「Brechtian doctrine of activity」、「ブレヒトの活動の原理」という言葉です。今われわれは、ブレヒトに立ち返らなければいけないとジェイムソンは言っています。なぜかというと、大学人や知識人たちがその職場で身動きの取れない状態に置かれているからだ、とジェイムソンは言っています。ジェイムソンの文章を訳しますと、「もはやどんな革命的な変化をも認めようとしない諸制度や専門化のプロセスの進行の中で、多くの人たちが身動きの取れない状態にされている。そのようなとき、ブレヒトの活動の原理を呼び起すことが極めて緊急なことであり、しかも時期にかなったことだ。今日の停滞状態はどうして起こっているのか。それは世界中のどこでもが、金融投機と消費市場主義といういわばデュアルな、双対的な条件の中で、我々は身動きの取れない状態にされているからだ。つまりいまや我々は、身動きが取れない。人間の活動というのは時代遅れのものとされており、我々はもはや、何もしない状態の中で生きるように要請されている。こういう状態の中でこそブレヒトが活動という風に言ったことを改めて我々は思い起こして、ブレヒト的な意味での活動の中へと入っていくべきだ」、という風に言っています。
じゃあ、活動とは何か?ブレヒト的な演劇における活動と言われているものは、どういうものなのか?一つは人間の能動的な活動の場として劇場、演劇的な活動を想定しなおすことです。どのような意味で、能動的で意識的な活動の場としての劇場なり演劇的活動があるのか、という風に考えた時に、参加型という言葉がありますが、問題はどのように参加するのか。その参加が、極めて意識的能動的になるような、そういう場所を組織することが必要なのではないか、ということが書かれていています。実際この本の中で、いくつかの劇場における観客の参加の形式について書かれていますが、残念ながら、それはあまり魅力的なものではありません。じゃあ、どうすればいいのか、それを今日は少しずつ話そうと思っています。
ちょうどその頃、『ブレヒトと方法』という本が書かれたのですが、そのなかに彼がなぜブレヒト(1898?1956)を今問題にするのかを書いた一節があります。ここでのポイントは、「Brechtian doctrine of activity」、「ブレヒトの活動の原理」という言葉です。今われわれは、ブレヒトに立ち返らなければいけないとジェイムソンは言っています。なぜかというと、大学人や知識人たちがその職場で身動きの取れない状態に置かれているからだ、とジェイムソンは言っています。ジェイムソンの文章を訳しますと、「もはやどんな革命的な変化をも認めようとしない諸制度や専門化のプロセスの進行の中で、多くの人たちが身動きの取れない状態にされている。そのようなとき、ブレヒトの活動の原理を呼び起すことが極めて緊急なことであり、しかも時期にかなったことだ。今日の停滞状態はどうして起こっているのか。それは世界中のどこでもが、金融投機と消費市場主義といういわばデュアルな、双対的な条件の中で、我々は身動きの取れない状態にされているからだ。つまりいまや我々は、身動きが取れない。人間の活動というのは時代遅れのものとされており、我々はもはや、何もしない状態の中で生きるように要請されている。こういう状態の中でこそブレヒトが活動という風に言ったことを改めて我々は思い起こして、ブレヒト的な意味での活動の中へと入っていくべきだ」、という風に言っています。
じゃあ、活動とは何か?ブレヒト的な演劇における活動と言われているものは、どういうものなのか?一つは人間の能動的な活動の場として劇場、演劇的な活動を想定しなおすことです。どのような意味で、能動的で意識的な活動の場としての劇場なり演劇的活動があるのか、という風に考えた時に、参加型という言葉がありますが、問題はどのように参加するのか。その参加が、極めて意識的能動的になるような、そういう場所を組織することが必要なのではないか、ということが書かれていています。実際この本の中で、いくつかの劇場における観客の参加の形式について書かれていますが、残念ながら、それはあまり魅力的なものではありません。じゃあ、どうすればいいのか、それを今日は少しずつ話そうと思っています。
3.観客の意識的、能動的な参加とは?
実際のグローバル化における停滞状態の中で、たとえばジェイムソンが構想すべきだと提唱している活動とは、<演劇を観る>という行為の中にある、意識的能動的な参加という活動の形式です。そのことをかなり具体的な形で実践している劇団を僕なりに考えると「モレキュラーシアター」「ポルトB」「劇団解体社」の3つぐらいです。ここで問題なのは、停滞状態におけるグローバル化した社会における現実に対する抵抗というものの姿勢を、どのような形で演劇的な活動の中にとり込むことができるかということです。そして、参加と言うならば、観客がそこで思考し、作品を作っていくような劇の形式が必要とされるはずです。
3−1.『ディクテ・フォーラム』(2008.12/26-28) ポルトBのツアーパフォーマンス
昨年(2008)の12月末に3泊4日で、『ディクテ・フォーラム』という作品が横浜で行われました[このプロジェクトの詳細なドキュメントは、コロノス芸術叢書『アートポリティクス』(論創社)に掲載されている]。横浜という街で何が起こっているのか、そこはどういう街か、抱えている問題はどういうものか?それは横浜に必ずしも住んでいない者が、横浜を媒介にしつつ、都市の問題について考えるという作品でした。具体的にはどのような作品なのかというと、30人くらいの人が集まって、フォーラムを開きます。例えば二人がゲストとして、現代美術でいま何が起こっているか議論する。ゲストが話した後、ディスカッションの時間に、聞いていた人たちも議論に参加していく。そして、そのあと別の場所にみんなで移動しますが、その移動の間も、参加者たちは話しているんですね。そうして、たとえば寿町というところに着くと、寿町という寄せ場や木賃宿で暮らしている人たちから日本の労働条件についていろいろな話を聞くことになる。そして、その後で、黄金町に移動するといった具合です。そして黄金町に着いたら黄金町の町会委員会の人と高山明というポルトBの演出家が話をする。その話を参加者たちがどういう風に考えていくかということが問題になるのです。ここはかつての有名ないわゆるセックスゾーンですから、当然、セックスゾーンが横浜のある一角に存在している意味について議論することになる。そのような議論がゲストだけでなく参加している全員によって展開されていく。このように今ここで何が起こっているのかという問題を全員が考えていくことになるのです。
ここでは、観客席の変貌ということが、一つの方法として試みられているのですね。都市のさまざまな場所、横浜の象徴的な場所を観客が移動しながら、それぞれの場所で、それぞれ違ったテーマについて議論する。移動しながらも議論をつづける。その意味で、一つの舞台を一つの観客席に座ってじっと観ているという形式とは違う形の観客のあり方が、ここでは構想されていると言えます。この形態の演劇では、劇団や演劇は、観客が考えるための、観客が移動しながら街というものを考察するということを組織するためのモデレーターとして存在することになります。モデレーターたちも考えていますが、しかしはるかに多く観客は思考しなければなりません。その観客の思考の自由度にこの作品の本質は関係しています。このような形式を生みだす努力をつづけなければ、停滞状態にあるこのグローバリゼーションの中で作品形成ができなくなりつつあるのです。こうした試みは、『ディクテ・フォーラム』だけでなく、以前の作品『サンシャイン62』(2008)でも行われました。観客がサンシャイン60の周辺を歩き、さまざまな仕掛けが施されている場所で多くの対話を交わすのです。観客の思考を促すための仕掛けを作り出していくというこの演劇の方法は、グローバル化に対する、停滞状態に対する打開策として、新たな展開を見せています。
ここでは、観客席の変貌ということが、一つの方法として試みられているのですね。都市のさまざまな場所、横浜の象徴的な場所を観客が移動しながら、それぞれの場所で、それぞれ違ったテーマについて議論する。移動しながらも議論をつづける。その意味で、一つの舞台を一つの観客席に座ってじっと観ているという形式とは違う形の観客のあり方が、ここでは構想されていると言えます。この形態の演劇では、劇団や演劇は、観客が考えるための、観客が移動しながら街というものを考察するということを組織するためのモデレーターとして存在することになります。モデレーターたちも考えていますが、しかしはるかに多く観客は思考しなければなりません。その観客の思考の自由度にこの作品の本質は関係しています。このような形式を生みだす努力をつづけなければ、停滞状態にあるこのグローバリゼーションの中で作品形成ができなくなりつつあるのです。こうした試みは、『ディクテ・フォーラム』だけでなく、以前の作品『サンシャイン62』(2008)でも行われました。観客がサンシャイン60の周辺を歩き、さまざまな仕掛けが施されている場所で多くの対話を交わすのです。観客の思考を促すための仕掛けを作り出していくというこの演劇の方法は、グローバル化に対する、停滞状態に対する打開策として、新たな展開を見せています。
3−2.『バレエ・ビオメハニカ』(2007) モレキュラーシアター
そういう意味で、モレキュラーシアターの『バレエ・ビオメハニカ』(青森県立美術館初演)も、観客の思考を活性化させるための方法を考えだしたもう一つのやり方でした。
舞台は100〜200席くらいの広くない空間です。そこに座っていると、後方のスピーカーから、声が聞えてくる。すると客席近くから誰かが一人立ち上がり、白い壁の方に進んでいく。これがパフォーマーなのですね。別の人がプロジェクターの光でこの立ち上がったパフォーマーを照らし出すと、壁には白い四角形の光の影が映ります。またもうひとり別の人がもう一つのプロジェクターの光で同じようにそのパフォーマーを照らし出します。するともう一つの四角形の光が壁に照射される。つまり、我々と同じ言葉を聞いていた人が立ち上がり、動き出す。白い壁に白い光が当てられ、その二つの白い光はほぼ同じ大きさで、その白い光が重なりあうように壁に二重に照射されているのです。このような光に照らされながら、壁とプロジェクターのあいだの狭い空間で、先ほどから聞えていた声を聞きながら、パフォーマーは、その声に突き動かされるように動いているというわけです。
この白い四角形の上の白い四角形というのは、ある芸術作品を思い起させますね。それはロシア・アヴァンギャルドの時代のマレーヴィチの『白い四角形の上の白い四角形』という作品です。これは、存在が消去された時になおかつ、無限という概念が立ち現れることがあるというコンセプトで作られた抽象絵画の極地のようなものといわれる作品です。ようするに、白いキャンバスの上に白い四角形が書かれていて、その上に重なる形でもう一つの白い四角形が書かれているということは、対象性の欠如、要するに何もない空間です。これは、いずれあらゆるものが消え去りあらゆる意味が無くなっていくであろう、つまりスターリン時代における粛正の嵐の中で起こるような出来事を暗示しているとも言われているわけです。
この光で作られた、白い四角形の内の白い四角形に照らし出されて踊っている人たちはまるで収容所のサーチライトに照らされた人間のようにそこにいる。つまりこの人は、あたかも収容所の中でサーチライトに照らし出されたかのように、いわば完全な無化の空間の中で踊っている。それを観ながら、われわれ観客はこの声を一生懸命聞きとろうとしている。するとその声とは何かがだんだん分かってくる。このことが重要です。われわれ観客は、この状態の中で聞えてくるこの声が何を言っているのかを必死になって捉えようとしている、非常な努力を払いながら、聞き取ろうとするのです。やがて、その声が、苦境にたったある人間の弁明の言葉であるということが分かってきます。それは、行き場を完全になくした人間がそこからなんとか回復する、脱出する手だてを考えて、つまり言語的弁解ができないだろうか、という風に考えつつ喋っている言葉なのです。
実は、これは、1939年、ソヴィエト共産党の指令により呼び出され、自らの芸術的立場を謝罪するよう要求された、しかし最終的には、それを拒否した人間の言葉なのです。『バレエ・ビオメハニカ』というタイトルからも想像できますが、1940年2月2日、国家反逆罪のかどで銃殺された演出家のメイエルホリドの言葉だったのです。20世紀でもっとも重要な演出家のひとり、メイエルホリドが、公開の場で最後に喋った言葉、死の直前の最後の弁明の言葉が、我々の背後から聞えてくる。その声を聞きながら、サーチライトに照らされたダンサーを観る。観客は座ったままで徐々に声の本質を理解するようになっていく、我々の耳が鋭敏に研ぎ澄まされ、語られていることの本質を聞き取ろうとする、ここでは、劇場の空間が、そういうことが起る場所として構想されている。つまり、この舞台は、先ほどから問題にしてきた停滞からの脱出、グローバリゼーションへの抵抗という形式としての演劇を、極めてシンプルな構造の下に創り出している。『バレエ・ビオメハニカ』も、そういう試みが日本の現代演劇の中にも出てきていることをわれわれに告げているのです。
いろいろな舞台がありますが、グローバリゼーションの中で新しい形態の演劇をどういう風に構想するかという思考がそこで立ち上がっているかどうかということが、極めて重要なのです。しかし、メイエルホリドが公開の場で最後に弁明している、その状況を再現する舞台が、なぜ今重要なのか。それは、まさに、メイエルホリドが置かれている苦境というのが、ジェイムソンが置かれていると彼自身感じていたアメリカの左翼的知識人の苦境とつながりがあるからです。
舞台は100〜200席くらいの広くない空間です。そこに座っていると、後方のスピーカーから、声が聞えてくる。すると客席近くから誰かが一人立ち上がり、白い壁の方に進んでいく。これがパフォーマーなのですね。別の人がプロジェクターの光でこの立ち上がったパフォーマーを照らし出すと、壁には白い四角形の光の影が映ります。またもうひとり別の人がもう一つのプロジェクターの光で同じようにそのパフォーマーを照らし出します。するともう一つの四角形の光が壁に照射される。つまり、我々と同じ言葉を聞いていた人が立ち上がり、動き出す。白い壁に白い光が当てられ、その二つの白い光はほぼ同じ大きさで、その白い光が重なりあうように壁に二重に照射されているのです。このような光に照らされながら、壁とプロジェクターのあいだの狭い空間で、先ほどから聞えていた声を聞きながら、パフォーマーは、その声に突き動かされるように動いているというわけです。
この白い四角形の上の白い四角形というのは、ある芸術作品を思い起させますね。それはロシア・アヴァンギャルドの時代のマレーヴィチの『白い四角形の上の白い四角形』という作品です。これは、存在が消去された時になおかつ、無限という概念が立ち現れることがあるというコンセプトで作られた抽象絵画の極地のようなものといわれる作品です。ようするに、白いキャンバスの上に白い四角形が書かれていて、その上に重なる形でもう一つの白い四角形が書かれているということは、対象性の欠如、要するに何もない空間です。これは、いずれあらゆるものが消え去りあらゆる意味が無くなっていくであろう、つまりスターリン時代における粛正の嵐の中で起こるような出来事を暗示しているとも言われているわけです。
この光で作られた、白い四角形の内の白い四角形に照らし出されて踊っている人たちはまるで収容所のサーチライトに照らされた人間のようにそこにいる。つまりこの人は、あたかも収容所の中でサーチライトに照らし出されたかのように、いわば完全な無化の空間の中で踊っている。それを観ながら、われわれ観客はこの声を一生懸命聞きとろうとしている。するとその声とは何かがだんだん分かってくる。このことが重要です。われわれ観客は、この状態の中で聞えてくるこの声が何を言っているのかを必死になって捉えようとしている、非常な努力を払いながら、聞き取ろうとするのです。やがて、その声が、苦境にたったある人間の弁明の言葉であるということが分かってきます。それは、行き場を完全になくした人間がそこからなんとか回復する、脱出する手だてを考えて、つまり言語的弁解ができないだろうか、という風に考えつつ喋っている言葉なのです。
実は、これは、1939年、ソヴィエト共産党の指令により呼び出され、自らの芸術的立場を謝罪するよう要求された、しかし最終的には、それを拒否した人間の言葉なのです。『バレエ・ビオメハニカ』というタイトルからも想像できますが、1940年2月2日、国家反逆罪のかどで銃殺された演出家のメイエルホリドの言葉だったのです。20世紀でもっとも重要な演出家のひとり、メイエルホリドが、公開の場で最後に喋った言葉、死の直前の最後の弁明の言葉が、我々の背後から聞えてくる。その声を聞きながら、サーチライトに照らされたダンサーを観る。観客は座ったままで徐々に声の本質を理解するようになっていく、我々の耳が鋭敏に研ぎ澄まされ、語られていることの本質を聞き取ろうとする、ここでは、劇場の空間が、そういうことが起る場所として構想されている。つまり、この舞台は、先ほどから問題にしてきた停滞からの脱出、グローバリゼーションへの抵抗という形式としての演劇を、極めてシンプルな構造の下に創り出している。『バレエ・ビオメハニカ』も、そういう試みが日本の現代演劇の中にも出てきていることをわれわれに告げているのです。
いろいろな舞台がありますが、グローバリゼーションの中で新しい形態の演劇をどういう風に構想するかという思考がそこで立ち上がっているかどうかということが、極めて重要なのです。しかし、メイエルホリドが公開の場で最後に弁明している、その状況を再現する舞台が、なぜ今重要なのか。それは、まさに、メイエルホリドが置かれている苦境というのが、ジェイムソンが置かれていると彼自身感じていたアメリカの左翼的知識人の苦境とつながりがあるからです。
3−3. Thomas Lips (2005、初演1975) M・アブラモヴィッチ
2005年、M・アブラモヴィッチ(1946?)という人が、NYのグッゲンハイム美術館で、七日間に渡る連続パフォーマンス上演を行いました。これは、おそらく2000年代にNYで行われた最も重要な舞台芸術の一つであるだろうと思います。アブラモヴィッチは非常に有名なパフォーマンス・アーティストですが、日本にも何度か来ています。記念碑的な作品にThomas Lipsという1975年初演の作品があります(2005年グッゲンハイムにおいてはThe Lips of Thomasというタイトルで上演された)。この作品はアブラモヴィッチが出てきて、テーブルの上のワインと蜂蜜を交互に食べたり、飲んだりして始まるんですが、食べ終った後に彼女は立ち上がって裸になる。そして裸になった後に、自分のお腹をカミソリで切っていく。見ていてちょっとつらくなり、眼を背けたくなるようなシーンです。彼女はそのにじんだ血を白い布で拭き取り、兵士の帽子をかぶり、小さな棒にその白い布をゆわいつける。それから、それを旗のようにして持ち、静かに、少しだけある歌を歌うのです。それは「地上に住む祝福されているはずの我々を、神よ、救いたまえ」という歌詞でした。その後、旗をおいて氷で作られた巨大な十字架の上に横たわる。しばらくすると、その十字架から降りて来て、さきほどとはまた違う別の線をお腹の上にカミソリで引いていく。出てくる血をまた白い布で拭き取り、また歌を歌い、氷に横たわる。これはかなり過酷なものですね。氷の上に裸で横たわるので、体はだんだん苦しくなってくる。そして、それを何度も繰り返していく、こうしてその傷は星形を形成していく。
僕は映像で観ただけですが、映像だけでもかなり苦痛に感じるパフォーマンスです。しかし、問題は、この作品を、身体的にあまりに過酷なものなので何度も上演できないこの作品を、2005年に彼女が再び遂行しようと決意したのはなぜかということです。ここには非常に重要な問題が含まれている。それは、S・ソンタグ(1933?2004)が死んだことと関係があるからです。このパフォーマンスの遂行はソンタグの死に捧げられていたのです。なぜ彼女は、この作品を、S・ソンタグに捧げる形で再演したのか? これは非常に大きな問題ですが、このパフォーマンスは肉体的に自分の体を傷つけているし、観る側も非常に苦痛を伴うけれども、なぜこのようなことをやらなければいけないのか。それは2001年9.11以降のアメリカのいわば軍事的なさまざまな攻撃、アメリカ国内におけるブッシュ的な考え方の跳梁に対して批判的であったS・ソンタグは極めて厳しい状態に陥り、そしてがんで死んでいったということとつながりがある。苦境に陥っていた、極めて良識的なアメリカの知識人が、そのような形で死んでいったということに対して、それに対する追悼として何ができるかを考えた時に、アブラモヴィッチは再びこのパフォーマンスを取り上げることにしたのです。
そもそもこのパフォーマンスは、苦境に陥った人たちといわば同志的な関係を結ぼうとして作られた作品だったのではないか。75年になぜこの上演が行われたのか。アブラモヴィッチはユーゴスラビア(今のセルビア)の生れで、彼女の父親はチトー政権の共産党の幹部だったのですが、彼女が興味を持ったのは、ユーゴスラビアが独立していく過程の中でのナチス・ドイツに対するレジスタンスだったのです。これは、そのレジスタンスで殺されていった多くの人たちに対する、いわば弔いとしてのパフォーマンスだったのです。何らかの形での抵抗としての芸術を考えている多くのアーティストたちがいて、自分の肉体を実際に痛めつける決意をさせるものがそこにはある、それはジェイムソンが90年代の苦境に陥っている自分たちに対する意志と共通する何かで、その何かとのつながりのなかでアブラモヴィッチは上演しているわけです。そういう共通認識を持った芸術家たちが、こういう活動をしているのです。
僕は映像で観ただけですが、映像だけでもかなり苦痛に感じるパフォーマンスです。しかし、問題は、この作品を、身体的にあまりに過酷なものなので何度も上演できないこの作品を、2005年に彼女が再び遂行しようと決意したのはなぜかということです。ここには非常に重要な問題が含まれている。それは、S・ソンタグ(1933?2004)が死んだことと関係があるからです。このパフォーマンスの遂行はソンタグの死に捧げられていたのです。なぜ彼女は、この作品を、S・ソンタグに捧げる形で再演したのか? これは非常に大きな問題ですが、このパフォーマンスは肉体的に自分の体を傷つけているし、観る側も非常に苦痛を伴うけれども、なぜこのようなことをやらなければいけないのか。それは2001年9.11以降のアメリカのいわば軍事的なさまざまな攻撃、アメリカ国内におけるブッシュ的な考え方の跳梁に対して批判的であったS・ソンタグは極めて厳しい状態に陥り、そしてがんで死んでいったということとつながりがある。苦境に陥っていた、極めて良識的なアメリカの知識人が、そのような形で死んでいったということに対して、それに対する追悼として何ができるかを考えた時に、アブラモヴィッチは再びこのパフォーマンスを取り上げることにしたのです。
そもそもこのパフォーマンスは、苦境に陥った人たちといわば同志的な関係を結ぼうとして作られた作品だったのではないか。75年になぜこの上演が行われたのか。アブラモヴィッチはユーゴスラビア(今のセルビア)の生れで、彼女の父親はチトー政権の共産党の幹部だったのですが、彼女が興味を持ったのは、ユーゴスラビアが独立していく過程の中でのナチス・ドイツに対するレジスタンスだったのです。これは、そのレジスタンスで殺されていった多くの人たちに対する、いわば弔いとしてのパフォーマンスだったのです。何らかの形での抵抗としての芸術を考えている多くのアーティストたちがいて、自分の肉体を実際に痛めつける決意をさせるものがそこにはある、それはジェイムソンが90年代の苦境に陥っている自分たちに対する意志と共通する何かで、その何かとのつながりのなかでアブラモヴィッチは上演しているわけです。そういう共通認識を持った芸術家たちが、こういう活動をしているのです。
3−4. Thomas Lips (2005、初演1975) M・アブラモヴィッチ
そもそも演劇という言葉は、シアターとヨーロッパ圏では言われていますけれども、シアターという言葉が生みだされたのはギリシアにおいてでしたね。古代ギリシアの劇場のさまざまな箇所の名称は、コロスが舞うところはオルケストラであり、恐らく俳優が着替えなどをしていた場所であろうとされている場所はスケーネーと言いますが、これが今の舞台、シーンです。オルケストラとスケーネーの間でヒーローたちアンティゴネー、クレオーンたちが演技をしていたのではないかと言われています。で、観客が座っている場所がテアートロン、つまりこれが我々が演劇と言っているシアターの語源なんですね。つまり、観客が重要なのです。舞台で起っていることを、観客が観て、それについて思考し、判断する、これがある種の喜びとともに行われているのが演劇という活動です。テアートロン、つまり観客席で何が起っているのか、何が起るべきなのか、それが舞台で起っていることとの関係の中で、構想されなければいけない。ですので、先ほどのアブラモヴィッチのパフォーマンスについての説明においても、彼女が何を意図してそれをやっているのかということが段々わかってくる。それを誰が分るのか、もちろん観客です。観客が彼女の行為というものをどう分析し解釈していくのか。ここが重要になってきます。アブラモヴィッチの活動が、S・ソンタグに捧げると彼女が銘打っているという、そこから我々は考えていかなければいけない。それが、テアートロンが観客席であるという意味だと思います。
そのような形で演劇活動を進めている人たちがいて、昨日僕は劇団解体社の作品を観てきました。この文脈で作品を作っている人たちの舞台をぜひ観られると良いと思います。今の現実をどう思考しているのか、観客である私たちも同時に思考するということですので、ぜひ行かれるといいと思います。
そのような形で演劇活動を進めている人たちがいて、昨日僕は劇団解体社の作品を観てきました。この文脈で作品を作っている人たちの舞台をぜひ観られると良いと思います。今の現実をどう思考しているのか、観客である私たちも同時に思考するということですので、ぜひ行かれるといいと思います。
4.グルポフ(ベルギー)の実践
もう一つご紹介したいのが、ベルギーのグルポフ(Le Groupov)という集団です。代表が、ジャック・デルキュヴェルリーという人ですが、来年(2010年)、日本に来るはずです。ワークショップをやりますので、私の話を聞いて興味を持たれた方は参加されるといいと思います。この人は『ルワンダ94』を作ることで国際的に物議をかもした演出家ですが、65歳くらいの人です。どのような演劇観を持っている人かというと、1970年代は、放送局で美術関係の映像作品、アブラモヴィッチの映像で1時間の番組を製作したりしていました。そして組合活動をあまり激しく行ったために、ラジオ局を放り出されしばらく行き場を無くしていたそうですが、やがてリエージュのコンセルヴァトワールで、教えることができるようになりました。そこで、学生たちとグルポフという集団を結成します。リエージュのコンセルヴァトワールの中心的なメンバーは、ブレヒト的な作品、ブレヒト的な理念によって作品を作っていくような人たちだったそうです。
4−1. 歴史と芸術
1980年代に日本でも流行りましたが、フランシス・フクヤマ(1952?)のいう「歴史の終焉」ということが言われた時に、これに同調していた人たちはたくさんいるわけですが、ジャック・デルキュヴェルリーはそんなことはない、世界は歴史に満ちあふれていると考えていました。いわゆる歴史の終焉一派、ソヴィエトが崩壊して世界は一極化して、グローバル化の中で世界は同じであるという、多層性復層性の終わり、歴史は終焉したという、この考え方は時おり世界のいろいろな箇所で出てくる考え方です。資本主義社会の中でこの考えが出てくる前に、実は極めて完全な形で世界の終焉の物語が流通していた場所があります。それがソヴィエト連邦です。ソヴィエト連邦は社会主義国家ですから、理想的なユートピアがソヴィエトに出現したということを公式的に表明していました。ソヴィエトでは、「至る所で、すべてがすばらしい」と言われていたのです。そうするとそれ以上改良する必要がありませんから、世界は停滞するわけです。そしてすばらしい世界をどのようにすばらしく描くかだけが芸術家に要求されていました。ソヴィエトの現実をすばらしいユートピアとして描くこと、これが社会主義リアリズムなわけです。ですから、社会主義リアリズムというのは、社会主義的でもないし、リアリズム的でもない。それに対して本来のソヴィエトの問題を考察しながら、何か新しい人間の可能性、社会の可能性を追求する一つの活動として演劇を考えていたメイエルホリドは、「ソヴィエトは必ずしも美しくないし、必ずしもユートピア的ではない」という形で作品を作ったために虐殺されてしまったわけです。この事態と今のグローバリゼーションの状況というのは、むしろ非常によく似ているという風に考えられます。その状況に対して抵抗することによって苦境に立たされている偉大なアーティストたち、あるいは研究者の中にジェイムソン、アブラモヴィッチ、ソンダグがいるわけです。ジャック・デルキュヴェルリーも、そのような潮流のなかにいるのです。つまり歴史の終焉グループが生みだしているユートピア的幻想に抵抗するために何をしなければならないかと彼が考えたかというと、1989年以降、ある種のレパートリーに帰っていこうということでした。それは、ドイツ語でいうところのヴェルタンシャウウング、「世界の概念」を持っている、天才的で力のある作家、何らかのヴィジョンを作ろうとする作家の作 品をレパートリーにして、それと格闘して作品をつくっていこうとすることでした。その時に彼が選んだ作品がまたブレヒトだったのです。つまりブレヒトと格闘することによって、このグローバル化した社会の閉塞状態をぶち壊そうとしていこうという、そういう動きがいろんなところで存在しているのです。ポルトBの人たちもドイツ文化と多くの接点があり、彼らもブレヒト的な演劇に大きく影響されています。そういう意味で、ブレヒトと格闘するということをやりつつ演劇活動を続けてきた人たちが新しい作品を作ろうとしていると言うことができるのです。
4−2.『同志ホモサピエンスよさらば』(グルポフが取り組んでいる新作)
グルポフが作ろうとしている新しい作品のタイトルは、Fare Thee Well,Tovaritch Homo Sapiensというものです。ホモサピエンスというのは人類種、タバーリッシュはロシア語で同志という意味ですね。革命運動の時、同志〜〜、タヴァーリシュチ・トロツキーのように使ったんですね、要するに共産主義者たちが仲間を同志と呼びあいました。そのような形で同志ホモサピエンス、さらば、と言っているわけです。タイトルからして不思議な感じですが、この作品を彼らは3、4年くらい前2005年くらいから作ろうとしてきた。『ルワンダ94』が立ち上がって来たのが、1997年で、2000年くらいから、ワーク・イン・プログレスとして、この作品は上演されはじめています。そして2004年にその作品を持ってグルポフはルワンダに行っています[このときの様子は、ドキュメンタリー映画『ルワンダーーわれわれを通して人間が…』(マリー=フランス・コラール監督)で見れる]。その後いくつか作品を作っていますが、いまはこの作品に取りかかっています。どのような作品に最終的になるのか分らないのですが、この作品は4部構成になっていて、第1部を来年(2010)の3月に上演するにあたって、これまでのところを整理しようということで、ベルギーのブリュッセルでワークショップが開かれました。ブリュッセルのナショナルシアター、フランス語系の劇場でかなり大きな空間を使ってそこに3週間寝泊まりしてワークショップが展開しました。二段ベッドを12個並べて、12人が共同生活をしていました。二段ベッドというのは、上で寝て下にはテーブルや椅子があってそこで本を読んだり、ワークショップの準備をしている。ナショナルシアターですので、かなり大きい施設で他の階にレストランやロビーがあってそこで自炊をしながら作品を作っていました。僕はその最後の2日間、このプロジェクトに参加しました。それは徹夜のワークショップでしたが、お昼頃始まって、翌日の朝まで一睡もせずという大変なものでした。ゲストが10人程いて、演劇批評家とか、第2部の演出家、第3部の演出家、第4部の演出家とかが来ていて、そういう人たちと話しながら僕は見ていたんですね。見ながら何を感じたかというと、これが『ルワンダ94』の続き、続編ではないのかということでした。
何を彼らがやろうとしているかというと、『ルワンダ94』ではルワンダに行って調査して作品を作っていました。94年の虐殺で何が実際に起っていたのか、どうしてそうしたことが起ったのかを調べはじめて、あの事件の前後を少し調べたぐらいでは本当のところは分らないということが分ってきた。つまり、100年にも及ぶルワンダにおける植民地統治の形態の中で、あの事件が起きたことに気づくようになるのです。ルワンダは事実上は当時ベルギーの植民地でしたが、初めは、1890年以来、ドイツの植民地でした。ドイツが第一次世界大戦で敗北し、植民地を手放さざるをえなくなった時に、イギリスとの闘争の据えに、最終的にベルギーがこの土地を手に入れます。なぜ手に入れようとしたのかというと、ルワンダはベルギー領コンゴに隣接していたからです。ルワンダは鉱山資源に恵まれていませんが、コンゴには鉄鉱石、ダイヤ、金などいろいろな鉱山資源がある。そこに隣接するルワンダを軍事的要所として活用したかったのです。そのためにルワンダを手に入れた。そして、それを支配するにあたって、フトゥとツチという民族的アイデンティティーを鼓舞して、それらを争わせる植民地政策を、ベルギーはずっと取ってきたわけです。憎悪を煽るような政策を取ることによってルワンダを統治していこうというドイツ、ベルギーの、つまりヨーロッパの植民地政策の中から、あの虐殺へ向けて展開していく何かが起こっていたのです。ああした衝突は94年にだけあったわけではありません。過去の多くの紛争を調べていく中で、ルワンダの虐殺とヨーロッパの責任ということが非常に大きな関連があることが分かってきました。そしてベルギーの劇団であるグルポフにとってみれば、それは自分たちの問題でもあった。そしてルワンダの人たちと協力しあいながら、ルワンダの人たちに証言を求め、実際に舞台に出てもらったりした。また、いろいろなことをルワンダの人たちに語ってもらい、そのような形で作品化していったのが『ルワンダ94』です。この作品では、舞台はあくまでルワンダでした。でも、そのようなことが起る植民政策を展開していったベルギーもしくはヨーロッパの文化の問題性は何なのでしょうか?
ここで、ホモサピエンスというのはヨーロッパ人ということなのだと思います。つまり、ヨーロッパ人の意識の中でホモサピエンスというのはヨーロッパ人のことなのです。ドルシー・ルガンバという『ルワンダ94』に登場するルワンダ人で、作品の制作にもテキスト執筆と言う形で関わった人ですが、彼がBloody Niggers!という作品を『ルワンダ94』の後に書きました。日本語に訳せば「血まみれネグロめ!」という感じですかね。要するにヨーロッパ、ホモサピエンスが「ブラッディニガーめ!」という風に言って差別していた色々な人たちのことが問題化されているのです。カニングハム・グラハム(1852?1936)というイギリスの作家がいるらしいんですが、トルコにおけるアルメニア人虐殺が起った当時イスラムに対する批判がイギリスで巻き起こりました。その同じ頃にイギリス人はタスマニア人を虐殺していた。ところが、その事実に対して誰も語らない。そのような時に、カニングハムは自分たちの虐殺については問題にしなくてもいいのかというようなエッセイを書いた。これがかなりのスキャンダルになったのです。そのカニングハム・グラハムが「Bloody Niggers」という言葉を使ったらしいです。ドルシー・ルガンバは、その言葉を使いながら世界各地で起きた虐殺の物語を舞台に次々にあげていくという作品を作った。その流れにそってFare Thee Well,Tovaritch Homo Sapiensという作品をグルポフの人たちは作ろうとしているんですね。
何を彼らがやろうとしているかというと、『ルワンダ94』ではルワンダに行って調査して作品を作っていました。94年の虐殺で何が実際に起っていたのか、どうしてそうしたことが起ったのかを調べはじめて、あの事件の前後を少し調べたぐらいでは本当のところは分らないということが分ってきた。つまり、100年にも及ぶルワンダにおける植民地統治の形態の中で、あの事件が起きたことに気づくようになるのです。ルワンダは事実上は当時ベルギーの植民地でしたが、初めは、1890年以来、ドイツの植民地でした。ドイツが第一次世界大戦で敗北し、植民地を手放さざるをえなくなった時に、イギリスとの闘争の据えに、最終的にベルギーがこの土地を手に入れます。なぜ手に入れようとしたのかというと、ルワンダはベルギー領コンゴに隣接していたからです。ルワンダは鉱山資源に恵まれていませんが、コンゴには鉄鉱石、ダイヤ、金などいろいろな鉱山資源がある。そこに隣接するルワンダを軍事的要所として活用したかったのです。そのためにルワンダを手に入れた。そして、それを支配するにあたって、フトゥとツチという民族的アイデンティティーを鼓舞して、それらを争わせる植民地政策を、ベルギーはずっと取ってきたわけです。憎悪を煽るような政策を取ることによってルワンダを統治していこうというドイツ、ベルギーの、つまりヨーロッパの植民地政策の中から、あの虐殺へ向けて展開していく何かが起こっていたのです。ああした衝突は94年にだけあったわけではありません。過去の多くの紛争を調べていく中で、ルワンダの虐殺とヨーロッパの責任ということが非常に大きな関連があることが分かってきました。そしてベルギーの劇団であるグルポフにとってみれば、それは自分たちの問題でもあった。そしてルワンダの人たちと協力しあいながら、ルワンダの人たちに証言を求め、実際に舞台に出てもらったりした。また、いろいろなことをルワンダの人たちに語ってもらい、そのような形で作品化していったのが『ルワンダ94』です。この作品では、舞台はあくまでルワンダでした。でも、そのようなことが起る植民政策を展開していったベルギーもしくはヨーロッパの文化の問題性は何なのでしょうか?
ここで、ホモサピエンスというのはヨーロッパ人ということなのだと思います。つまり、ヨーロッパ人の意識の中でホモサピエンスというのはヨーロッパ人のことなのです。ドルシー・ルガンバという『ルワンダ94』に登場するルワンダ人で、作品の制作にもテキスト執筆と言う形で関わった人ですが、彼がBloody Niggers!という作品を『ルワンダ94』の後に書きました。日本語に訳せば「血まみれネグロめ!」という感じですかね。要するにヨーロッパ、ホモサピエンスが「ブラッディニガーめ!」という風に言って差別していた色々な人たちのことが問題化されているのです。カニングハム・グラハム(1852?1936)というイギリスの作家がいるらしいんですが、トルコにおけるアルメニア人虐殺が起った当時イスラムに対する批判がイギリスで巻き起こりました。その同じ頃にイギリス人はタスマニア人を虐殺していた。ところが、その事実に対して誰も語らない。そのような時に、カニングハムは自分たちの虐殺については問題にしなくてもいいのかというようなエッセイを書いた。これがかなりのスキャンダルになったのです。そのカニングハム・グラハムが「Bloody Niggers」という言葉を使ったらしいです。ドルシー・ルガンバは、その言葉を使いながら世界各地で起きた虐殺の物語を舞台に次々にあげていくという作品を作った。その流れにそってFare Thee Well,Tovaritch Homo Sapiensという作品をグルポフの人たちは作ろうとしているんですね。
4−3. 暴力とエロティシズム
ところが、この作品は一つのきわめて複雑な問題を提示していました。暴力とエロティシズムの問題です。暴力とエロスの関係の西欧における極めて難しい部分へと斬り込むことなしに植民地主義における暴力のすごさを追求していくとどこかで限界にぶつかるという発想の下に作られているようです。というのはここに、サドの描いた物語が、現在作成中の舞台Fare Thee Well,Tovaritch Homo Sapiensの中に、一つのエピソードとして登場してくるのですけれども、そのサドの物語が上演されあとで、そしてそれについての分析が演出家のジャックによってレクチャーのような形で語られるのですが、その直後に、隠し撮りされたルワンダでの虐殺の光景の映像が、後ろの壁面に映し出されるのです。ルワンダは高原の非常に美しいところです。ベルギー領コンゴは低地帯で鉱山資源が蓄積されていきますが、それを見張るような場所に位置する高原地帯がルワンダで、ルワンダは緑に包まれた灌木林のある非常に美しい場所なのです。緑のなかで木漏れ日がゆれるような美しい映像を見ていると、カメラがズームアップしていく、すると何かが特定されて来るように、何かが見えてくる。そこには点のような人影が動いていて、さらに近づいていくと、人が膝まずいて命乞いをしているような格好が見えてくるのです。その瞬間、マシェットと呼ばれる斧が振り下ろされて、その人の首がぱっと切り落とされるんです。この映像は舞台『ルワンダ94』でも使用されていて、僕はこれを2002年にモントリオールで観ました。夜の9時くらいに始まって、明け方まで9時間ちかくつづく上演なのですが、おそらくこのシーンは12時をまわっている頃に映し出されました。このとき私は、初めからいろいろ衝撃的なことを観ていたのですが、それを観た瞬間、思わずあっと声をあげてしまいました。
つまり、そういう自然の美しさによってより誇張される、虐殺の、残虐の力、暴力がエロチックであるという、「虐殺はエロチックである」というそういう言葉で表現することが可能であるようなそういう問題性をどう考えるのか? 今まで僕が話してきたような文脈で虐殺を語るのか、「虐殺はエロチックである」と言い変えるのか。実際の虐殺はエロチックですか? という問題と、サドにおけるエロティシズムと暴力という問題です。サドは誰一人として殺していませんから、表象としての代行の中でなされること、それから現実のルワンダの中でなされる暴力のエロティシズムというものとの、その違いをどう考えるのかという問題があります。しかし、エロスと暴力が常につながるというような発想の中で展開されていたヨーロッパの思考形態というようなもの、このホモサピエンスの思考の方式にfarewellと言えるのかどうか。こういう問題を含めた形でジャック・デルキュヴェルリーたちは作品を作ろうとしているんですね。非常に複雑な形での、現実への試みとして、『ルワンダ94』はさらなる展開をみせている。
つまり、そういう自然の美しさによってより誇張される、虐殺の、残虐の力、暴力がエロチックであるという、「虐殺はエロチックである」というそういう言葉で表現することが可能であるようなそういう問題性をどう考えるのか? 今まで僕が話してきたような文脈で虐殺を語るのか、「虐殺はエロチックである」と言い変えるのか。実際の虐殺はエロチックですか? という問題と、サドにおけるエロティシズムと暴力という問題です。サドは誰一人として殺していませんから、表象としての代行の中でなされること、それから現実のルワンダの中でなされる暴力のエロティシズムというものとの、その違いをどう考えるのかという問題があります。しかし、エロスと暴力が常につながるというような発想の中で展開されていたヨーロッパの思考形態というようなもの、このホモサピエンスの思考の方式にfarewellと言えるのかどうか。こういう問題を含めた形でジャック・デルキュヴェルリーたちは作品を作ろうとしているんですね。非常に複雑な形での、現実への試みとして、『ルワンダ94』はさらなる展開をみせている。
5.終わりに
こういう中に、最初言ったジェイムソンが置かれている苦境からの脱出の試みという形での演劇的な活動が、例えばグルポフという集団の、いわば80年代のブレヒトへの回帰から始まり、ルワンダでの作品作成、『ルワンダ94』の成立、そして現在、来年に向けて準備されつつあるFare Thee Well,Tovaritch Homo Sapiensという作品の中にも息づいています。つまり「舞台芸術の現在」というようなものは、こういう極めて大きなしかし複雑な問題と接触しつつ、そことの関わりの中で立ち向かいつつ展開する人たちの手によってこれがどの程度大きな動きか分りませんけれども、続けられていると思います。
そして僕は最初にあげた、ポルトB、モレキュラーシアター、解体社の活動もグルポフほど巨大ではないにしても、身動きの取れない状態から脱出する動きを掴み出そうとする試みとして非常に意味があると思っています。G・アガンベン(1942?)の有名なエッセイに「身振りについての覚書」(『人権の彼方に』所載)があります。ここで、彼は19世紀ヨーロッパのブルジョワジーは身振りを失ってしまったと書いています。身振りとはゲストゥス、ゲレーレ、遂行することという意味です。つまり、そうした身動きが取れない中で何かを遂行すること、パフォームすること、つまりパフォーマティビティを手に入れること。これが非常に重要ですが、19世紀のブルジョワジーたちはそれを失ってしまった。その証拠としてパリでディアギレフバレエ、裸足のイサドラ・ダンカンが喝采を受けた、それは一種の身体の抵抗ではあるが、アガンベンは、そうした抵抗は無意味だと言っています。アガンベンはアイロニカルにもう手遅れだと言っているのですが、ジェイムソンもアメリカでの完全な苦境に対する自分の辛い告白を『ブレヒトと方法』という本の最初のプロローグの中でしていたというわけなのですね。しかし、そのような場所にいながらも、なにか抵抗をしなければならない、その時の一つの手がかりとして、かすかながらにそれをさぐるとすれば、それがブレヒトにあるのではないかとジェイムソンは言っているのだと思います。そうした試みとして、演劇のさまざまな試みを見ていくことが非常に重要なのだと思います。
そして僕は最初にあげた、ポルトB、モレキュラーシアター、解体社の活動もグルポフほど巨大ではないにしても、身動きの取れない状態から脱出する動きを掴み出そうとする試みとして非常に意味があると思っています。G・アガンベン(1942?)の有名なエッセイに「身振りについての覚書」(『人権の彼方に』所載)があります。ここで、彼は19世紀ヨーロッパのブルジョワジーは身振りを失ってしまったと書いています。身振りとはゲストゥス、ゲレーレ、遂行することという意味です。つまり、そうした身動きが取れない中で何かを遂行すること、パフォームすること、つまりパフォーマティビティを手に入れること。これが非常に重要ですが、19世紀のブルジョワジーたちはそれを失ってしまった。その証拠としてパリでディアギレフバレエ、裸足のイサドラ・ダンカンが喝采を受けた、それは一種の身体の抵抗ではあるが、アガンベンは、そうした抵抗は無意味だと言っています。アガンベンはアイロニカルにもう手遅れだと言っているのですが、ジェイムソンもアメリカでの完全な苦境に対する自分の辛い告白を『ブレヒトと方法』という本の最初のプロローグの中でしていたというわけなのですね。しかし、そのような場所にいながらも、なにか抵抗をしなければならない、その時の一つの手がかりとして、かすかながらにそれをさぐるとすれば、それがブレヒトにあるのではないかとジェイムソンは言っているのだと思います。そうした試みとして、演劇のさまざまな試みを見ていくことが非常に重要なのだと思います。
○映像資料、ドキュメンタリー映画『ルワンダ;われわれを通して人間が』
(マリー=フランス・コラール監督)について
(マリー=フランス・コラール監督)について
この映像作品は、2006年に完成しています。2004年にグルポフがルワンダに行って『ルワンダ94』を上演していますが、そのときにルワンダで虐殺された人たちの親族がこの舞台を観にきています。この作品のルワンダ上演を現実に遂行しようとしたときに、グルポフの人たちは、非常に緊張したと話していました。コラールさんは、2004年の上演を1年半かけて編集し、この映画をつくりました。来年(2010)、マリー=フランス・コラールさんと演出家のジャック・デルキュヴェルリーが来る予定です。この映画の上映会も予定していますので、ぜひ観にきてください。
この舞台上で最初に話をしている女性ヨランダ・ムカガサナさんは、家族が全員殺されてしまい、偶然助けてもらって生き延びた女性で、その時の状況をずっと、たしか、30分近く、話していました。モントリオールの上演のときは、しばらくすると会場からすすり泣き、号泣が聞えてきました。いわゆる現実とフィクション、演劇と言う表現の中での実際の当事者、虐殺の現場で奇跡的に生き延びることのできた人が語るリアリティーが演劇という場でどういう意味、機能を持っているのかは非常に難しい問題です。
最初にお渡ししたカントールの英文の資料は、実は「舞台芸術10」という私が編集していた雑誌に、工藤幸雄さんの翻訳で載っているものです。1914年と書いてあるところを見てくれますか。訳しますと、「第一次世界大戦、何千何百万の死体、ばかげた大虐殺のなか、現実に対するあざけり、無関心、すなわち抵抗、否定、あらゆる社会的な価値が疑問にふされ、そして聖なる概念というものはいわば嘲笑されるようになった」「そういう中で、ダダ、シュールレアリスムというものが出てくる。それはリアルネス、形式が現実によって置き換えられるような芸術活動が出てくる」だが、ここが一番大事なところですが、「四半世紀が過ぎ、第二次世界大戦が起った。ジェノサイド、強制収容所、火葬場、人間という獣、死、拷問」。「人類は泥になり、石鹸にされ、灰となった。堕落、あなどり。次に述べることがわたしの、そして我々の課題なのだ。もはや、芸術作品は存在しない。聖なる幻想は存在しない。聖なるパフォーマンスも存在しない。生と現実から引き放されたオブジェだけが存在する。だから、泥のこびりついた荷車、そうしたものが芸術作品となったのだ。もはや芸術的な空間は存在しない。現実の空間だけしか存在しない」という風に、1986年に、ミラノ講義の中で、「20世紀の終わりを前にして」という最終レクチャーをした時に、タデウシュ・カントールはこういう形で述べています。芸術作品と呼ばれるような聖なるイリュージョン、聖なるパフォーマンスはもはやない。そうした中で作品を作るにはどうしたらいいのか。そういう作品を作ることによって初めて、芸術は現実に応答できる。そのようなものとしての具体的な展開を誰がどのようにやっているのか、その例として、最後にあげましたグルポフの『ルワンダ94』が出現してきている。そのような人たちは無数にはいないにしても、かなりの人たちがそういう形で現実に応答してさくひんを作っている。今日の私のレクチャーのタイトルは、『グローバリゼーションの時代における演劇的抵抗と実践』ですが、このタイトルから想像できるような具体的な事例をいくつか語ることができたと思っています。
この舞台上で最初に話をしている女性ヨランダ・ムカガサナさんは、家族が全員殺されてしまい、偶然助けてもらって生き延びた女性で、その時の状況をずっと、たしか、30分近く、話していました。モントリオールの上演のときは、しばらくすると会場からすすり泣き、号泣が聞えてきました。いわゆる現実とフィクション、演劇と言う表現の中での実際の当事者、虐殺の現場で奇跡的に生き延びることのできた人が語るリアリティーが演劇という場でどういう意味、機能を持っているのかは非常に難しい問題です。
最初にお渡ししたカントールの英文の資料は、実は「舞台芸術10」という私が編集していた雑誌に、工藤幸雄さんの翻訳で載っているものです。1914年と書いてあるところを見てくれますか。訳しますと、「第一次世界大戦、何千何百万の死体、ばかげた大虐殺のなか、現実に対するあざけり、無関心、すなわち抵抗、否定、あらゆる社会的な価値が疑問にふされ、そして聖なる概念というものはいわば嘲笑されるようになった」「そういう中で、ダダ、シュールレアリスムというものが出てくる。それはリアルネス、形式が現実によって置き換えられるような芸術活動が出てくる」だが、ここが一番大事なところですが、「四半世紀が過ぎ、第二次世界大戦が起った。ジェノサイド、強制収容所、火葬場、人間という獣、死、拷問」。「人類は泥になり、石鹸にされ、灰となった。堕落、あなどり。次に述べることがわたしの、そして我々の課題なのだ。もはや、芸術作品は存在しない。聖なる幻想は存在しない。聖なるパフォーマンスも存在しない。生と現実から引き放されたオブジェだけが存在する。だから、泥のこびりついた荷車、そうしたものが芸術作品となったのだ。もはや芸術的な空間は存在しない。現実の空間だけしか存在しない」という風に、1986年に、ミラノ講義の中で、「20世紀の終わりを前にして」という最終レクチャーをした時に、タデウシュ・カントールはこういう形で述べています。芸術作品と呼ばれるような聖なるイリュージョン、聖なるパフォーマンスはもはやない。そうした中で作品を作るにはどうしたらいいのか。そういう作品を作ることによって初めて、芸術は現実に応答できる。そのようなものとしての具体的な展開を誰がどのようにやっているのか、その例として、最後にあげましたグルポフの『ルワンダ94』が出現してきている。そのような人たちは無数にはいないにしても、かなりの人たちがそういう形で現実に応答してさくひんを作っている。今日の私のレクチャーのタイトルは、『グローバリゼーションの時代における演劇的抵抗と実践』ですが、このタイトルから想像できるような具体的な事例をいくつか語ることができたと思っています。
質疑応答
Q1: 『ルワンダ94』ですとか、Fare Thee Well,Tovaritch Homo Sapiensは作品ができるまで
5年間という長い時間がかかっていますが、経済的に誰が支えているか教えてください。
Fare Thee Well,Tovaritch Homo Sapiensの方はテアトルナショナルの企画なので、お金は
基本的にはベルギー政府から出ています。ベルギー政府というのは複雑で、フランス系とフ
ラマン系とがあるわけが、この劇場はフランス語系です。この前、ジャックに会った時に、
ジャックが言っていましたが、『ルワンダ94』は自分たちでやったそうです。『ルワンダ94』
は非常に評価が高かったので、それで国からお金が降りるようになってその続きをやるに対
して、前回の『ルワンダ94』は、間接的にベルギー政府を批判したものでしたが、にもか
かわらず、今回のプロジェクトにたいしてお金が出たので、直接的にヨーロッパを批判する
作品を作ろうという話になったそうです。以前はブレヒトの『母』などをやっていましたが、
当時は全然お金がなかったと言っていました。
Q2: 日本のモレキュラーシアターやポルトBもですが、『ルワンダ94』に来るような方々は何か
興味があるという人、つまり考えたくてきている人が多いのか、それとも知識人などが多い
のか。どのような人たちが思考を刺激されるのかを教えてください。
『ルワンダ94』に関しては、ワーク・イン・プログレスとして、アヴィニョンで上演して
いますから、フェスティバルに来た人は観ています。それから、僕が2002年モントリオー
ルで観た時は、テアトル デ アメリカズという諸アメリカ演劇祭で、三回上演されて、
大体800席くらいなので、2,500人くらいが観ていました。このフェスティバルに来た人
たちはみんなこれを観たがっていて、なかなかチケットを取れなくて、泣くなく帰った人も
いました。だから演劇に興味がある人たちが観にきているということです。
ヨーロッパにおいては、演劇が考える場所であり、演劇で思考が活性化されるという、 さらにそこで問題が批評的に提起されるというのは、ヨーロッパの伝統なんです。僕はハン ブルクで仕事をしてましたけど、あるとき、「考える、クリティカルな演劇」を中心に据え て、演劇祭を組織したいと言ったら、お前何を言ってるんだと言われました。日本ではそう いうことをいうと少数派になりますが、クリティカルじゃない演劇というのはあまり考えら れないんですね。現実に対するクリティカルな応答としての演劇、だから『ルワンダ94』 によってお金が国からも出るようになってるわけですから、演劇における多数派ですね。 ヤン・ファーブルがこの前のベネチアビエンナーレで『ルワンダ94』に刺激されて新作を 作っています。
日本の場合は、モレキュラーシアターの『バレエ・ビオメハニカ』(2007)は、ディアギレ フ展の関連上演として1回だけ上演されただけで、200人くらいでした。あと2008年、 東京の月島のビール工場跡地のギャラリー「テンポラリー・コンテンポラリー」で行ったと きは、3回上演して、観客は450人くらいでした。3回とも上演の後にシンポジウムがあっ て、僕は3回ともシンポジウムに出ていたので3回とも行きましたが、僕の知っているいわ ゆる演劇業界で仕事をしている人はあまり来てなかったですね。そういう意味でいうと、 考える演劇は、日本の演劇の中では極めて少数派で、そこに来ているのは、ある種知的関心 を初めから持っている人たちだと思います。ポルトBは少し増えたんじゃないですか。劇団 解体社も外国だと入るということですが、日本だとあまり見てもらえないみたいです。
ヨーロッパにおいては、演劇が考える場所であり、演劇で思考が活性化されるという、 さらにそこで問題が批評的に提起されるというのは、ヨーロッパの伝統なんです。僕はハン ブルクで仕事をしてましたけど、あるとき、「考える、クリティカルな演劇」を中心に据え て、演劇祭を組織したいと言ったら、お前何を言ってるんだと言われました。日本ではそう いうことをいうと少数派になりますが、クリティカルじゃない演劇というのはあまり考えら れないんですね。現実に対するクリティカルな応答としての演劇、だから『ルワンダ94』 によってお金が国からも出るようになってるわけですから、演劇における多数派ですね。 ヤン・ファーブルがこの前のベネチアビエンナーレで『ルワンダ94』に刺激されて新作を 作っています。
日本の場合は、モレキュラーシアターの『バレエ・ビオメハニカ』(2007)は、ディアギレ フ展の関連上演として1回だけ上演されただけで、200人くらいでした。あと2008年、 東京の月島のビール工場跡地のギャラリー「テンポラリー・コンテンポラリー」で行ったと きは、3回上演して、観客は450人くらいでした。3回とも上演の後にシンポジウムがあっ て、僕は3回ともシンポジウムに出ていたので3回とも行きましたが、僕の知っているいわ ゆる演劇業界で仕事をしている人はあまり来てなかったですね。そういう意味でいうと、 考える演劇は、日本の演劇の中では極めて少数派で、そこに来ているのは、ある種知的関心 を初めから持っている人たちだと思います。ポルトBは少し増えたんじゃないですか。劇団 解体社も外国だと入るということですが、日本だとあまり見てもらえないみたいです。
Q3: Fare Thee Well,Tovaritch Homo Sapiensは作品を作って、上演するために日本に来るの
ですか?
ごめんなさい。作品は来ません。来るのはワークショップで、演出家と映像作家の二人だけ
が来る可能性が今あります。彼らに時間があれば来ます。シンポジウムとワークショップを
東京で5日間やります。劇作家協会か演出家協会のプロジェクトの中に入っていて、僕が
連絡を取ることになっています。このワークショップはFare Thee Well Tovaritch Homo
Sapiens とは全く違ったものになると思います。テーマをどうするとか、また話合いがある
と思います。いずれにしても現代的な重大な問題をどうやって演劇的な活動とつなげていく
のかということと関連すると思います。純粋に技法的な問題ではなくなると思います。

配布資料:
Fredric Jameson Brecht and Method, UK:Verso,1998 (p.4)
Tisch School of the Arts TDR a journal of performance studies, New York:MIT Press 1991 (pp.160-161) (Tadeusz Kantor‘Before the End of the Twentieth Century XIIth Milano Lesson’)
映像資料:
モレキュラーシアター『バレエ・ビオメハニカ』(2007)
グルポフ『ルワンダ94』〔映像作品〕(2006)
Fredric Jameson Brecht and Method, UK:Verso,1998 (p.4)
Tisch School of the Arts TDR a journal of performance studies, New York:MIT Press 1991 (pp.160-161) (Tadeusz Kantor‘Before the End of the Twentieth Century XIIth Milano Lesson’)
映像資料:
モレキュラーシアター『バレエ・ビオメハニカ』(2007)
グルポフ『ルワンダ94』〔映像作品〕(2006)

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.


