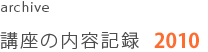


『プロデューサーの仕事』
Vol.3 「国際共同製作作品のプロデュース」
2010年8月18日(水) 19時〜21時
穂坂 知恵子
(世田谷パブリックシアター劇場部 チーフプロデューサー)
《所 感》
本講座では国境を越えて舞台作品をつくるプロセスについて、世田谷パブリックシアターで制作された『赤鬼』と『エレファント・バニッシュ』の2作品を中心に、具体的な事例に即して説明がなされた。
海外のアーティストと作品を創造する際には、大規模な予算獲得の見込みをつけるだけでなく、言語的・文化的な相違や、あるいは各国の習慣や制度の違いから発する誤解も、一つ一つ乗り越えていかなくてはならない。国内制作では遭遇しないような思わぬアクシデントも多発する。知識やノウハウだけでなく、現実的に状況に対処できる経験とアクシデントを回避する先見性が必要である。東京グローブ座制作部を経て、開場準備室から世田谷パブリックシアターの業務に携わっている講師が語る豊富な具体例によって、劇場プロデューサーの仕事内容がより明瞭に伝えられたように思う。
また単に仕事上のネットワークというわけではなく、人と人のつながりとしての血の通ったネットワークを垣間見ることができた。多くの作品やアーティストを愛することもまた「プロデューサーの仕事」なのだと感じさせてくれた講座となったように思う。
本講座では国境を越えて舞台作品をつくるプロセスについて、世田谷パブリックシアターで制作された『赤鬼』と『エレファント・バニッシュ』の2作品を中心に、具体的な事例に即して説明がなされた。
海外のアーティストと作品を創造する際には、大規模な予算獲得の見込みをつけるだけでなく、言語的・文化的な相違や、あるいは各国の習慣や制度の違いから発する誤解も、一つ一つ乗り越えていかなくてはならない。国内制作では遭遇しないような思わぬアクシデントも多発する。知識やノウハウだけでなく、現実的に状況に対処できる経験とアクシデントを回避する先見性が必要である。東京グローブ座制作部を経て、開場準備室から世田谷パブリックシアターの業務に携わっている講師が語る豊富な具体例によって、劇場プロデューサーの仕事内容がより明瞭に伝えられたように思う。
また単に仕事上のネットワークというわけではなく、人と人のつながりとしての血の通ったネットワークを垣間見ることができた。多くの作品やアーティストを愛することもまた「プロデューサーの仕事」なのだと感じさせてくれた講座となったように思う。
記録:横田宇雄(学習院大学大学院人文科学研究科身体表象文化学専攻博士前期課程在籍)
※本記録は、講座の記録をもとに、講師による大幅な加筆を加えて掲載しています
※本記録は、講座の記録をもとに、講師による大幅な加筆を加えて掲載しています

1.「国際共同製作」の変遷(明治期から現在まで)
◎ 明治期から戦後にかけて(一方方向の交流)
「国際共同製作」という言葉に、どのようなイメージを抱くであろうか。欧米のように複数の劇場や演劇祭で共同出資して作品を製作するような形態であろうか。あるいはピーター・ブルックのように異文化の人たちと作品を製作するような形態であろうか。
「国際共同制作」という制作形態が人口に膾炙する前の時代から、日本の舞台芸術界では、様々な形で異文化を紹介し、と同時に、古典芸能を中心に多種多様の日本発の文化を海外で紹介していた。明治以降、新劇が海外戯曲の上演を積極的に行っていたが、この時はまだ欧米文化の「受容」に重きが置かれていたことは否めない。一方、川上音二郎一座の欧米ツアー以降も、第二次世界大戦前に、宝塚歌劇団がドイツ、イタリアやアメリカで公演する流れもあった。戦後、モスクワ芸術座やRSCの来日公演を皮切りに招聘公演が増えたが、同時に、60年代以降、鈴木忠志や寺山修司、あるいは暗黒舞踏の集団などが果敢に海外公演を行うようになった。後述のサイモン・マクバーニーは、寺山修司の『奴婢訓』ロンドン公演を観て以来、日本文化への憧憬を深めていったと語っている。70年代、世界経済の一翼を担うようになった日本では国際交流基金が設立され、「国際交流」という側面が文化政策の中で、さらに言えば外交政策の一つの柱として大きな位置を占めるようになる。
「国際共同制作」という制作形態が人口に膾炙する前の時代から、日本の舞台芸術界では、様々な形で異文化を紹介し、と同時に、古典芸能を中心に多種多様の日本発の文化を海外で紹介していた。明治以降、新劇が海外戯曲の上演を積極的に行っていたが、この時はまだ欧米文化の「受容」に重きが置かれていたことは否めない。一方、川上音二郎一座の欧米ツアー以降も、第二次世界大戦前に、宝塚歌劇団がドイツ、イタリアやアメリカで公演する流れもあった。戦後、モスクワ芸術座やRSCの来日公演を皮切りに招聘公演が増えたが、同時に、60年代以降、鈴木忠志や寺山修司、あるいは暗黒舞踏の集団などが果敢に海外公演を行うようになった。後述のサイモン・マクバーニーは、寺山修司の『奴婢訓』ロンドン公演を観て以来、日本文化への憧憬を深めていったと語っている。70年代、世界経済の一翼を担うようになった日本では国際交流基金が設立され、「国際交流」という側面が文化政策の中で、さらに言えば外交政策の一つの柱として大きな位置を占めるようになる。
◎ 1980年以降
1980年代以降、松竹や日生劇場、東京グローブ座、銀座セゾン劇場などが競うように海外作品の招聘を行う時代が到来する。大型ミュージカルの招聘やブロードウェイ・ミュージカルのオリジナル・クリエイターを招聘して共同制作することも活発化してきた。1988年に東京グローブ座がシェイクスピア劇専門の劇場としてオープンして、海外のトップレベルのシェイクスピア作品が、年間数十本の割合で上演されるようになった。その後、同劇場は、シェイクスピア作品だけでなく海外の優れた現代演劇作品の招聘も活発に行い、後に、ロベール・ルパージュやサイモン・マクバーニーとの共同制作の萌芽ともなるべき招聘公演が積極的に行われていたことは注目に値する。
◎ 現在の新しい姿(双方向の交流へ)
時代の流れとともに、国際交流は、「受容」から「共同作業」へと変化していった。60年代以降、鈴木忠志や佐藤信らが「国際共同作業」を実践してきたが、90 年以降は、TPT(Theatre Project Tokyo)のディヴィット・ルヴォー(David Leveaux)やロバート・アラン・アッカーマン(Robert Allan Ackerman)らの東京での活躍によって多国籍のアーティストが参画する現場が増えてきた。しかしながら、この段階での公演形態は、日本側のみが出資している「国際的なスタッフによる日本での共同作業」という側面が強かった。ところが、21世紀に入り、出資面でも「共同」で責任を負う(つまり、リスクを共同で負担する)、名実ともに「国際共同制作」という形態が根付き始めた。近年では2006年に世田谷パブリックシアターが制作した平田オリザ作『ソウル市民』[ 演出: フレデリック・フィスバック(Frederic Fisbach)]がアヴィニョン演劇祭に正式招待作品として上演された。1998年、ワールドカップ開催時のドラマリーディング以降、フランスでの平田の活躍は目覚ましいことは周知のことである。また、日本の新しい世代の声を代表する一人として注目されている岡田利規の『三月の5 日間』がクンステン演劇祭(Kunsten Festival des Arts)に招聘され、その後、同作品は多くの演劇祭から招聘されるようになった。岡田はその成功を受けて、クンステン演劇祭とウィーン演劇祭から新作の委嘱を受け、『フリータイム』を制作して、世界ツアーを行っている。
◎ 世田谷パブリックシアターの「国際共同製作作品」
世田谷パブリックシアターはこれまで、サイモン・マクバーニー(Simon McBurney)演出による『エレファント・バニッシュ』(2003/04)、『春琴』(2008/09/10)、フレデリック・フィスバックと江戸糸あやつり人形劇団〈結城座〉の日仏演劇コラボレーション『屏風』(2004)、フィスバック演出による『ソウル市民』(2005)、ロベール・ルパージュ(Robert Lepage)演出の日本版『アンデルセン・プロジェクト』(2006)、ジョセフ・ナジ(Josef Nadj)演出の『遊*ASOBU』(2007)のほか、アジアとの共同制作作品などを数多く製作してきた。今回の講座では、野田秀樹の『赤鬼』とマクバーニーの『エレファント・バニッシュ』の2作品を実例に、「国際共同製作」の仕事について考えていきたい。
2. 日タイ国際共同製作版『赤鬼』上演の経緯(映像あり)
◎ 企画の出発点(国際交流基金の要請)
国際共同製作には、国内の製作作品以上に思いもよらない「予期せぬこと」が起こる。『赤鬼』の製作は、まさに「予期せぬこと」の連続であった。
『赤鬼』製作時、世田谷パブリックシアターは世田谷区コミュニティ振興交流財団が運営しており、財団の掲げる「交流」というミッションを舞台芸術によっていかに実現するかを模索していた。世田谷区レベルの「交流」事業はカナダのウィニペグ市、オーストラリアのバンバリー市との姉妹都市交流であったが、当財団は舞台芸術界に風穴を空けるような活動を「交流」であると位置づけ、どのような作品づくりが相応しいのか模索していた。
1997年、国際交流基金よりタイとの共同製作作品の依頼があった。劇場がオープンして3ヶ月目のことである。当時の国際交流基金の「国際共同制作」プログラムは、先進国が発展途上国に「教える」という感が否めなかったようだ。そこで、この状況を打破するような舞台作品の製作によって、「交流」の新しい姿を提示していこうとしていた。基金側からの要請は「タイのキャストとスタッフを日本人スタッフと対等に扱うこと」であった。
『赤鬼』製作時、世田谷パブリックシアターは世田谷区コミュニティ振興交流財団が運営しており、財団の掲げる「交流」というミッションを舞台芸術によっていかに実現するかを模索していた。世田谷区レベルの「交流」事業はカナダのウィニペグ市、オーストラリアのバンバリー市との姉妹都市交流であったが、当財団は舞台芸術界に風穴を空けるような活動を「交流」であると位置づけ、どのような作品づくりが相応しいのか模索していた。
1997年、国際交流基金よりタイとの共同製作作品の依頼があった。劇場がオープンして3ヶ月目のことである。当時の国際交流基金の「国際共同制作」プログラムは、先進国が発展途上国に「教える」という感が否めなかったようだ。そこで、この状況を打破するような舞台作品の製作によって、「交流」の新しい姿を提示していこうとしていた。基金側からの要請は「タイのキャストとスタッフを日本人スタッフと対等に扱うこと」であった。
◎ 野田秀樹『赤鬼』の選出
当時、世田谷パブリックシアターの劇場監督であった佐藤信(1997年から2002年在任)は、自身が主宰する劇団〈黒テント〉で既に東南アジアとの交流を活発に行っていた。
佐藤は、国際交流基金からの委嘱があった時点ではほかの作品を想定しており、既に、その演出家の許諾も得て、最終調整のためタイに赴いた。ところが、現地の演劇人と交流するなかで、タイの出演者とスタッフで『赤鬼』の上演を構想する。帰国後、佐藤は直接、野田に演出交渉をした。野田の受諾を受け、上演作品を『赤鬼』に変更。そこで、既に依頼していた作品に関わる人たちに事情を説明しつつ、『赤鬼』上演のための予算の組み直し、キャスティングやスタッフィングの確定、劇場の確保、広報活動などをわずか半年足らずでこなさなくてはならなかった。
佐藤は、国際交流基金からの委嘱があった時点ではほかの作品を想定しており、既に、その演出家の許諾も得て、最終調整のためタイに赴いた。ところが、現地の演劇人と交流するなかで、タイの出演者とスタッフで『赤鬼』の上演を構想する。帰国後、佐藤は直接、野田に演出交渉をした。野田の受諾を受け、上演作品を『赤鬼』に変更。そこで、既に依頼していた作品に関わる人たちに事情を説明しつつ、『赤鬼』上演のための予算の組み直し、キャスティングやスタッフィングの確定、劇場の確保、広報活動などをわずか半年足らずでこなさなくてはならなかった。
◎ 企画立案から上演まで
佐藤からの打診を受け、野田はすぐにタイに向かい出演者のオーディションを行った。国際交流基金の尽力によって、バンコクでのオーディションには50名もの俳優が参加した。ワークショップを重ねて、最終的に25人にまで絞る。『赤鬼』のオリジナル・プロダクションは、4名の俳優(日本人3人+英国人1人)で演じられた。タイ版では、演出家の意向で、出演人数を4人から15人へと大幅に増やすことを決定する。
こうしてキャスティングは決まったが、演出家の希望上演時期には他団体による劇場の使用が決まっていため、本来なら劇場休館日にあたる年末1997年12月29日から12月31日に、劇場をオープンして上演することにした。いざ幕が開くと、年末にもかかわらず、初日の評判を聞きつけたお客様が、2日目には劇場の前に行列が出来るほど集まり、最終的には大晦日に追加公演をしようか、という提案がキャストやスタッフから出るほどであった(実際には、追加公演はしなかった)。
こうしてキャスティングは決まったが、演出家の希望上演時期には他団体による劇場の使用が決まっていため、本来なら劇場休館日にあたる年末1997年12月29日から12月31日に、劇場をオープンして上演することにした。いざ幕が開くと、年末にもかかわらず、初日の評判を聞きつけたお客様が、2日目には劇場の前に行列が出来るほど集まり、最終的には大晦日に追加公演をしようか、という提案がキャストやスタッフから出るほどであった(実際には、追加公演はしなかった)。
◎『赤鬼』その後の展開
翌年のタイでの上演では、現代演劇としては異例の3週間の連続上演をバンコクで敢行する。この成功を受け、1999年には世田谷パブリックシアターの単独企画として東京で再演を行う。その後、野田は自身の活動範囲を広げ、2003年に『赤鬼』(英名“RED DEMON”)をロンドンで上演し、翌04年に、Bunkamura シアターコクーンで日本版・タイ版・イギリス版『赤鬼』の連続公演として上演された。また2005年にはソウル国際芸術祭に野田が招聘され、韓国版『赤鬼』を上演する広がりをみせた(韓国語名『パルガントッケビ』)。その後も、『赤鬼』は発展を続け、2009年には日本メコンフェスティバルにおいてタイの大衆演劇リケエの手法での上演も行われ(翻案・演出: プラディット・プラサートーン)、同年、野田が芸術監督に就任した東京芸術劇場でこのリケエ版『赤鬼』で上演された。国際交流基金のバックアップの下、いわば国家プロジェクトとして始まった企画が十数年の歳月を経て、多くの実を結んでいった。このプロジェクトに関わったアーティストたちが、日本とアジアの共同制作の現場で、今現在、中心的な役割を果たしている現状を考えると、国際交流基金の蒔いた種の大きな成長ぶりには目を見張るものがある。
3.『エレファント・バニッシュ』上演の経緯(映像あり)
◎ 企画立案から「谷崎ワークショップ」開始まで
『エレファント・バニッシュ』もまた、企画から幕開きまで「予期せぬこと」の連続で、まさに綱渡りの状態であった。
1999年、ある助成財団から、ヨーロッパ諸国との国際共同製作作品に対する資金援助の申し出があり、世田谷パブリックシアターは2002年の上演を目処にマクバーニーと共同製作を行うことを決定する。しかし、資金援助の話は突如立ち消えとなり、企画は窮地に立たされたが、同時期に文化庁の助成制度が変わり、「国際共同制作」という枠組みで作品作りが可能になったため、翌03年の上演を目指すことにした。
マクバーニーとの共同製作の題材は、当初、谷崎潤一郎を予定していた。1998年よりマクバーニーは谷崎の『陰影礼賛』と『春琴抄』を使った「谷崎ワークショップ」を世田谷パブリックシアターの稽古場で断続的に行っていたからである。このワークショップが、本公演として結実するのは、ワークショップを立ち上げてから十年後の2008年の『春琴』まで待つこととなる。演出家や海外クリエーターや日本人の俳優にとっても、谷崎文学に内在する日本文化の綾を理解する「時間の蓄積」が必要であった。
1999年、ある助成財団から、ヨーロッパ諸国との国際共同製作作品に対する資金援助の申し出があり、世田谷パブリックシアターは2002年の上演を目処にマクバーニーと共同製作を行うことを決定する。しかし、資金援助の話は突如立ち消えとなり、企画は窮地に立たされたが、同時期に文化庁の助成制度が変わり、「国際共同制作」という枠組みで作品作りが可能になったため、翌03年の上演を目指すことにした。
マクバーニーとの共同製作の題材は、当初、谷崎潤一郎を予定していた。1998年よりマクバーニーは谷崎の『陰影礼賛』と『春琴抄』を使った「谷崎ワークショップ」を世田谷パブリックシアターの稽古場で断続的に行っていたからである。このワークショップが、本公演として結実するのは、ワークショップを立ち上げてから十年後の2008年の『春琴』まで待つこととなる。演出家や海外クリエーターや日本人の俳優にとっても、谷崎文学に内在する日本文化の綾を理解する「時間の蓄積」が必要であった。
◎「村上ワークショップ」への変更
1998年から毎年継続的に東京でワークショップを行ってきたが、上演を目前にした2002年、マクバーニーは、ロンドンで2週間行ったワークショップで、谷崎作品から一転して、村上春樹の短編小説を取り上げることにした。日本に毎年通い続けたマクバーニーは、現在の日本の表層的な現象は、違和感なく受容できたようだが、幾層にも堆積している日本文化の深層やら「綾」を探ろうとすればするほど、自分の手から砂が零れ落ちるような虚無感に囚われていたようだ。そんな折、マクバーニーは、「都会人の孤独」が通奏低音として響く村上文学の初期短編集に出会った。村上文学で描かれる「空虚感」なら、イギリス人の演出家にもたやすく理解でき、文化の違いを乗り越えて作品ができる可能性を感じたようだ。なにより、村上作品の魅力でもある「ユーモア」のセンスに、心引かれたのだろう。
02年のワークショップで作った数々の場面は秀逸であり、翌年の上演演目は、谷崎潤一郎ではなく村上春樹にと、大きく舵を切ることにした。この突然の変更は5年間、ワークショップに参加し続けてくれていた俳優たちにとっても、晴天の霹靂ではあったが、ロンドンのワークショップで作った場面が上演可能なレベルに達していたことも、変更を受け入れる後押しとなった。さらに言えば、このロンドンでのワークショップには、当時の世田谷パブリックシアターの運営財団の館長、制作部長とプロデューサーの3名がリレー形式で、それぞれ数日ずつロンドンに滞在し、創作現場に立ち会っていたため、プロデューサー・サイドからの企画変更提案を「諾」としてもらえたことが大きかった。
マクバーニーは「決めない勇気を持とう」という信条をモットーとしており、広報を行わなければならない時期になっても、キャストや台本は未定のままだが、本人は一向に意に介さない。プロジェクトが本格稼動する前には、著作権者・村上春樹に上演許可を得なければならず、村上サイドからは、台本の提出を求められたが、その時点では、「『エレファント・バニッシュ』に収められている17編の短編のどれかを使う予定ですが、作品の選定は稽古途中で決まります」としか伝えられない状況であった。キャストも作品選定も未定のままという「演出家以外、全てが謎」の中、大胆な広報宣伝を展開し、チケット発売が始まった。著作権者には、口頭では上演許可を内諾してもらっていたが、正式に契約書にサインができたのは、つまり、「上演台本が形になった」のは、本番の三週間前。実にスリリングな制作進行であったことを、今だから告白できる。演出家の力量を信じて待ってくださった著作権者・村上さんには、ひたすら感謝するのみである。
02年のワークショップで作った数々の場面は秀逸であり、翌年の上演演目は、谷崎潤一郎ではなく村上春樹にと、大きく舵を切ることにした。この突然の変更は5年間、ワークショップに参加し続けてくれていた俳優たちにとっても、晴天の霹靂ではあったが、ロンドンのワークショップで作った場面が上演可能なレベルに達していたことも、変更を受け入れる後押しとなった。さらに言えば、このロンドンでのワークショップには、当時の世田谷パブリックシアターの運営財団の館長、制作部長とプロデューサーの3名がリレー形式で、それぞれ数日ずつロンドンに滞在し、創作現場に立ち会っていたため、プロデューサー・サイドからの企画変更提案を「諾」としてもらえたことが大きかった。
マクバーニーは「決めない勇気を持とう」という信条をモットーとしており、広報を行わなければならない時期になっても、キャストや台本は未定のままだが、本人は一向に意に介さない。プロジェクトが本格稼動する前には、著作権者・村上春樹に上演許可を得なければならず、村上サイドからは、台本の提出を求められたが、その時点では、「『エレファント・バニッシュ』に収められている17編の短編のどれかを使う予定ですが、作品の選定は稽古途中で決まります」としか伝えられない状況であった。キャストも作品選定も未定のままという「演出家以外、全てが謎」の中、大胆な広報宣伝を展開し、チケット発売が始まった。著作権者には、口頭では上演許可を内諾してもらっていたが、正式に契約書にサインができたのは、つまり、「上演台本が形になった」のは、本番の三週間前。実にスリリングな制作進行であったことを、今だから告白できる。演出家の力量を信じて待ってくださった著作権者・村上さんには、ひたすら感謝するのみである。
◎ 稽古から本番まで
国際共同製作の場合、稽古期間中は、通訳が入るため、通常の1.5倍から2倍以上の時間を確保しなくては得心のゆく稽古時間が保証できない。稽古場通訳は、言葉の翻訳伝達以外にも、文化的意味合いの「翻訳」に時間を割かなくてはならない瞬間が多い。例えば、演出家が質問を発して、沈黙する日本人の役者たち。この構図は、日本人なら、「役者は演出家の問いに対して、納得のいく答えを出してあげられるよう沈思熟考の時間が必要なのだ」と判断する。ところが、英国人の演出家にとって、「沈黙」ほど不気味な瞬間はない。「沈黙は金」どころか、「相手が何を考えているのか、わからない」、あるいは、「自分の質問が的外れで、答えに窮しているのではないか。」という疑心暗鬼に陥りやすく、英国人演出家にとって「沈黙は恐怖」以外の何者でもない。この文化的齟齬をうめる努力は、演出家や役者自身が向き合わなければ、先に進めないのが、異文化が交差する現場なのである。本作の場合、5週間はロンドンで、その後5週間は東京で稽古を行った。長期間に及ぶ稽古のため、俳優やスタッフの肉体的疲労に対するケアや精神的なケアが必要となってくる。現場判断でその場にふさわしい変更や臨機応変さが、常に求められてくる。ロンドンでの稽古期間中に、米軍のイラク侵攻(まさに岡田利規の『三月の5日間』の時期)が始まり、ロンドンと東京を何度か往復していたプロデューサーや技術スタッフは、渡航を控えるように財団事務局から促された時期でもあった。しかし、ロンドンで日々稽古に励むキャストやスタッフを勇気づけるためにも、あえて渡航した。
『エレファント・バニッシュ』を特徴づけるのは、映像を多用した舞台装置である。現在の東京らしさを表現するには、「過剰な照明」に縁取られた地下街からオフィス群、あるいは、繁華街に設置された大型スクリーン上に流れては消える「過剰な情報映像」だと感じたカナダ人舞台デザイナーは、舞台上に、大きさの異なる7台の映像機器を組み込んだ。(このあたりからも、のちに『春琴』で表現される暗闇にほのかに浮かび上がる美、とは対照的な、現在の東京の姿に戸惑いを覚えたマクバーニーの日本への印象が伺える。)上演中は、7台の映像機器を同時に起動し、日本では使われたことのない新ソフトを使用した。そのため、機材にまつわるトラブルが絶えなかった。ある時、本番中に映像が停止してしまうという事態が起きた。この時、プロデューサー自らが観客の前に出、状況説明をして、上演の一時停止を求めた。その間、スタッフが必死の思いでバックアップ用に用意していたプログラムを起動させ、不具合をチェックし、20分後には再開することができた。
また、マクバーニーは、あくなき向上心ゆえ、得心のいく稽古ができない場合は、上演を遅らせるよう要求することが多い(これは、世界中で有名な話。アル・パチーノ主演の舞台では、やはり映像トラブルのため、プレビュー公演を延期している)。『エレファント・バニッシュ』初日、開演を2時間遅らせてほしいと、開演3時間前に要求した。あいにく東京では、2時間以上かけて劇場にいらっしゃるお客様も多いので、帰りの足を確保するためにも、2時間も開演を遅らせることはできない。幸い、公演時間が1時間40分であろうと推測できたので(それまでランスルー(本番通りに、最初から最後まで通す稽古)をしていないので、実際の上演時間は、かなり未知数であった)、妥協案として、1時間、開演を遅らせることにした。この時、マクバーニーは自分自身で観客の前に出て行って「実は、今日までランスルーをしておりません。今日お集りの皆さんには、今まで10週間の稽古の成果をお見せしたいのです。この瞬間を共有してくださる皆様は、是非、お残りください。もし、お帰りになりたいお客様がいらしたら、チケット料金はお返しいたします」と謝罪した。1 時間お待ちいただいている間に、制作部スタッフが結集して有料パンフレットを観客全員に無料配布し、本作の性質を理解してもらっていたこともあり、観客は誰一人出て行かなかった。初日以降、東京、大阪、ロンドンと公演をし、公演期間中も毎日毎日、舞台上でリハーサルを繰り返し、翌年には、東京、ニューヨーク、ロンドン、パリ、ミシガンでの公演を行うまで、作品が成長した。
国際共同製作には多くの予期せぬことが起こる。プロデューサーは、企画を立ち上げる際には、無から有を生じさせるクリエイティビティ(創造力)を発揮し、プロジェクトが進行したら、もう一つの「そうぞう力」、イマジネーション(想像力)によって先読みをする力が必要である。アーティストを信頼し、観客の心の奥底を揺さぶるような、今まで気づきもせずにいた深層意識に訴えかけるような作品を世に送り出す努力を怠らないことが肝要である。「決めない勇気を持とう」とする演出家と伴走するには、信頼するアーティストに対して「待つ勇気」を持とうと心に決めた。そう決心した瞬間から、「決まらない」ことがらの多さに悩む日々は、想像力で先読みをしながら、一歩ずつ足元を固めていく喜びの日々へと変わっていった。
『エレファント・バニッシュ』を特徴づけるのは、映像を多用した舞台装置である。現在の東京らしさを表現するには、「過剰な照明」に縁取られた地下街からオフィス群、あるいは、繁華街に設置された大型スクリーン上に流れては消える「過剰な情報映像」だと感じたカナダ人舞台デザイナーは、舞台上に、大きさの異なる7台の映像機器を組み込んだ。(このあたりからも、のちに『春琴』で表現される暗闇にほのかに浮かび上がる美、とは対照的な、現在の東京の姿に戸惑いを覚えたマクバーニーの日本への印象が伺える。)上演中は、7台の映像機器を同時に起動し、日本では使われたことのない新ソフトを使用した。そのため、機材にまつわるトラブルが絶えなかった。ある時、本番中に映像が停止してしまうという事態が起きた。この時、プロデューサー自らが観客の前に出、状況説明をして、上演の一時停止を求めた。その間、スタッフが必死の思いでバックアップ用に用意していたプログラムを起動させ、不具合をチェックし、20分後には再開することができた。
また、マクバーニーは、あくなき向上心ゆえ、得心のいく稽古ができない場合は、上演を遅らせるよう要求することが多い(これは、世界中で有名な話。アル・パチーノ主演の舞台では、やはり映像トラブルのため、プレビュー公演を延期している)。『エレファント・バニッシュ』初日、開演を2時間遅らせてほしいと、開演3時間前に要求した。あいにく東京では、2時間以上かけて劇場にいらっしゃるお客様も多いので、帰りの足を確保するためにも、2時間も開演を遅らせることはできない。幸い、公演時間が1時間40分であろうと推測できたので(それまでランスルー(本番通りに、最初から最後まで通す稽古)をしていないので、実際の上演時間は、かなり未知数であった)、妥協案として、1時間、開演を遅らせることにした。この時、マクバーニーは自分自身で観客の前に出て行って「実は、今日までランスルーをしておりません。今日お集りの皆さんには、今まで10週間の稽古の成果をお見せしたいのです。この瞬間を共有してくださる皆様は、是非、お残りください。もし、お帰りになりたいお客様がいらしたら、チケット料金はお返しいたします」と謝罪した。1 時間お待ちいただいている間に、制作部スタッフが結集して有料パンフレットを観客全員に無料配布し、本作の性質を理解してもらっていたこともあり、観客は誰一人出て行かなかった。初日以降、東京、大阪、ロンドンと公演をし、公演期間中も毎日毎日、舞台上でリハーサルを繰り返し、翌年には、東京、ニューヨーク、ロンドン、パリ、ミシガンでの公演を行うまで、作品が成長した。
国際共同製作には多くの予期せぬことが起こる。プロデューサーは、企画を立ち上げる際には、無から有を生じさせるクリエイティビティ(創造力)を発揮し、プロジェクトが進行したら、もう一つの「そうぞう力」、イマジネーション(想像力)によって先読みをする力が必要である。アーティストを信頼し、観客の心の奥底を揺さぶるような、今まで気づきもせずにいた深層意識に訴えかけるような作品を世に送り出す努力を怠らないことが肝要である。「決めない勇気を持とう」とする演出家と伴走するには、信頼するアーティストに対して「待つ勇気」を持とうと心に決めた。そう決心した瞬間から、「決まらない」ことがらの多さに悩む日々は、想像力で先読みをしながら、一歩ずつ足元を固めていく喜びの日々へと変わっていった。
4. 世田谷パブリックシアター「国際共同製作」の今後
タイとの共同製作の後、2001年にマレーシアよりジョー・クカサス(Jo Kukathas)を迎え『あいだの島(PulauAntara)』(Kam Raslan と共同脚本)を上演した。
2005 年には国際交流基金の援助を受け7カ国・16人の演出家を迎えたアジア現代演劇コラボレーションプロジェクト『ホテル グランド アジア』を上演した。
マクバーニーとは2008年に谷崎潤一郎『春琴』を上演し、同作品は2009年にロンドン公演のあと、東京で再演、2010年秋には、Barbican Theatre(ロンドン)、パリ市立劇場(パリ)、東京、台湾国立劇場(台北)のワールドツアーをおこなった。『春琴』は、クリエイティブ・アーティストとして、日本人の美術家と作曲家を擁したことで、『エレファント・バニッシュ』より、さらに一歩進んだ国際共同制作作品となった。
現在、世田谷パブリックシアターは、これまで行ってきたコラボレーションを踏まえながら、「国際共同製作」の新たな道を模索している。例えば、漢字文化圏の日中韓との共同作業、『赤鬼』から綿々と続く東南アジア諸国との共同作業、マクバーニーとの共同制作第3弾、他のヨーロッパ諸国との共同作業等々。2010年代の私達が共に手を携えて作業すべきアーティストは世界中にいる。言うまでもなく、この日本にも。国境を越えて作品に相応しい組み合わせの妙により、かつて経験したことのない化学反応がおこるような「しかけ」を企画して立ち上げ、作品が次のステップに進んでいくように腐心するのが、プロデューサーの醍醐味である。
2005 年には国際交流基金の援助を受け7カ国・16人の演出家を迎えたアジア現代演劇コラボレーションプロジェクト『ホテル グランド アジア』を上演した。
マクバーニーとは2008年に谷崎潤一郎『春琴』を上演し、同作品は2009年にロンドン公演のあと、東京で再演、2010年秋には、Barbican Theatre(ロンドン)、パリ市立劇場(パリ)、東京、台湾国立劇場(台北)のワールドツアーをおこなった。『春琴』は、クリエイティブ・アーティストとして、日本人の美術家と作曲家を擁したことで、『エレファント・バニッシュ』より、さらに一歩進んだ国際共同制作作品となった。
現在、世田谷パブリックシアターは、これまで行ってきたコラボレーションを踏まえながら、「国際共同製作」の新たな道を模索している。例えば、漢字文化圏の日中韓との共同作業、『赤鬼』から綿々と続く東南アジア諸国との共同作業、マクバーニーとの共同制作第3弾、他のヨーロッパ諸国との共同作業等々。2010年代の私達が共に手を携えて作業すべきアーティストは世界中にいる。言うまでもなく、この日本にも。国境を越えて作品に相応しい組み合わせの妙により、かつて経験したことのない化学反応がおこるような「しかけ」を企画して立ち上げ、作品が次のステップに進んでいくように腐心するのが、プロデューサーの醍醐味である。

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.


