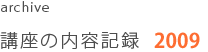


『劇場における公共性』
「公共劇場の根にあるもの」
2009年8月19日(水)、21日(金) 19時〜21時30分
佐伯 隆幸
(演劇評論家)
《所 感》
二日間のレクチャーで、タイトルの通り舞台芸術界の「根」の部分のこと、つまり演劇の在り方そのものについてのお考えを計約五時間にわたってお話くださいました。話題は多岐にわたりましたが、根本的には「演劇とは何か」という大きな問いであったように思います。そのなかには、「民衆演劇」というときの「民衆」は本当にあり得るのか、という人間の在り方への深い洞察も含まれていました。希望と絶望が入り混じったような「民衆」へのアンヴィバレントな気持ちからは、さまざまなご経験の上で葛藤もお持ちなのだということも伝わってきました。
時間がたつのを忘れてしまうような、流れるようなお話はどれも大変興味深く、刺激的でした。これから舞台芸術そのものの可能性を探っていくときの道標になるのではないかと感じています。
二日間のレクチャーで、タイトルの通り舞台芸術界の「根」の部分のこと、つまり演劇の在り方そのものについてのお考えを計約五時間にわたってお話くださいました。話題は多岐にわたりましたが、根本的には「演劇とは何か」という大きな問いであったように思います。そのなかには、「民衆演劇」というときの「民衆」は本当にあり得るのか、という人間の在り方への深い洞察も含まれていました。希望と絶望が入り混じったような「民衆」へのアンヴィバレントな気持ちからは、さまざまなご経験の上で葛藤もお持ちなのだということも伝わってきました。
時間がたつのを忘れてしまうような、流れるようなお話はどれも大変興味深く、刺激的でした。これから舞台芸術そのものの可能性を探っていくときの道標になるのではないかと感じています。
記録:加藤千夏(世田谷パブリックシアター研修生)

レクチャー要約(二日分)
これまで私がいわば自明のこととしてきた考えの根の部分、たとえば「民衆演劇」の「民衆」などを次第に疑わしいと思うようになってきた。いろいろな概念を定義するのは簡単だが、あらためてそれは設定可能かという部分を含めてぼく自身が本当に揺らいでいる。そういった眼から、演劇というもの、その幅などについて考えてみたい。
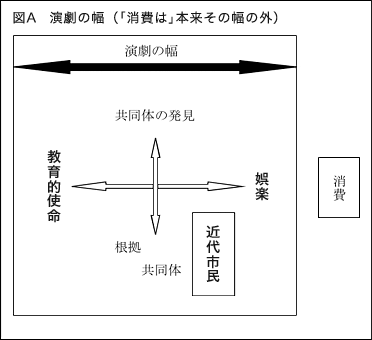 表現は絶対的な「軸」が必ずあるもので、だから評論が重要なのだが、いまの東京ではそれが成り立たず、すべて、「違っていてそれぞれでよい」という相対の論理に回収されてしまっている。また、その表現をどう考えるのか、という座標がないため、「消費」すればよい構造になっている。本来は、図Aのように、消費とは「演劇の幅」の外にあったような気がするが、いまは「娯楽」とごっちゃに認識され、「消費できるものが娯楽的で面白い」というロジックになっている。演劇が、「哲学的なもの(図における教育的使命の部分)」か、「消費商品(図における娯楽:消費と混同されている)」か、という二項対立の問題と認識されている。そういう世の中においては、そもそも「演劇表現」とは何かという部分を問わなくてはいけないが、そこにも、私は実は相当消耗してきている。同じことをずっと言っているのだし…。
表現は絶対的な「軸」が必ずあるもので、だから評論が重要なのだが、いまの東京ではそれが成り立たず、すべて、「違っていてそれぞれでよい」という相対の論理に回収されてしまっている。また、その表現をどう考えるのか、という座標がないため、「消費」すればよい構造になっている。本来は、図Aのように、消費とは「演劇の幅」の外にあったような気がするが、いまは「娯楽」とごっちゃに認識され、「消費できるものが娯楽的で面白い」というロジックになっている。演劇が、「哲学的なもの(図における教育的使命の部分)」か、「消費商品(図における娯楽:消費と混同されている)」か、という二項対立の問題と認識されている。そういう世の中においては、そもそも「演劇表現」とは何かという部分を問わなくてはいけないが、そこにも、私は実は相当消耗してきている。同じことをずっと言っているのだし…。
そうはいっても、人生を降りるのではない以上、「演劇の幅」についてはいぜん考えなくてはなるまい。その問いはつまり、それを享受する「観客」について考えることでもある。そもそも演劇は「共同体」を根拠として存在してきたが、近代になり、「個人」なるものが登場し、「自立的な近代市民」というカテゴリーが派生してきた。「共同体」は遠い神話となり、近代における「変化し続ける進歩という時間」とは別のものとなった。「神話」とは、たとえば天皇制のような、「更新され続ける同一のもの」であるが、それに対して19世紀後半になると次々と「国民国家」が生まれた。国民国家が根拠とするのは、近代市民という「個人」であり、もはや「共同体」ではない。「共同体」はしばしば忘れられる記憶となった。日本のような場合はさておき。
「国民国家」は原則として共通の一「言語」で成り立つもの、共同性ではなく言語でつながった形のない「契約」である。で、近代市民の発達によって「共同体」は消されていき、要らないものとなっていく。国民国家が成立していくにつれ、学校教育が義務化され、「言葉」が基本言語として成立してきた。それは近代演劇の確立とパラレルであり、近代演劇はそういういわば規範的言語を土台として成立していった。それはつまり、「共同体」の根にある、「根拠のない神話」はもう使えなくなるということであり、それが機能しなくなるということであった。これも、日本の場合は、いわば特殊例である。
話を現代に戻して、現在のマスメディアに注目しよう。いまのメディアは、出来事を「こしらえる」。まず「ドラマ」を作り、「本当の出来事」のフリをした、本質など関係のない「出来事性」のようなものを作る。「表現」は「出来事」でなければならないが、消費においては「出来事」はない。「リアルな出来事」を受け取るのが怖いオーディエンス「集合」のため、それを煽るために、「出来事性」で作られた「消費商品」ができていく。演劇はそのなかにあり、もろにその構造を反復しかねない。事実、「もの」を考えて舞台をみることができ、演劇の幅にも対応できる批判力のある「個人」がますます減っている。
ここで一つ、「個人」、つまり、「近代市民」について考える必要が出てくる。公共劇場が想定する観客についても考えなくてはならない。少なくとも日本では「近代市民」は曖昧である。そもそも「公共性」とは日本では最近やっと作りだされてきた概念である、メディア大衆が「近代市民」と抱き合わせに与えられている。「市民」とは与えられるものではないのに。とすると共通するものは、「知」しかないという状況が現在である。また一方で、こうも考える。「近代市民」だけではだめなのだということだ。消えた「共同体」の問題をいぜん考えるときなのではないかとも思っている。
劇場に関していえば、劇場は「考える場所」であってほしいと思う。ただ観劇して消費するという構造を抜けたい。いまの劇団は多く、「消費財」を作っているが、本来はその構造を壊すべきだとぼくは思っている。つまり、観客をこしらえることだ。楽しませるだけじゃない、それこそ(図Aにあるような、演劇の幅のなかでも)教育的使命を帯びた劇をクリティカルにとらえられるような観客ができていくべきだよ。
ここで「記憶」の問題を考えたい。人のお互いの関係の根っこにあるものは、私たちだけの「同時代」だけではないということを言いたい。ハンナ・アーレントは「私の前の世界」と「私の後の世界」を前提とし、そこに存在する者を「近代市民」だとした。「市民」とはそれ以外ありようがない。記憶というのは、そこ(・・)に「宿ってしまうもの」であり「侵入するもの」であり、また「運び込まれてしまったもの」である。つまり、いまの時代に自分が体験したことのみが記憶なのではなく、個を超えた「連続性」のなかに在るものだということだ。それがいわば「身体」である。そこにこそ、広い意味で人の活きた関係性があるのではないか。現代は携帯電話に代表されるような人間関係が中心的といえるだろう。つまり、「私」と「私のまわりの人」だけ、という関係が携帯電話に登録され、そこで世界を密封してしまう。パーソナルスペースは閉じられ、互いに携帯に登録されると安心、という死んだような固定された関係で完結してしまい、生の活きた関係性はなくなる。人間の活きた関係性とは、そこに対して切実であること、舞台というのはその関係性を表わし、毎日違うその瞬間が表出するともいえる。その瞬間に「永遠」がつまっていて、一瞬を繰り返しながらつねに更新されながら積み重なるものである。表現の源とは「近代的な個人/個体を超えたもの」にあり、同時代に収まらない記憶こそが重要なのだといってもいい。簡単にいえば、「地球誕生を見た」と言えるほどの創造=想像力がないと。それはつねに自己批判の作業の繰り返しでもあるのだ。また「記憶」とは、ひとりのものではないということから「共同体の発見」という発想にもつながる。共同体は自明のものでもなく、「つながりの中で創りだされるもの」なのだ。
ここからは、共同体のなかの「矛盾」について話したい。市民共同体のもともとの規範=理想はギリシアの古典古代演劇の共同体である。しかしそのなかに「女」と「奴隷」はいなかったということを見落としてはいけない。これは非常に重要なことである、劇場=市民共同体空間はいつもなんらかの「存在」を排除してきたし、ある暗く深い「闇」をもっているということを。しかしながら、逆説的なことをついでに言うと、そうした「存在」の僭称者、自称「歴史のなかの被害者」たちで劇場を満杯にしてはならない。それは、創造、「闇」を見据えること、記憶の想像力をめぐらせることとは似て非なることだ。劇場が新しい共同体を創ること、一人一人の個々人をつくることと、ここにいる集合、みんながそのまま市民であることとは千里の径庭があるのだ。「である」という状態の現認、そんなことは似非ヒューマニズムである。そこに「民衆演劇」の「民衆」はみいだしえない。冒頭で民衆なるものを疑いはじめていると述べたが、たとえ見失われたとしても、その機軸はつねに必要不可欠であるし、しかも、その機軸は実態的に、なににも、だれにも、還元されえず、仮託されえないというのが要諦だ。東京の演劇人たちはそのことを骨の髄から噛みしめるべきなのだ、まして、「公共の演劇」をつくり、担おうとする者たちは。下手をすると、現在の東京の劇場は、そうしたニセの市民たち、小市民たち(だけ)がひしめいているのだから。新国立劇場研修所の発表公演で、先日アーサー・ミラーの『るつぼ』を観たが、その話はいまの日本の状況とよく似ていると思う。「事実の作成」が先にあって、事実がその後につくられるという状態。「大衆」がさわぐことが「事実」となり、そこから免れようとしたら、地位とか名=権力を持っていなくちゃいけない。それこそ共同体=「市」のなかの権力差という矛盾でもある。劇場に関していうならば、そこに「いない人」が見えるかどうか。チケットの売買契約でない、ひと相互の関係性があるかどうか。そこが重要なのである。
封建制の時代において、貴族は「本質的」に気高いという黙契があった。幻想。実際はどうだったかは措いておいて、そういう像が先に作られ、前提だった。近代以降はその枠が外れ、「個人」が行なうことにフォーカスが当った。なるほど、「進歩」には違いない。資本主義の命題は、「コツコツやればよくなる」というイメージ=約束をこしらえたということだ。ある意味では、個人の選択の幅が広がった。「努力が決定する」という制度が作られた。つまり、人間関係ではなく制度が自分を保障し、すべてが「自発的」(な、と幻想される個人の決定)という「幻想」が作られた。しかし、個人とは資本主義の金がつくるのでない、「気高くあること」はいつでも必要である。それは金銭や権力や映像=イメージがこしらえるのではない、個々人が自分をそうするのである。「表現」はそこにある。
以上のような状況のなかで、権力のない場所をつくるにはやはり「表現」にしかない。本当の意味での「自発的個人」がいて、関係性があるということ、そこに「共同体」や「民衆演劇」への希望をまだかすかに持つ。一人一人の個人が異なりながら、「自発性」でつながりうる場所を根底において、それを座標軸にしないとただの妄想となってしまう。上記にも出た「イメージ」の話にもどるが、「イメージもどき」がイメージをつくり、そのイメージが事実をこしらえるという厄介な状況ではあるが、演劇人の土台は「イメージ」ではだめだろう。本当の「自発的個人」とは「表現できるかどうかの可能性をみずから探っている人」であり、社会ではそうあることはいまやとてもではなく難しいが、そこが重要。
最後に、一種のまとめとして「記憶」の話にもう一度戻ろう。いろいろ見てしまった「私」、いろいろ見ている「私」という、運び込まれてしまったような「記憶」を背負った私ということからすべては始まる。「自発的」と言えるかどうかはまるでわからない、メディアの出来事性に踊らされたような「近代市民」の枠組だけではしょうもないが、しかし、そこを最低限の踏み台としていき、「共同体」の「記憶」の可能性を探ることが重要なのではなかろうか。いまのところ、いぜんひとりの呟きである。
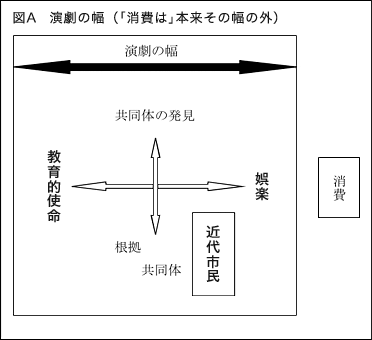
そうはいっても、人生を降りるのではない以上、「演劇の幅」についてはいぜん考えなくてはなるまい。その問いはつまり、それを享受する「観客」について考えることでもある。そもそも演劇は「共同体」を根拠として存在してきたが、近代になり、「個人」なるものが登場し、「自立的な近代市民」というカテゴリーが派生してきた。「共同体」は遠い神話となり、近代における「変化し続ける進歩という時間」とは別のものとなった。「神話」とは、たとえば天皇制のような、「更新され続ける同一のもの」であるが、それに対して19世紀後半になると次々と「国民国家」が生まれた。国民国家が根拠とするのは、近代市民という「個人」であり、もはや「共同体」ではない。「共同体」はしばしば忘れられる記憶となった。日本のような場合はさておき。
「国民国家」は原則として共通の一「言語」で成り立つもの、共同性ではなく言語でつながった形のない「契約」である。で、近代市民の発達によって「共同体」は消されていき、要らないものとなっていく。国民国家が成立していくにつれ、学校教育が義務化され、「言葉」が基本言語として成立してきた。それは近代演劇の確立とパラレルであり、近代演劇はそういういわば規範的言語を土台として成立していった。それはつまり、「共同体」の根にある、「根拠のない神話」はもう使えなくなるということであり、それが機能しなくなるということであった。これも、日本の場合は、いわば特殊例である。
話を現代に戻して、現在のマスメディアに注目しよう。いまのメディアは、出来事を「こしらえる」。まず「ドラマ」を作り、「本当の出来事」のフリをした、本質など関係のない「出来事性」のようなものを作る。「表現」は「出来事」でなければならないが、消費においては「出来事」はない。「リアルな出来事」を受け取るのが怖いオーディエンス「集合」のため、それを煽るために、「出来事性」で作られた「消費商品」ができていく。演劇はそのなかにあり、もろにその構造を反復しかねない。事実、「もの」を考えて舞台をみることができ、演劇の幅にも対応できる批判力のある「個人」がますます減っている。
ここで一つ、「個人」、つまり、「近代市民」について考える必要が出てくる。公共劇場が想定する観客についても考えなくてはならない。少なくとも日本では「近代市民」は曖昧である。そもそも「公共性」とは日本では最近やっと作りだされてきた概念である、メディア大衆が「近代市民」と抱き合わせに与えられている。「市民」とは与えられるものではないのに。とすると共通するものは、「知」しかないという状況が現在である。また一方で、こうも考える。「近代市民」だけではだめなのだということだ。消えた「共同体」の問題をいぜん考えるときなのではないかとも思っている。
劇場に関していえば、劇場は「考える場所」であってほしいと思う。ただ観劇して消費するという構造を抜けたい。いまの劇団は多く、「消費財」を作っているが、本来はその構造を壊すべきだとぼくは思っている。つまり、観客をこしらえることだ。楽しませるだけじゃない、それこそ(図Aにあるような、演劇の幅のなかでも)教育的使命を帯びた劇をクリティカルにとらえられるような観客ができていくべきだよ。
ここで「記憶」の問題を考えたい。人のお互いの関係の根っこにあるものは、私たちだけの「同時代」だけではないということを言いたい。ハンナ・アーレントは「私の前の世界」と「私の後の世界」を前提とし、そこに存在する者を「近代市民」だとした。「市民」とはそれ以外ありようがない。記憶というのは、そこ(・・)に「宿ってしまうもの」であり「侵入するもの」であり、また「運び込まれてしまったもの」である。つまり、いまの時代に自分が体験したことのみが記憶なのではなく、個を超えた「連続性」のなかに在るものだということだ。それがいわば「身体」である。そこにこそ、広い意味で人の活きた関係性があるのではないか。現代は携帯電話に代表されるような人間関係が中心的といえるだろう。つまり、「私」と「私のまわりの人」だけ、という関係が携帯電話に登録され、そこで世界を密封してしまう。パーソナルスペースは閉じられ、互いに携帯に登録されると安心、という死んだような固定された関係で完結してしまい、生の活きた関係性はなくなる。人間の活きた関係性とは、そこに対して切実であること、舞台というのはその関係性を表わし、毎日違うその瞬間が表出するともいえる。その瞬間に「永遠」がつまっていて、一瞬を繰り返しながらつねに更新されながら積み重なるものである。表現の源とは「近代的な個人/個体を超えたもの」にあり、同時代に収まらない記憶こそが重要なのだといってもいい。簡単にいえば、「地球誕生を見た」と言えるほどの創造=想像力がないと。それはつねに自己批判の作業の繰り返しでもあるのだ。また「記憶」とは、ひとりのものではないということから「共同体の発見」という発想にもつながる。共同体は自明のものでもなく、「つながりの中で創りだされるもの」なのだ。
ここからは、共同体のなかの「矛盾」について話したい。市民共同体のもともとの規範=理想はギリシアの古典古代演劇の共同体である。しかしそのなかに「女」と「奴隷」はいなかったということを見落としてはいけない。これは非常に重要なことである、劇場=市民共同体空間はいつもなんらかの「存在」を排除してきたし、ある暗く深い「闇」をもっているということを。しかしながら、逆説的なことをついでに言うと、そうした「存在」の僭称者、自称「歴史のなかの被害者」たちで劇場を満杯にしてはならない。それは、創造、「闇」を見据えること、記憶の想像力をめぐらせることとは似て非なることだ。劇場が新しい共同体を創ること、一人一人の個々人をつくることと、ここにいる集合、みんながそのまま市民であることとは千里の径庭があるのだ。「である」という状態の現認、そんなことは似非ヒューマニズムである。そこに「民衆演劇」の「民衆」はみいだしえない。冒頭で民衆なるものを疑いはじめていると述べたが、たとえ見失われたとしても、その機軸はつねに必要不可欠であるし、しかも、その機軸は実態的に、なににも、だれにも、還元されえず、仮託されえないというのが要諦だ。東京の演劇人たちはそのことを骨の髄から噛みしめるべきなのだ、まして、「公共の演劇」をつくり、担おうとする者たちは。下手をすると、現在の東京の劇場は、そうしたニセの市民たち、小市民たち(だけ)がひしめいているのだから。新国立劇場研修所の発表公演で、先日アーサー・ミラーの『るつぼ』を観たが、その話はいまの日本の状況とよく似ていると思う。「事実の作成」が先にあって、事実がその後につくられるという状態。「大衆」がさわぐことが「事実」となり、そこから免れようとしたら、地位とか名=権力を持っていなくちゃいけない。それこそ共同体=「市」のなかの権力差という矛盾でもある。劇場に関していうならば、そこに「いない人」が見えるかどうか。チケットの売買契約でない、ひと相互の関係性があるかどうか。そこが重要なのである。
封建制の時代において、貴族は「本質的」に気高いという黙契があった。幻想。実際はどうだったかは措いておいて、そういう像が先に作られ、前提だった。近代以降はその枠が外れ、「個人」が行なうことにフォーカスが当った。なるほど、「進歩」には違いない。資本主義の命題は、「コツコツやればよくなる」というイメージ=約束をこしらえたということだ。ある意味では、個人の選択の幅が広がった。「努力が決定する」という制度が作られた。つまり、人間関係ではなく制度が自分を保障し、すべてが「自発的」(な、と幻想される個人の決定)という「幻想」が作られた。しかし、個人とは資本主義の金がつくるのでない、「気高くあること」はいつでも必要である。それは金銭や権力や映像=イメージがこしらえるのではない、個々人が自分をそうするのである。「表現」はそこにある。
以上のような状況のなかで、権力のない場所をつくるにはやはり「表現」にしかない。本当の意味での「自発的個人」がいて、関係性があるということ、そこに「共同体」や「民衆演劇」への希望をまだかすかに持つ。一人一人の個人が異なりながら、「自発性」でつながりうる場所を根底において、それを座標軸にしないとただの妄想となってしまう。上記にも出た「イメージ」の話にもどるが、「イメージもどき」がイメージをつくり、そのイメージが事実をこしらえるという厄介な状況ではあるが、演劇人の土台は「イメージ」ではだめだろう。本当の「自発的個人」とは「表現できるかどうかの可能性をみずから探っている人」であり、社会ではそうあることはいまやとてもではなく難しいが、そこが重要。
最後に、一種のまとめとして「記憶」の話にもう一度戻ろう。いろいろ見てしまった「私」、いろいろ見ている「私」という、運び込まれてしまったような「記憶」を背負った私ということからすべては始まる。「自発的」と言えるかどうかはまるでわからない、メディアの出来事性に踊らされたような「近代市民」の枠組だけではしょうもないが、しかし、そこを最低限の踏み台としていき、「共同体」の「記憶」の可能性を探ることが重要なのではなかろうか。いまのところ、いぜんひとりの呟きである。

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.


