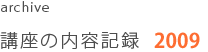


『劇場における公共性』
「公共性と行為/批評の空間 --- H.アーレントの議論に沿って」
2009年8月5日(水) 19時〜21時
斎藤 純一
(早稲田大学教授)
《所 感》
「公共」あるいは「公共性」という語は、きわめて多義的に用いられており、混乱が生じることも少なくない。本講演は、「公共性」の主要な論者の一人であるハンナ・アーレントの議論をベースに、各種関連概念の整理を試みるものである。特に、「他者」と出会う場としての「公共的空間」が重要視され、一人一人がユニークでかけがえのないものとして存在するという「複数性」の重要性が説かれることにより、「声が聞かれない者」としての少数者・非抑圧者の声が聞かれる場としての「公共」の可能性が提示される。「公共の劇場」、「演劇の公共性」を考えるための概念的基盤を提供するものであっただけでなく、今後議論を発展させていく上でも数多くの示唆に満ちた講演であった。
「公共」あるいは「公共性」という語は、きわめて多義的に用いられており、混乱が生じることも少なくない。本講演は、「公共性」の主要な論者の一人であるハンナ・アーレントの議論をベースに、各種関連概念の整理を試みるものである。特に、「他者」と出会う場としての「公共的空間」が重要視され、一人一人がユニークでかけがえのないものとして存在するという「複数性」の重要性が説かれることにより、「声が聞かれない者」としての少数者・非抑圧者の声が聞かれる場としての「公共」の可能性が提示される。「公共の劇場」、「演劇の公共性」を考えるための概念的基盤を提供するものであっただけでなく、今後議論を発展させていく上でも数多くの示唆に満ちた講演であった。
記録:滝口健(シンガポール国立大学)

はじめに
劇場における「公共性」とはなにか。今回は、私が専門にしているハンナ・アーレントの議論をもとに考えてみたい。
アーレントにとっては、「公共的空間」とは、「互いに異なった人々(あるいは価値観)が出会う場」である。つまり、我々が「新しいものに出会う場」として公共の空間は存在する。「出会う」ためには参加involvementが必要不可欠であり、「もし自分が〜だったら」というヴァーチャルな視点も重視される。
カントは「理性の公共的使用」を論じて、「『国家』のために」と考えるのは理性の「私的使用」であり、自分の属する共同体を超える、いわばコスモポリタン的な思考を「公共的」であるとした。アーレントの議論には、カントのこうした考え方の強い影響が見られる。
アーレントにとっては、「公共的空間」とは、「互いに異なった人々(あるいは価値観)が出会う場」である。つまり、我々が「新しいものに出会う場」として公共の空間は存在する。「出会う」ためには参加involvementが必要不可欠であり、「もし自分が〜だったら」というヴァーチャルな視点も重視される。
カントは「理性の公共的使用」を論じて、「『国家』のために」と考えるのは理性の「私的使用」であり、自分の属する共同体を超える、いわばコスモポリタン的な思考を「公共的」であるとした。アーレントの議論には、カントのこうした考え方の強い影響が見られる。
1.公的・公共的publicの3つの含意 (レジュメA)
「公的」あるいは「公共的」と言った場合、次の3つの意味が含まれていると考えられる。すなわち、
- “official”=国家(政府)の活動に関連する
- “common”=「すべて」の人々の関心・利益に関係する
- “open”=誰に対しても開かれている(アクセスが拒まれていない)
これらは、常に調和するわけではなく、相互に対立する場合もある。一例をあげよう。早稲田大学での事例だが、大学構内での表現活動が当局によって規制され、排除・逮捕されるという事件が起こった。これは、大学は“open”な場所である(すなわち、何人も排除されず、自由に表現行為を行いうる)という「公共」と、それを規制しようとする権力、すなわち“official”な「公共」との対立である。そして、そこで問われているのは、守られるべき「すべての人々の関心・利益」、すなわち“common”な「公共性」とはどこまでの範囲であるべきなのか、という問いなのである。
このような問題は、公園などでも発生しうる(例えば渋谷の宮下公園の命名権売却問題など)。元最高裁判事である伊藤正己が提唱した「パブリック・フォーラム論」は、こうした問題を考える際の参考となろう。
このような問題は、公園などでも発生しうる(例えば渋谷の宮下公園の命名権売却問題など)。元最高裁判事である伊藤正己が提唱した「パブリック・フォーラム論」は、こうした問題を考える際の参考となろう。
2.共同体と公共性 (レジュメB)
(1) 「共同体」と「公共性」の対比
「共同体」と「公共性」とは、時として混同して用いられるが、以下に見るごとく、本質的に異なる概念である。「共同体」の特質は「同一性identity」である。「内」と「外」を明確に区別する閉鎖性を持ち、「内」の中では人々が等質であることを前提する。
これに対し、「公共性」の特質は「複数性plurality」にある。個々人はそれぞれがユニークでかけがえのない存在であるととらえられ、そうした「異質」な人々の間に成立するのが「公共性」である。「内」と「外」の区別は存在せず、開放性/非排除性が確保される。
日本においては、「公共性」の語を用いながらも、それを「国民共同体national community」の意味に解する思想と行動が一般にまかり通ってきた。近年も西部邁や小林よしのりらが「公共」の語を使う時、実は「共同体」を語っているのはその一例である。ただし、中世後期、幕末、戦後といった秩序の動揺期に別の形で「公共」が現れたことはあるし、網野善彦の「公界(くがい)」の概念のように、独自の「公共性」の議論をおこなった思想家も存在する。
これに対し、「公共性」の特質は「複数性plurality」にある。個々人はそれぞれがユニークでかけがえのない存在であるととらえられ、そうした「異質」な人々の間に成立するのが「公共性」である。「内」と「外」の区別は存在せず、開放性/非排除性が確保される。
日本においては、「公共性」の語を用いながらも、それを「国民共同体national community」の意味に解する思想と行動が一般にまかり通ってきた。近年も西部邁や小林よしのりらが「公共」の語を使う時、実は「共同体」を語っているのはその一例である。ただし、中世後期、幕末、戦後といった秩序の動揺期に別の形で「公共」が現れたことはあるし、網野善彦の「公界(くがい)」の概念のように、独自の「公共性」の議論をおこなった思想家も存在する。
(2) 公共的空間public spaceの特徴
アーレントによれば、公共的な空間には、以下の3つの特徴がある。
第1は、「利益や価値観を異にする他者の存在」である。逆に言えば、私的空間とは、そうした他者が存在しない空間ということができる。近年では、高級住宅地に見られる“gated community”(高い壁や監視カメラなどによって高度のセキュリティを施した住宅地)の発生や、インターネット上での同趣味の人々だけの集まり(“group polarization”)など、他者を排除し、私的なものを自ら囲い込んでいく動きが加速している。これは、公共的空間の衰退現象ととらえることも可能である。
第2は「他者との交渉」である。他者との新しい関係性が創出される場が「公共的空間」なのであり、ここでは、「他者」は交渉が不可能な者、交渉が不必要な者であると見なされることはない。こうした交渉は、国境を越えて広がっていくことになるだろう。サミュエル・ハンティントンが提唱した、世界は文明ごとに分断され、交渉が不可能であるという「文明の衝突」論と比較対照すると、アーレントの議論の特徴がよく理解できる。
第3は、「他者との交渉が引き起こす脱−中心化」である。アーレントは、マルクス主義に代表されるような「世界には絶対の真理が存在する」という考え方を否定し、ある意見が形成されるには、異なる意見のダイナミックな交換が不可欠であると主張した。それを可能にするのはパースペクティブの複数性である。ここには、個々人が他にかけがえのない存在であり、一人一人の言葉が聞かれなければならないというアーレントの信念が反映している。
第1は、「利益や価値観を異にする他者の存在」である。逆に言えば、私的空間とは、そうした他者が存在しない空間ということができる。近年では、高級住宅地に見られる“gated community”(高い壁や監視カメラなどによって高度のセキュリティを施した住宅地)の発生や、インターネット上での同趣味の人々だけの集まり(“group polarization”)など、他者を排除し、私的なものを自ら囲い込んでいく動きが加速している。これは、公共的空間の衰退現象ととらえることも可能である。
第2は「他者との交渉」である。他者との新しい関係性が創出される場が「公共的空間」なのであり、ここでは、「他者」は交渉が不可能な者、交渉が不必要な者であると見なされることはない。こうした交渉は、国境を越えて広がっていくことになるだろう。サミュエル・ハンティントンが提唱した、世界は文明ごとに分断され、交渉が不可能であるという「文明の衝突」論と比較対照すると、アーレントの議論の特徴がよく理解できる。
第3は、「他者との交渉が引き起こす脱−中心化」である。アーレントは、マルクス主義に代表されるような「世界には絶対の真理が存在する」という考え方を否定し、ある意見が形成されるには、異なる意見のダイナミックな交換が不可欠であると主張した。それを可能にするのはパースペクティブの複数性である。ここには、個々人が他にかけがえのない存在であり、一人一人の言葉が聞かれなければならないというアーレントの信念が反映している。
3.公私区分とその脱構築 (レジュメC)
私的な領域と公的な領域とは区別されうるし、また区別されるべきである。例えば、ある人の個人情報は私的なものとして保護されるべきであり、他者が恣意的にアクセスしてよいものではない。
ただし、「私的」と「公共的」の境界線は固定したものではなく、常に変化しうるものであるということは理解しておく必要がある。例えば、ドメスティック・バイオレンスの問題は、30年前であれば、おそらく「私的な不運」として片付けられてしまっていたであろう。それが、現在では「公的な不正義」として捉えられるようになっている。また、介護の問題も同様に、かつては「私的な不運」として、家族が自らを犠牲にしてケアをおこなうことが当然とされていたが、現在ではそのように自分自身の人生をあきらめざるをえない状況は「公的な不正義」であると認識され、各種措置がとられるようになってきているのである。
ただし、「私的」と「公共的」の境界線は固定したものではなく、常に変化しうるものであるということは理解しておく必要がある。例えば、ドメスティック・バイオレンスの問題は、30年前であれば、おそらく「私的な不運」として片付けられてしまっていたであろう。それが、現在では「公的な不正義」として捉えられるようになっている。また、介護の問題も同様に、かつては「私的な不運」として、家族が自らを犠牲にしてケアをおこなうことが当然とされていたが、現在ではそのように自分自身の人生をあきらめざるをえない状況は「公的な不正義」であると認識され、各種措置がとられるようになってきているのである。
4.公共性の2つのモデル (レジュメD)
「公共性」は次の2つのモデルで捉えることができる。1つは、ハーバーマスが提唱した、討議/熟議deliberationにもとづく意思形成・意志決定を重要視する「コミュニケーション・モデル(アゴラ・モデル)」である。このモデルでは、価値観の異なる人々が理解し、受容できる「公共的理由」が、ある主張を正当化すると考える。
もう1つは、ニーチェやブルクハルトが重要視した、観客を前にした技量の競い合いの場として「公共性」を捉える「劇場モデル(アゴーン・モデル)である。このモデルは「現れ」を奪われてきた人々に、言葉や行為への応答可能性を開くものであると考えられる。すなわち、「公共的な自己」=政治的存在者として行為しうるアリーナを開くことにより、そこに存在する人々の声を聞き取ることを可能にしていくことがイメージされている。
アーレントの公共性論は、上記の2つのモデルの両方の側面を含むものである。しかし、ユダヤ人のように「現れ」を奪われた人々への深い関心から、アーレントにとっては第2のモデルの方がより重要であった。ただし、アーレントは、「現れ」を奪われたのは、奪われた人々自身にも責任があるのだとしている点に留意すべきである。その上で、「公共的な自己」を実現するアリーナをどのように開いていくのかがアーレントの課題となったのである。
もう1つは、ニーチェやブルクハルトが重要視した、観客を前にした技量の競い合いの場として「公共性」を捉える「劇場モデル(アゴーン・モデル)である。このモデルは「現れ」を奪われてきた人々に、言葉や行為への応答可能性を開くものであると考えられる。すなわち、「公共的な自己」=政治的存在者として行為しうるアリーナを開くことにより、そこに存在する人々の声を聞き取ることを可能にしていくことがイメージされている。
アーレントの公共性論は、上記の2つのモデルの両方の側面を含むものである。しかし、ユダヤ人のように「現れ」を奪われた人々への深い関心から、アーレントにとっては第2のモデルの方がより重要であった。ただし、アーレントは、「現れ」を奪われたのは、奪われた人々自身にも責任があるのだとしている点に留意すべきである。その上で、「公共的な自己」を実現するアリーナをどのように開いていくのかがアーレントの課題となったのである。
5.行為者の公共性 (レジュメE)
先にも述べたとおり、アーレントの公共性論においては、「他者」の存在が決定的に重要である。「自由であること」とは、「公共的空間に現れること」と同義であり、「行為および言葉において他者と出会うこと」を意味する。
ここでいう「行為」Actionとは、予測不可能・代替不可能なものであり、「正常」な規範の反復にズレ、あるいは裂け目を作り出すものである。この点で、「行為」は「正常」な規範を単純に反復する「行動」behaviorとは明確に区別される。こうした「裂け目」を導入することにより、規範を越えた「新たな始まり」をもたらす可能性があるものと理解される。
また、「現れ」とは、個々の言葉・行為に対する判断である。つまり、属する集団(例えば「女」、「ユダヤ人」、「障碍者」、「ゲイ」など)のステレオタイプな理解(これを「表象」representationと呼ぶ)をおこなうのではなく、個々人をユニークでかけがえのない存在と捉えることが前提されている。
ここでいう「行為」Actionとは、予測不可能・代替不可能なものであり、「正常」な規範の反復にズレ、あるいは裂け目を作り出すものである。この点で、「行為」は「正常」な規範を単純に反復する「行動」behaviorとは明確に区別される。こうした「裂け目」を導入することにより、規範を越えた「新たな始まり」をもたらす可能性があるものと理解される。
また、「現れ」とは、個々の言葉・行為に対する判断である。つまり、属する集団(例えば「女」、「ユダヤ人」、「障碍者」、「ゲイ」など)のステレオタイプな理解(これを「表象」representationと呼ぶ)をおこなうのではなく、個々人をユニークでかけがえのない存在と捉えることが前提されている。
6.観察者の公共性 (レジュメF)
従来、公共性を理解しようとする試みは行為者に注目するのが一般的であった。しかし、「劇場モデル」の公共性を考える時、観察者に注目することがきわめて重要である。ここでいう「観察者」とは、単にスペクタクルを自分のために消費する「観客」ではなく、むしろ「批評家」としての位置を占めることになる。観察者は、行為者に比べて(1)「劇」の一部分にとらわれることなく全体を捉えることができる、(2)利害関係にとらわれる危険性が小さいため、より客観的な判断が可能である、という点において、「批評家」として大きなアドバンテージがある。
観察者は相互の判断・批評を交換することで批評空間を形成し、意見交換の領域としての公共性を構成する。ここで提起される評価は、過去や同時代における事柄に向けられるだけではなく、「未来の可能性へ変形される」(アーレント『アウグスティヌスの愛の概念』)ことが重要である。
ただし、こうした評価は、普遍的・絶対的な真理を前提として行われるべきものではない。ここでも「複数性」が確保され、さまざまなパースペクティブからの評価を通じて一般性generalityを獲得することが必要である。このような他者とのコミュニケーションを可能にし、判断の基準となる「共通感覚」は所与のものとして与えられてはいない。「共通感覚」は、判断・批評の交換を通じてパフォーマティブに再形成されるのである。
行為者は不特定の観察者(=他者)の判断にさらされることを予期しなければならず、観察者は行為者の現れに応答する責任を負っている。ただし、行為者と観察者の区別は固定的なものではない。むしろ、ある人が同時に行為者であり観察者であることの方が常態に近い。このため、各人のうちで「思考−判断すること」と「他者と協調して行為する」こととが並立し、相互に緊張関係が維持されることになるのである。
観察者は相互の判断・批評を交換することで批評空間を形成し、意見交換の領域としての公共性を構成する。ここで提起される評価は、過去や同時代における事柄に向けられるだけではなく、「未来の可能性へ変形される」(アーレント『アウグスティヌスの愛の概念』)ことが重要である。
ただし、こうした評価は、普遍的・絶対的な真理を前提として行われるべきものではない。ここでも「複数性」が確保され、さまざまなパースペクティブからの評価を通じて一般性generalityを獲得することが必要である。このような他者とのコミュニケーションを可能にし、判断の基準となる「共通感覚」は所与のものとして与えられてはいない。「共通感覚」は、判断・批評の交換を通じてパフォーマティブに再形成されるのである。
行為者は不特定の観察者(=他者)の判断にさらされることを予期しなければならず、観察者は行為者の現れに応答する責任を負っている。ただし、行為者と観察者の区別は固定的なものではない。むしろ、ある人が同時に行為者であり観察者であることの方が常態に近い。このため、各人のうちで「思考−判断すること」と「他者と協調して行為する」こととが並立し、相互に緊張関係が維持されることになるのである。
7.言説の空間とイメージの空間
公共性についての重要な議論を展開した思想家にユルゲン・ハーバーマスがいる。彼にはナチスドイツがおこなった、拍手喝采による「街頭の公共性」、すなわちイメージあるいはシンボルの空間としての公共性への根強い反感があった。そのため、ハーバーマスは主著『公共性の構造転換』において、17〜18世紀に成立した公共性を言説の空間として描くとともに、現代はイメージの公共性による中世の再生=公共性の再封建化がおこっていると批判した。ここには、アドルノが唱えた文化産業論、つまり文化が批評の空間としての機能を喪失し、娯楽の空間=文化産業へと変質してしまっているという批判からの強い影響が見られる。
アドルノ−ハーバーマスにより、イメージ・シンボルによる「劇場型民主主義」=ポピュリズム=悪という図式は一般に広く流布するようになった。しかしながら、ポピュリズムは民主主義には常に内在するものであり、いくら討議が活発に行われたとしても、完全には排除することが不可能な要素であることも事実である。
さらに、シンボルによって人々のイメージを喚起していくことは、必ずしも「理」を排除することを意味しないのである。例えば、フランスにおいては、街頭でのデモや集会など、「街頭の公共性」がしばしば表明されている。この場では討議が行われているのではなく、イメージ(ディスプレイ)によって「ノン」が表明されているのである。イメージは人々の感情や情念を反映しているが、その一方で、規範的な判断をも含んでいる。つまり、イメージは「情」だけではなく、「理」にも働きかけている側面も大きいのである。アジアのゲリラ演劇などにも同様のことが言える。
「言説の空間か、イメージの空間か」という二者択一の問題として捉えるのは誤りである。むしろ、公共性にはこの2つが共に存在すると理解すべきだと思われる。
アドルノ−ハーバーマスにより、イメージ・シンボルによる「劇場型民主主義」=ポピュリズム=悪という図式は一般に広く流布するようになった。しかしながら、ポピュリズムは民主主義には常に内在するものであり、いくら討議が活発に行われたとしても、完全には排除することが不可能な要素であることも事実である。
さらに、シンボルによって人々のイメージを喚起していくことは、必ずしも「理」を排除することを意味しないのである。例えば、フランスにおいては、街頭でのデモや集会など、「街頭の公共性」がしばしば表明されている。この場では討議が行われているのではなく、イメージ(ディスプレイ)によって「ノン」が表明されているのである。イメージは人々の感情や情念を反映しているが、その一方で、規範的な判断をも含んでいる。つまり、イメージは「情」だけではなく、「理」にも働きかけている側面も大きいのである。アジアのゲリラ演劇などにも同様のことが言える。
「言説の空間か、イメージの空間か」という二者択一の問題として捉えるのは誤りである。むしろ、公共性にはこの2つが共に存在すると理解すべきだと思われる。
質疑応答
Q1: 将来、公共劇場で仕事をしたいと考えている。それに関連する問題意識から質問をしたい。
(1)公共劇場において、ある特定のアーティストの表現が突出した場合、メディアなどが 批判的に取り上げれば、表現を抑えられてしまうような局面が発生するかもしれない。 それに対抗するためには、どのような言語を持つことができるだろうか。
(2)日本では「公共性」が「共同体」と混同されて用いられたという話があった。 欧米ではどうだろうか。いつからアーレント的な「公共」が語られるようになったのか。
(1)公共劇場において、ある特定のアーティストの表現が突出した場合、メディアなどが 批判的に取り上げれば、表現を抑えられてしまうような局面が発生するかもしれない。 それに対抗するためには、どのような言語を持つことができるだろうか。
(2)日本では「公共性」が「共同体」と混同されて用いられたという話があった。 欧米ではどうだろうか。いつからアーレント的な「公共」が語られるようになったのか。
(1)ハーバーマスは批評の存在しない状態、日常言語によるコントロールが不可能な状態を
「文化的貧困化」と呼んだ。こうした状況に対応するための一つの方法は、対抗的知識
人・専門家を動員することである。これは科学技術の世界では実際におこなわれている。
しかし、演劇の分野でそれが可能かどうかについては疑問がないわけではない。
(2)かつては「公共的」の語には、ハイデガーやキルケゴールが提示した、同調圧力の渦 まく「公共」というイメージがつきまとっており、アカデミックな世界や社会運動の 現場では、80年代まではネガティブなイメージで語られることが多かった。アメリカ でハーバーマスの『公共性の構造転換』が翻訳されたことも手伝って、議論が盛り上 がったのは90年代、特に90年代の後半からである。しかし、フランスにおいては、 いまも「公共」は「共和的」と同義のものとして用いられている。
(2)かつては「公共的」の語には、ハイデガーやキルケゴールが提示した、同調圧力の渦 まく「公共」というイメージがつきまとっており、アカデミックな世界や社会運動の 現場では、80年代まではネガティブなイメージで語られることが多かった。アメリカ でハーバーマスの『公共性の構造転換』が翻訳されたことも手伝って、議論が盛り上 がったのは90年代、特に90年代の後半からである。しかし、フランスにおいては、 いまも「公共」は「共和的」と同義のものとして用いられている。
Q2: アーレントが自分の境遇を政治的な言葉で語ることに感動した。どうやったらそこまで自分を追い込んでいけるのだろうか。
アーレントが『イェルサレムのアイヒマン』を書いたとき、「あなたにはユダヤの娘として
考えてほしい」という批判を受けた。これに対し、彼女は「私はユダヤ人として考えたこ
ことはない。ある人を愛することはできるが、集団を愛することはできない」と答えてい
る。「○○としてどう思うか」という質問には、質問者が聞きたいと思っている答えに誘導
しようとする権力が作動している。アーレントはこの種の権力に非常に敏感に反応した。
このような考え方が一つのヒントになるのではないか。
Q3: 最近、江古田にあった小劇場が、消防の査察が入ったことで閉鎖に追い込まれるという
事例があった。その一方で公共劇場は次々に建てられているという状況がある。そうした
現状を踏まえ、昔の劇場と今の劇場とを比べると、どのような違いがあると感じるか。
自分が劇場に足繁く通っていたのは、紅テント、黒テント、さらには野田秀樹の時代
だった。特にテント劇場においては、ドラマティックな要素が異化効果として駆使されて
いたように思う。ゲリラ的に「出会ってしまう」、すなわち思わぬ接続が起こった方がイン
タラクションが生じやすいと言えるだろう。こうした演劇は、現在では消失してしまって
いるのではないか。どこか「予期できる演劇」となり、必ずしも思考を触発しないものに
なっているように思われる。
Q4: 行為者と観察者の関係において「観察者からの応答が不在の場合、行為者の現れは生起
しない」とされているが、「応答なし」も応答の一つであると考えることはできないか。
ここで「応答が不在」と言っているのは、「受けとめられずに終わる」ことを意味している。
例えば、従軍慰安婦の問題は、90年代になってから初めて語られたわけではない。ただ、
それ以前には「聞かれなかった」のである。これが「応答の不在」である。サルトルが
「ユダヤ人問題とは非ユダヤ人問題である」と言ったのはまさにこの意味であり、非ユダ
ヤ人によって受けとめられなければユダヤ人の「現れ」は生起しないのである。
「応答」とは新たに「関係がつくられること」と言い換えてもいいだろう。聞き手の不在
という状況は実際には頻発していると考えられるのではないだろうか。

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.


