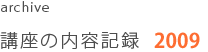


『日本の公共劇場を考える』
Vol.8「公共劇場の『公共性』を、原点から再考する」
2009年9月11日(金) 19時〜21時
伊藤 裕夫
(富山大学芸術文化学部教授)
《所 感》
行政では「公共性」を考える場合「市民に開かれた劇場」(アクセスの保障)に重点をおいて論じられることが多い。もちろん、この点も重要ではあるが、ギリシャ悲劇に遡って、考えていくと、「公共性」のもう一つのあり方として「舞台芸術の創造における公共性」、つまり、舞台芸術の中身に関する公共性があると捉えることができる。ギリシャ悲劇は一種の裁判劇であり、社会から排除された人の数奇な運命を市民が、神々と共に見て論じ合う場を提供していた。一般社会では否定され排除されてしまう類の人々の話から、ある普遍性を引きだし、秩序や政治的ルールに潜むジレンマを認識する。この行為は、政治的公共性を理解するために不可欠であり、民主主義社会を保つ要であろう。講師は、これを「文化的昇華」と呼んでいる。この種の「公共性」は、アメリカの陪審員制度や日本の天神信仰にも見ることができる。それでは日本の公共劇場はどうであろうか。 本講座では2種類の「公共性」を念頭に置き、公共劇場の現状を捉えるとともに、昨今話題となっている裁判員制度を新しい視点で見直す機会となった。
行政では「公共性」を考える場合「市民に開かれた劇場」(アクセスの保障)に重点をおいて論じられることが多い。もちろん、この点も重要ではあるが、ギリシャ悲劇に遡って、考えていくと、「公共性」のもう一つのあり方として「舞台芸術の創造における公共性」、つまり、舞台芸術の中身に関する公共性があると捉えることができる。ギリシャ悲劇は一種の裁判劇であり、社会から排除された人の数奇な運命を市民が、神々と共に見て論じ合う場を提供していた。一般社会では否定され排除されてしまう類の人々の話から、ある普遍性を引きだし、秩序や政治的ルールに潜むジレンマを認識する。この行為は、政治的公共性を理解するために不可欠であり、民主主義社会を保つ要であろう。講師は、これを「文化的昇華」と呼んでいる。この種の「公共性」は、アメリカの陪審員制度や日本の天神信仰にも見ることができる。それでは日本の公共劇場はどうであろうか。 本講座では2種類の「公共性」を念頭に置き、公共劇場の現状を捉えるとともに、昨今話題となっている裁判員制度を新しい視点で見直す機会となった。
記録:有賀沙織(東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学研究専攻修士課程)

はじめに
これまで公共劇場についての議論は、「公共の劇場」か「劇場の公共性」か」が主であったが、ここで話題にする公共劇場は、「公共(行政)設立の劇場」ではなく、「劇場=(演劇)の公共性」が担保されている劇場をいうことで捉えておく。もちろん劇場を「担保」するのが行政であることは構わないが、民間―個人であろうが、市民社会であってもよいと考える。まず、劇場の公共性とは何かを抑えておく必要がある。劇場の公共性を考えると、日本では「市民に開かれた劇場」と言われているが、果たしてこれだけで十分なのだろうか? 話の一部は、斉藤純一の著書『公共性』を参考にする。
1.「公共劇場」の理念型
○歴史的にみた「公共劇場」
近代市民社会(=国民国家)がつくりあげてきた文化<制度(institution)>の一つである。市民社会のニーズに応えた舞台芸術の創造と、その成果を広く市民社会が享受する基盤である。
○「文化制度」の意義
具体的な例は、博物館・美術館やオーケストラである。国によって、違ったタイプのものができる。政府が中心となってつくられたところもあれば、市民階級等々が切り開いていったところもある。例を出すならば、一つはルーブル美術館がある。ルーブル美術館は、特権階級が美術品を集め、それを整理するために学芸員が生まれた。フランス革命がおこるまでは、これらの美術品は一般に公開されることはなかった。1793年、ルーブル美術館が一部公開されるようになり、それによって、収集、保管だけでなく、公開する美術館の制度が出来てきた。ここでの「公開」とは、市民階級が共有財産として所持できるということである。もう一つの例として、オーケストラ=定期コンサートがある。近代のオーケストラは18世紀に各地、特にドイツで多く生まれた。オーケストラは、宮廷、オペラ劇場、教会等々に雇われていた楽師たちが、市民階級によって集められ、当時の新しい音楽であった交響曲を演奏するための定期的なコンサートというかたちでつくられていった。オーケストラは市民階級が聞くためできた仕組みといってよいだろう。
○舞台芸術の特殊性
近舞台芸術は、オペラやバレエを除くと、必ずしも特権階級の専有物ではなかった。シェイクスピア劇についていえば、テムズ川の南岸にグローブ座が造られたが、一般の市民が主な観客であった。王もパトロンとして関係はあったが、王の専有物としてあったわけではない。その点が音楽、美術とは違った要素であった。
古代ギリシャにおいては、演劇は祭と非常に深く結びつくかたちで存在していた。「共同体(コミュニティ)」に根ざした祭祀が起源となっており、このような現象は各地に見られる。中世・近世にあっても、演劇は教会や寺社と深い関わりを持っていた。日本でも寺社が保護するかたちで、猿楽、田楽が広がっていった。では、演劇は庶民のためにあったのかというと、そうでもない面もいくつかある。基本的には都市生活の中で祝祭空間として市民・民衆の支持を受けて発展してきたものと言えるが、市民の支持を権力が利用してきた例は数多くあった。例えばフランスの絶対王制の時代に、1680年、ルイ14世がコメディフランセーズを創り上げた。意図は、フランス統一の一つの柱とすべく文化的統一をめざすものであった。これは国王が新興市民階級を味方に取り込んでいく仕組みであり、言い換えれば文化的統合を目的とする文化政策であった。この使命をもってコメディフランセーズはつくられていった。旧勢力である教会や貴族の対抗策としても演劇はうまく用いられた。たとえば、モリエールのタルチェフといった種類の芝居は、教会や貴族を諷刺した作品である。事実、ルイ14世はこの上演をバックアップしようと試み、最初は挫折するものの再起を図り、この種の芝居が上演されていくようになる。演劇は民衆の支持を受けていた故に、統一国家をつくっていこうとする新しい支配者にとっては、旧支配者層を倒していくための道具として用いられた性格が強い。政治的要素を持つ文化装置として、文化政策に取り込まれていったと見ることができる。
このように演劇も含め文化制度は、市民革命前後につくられたものとして今日に至っている。もともと国民の統合手段としてあったが、19世紀になってくると、市民生活において、教養や娯楽を提供し、社会的ニーズに応えていくものとして発展してきた。
演劇はコミュニティと深く関わっている芸能である。近世、近代においては、創造と公開により、演劇をつくること、みることの双方がされるようになった。これを通じて祝祭としての演劇、つまり“幻想の共同体”をつくる装置として公共劇場がつくられていった歴史を見ることができる。
文化政策は必ずしも芸術文化を支援するものではなく、近代の国民・国家を創り上げていく手段として用いられてきた。演劇は博物館・美術館・オーケストラよりも一般民衆に対してインパクトを持つものとして、文化政策に対しては主役の地位を占めていたと言ってよいだろう。
古代ギリシャにおいては、演劇は祭と非常に深く結びつくかたちで存在していた。「共同体(コミュニティ)」に根ざした祭祀が起源となっており、このような現象は各地に見られる。中世・近世にあっても、演劇は教会や寺社と深い関わりを持っていた。日本でも寺社が保護するかたちで、猿楽、田楽が広がっていった。では、演劇は庶民のためにあったのかというと、そうでもない面もいくつかある。基本的には都市生活の中で祝祭空間として市民・民衆の支持を受けて発展してきたものと言えるが、市民の支持を権力が利用してきた例は数多くあった。例えばフランスの絶対王制の時代に、1680年、ルイ14世がコメディフランセーズを創り上げた。意図は、フランス統一の一つの柱とすべく文化的統一をめざすものであった。これは国王が新興市民階級を味方に取り込んでいく仕組みであり、言い換えれば文化的統合を目的とする文化政策であった。この使命をもってコメディフランセーズはつくられていった。旧勢力である教会や貴族の対抗策としても演劇はうまく用いられた。たとえば、モリエールのタルチェフといった種類の芝居は、教会や貴族を諷刺した作品である。事実、ルイ14世はこの上演をバックアップしようと試み、最初は挫折するものの再起を図り、この種の芝居が上演されていくようになる。演劇は民衆の支持を受けていた故に、統一国家をつくっていこうとする新しい支配者にとっては、旧支配者層を倒していくための道具として用いられた性格が強い。政治的要素を持つ文化装置として、文化政策に取り込まれていったと見ることができる。
このように演劇も含め文化制度は、市民革命前後につくられたものとして今日に至っている。もともと国民の統合手段としてあったが、19世紀になってくると、市民生活において、教養や娯楽を提供し、社会的ニーズに応えていくものとして発展してきた。
演劇はコミュニティと深く関わっている芸能である。近世、近代においては、創造と公開により、演劇をつくること、みることの双方がされるようになった。これを通じて祝祭としての演劇、つまり“幻想の共同体”をつくる装置として公共劇場がつくられていった歴史を見ることができる。
文化政策は必ずしも芸術文化を支援するものではなく、近代の国民・国家を創り上げていく手段として用いられてきた。演劇は博物館・美術館・オーケストラよりも一般民衆に対してインパクトを持つものとして、文化政策に対しては主役の地位を占めていたと言ってよいだろう。
○日本の現実
我が国においては、「公共劇場」はながらく政府が設置した劇場であると見られてきた。しかも、建物を中心に考えられてきた。最近では「新しい公共」という概念で捉えられるようになり、公共とは市民が担うものであることが前提となって、市民に開かれた劇場を「公共劇場」と呼ぼうという議論が盛んに行われるようになってきた。そして劇場作りの構想に市民が参加していく。運営に参加していく「市民参加」が話題になり、公共劇場の議論の中核を占めるようになってきた。
日本の行政の中では、「市民に開かれた」という概念は、劇場のスペースが開かれているというケースが多い。誰もが使用可能という考え方である。市民演劇をつくる、アウトリーチを行う。ワークショップを行うといった活動も議論の対象になってくる。しかしながら、抜け落ちているものはないか。ここでは演劇そのものの公共性が抜け落ちているのではないかということを考えていく。
日本の行政の中では、「市民に開かれた」という概念は、劇場のスペースが開かれているというケースが多い。誰もが使用可能という考え方である。市民演劇をつくる、アウトリーチを行う。ワークショップを行うといった活動も議論の対象になってくる。しかしながら、抜け落ちているものはないか。ここでは演劇そのものの公共性が抜け落ちているのではないかということを考えていく。
◆公共劇場のもつ公共性
*アクセス面における公共性―普及教育、アウトリーチ、ソーシャルインクルージョンといった議論、バリアフリーの建築など。
*創造の公共性―芸術そのものが持っている中味の公共性。(共同体)社会のニーズにこたえていくことの公共性。例)水戸芸術館、ピッコロ劇場、静岡県舞台芸術センター、世田谷パブリックシアターといったところの取り組み。
演劇の場合は2つの公共性が同時に行われる。しかし、アクセスの方の議論にいきがちである。一方で、演劇人がつくった劇場(民間の劇場)、たとえば、アゴラ劇場、鳥の劇場は、アクセスの公共性はもちろんだが、創造の公共性の方に力を入れている。私はこちらに可能性があるのではないかと考える。
*創造の公共性―芸術そのものが持っている中味の公共性。(共同体)社会のニーズにこたえていくことの公共性。例)水戸芸術館、ピッコロ劇場、静岡県舞台芸術センター、世田谷パブリックシアターといったところの取り組み。
演劇の場合は2つの公共性が同時に行われる。しかし、アクセスの方の議論にいきがちである。一方で、演劇人がつくった劇場(民間の劇場)、たとえば、アゴラ劇場、鳥の劇場は、アクセスの公共性はもちろんだが、創造の公共性の方に力を入れている。私はこちらに可能性があるのではないかと考える。
2.「公共性」とは
○歴史的にみた「公共劇場」
- 国家に関する公的なもの(official)
- 特定の誰かではなく、すべての人々に共通するもの(common)=共通性
- 誰に対しても開かれている。(open)=公開性
publicという概念は、語源からみると、全ての人に対して開かれているというopenという意味が原義であったと考えられる。“open”という概念は、これは推測だが、ローマの時代に都市国家が形成されていく中で、すべての人に開かれたという概念から、すべての人に共通するもの“common”の意味に変わってきたのではないかと考えている。そして近代になると、国家に関する公という意味合いを持ち、officialとなったのではないかと考えられる。斉藤の『公共性』の1)、2)、3)の説明を、私は3)、2)、1)と歴史的に変化したと見ている。
「誰に対しても開かれている=すべての人に開かれている」
ここでは、openの概念がcommonの概念に変化していくところに注目をしていきたい。この変化が起こったのは古代ギリシャ、あるいはローマの社会である。古代の都市共同体は、共同体構成員である市民の社会であった。その社会が都市国家を形成していていくプロセスの中で共通の関心事を明確化していく。それに伴い、共通性を押し付けていく動きが起こっていったと考えられる。斉藤の『公共性』は、commonという概念には権利の制限や受任を求める力、個性の力を押さえつける不特定多数の圧力といった側面があると述べている。
こういった公共性をめぐる内部抗争が生まれてくる中で、他方で演劇が生まれていった。ここを検討してみたい。公共性の3つの側面については先に触れたが、officialという意味の公共性の概念は、最近は否定されている。しかしながら、公開性と共通性の違いについては議論が非常に少ない。演劇の公共性、市民的公共性の議論の中には出てこないが、斉藤もハンナ・アーレントの考えを用いて指摘しているように、私は「公開性」「共通性」の差を認識しておかないと、議論があいまいになると考えている。たとえば、NPOがそうだ。「公開性」「共通性」の差(内部矛盾)を明確にしていなかったために、NPOの活動がすべて小泉改革の中に取り込まれてしまったように思われる。
こういった公共性をめぐる内部抗争が生まれてくる中で、他方で演劇が生まれていった。ここを検討してみたい。公共性の3つの側面については先に触れたが、officialという意味の公共性の概念は、最近は否定されている。しかしながら、公開性と共通性の違いについては議論が非常に少ない。演劇の公共性、市民的公共性の議論の中には出てこないが、斉藤もハンナ・アーレントの考えを用いて指摘しているように、私は「公開性」「共通性」の差を認識しておかないと、議論があいまいになると考えている。たとえば、NPOがそうだ。「公開性」「共通性」の差(内部矛盾)を明確にしていなかったために、NPOの活動がすべて小泉改革の中に取り込まれてしまったように思われる。
○舞台芸術の公共性
公開性とは、すべてのひとに開かれている。共通性とは、“特定の誰か”ではなくすべての人に共通するというかたちで、特定の誰かを排除することにより、すべての人から“特定の誰か”を排除する。“特定の誰か”というのは、例えば特権をもった人たちで今日で言えば、天下り役人のような人たちかもしれないが。
公共性の概念の中に“特定の誰か”を排除することで限定する点が大きなポイントである。すなわち、commonの方の公共性は、特定の誰かを排除することによって、すべての人に開かれていることではなく、その他大勢というように変化していったということがポイントである。
論理学的にいうと、「すべての人に開かれた」=「たった一人のひとをも排除しない」ということである。つまり、たった一人の声をどのように拾い上げていくかが、公共性の中で議論されていかなければいけない問題である。
政治的原理においては、政治的公共性は、何らかのかたちで世界を動かしていくためには、たったひとりのためにこだわっていくことはできない。従って、すべての人に開かれたという公共観では統治はできない。それゆえ、政治は多数決原理を生み出し、社会的運用を遂げてきた。政治的には否定するべきことではないが、文化的には疑問が残る。
公共性の概念の中に“特定の誰か”を排除することで限定する点が大きなポイントである。すなわち、commonの方の公共性は、特定の誰かを排除することによって、すべての人に開かれていることではなく、その他大勢というように変化していったということがポイントである。
論理学的にいうと、「すべての人に開かれた」=「たった一人のひとをも排除しない」ということである。つまり、たった一人の声をどのように拾い上げていくかが、公共性の中で議論されていかなければいけない問題である。
政治的原理においては、政治的公共性は、何らかのかたちで世界を動かしていくためには、たったひとりのためにこだわっていくことはできない。従って、すべての人に開かれたという公共観では統治はできない。それゆえ、政治は多数決原理を生み出し、社会的運用を遂げてきた。政治的には否定するべきことではないが、文化的には疑問が残る。
3.(舞台)芸術の「公共性」
○古代ギリシャの都市国家
古代ギリシャの市民社会とは奴隷所有者である「市民」たちの「都市共同体=共和国」であった。そこでは奴隷、女性、異民族、その他“特定の誰か”(特異な存在)の政治的排除が前提されていた。しかし一方で「誰に対しても開かれた」公開性理念も色濃く残っていた。
この2つの公共性を橋渡ししたのが、ギリシャ演劇であって、それによってアテネの民主主義が保たれていた。排除されていったものに対する慰撫、救いが必要になり、この結実として演劇があったのではないか。こういう視点でギリシャ悲劇について考察してみたい。
この2つの公共性を橋渡ししたのが、ギリシャ演劇であって、それによってアテネの民主主義が保たれていた。排除されていったものに対する慰撫、救いが必要になり、この結実として演劇があったのではないか。こういう視点でギリシャ悲劇について考察してみたい。
○ギリシャ悲劇の意義
ギリシャ悲劇に登場する主人公は、その多くが特異な存在で、神々の怒り、特異な運命に遊ばれた人たちである。これらの人たちをとりあげ、美しい詩文にしてこれを年1回上演する。そのなかに市民がさまざまなかたちで参加している。特異なものに触れ合う機会を提供する役割として古代ギリシャの演劇が存在していたのではないか。
私は、「ギリシャ悲劇は一種の裁判劇」と捉えている。一万人以上の市民が一緒になってこれを見る。それを神々とともに論じている。そして、自分たちの抱えている一種のジレンマをとらえることによって、政治的公共性の意味を理解していく。このような役割をギリシャ悲劇は持っている。私は、これを「文化的昇華」という言い方で提起できないかと考えている。
非常に特異なものを認識することが、平和や秩序には欠かせない。しかしそれは単に、裁判員裁判のように、裁判に市民が立ちあうということではない。ただ、裁判員裁判もある面、民主主義を維持していくには必要だと感じている。
アメリカの民主主義は、古代ギリシャの直系であり、非常によいとハンナ・アーレントは随所で述べているが、今日のアメリカを見ると、必ずしもハンナ・アーレントの考えに賛成できない点は多々あるものの、たとえば陪審員制度をみてみると、共同体を構成している人たちが、何らかの意味で共同体の抱えている膿から生まれてきた特異な犯罪の裁判に立ちあっていく。こういったことが、民主主義を維持していく要になっていると考えるとギリシャ悲劇の果たしたことは、アメリカでは陪審制度が果たしている。日本の裁判員については、そうなるかはわからないが、このような側面があると指摘することはできるのかもしれない。このような要素をギリシャ悲劇にみていきたい。
美術や音楽は、個人的で私的なことがベースになっていることから言えば、いわゆる公共性がないように思われるが、人々に見られるという行為を通して、共感を及ぼさせることで、多くの人を惹きつけている。
日本の天神信仰について考えてみると、菅原道真は政治的には失脚して太宰府に流され、その怨念が都にさまざまな祟りをもたらした。それを鎮めるために怨霊を祀り、天満宮をつくりあげて天神信仰が、学問の神、文化の神として多くの人に信仰され、受け継がれていくことは、ギリシャ悲劇と通ずるところがあると言えるであろう。怨霊を祭るということには、特異性の中にある普遍性を引きだしていく、そうすることによって、一つの「文化的昇華」というかたちで社会的安定を達していく面が見えてくる。
私は、「ギリシャ悲劇は一種の裁判劇」と捉えている。一万人以上の市民が一緒になってこれを見る。それを神々とともに論じている。そして、自分たちの抱えている一種のジレンマをとらえることによって、政治的公共性の意味を理解していく。このような役割をギリシャ悲劇は持っている。私は、これを「文化的昇華」という言い方で提起できないかと考えている。
非常に特異なものを認識することが、平和や秩序には欠かせない。しかしそれは単に、裁判員裁判のように、裁判に市民が立ちあうということではない。ただ、裁判員裁判もある面、民主主義を維持していくには必要だと感じている。
アメリカの民主主義は、古代ギリシャの直系であり、非常によいとハンナ・アーレントは随所で述べているが、今日のアメリカを見ると、必ずしもハンナ・アーレントの考えに賛成できない点は多々あるものの、たとえば陪審員制度をみてみると、共同体を構成している人たちが、何らかの意味で共同体の抱えている膿から生まれてきた特異な犯罪の裁判に立ちあっていく。こういったことが、民主主義を維持していく要になっていると考えるとギリシャ悲劇の果たしたことは、アメリカでは陪審制度が果たしている。日本の裁判員については、そうなるかはわからないが、このような側面があると指摘することはできるのかもしれない。このような要素をギリシャ悲劇にみていきたい。
美術や音楽は、個人的で私的なことがベースになっていることから言えば、いわゆる公共性がないように思われるが、人々に見られるという行為を通して、共感を及ぼさせることで、多くの人を惹きつけている。
日本の天神信仰について考えてみると、菅原道真は政治的には失脚して太宰府に流され、その怨念が都にさまざまな祟りをもたらした。それを鎮めるために怨霊を祀り、天満宮をつくりあげて天神信仰が、学問の神、文化の神として多くの人に信仰され、受け継がれていくことは、ギリシャ悲劇と通ずるところがあると言えるであろう。怨霊を祭るということには、特異性の中にある普遍性を引きだしていく、そうすることによって、一つの「文化的昇華」というかたちで社会的安定を達していく面が見えてくる。
おわりに
○「劇場の公共性」を担う公共劇場
公共性には「アクセスの公共性」と「舞台芸術の創造における公共性」の二つがある。どうしても行政はアクセスの公共性に重点を置いている。しかしながら、舞台芸術の創造性における公共性を議論しているからアクセスの公共性は無視しているかというと、そうではない。
「市民に開かれた劇場」=「アクセスの保障」を必要条件と考える。加えて「舞台芸術の公共性」を十分条件と考える。行政がアクセスの公共性を保障する行為は、アクセスする場で行われている内容に合意がされなければ、実行されない。つまり、アクセスの対象が認められる必要がある。日本の場合は、演劇に関して、舞台芸術に対しては行政側にその考え方が欠如しており、他国では、議論されている。教育に関しては、教育の権利、義務教育といったアクセスの保障が行政によってされている。これは、あくまで教育に公共性があることが前提であり、合意されているからである。舞台芸術はアクセスの公共性だけが突出してしまい、その対象である芸術に対する議論については敬遠しがちであるのが現状といえる。
「舞台芸術の公共性」は「特異性」を表現することであり、芸術家の創造が前提にないと舞台芸術の公共性は見えてこない。したがって、特異性を表現する芸術集団の存在とその活動を担保するシステム(人材や経済基盤など)の双方が存在していないといけないのではないか。その機能が専属劇団になるのか、プロデュースという役割になるのかは、さまざまだが、いずれにせよ、現段階では舞台芸術の公共性に対してあまり議論がされない。行政における「公共性」の議論は、かたちとしての「公共性」の話につい行きがちであるという傾向は否めない。この問題を打開する可能性は、私設劇場(芸術家が主宰する劇場)にあると考えている。公設の劇場の限界は、不特定多数のアクセスの保障という「圧力」から「特異性」の排除を招くこととなる。一方、私設の劇場は、お金がない、施設の面で恵まれていないといった弱みはあるものの、主宰する芸術家による「特異性」の創造・表現から生まれる可能性がある。
「市民に開かれた劇場」=「アクセスの保障」を必要条件と考える。加えて「舞台芸術の公共性」を十分条件と考える。行政がアクセスの公共性を保障する行為は、アクセスする場で行われている内容に合意がされなければ、実行されない。つまり、アクセスの対象が認められる必要がある。日本の場合は、演劇に関して、舞台芸術に対しては行政側にその考え方が欠如しており、他国では、議論されている。教育に関しては、教育の権利、義務教育といったアクセスの保障が行政によってされている。これは、あくまで教育に公共性があることが前提であり、合意されているからである。舞台芸術はアクセスの公共性だけが突出してしまい、その対象である芸術に対する議論については敬遠しがちであるのが現状といえる。
「舞台芸術の公共性」は「特異性」を表現することであり、芸術家の創造が前提にないと舞台芸術の公共性は見えてこない。したがって、特異性を表現する芸術集団の存在とその活動を担保するシステム(人材や経済基盤など)の双方が存在していないといけないのではないか。その機能が専属劇団になるのか、プロデュースという役割になるのかは、さまざまだが、いずれにせよ、現段階では舞台芸術の公共性に対してあまり議論がされない。行政における「公共性」の議論は、かたちとしての「公共性」の話につい行きがちであるという傾向は否めない。この問題を打開する可能性は、私設劇場(芸術家が主宰する劇場)にあると考えている。公設の劇場の限界は、不特定多数のアクセスの保障という「圧力」から「特異性」の排除を招くこととなる。一方、私設の劇場は、お金がない、施設の面で恵まれていないといった弱みはあるものの、主宰する芸術家による「特異性」の創造・表現から生まれる可能性がある。
質疑応答
Q1: 民間、私設の劇場、公共の施設における専属の劇団、創造集団がいる場合は、たとえば、
市民が、自分たちが発表をする場がかなり限られている現状があると思うが、その時に、
市民がプロデュースするということを考えると、それは専属集団がいることによって制約
されることについてどう考えるか?
市民に開かれたということを「アクセス」という観点についてのみ焦点をおくと、その
矛盾は当然おきる。専属の舞踊団、劇団が優先使用すれば、市民がそこを使う自由が制限
されていくことは問題と思われるであろう。しかしながら、舞台芸術の公共性を担保する
システムとして考えると違ってくる。市民たちが舞台を使って公演活動をしていくことは
あくまで、アクセスの一環であって、公共劇場の持っている公共性から見た場合は、一面
的なものであると考えている。確かにその問題はあるし、その批判は起こっているが、公
共劇場のあり方として、そうでない議論をしたほうがよいのではと考えている。
Q2: 「特異性」を芸術家と特定してしまっているが、市民は、その芸術家ではないのか。
市民がプロデュースしていくことは特異性ではないのか。
市民がプロデュースしていくことは特異性ではないのか。
市民がプロデュースすることは公共性とは考えていない。むしろ市民が「見る」という
ことについては、考えなければいけないところがあると思う。見るということに対しては、
消極的に考えられているが、実は、ここにギリシャの観客が持っていた積極性があること
を考えていかなければならない。
Q3: 市民に開かれた劇場、舞台芸術の公共性、この二つの柱で話がすすめられているが、今ある
公共劇場に両方を相容れて考えていくのは難しいのではないか?
そうすると、二つの公共劇場が別々にあると、一つは今でいうハコモノみたいなもの、 一つは特異性を前面に打ち出しているもの、その二つの劇場の姿があるのか。特異性を前面 に出したものと考えると、資金がある民間の劇場が積極的に「舞台芸術の公共性」に向かい 合うべきなのか、そういった考えを持っているのか。
そうすると、二つの公共劇場が別々にあると、一つは今でいうハコモノみたいなもの、 一つは特異性を前面に打ち出しているもの、その二つの劇場の姿があるのか。特異性を前面 に出したものと考えると、資金がある民間の劇場が積極的に「舞台芸術の公共性」に向かい 合うべきなのか、そういった考えを持っているのか。
公共の劇場、私設の劇場とも、公共劇場になりうる。自分たちの行く道を選ぶべきである。
かつてまとめた報告書に三つの方向性を示した。第一は「創造型の劇場」、第二は「プロ
デュース型機能の劇場」娯楽や教養を提供するという意味合いをもつ劇場、第三は「コミュ
ニティ・アートセンター型の劇場」。ただ、その時に「創造型の劇場」が、あいまいであり、
一番行政から批判を受けたりする。そこで、突き詰めて考えていく必要があると考えるよう
になった。二つの公共性はむしろ個人の芸術家が主宰している劇場、たとえばアゴラ劇場、
にしすがも創造舎、鳥の劇場の活動のような演劇そのもので勝負をしていこうとしている
劇場が挙げられる。
Q4: 日本の公共劇場で海外との共同制作はどのように見えてくるか?
日頃考えていることとしては、創造においては異質なものをどのようにみるかが重要。とん
でもないことが入ってくる。それを理解しようとする。それを表現していく。国際的な共同
制作は、言葉、コミュニケーションも違ってくるから、多様性を保証していくのはいいので
はないか。日本の場合は、オフィシャルという意味の「公共劇場」が主流だが、欧米の劇場
には専属の芸術家集団がいる。そういった面で、外国とコラボレーションするのは劇場の
運営についても新しい風を吹き込むことができるのではないか。
欧米の劇場としても、最近は惰性で運営されていることもあることから、よい刺激となり うる。アジアとの共同制作は、他者性(特異性)を感じられるのではないだろうか。
欧米の劇場としても、最近は惰性で運営されていることもあることから、よい刺激となり うる。アジアとの共同制作は、他者性(特異性)を感じられるのではないだろうか。
Q5: 創造性のある演劇を育てることについて、教育との関係についてはどう考えるか?
スタンダードの形成が非常に遅れている。スタンダードのない芸術は空回りしてしまう。
かつては新劇がスタンダードとしてとらえられ、アングラがそれに反する動きとして
あった。しかし、教育があれば、演劇の公共性が担保されるかというと、そうでもない。
Q6: 見るという観客の行為についての議論が抜け落ちているということだった。芸術の公共性を
通して、文化的昇華機能というように触れられているが、観客の立場からは、公共劇場の公
共性をとらえることはむずかしい。単なる消費者としてあるような気がするがどう考えるか。
斉藤先生の本の中でも「批評」というかたちで触れているが、裁判劇に立ちあっているかの
ごとく感じること。なぜそんな悲劇が起こっているのか、思いをはせていく。人間の業を、
演劇を通してみていく。国家をどのようなかたちで守り、発展させていくのか。
その媒介として、見るという行為を用いている。
その媒介として、見るという行為を用いている。
Q7: 裁判員、批評もそうだが、話す場がないということが問題としてあげられていたが、
話す場がないという他に話すための作法がない。演劇のことについて話すことというのは、
趣味の問題も関わってきて、非常に繊細な面があると思うが、その点はどう考えるか?
裁判員は何らかの判断を迫られている。傍観者としてではなく、共同体を維持していく中に
必要。たとえば演劇を考えたときには、文化を共有しあっているコミュニティの中で、議論
をしあう場を作った方がよい。ギリシャ劇の場合では、投票みたいなことを行って、順位を
決めたことがあった。開票については、偶然を入れるために、集まった票の半分を捨てて
しまう。判断はするが、正しいか間違っているかはわからない。目に見えない判断を入れる
ことによって、合理性を高めていく。偶然性を入れると、面白いと思う。

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.


