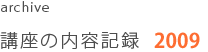


『地域社会と芸術』
Vol.3「死と生を接続する場として:お寺のコミュニケーションデザイン」
2009年12月22日(水) 19時〜21時
山口 洋典
(浄土宗應典院主幹・應典院寺町倶楽部事務局長)
《所 感》
お寺で演劇やアートを行う―― 一見、奇抜とも思われる発想である。應典院では年間50本の演劇公演を始めとしてさまざまなイベントが行われ、若者の創作の場として開放されているお寺である。なぜ、お寺なのか?あるいは、なぜ、アートなのか?本講座では應典院の建設に至る経緯、及びその理念と活動の紹介を通し、お寺とNPO、そして宗教施設と創造活動との協働関係が決して奇抜な結びつきではなく、豊かな可能性をもたらすものであることが示唆される。お寺を劇場としてみたとき、そこに浮かび上がってくるのは生死を越えた色濃い他者とのつながりである。少子高齢化に続く多死社会の到来、さらに葬送における自己決定とサービス化が進む中で、生と死のあり様は急速に変容を遂げてきた。その中で薄れつつある寺院が「公」であることの感覚、あるいは他者とのつながりを結び直す場としての寺院、それらを温故知新で再興を図ったのが應典院であり、その媒介となるのが演劇やアートである。そもそもお寺は芸術・文化の発祥との関係が深く、日常の時間から切り離された場として劇場とも関連性がある。つまり、演劇やアートは歴史的に寺院と密接な結びつきを持っていた。しかし、そこに見出される生と死の見つめ直し、他者とのつながりの結び直しという意義は、現代だからこそ求められるものである。應典院の実践はお寺の原点回帰の営みである。そして、表現という営みを「他者とのつながり」という観点から問い直すことで、表現の場、ひいては劇場と地域とのつながりを考え直す機会をも、應典院は与えてくれる。
お寺で演劇やアートを行う―― 一見、奇抜とも思われる発想である。應典院では年間50本の演劇公演を始めとしてさまざまなイベントが行われ、若者の創作の場として開放されているお寺である。なぜ、お寺なのか?あるいは、なぜ、アートなのか?本講座では應典院の建設に至る経緯、及びその理念と活動の紹介を通し、お寺とNPO、そして宗教施設と創造活動との協働関係が決して奇抜な結びつきではなく、豊かな可能性をもたらすものであることが示唆される。お寺を劇場としてみたとき、そこに浮かび上がってくるのは生死を越えた色濃い他者とのつながりである。少子高齢化に続く多死社会の到来、さらに葬送における自己決定とサービス化が進む中で、生と死のあり様は急速に変容を遂げてきた。その中で薄れつつある寺院が「公」であることの感覚、あるいは他者とのつながりを結び直す場としての寺院、それらを温故知新で再興を図ったのが應典院であり、その媒介となるのが演劇やアートである。そもそもお寺は芸術・文化の発祥との関係が深く、日常の時間から切り離された場として劇場とも関連性がある。つまり、演劇やアートは歴史的に寺院と密接な結びつきを持っていた。しかし、そこに見出される生と死の見つめ直し、他者とのつながりの結び直しという意義は、現代だからこそ求められるものである。應典院の実践はお寺の原点回帰の営みである。そして、表現という営みを「他者とのつながり」という観点から問い直すことで、表現の場、ひいては劇場と地域とのつながりを考え直す機会をも、應典院は与えてくれる。
記録:山口真由(東京大学大学院学際情報学府文化・人間情報学コース博士課程)

1.應典院・應典院寺町倶楽部とは
◎應典院・應典院寺町倶楽部の概要
*應典院
浄土宗大蓮寺の搭頭寺院であり、創建は1614年。第二次世界大戦の際、大阪大空襲による大蓮寺の完全焼失の際、類焼。コンクリート打ちっぱなしのモダンな外観と劇場仕立ての本堂や研修室を備えた現在の建物は、1997年に再建されたもの。シアトリカル應典院と名づけられた本堂ホールをはじめ、寺院の施設が活用され、さまざまな演劇やアート活動が行われている。
*應典院寺町倶楽部
應典院を拠点に文化・芸術活動を行い、市民活動や芸術・文化活動を通じて、市民活動の基盤づくりや人材育成を行うNPO組織。ワークショップや各種イベントの開催、会報「サリュ」の発行、その他自治体の事業も受託するなどの多彩な活動を行っている。
◎メディアによる應典院の紹介
著者:上田紀行(文化人類学者、東京工業大学大学院准教授)
「がんばれ仏教!」の内容に基づき、上田紀行さんが寺院を訪問。應典院では秋田光彦住職と対談。
→日本で一番若者の集まる寺(年間およそ3万人)として紹介される
◎應典院は「3ない寺院」
「檀家がいない・お墓を持たない・葬式を出さない」
-
檀家がいない
→檀家制度に頼らず、寺院での事業運営もNPOを設立して市民にゆだねている。 -
お墓を持たない
→亡くなった後で何かをするのとは異なる形での他者との関わり方を探る。 -
式を出さない
→「イベント寺」として個人の想いや願いに応える催しの場を提供する。
浄土宗の寺院ではあるものの積極的な布教活動が行われず、各種の催しでは宗教的側面が前面には打ち出されていない。事業の運営を行うNPO団体である寺町倶楽部への加入も「入信」ではなく「入会」であり、退会も自由である。お寺と会員とがサポーターかつパートナーという関係性のもとに、活動が行われている。
◎なぜお寺で演劇やアートを行うのか?
(1) お寺にそもそも備わっていた機能との親和性
- 近代以降の行政システムが担う機能、つまり「学び−教育」「癒し−福祉」「楽しみ−芸術・文化」の3つの機能をお寺はもともと備えていた。また、そうした場であったからこそ日本の社会に根をおろすことができた。
cf.勧進興行…建立や修繕の費用を募るため、お寺では芸人を呼んで奉納芸を行い、観覧料を徴収していた。一説にはその「ただ見」を防ぐために柵を設けたのが劇場の始まりであると言われている。つまり、お寺はそもそも劇場の機能を内包していたのだ。 - そもそも人生の最後に必ずやってくる「死」というイベントはお寺で演出されてきた。その場の担い手が僧侶であったことを考えると、お寺でイベントを行うという発想自体は新奇なものではない。
(2) 現代の生活における「お寺」の位置づけ
- 純粋に数だけを見ればお寺はコンビニの倍ほども存在しているが、日常的にお寺を訪れる人は極めて少なく、多くは観光目的である。しかし「寺子屋」「駆け込み寺」「縁切り寺」などといった言葉が今でも残るように、生活文化の拠点としてのお寺の記憶は、現代もなお、完全になくなってしまったわけではない。
- かつてお寺が中心的に担ってきた葬送は葬儀社によって行われるようになった。それに伴い、遺族が自らの悲しみと向き合う時間がサービスの中から選択する時代が到来している。
- 宗教法人として固定資産税がかからないお寺は、現代社会の中で守られている立場にある。それに対する社会への応答責任、レスポンシビリティをお寺は果たす必要がある。
(3) 時代と共振する仏教の可能性
-
守る時代からつくる時代へ
…信者に対して啓蒙するのではなく、ともに学び「共生」するお寺、あるいは僧侶への変容が必要である。 - 死や生と向き合うことに対して、従来の葬儀に止まらない多様なサービスの需要がある。
-
ふだんの生活とは異なった場、人と人がつながる場の提供
…生きづらい社会の中で癒しを求める人が多く、「癒し」ブームが到来する中で、時間の流れを少しずらして記憶を再生したり、誓いを立てたりする空間を提供する。敷地も広く、比較的郊外に建てられることの多いお寺では騒音も少なく、ふだんの生活から切り離された場を提供できるという点で、お寺はやはり劇場の営みと重なる。
應典院の活動は「寺を開く」試みであるとも評されている。しかし、ただ多くの人が立ち寄ってくれることをもって「寺が開かれた」としているのではない。あくまでも共同体の中での「公(おおやけ)」性、人とのつながりを感覚として取り戻すことのできる場を提供することが應典院の活動の主眼である。
2.お寺に若い人たちが集まることの意味
◎應典院の再建に至る経緯
*1995年:創作の場としての機能を備えた現在の應典院の建設計画が始まる。この年には阪神・淡路大震災、オウム真理教に関連した一連の事件が続いて起こり、わずかな間に住職は若者の希望と絶望を同時にみることになった。
應典院を若者の創作の場として開放した住職である秋田光彦さんは、仏教をもとにしているオウム真理教の信者にとっては、お寺が一つの「風景」でしかなかったことに衝撃を受けた。
應典院を若者の創作の場として開放した住職である秋田光彦さんは、仏教をもとにしているオウム真理教の信者にとっては、お寺が一つの「風景」でしかなかったことに衝撃を受けた。
→お寺はそもそも、かけがえのない先祖が祀られている場であるはず。しかしそのことが、「わたし」と「あなた」のいのちの結び目となることにうまく連結していない。このような内に閉じたお寺の現状を危惧した。
→人と人の関係性を結び直すきっかけを提供するものとしてのコミュニケーションデザインを強く意識して再建のプランニングがなされた。
→人と人の関係性を結び直すきっかけを提供するものとしてのコミュニケーションデザインを強く意識して再建のプランニングがなされた。
*1996年:再建の基本理念がまとめられた「應典院コンセプトブック」がまとめられる。
扇町ミュージアムスクエア(2003年に閉館)などの文化事業を行っていた関係者(大阪ガスの研究部門の社員や関連するプランニング会社のスタッフ)をはじめ、90年代前半における大阪の文化シーンをつくった人たちによって計画が進められた。スーパーバイザーは橋爪紳也さん(当時・京都精華大学助教授)が務めた。
*1997年:現在の應典院の建物が完成 キャッチコピー「人は、あなたに出会って、わたしになる」 →かけがえのない「わたし」と「あなた」とのつながりを結び直すことへの提案
扇町ミュージアムスクエア(2003年に閉館)などの文化事業を行っていた関係者(大阪ガスの研究部門の社員や関連するプランニング会社のスタッフ)をはじめ、90年代前半における大阪の文化シーンをつくった人たちによって計画が進められた。スーパーバイザーは橋爪紳也さん(当時・京都精華大学助教授)が務めた。
*1997年:現在の應典院の建物が完成 キャッチコピー「人は、あなたに出会って、わたしになる」 →かけがえのない「わたし」と「あなた」とのつながりを結び直すことへの提案
人は他者と出会うことによって初めて、自分がどんな人間であるかを知ることができる。そしてその他者は、今現在目の前にいる人に限らず、たとえばご先祖様であるかもしれない。絶対的に超越した他者という手がかりや物語を与えることのできるお寺だからこそ、現代社会に対して関係性の結び直しを提案することができる。
◎應典院の活動
年間約50本の演劇、10本前後の映画、70程度のワークショップを行っている。
*主な事業
-
「寺子屋トーク」(教育)
…出会いと気づきと学びと交流の場。実践家や研究者による講演会、シンポジウムを開催。 -
「いのちと出会う会」(福祉)
…生と死の連続性を見つめる学びあいの場。医療や看護、ターミナルケアを題材に、 市民が語りあう例会や施設の見学会を行っている。 -
「コモンズフェスタ」(アート)
…表現活動を通した社会的な問題提起と人材育成の場。毎年開催されるアートと社会活動の 総合文化祭であり、毎年掲げられるテーマに即したイベントが開催される。 -
「エンディング見本市」(葬送)
…大蓮寺・エンディングを考える市民の会との連携。人生のエンディングを生き切るための 情報提供を目指し、お葬式やお墓、エンディングサポートに関わる展示を行った。
3.各種プロジェクトが導く「協働想起」
◎取り組みの前提としての「生死一如」
「生死一如」とは:生と死をコインの裏表のような関係にあるものとしてとらえる、仏教の考え方。
告別式で「あなたに恥ずかしくない生き方をしていきます」「あなたのぶんまで生きます」といった言葉が述べられるように、死んだ後も「あなた」という存在は消えるものではない。ただ、生きている時間と死んでいる時間の境目となる一線を越えることには恐怖が伴う。しかし、この「死ぬ」ことの意味の捉え方が変わってきているのが現代である。
告別式で「あなたに恥ずかしくない生き方をしていきます」「あなたのぶんまで生きます」といった言葉が述べられるように、死んだ後も「あなた」という存在は消えるものではない。ただ、生きている時間と死んでいる時間の境目となる一線を越えることには恐怖が伴う。しかし、この「死ぬ」ことの意味の捉え方が変わってきているのが現代である。
◎社会の変容と「死」の変質
*自宅での死から施設での死へ
人口動態調査をみると、自宅での死と施設(病院、サナトリウムなど)での死の割合が1975年−1976年を境に反転している。調査が行われ始めた1951年には自宅での死が82.5%、施設での死が11.6%であったのに対し、2008年の調査では自宅での死はわずか12.6%であるのに対し、施設での死が84.9%となっている。
*多死社会の到来
少子高齢化社会が到来し、高齢者が増えるとともに死者の数も増えた。言わば、多死社会が到来している。これも人口動態調査によると、1951年時点では年間83万人であった死者数が2008年では114万人にのぼっている。さらに20年後には150万人、ピーク時で年間173万人の死者が生じるという推計結果も出ている。
人口動態調査をみると、自宅での死と施設(病院、サナトリウムなど)での死の割合が1975年−1976年を境に反転している。調査が行われ始めた1951年には自宅での死が82.5%、施設での死が11.6%であったのに対し、2008年の調査では自宅での死はわずか12.6%であるのに対し、施設での死が84.9%となっている。
*多死社会の到来
少子高齢化社会が到来し、高齢者が増えるとともに死者の数も増えた。言わば、多死社会が到来している。これも人口動態調査によると、1951年時点では年間83万人であった死者数が2008年では114万人にのぼっている。さらに20年後には150万人、ピーク時で年間173万人の死者が生じるという推計結果も出ている。
◎生きることへのお寺の存在意義
社会が膨大な数の死者を抱えるようになる中で、その「死」をどう扱うかが問題となる。例えば死に臨む本人や遺族が納得していないのに、死、あるいは死者を悼む時間が、効率性の名のもとに処理されることが危ぶまれる。その一方、自分の死に臨み、告別式で流される音楽や祭壇に飾られる花を予め選択し託しておくなど、「死」の扱いに関する自己決定が重視され、「死」の個別化・個人化が進んでいる。しかし、多死に向かう社会の中で必要とされるのは、そのように効率化・個別化されたものとして「死」を処理することではなく、公共性の高い問題としてきちんと死者を扱い、今という時間で「死者と」もっと愚直に向き合い生きる姿勢を見出していくことである。
また、葬送の文化は、死の床についた人を「看取り」、「死」に立ち会うことで逝く人を「見送り」、葬儀式に臨むというプロセスをたどることで継承されてきた。そして、仏式であれば僧侶が在籍する「葬儀」の部分と、友人たちが故人を悼む「告別式」の部分があって葬儀式は構成されているが、告別式から故人の「供養」がはじまる。ただし、現代ではこの「供養」の時間をどう過ごすかに重点がおかれつつある。しかし、死後の「供養」の時間は、どう「看取る」か、どう「見送る」かという生前の時間の過ごし方が大きな影響を与える。特に、施設での死の増加に伴い、家族が臨終の場に立ち会わないことも珍しいことではなくなっている今、この「看取り」の時間も変容しつつある。よって、看取りの時間を共に過ごさないことによって、見送りのかたちや、供養のかたちが多様化してきていると考えられる。
また、葬送の文化は、死の床についた人を「看取り」、「死」に立ち会うことで逝く人を「見送り」、葬儀式に臨むというプロセスをたどることで継承されてきた。そして、仏式であれば僧侶が在籍する「葬儀」の部分と、友人たちが故人を悼む「告別式」の部分があって葬儀式は構成されているが、告別式から故人の「供養」がはじまる。ただし、現代ではこの「供養」の時間をどう過ごすかに重点がおかれつつある。しかし、死後の「供養」の時間は、どう「看取る」か、どう「見送る」かという生前の時間の過ごし方が大きな影響を与える。特に、施設での死の増加に伴い、家族が臨終の場に立ち会わないことも珍しいことではなくなっている今、この「看取り」の時間も変容しつつある。よって、看取りの時間を共に過ごさないことによって、見送りのかたちや、供養のかたちが多様化してきていると考えられる。
→お寺は先祖供養というかたちで死者を軸とした活動を行ってきた。しかしこのような時代の変化に対し、必ずしも死者だけを軸としなくてもよいのではないか。いのちの尊さや死の恐怖までをも含め、もっと色々な他者と関わる場を提供する可能性がある。
→Collaborative remembering…「協働想起」の場の創出
「協働想起」とは、「何か」のために「誰か」を思い起こすことである。思いが馳せられる限り、その人の「いのち」は終わらない。つまり、いつか生命には終わりが来るが、一方で終わることのない「いのち」を考えることができる。ただし、思い起こす「誰か」とは、必ずしも死者というわけではない。もっと、他者に思いを馳せる場を創出し、さまざまな他者と関わることによって、誰かの、そして私の「いのち」を考えるきっかけを与えることができれば、個人化・個別化された判断ばかりが優先されやすい現代社会で、お寺はじゅうぶんにその存在意義を果たすことができる。
→Collaborative remembering…「協働想起」の場の創出
「協働想起」とは、「何か」のために「誰か」を思い起こすことである。思いが馳せられる限り、その人の「いのち」は終わらない。つまり、いつか生命には終わりが来るが、一方で終わることのない「いのち」を考えることができる。ただし、思い起こす「誰か」とは、必ずしも死者というわけではない。もっと、他者に思いを馳せる場を創出し、さまざまな他者と関わることによって、誰かの、そして私の「いのち」を考えるきっかけを与えることができれば、個人化・個別化された判断ばかりが優先されやすい現代社会で、お寺はじゅうぶんにその存在意義を果たすことができる。
◎死と向き合う、<いのち>と向き合う
典院での活動事例〜特に死を正面から扱ったもの。
(1)エンゼルメイク
京都南病院の看護師らによる院内の演劇サークルによるエンゼルメイクを題材とした公演と、医師・葬儀社・僧侶らによる講演会がセットで行われた。(2006年10月1日)
京都南病院の看護師らによる院内の演劇サークルによるエンゼルメイクを題材とした公演と、医師・葬儀社・僧侶らによる講演会がセットで行われた。(2006年10月1日)
*エンゼルメイクとは
死化粧をする看護師らの取り組みのことを指す。小林光恵氏らの定義によれば、医療行為による侵襲や病状などのために失われた生前の面影を可能な範囲で取り戻すための顔の造作を整える作業や保清を含んだ「ケアの一環としての死化粧」とされている。医師による死亡判定がなされた後、死後処置の段階において行われ、グリーフケアの意味合いも併せ持つ行為という。
病院で死を迎える場合、家族が頻繁に見舞いに来られないと、看取りまでの時間の多くを病院スタッフが共に過ごすことになる。そのため。看護師もまた、遺族の一人となる。そこで、医療行為としてではなく、最後のお世話をしたいという気持ちのもとに、看護師らによる最後のケアの一環としてエンゼルメイクが行われつつある。先に示した人口動態調査でも章化のように、人を見送ることが多い病院ではあるが、そこで働く人々にとって、人の死が悲しいものであることには変わりがない。そうして生前と同じように整えられた姿に、遺族は新たな悲しみを呼び起こされることもある。しかし、このことによって、改めて亡くなったこと悲しむ時間、つまり死ときちんと向かい合う時間が創出されるのだ。そもそも看取りの場面に立ち合った人々によってなされるエンゼルメイクは、手元供養(故人のお骨をお寺やお墓に納骨することなく、ペンダントや指輪などにして常に身につけていられるかたちにするもの)のように、個人化された死のニーズに応えるサービスには見出されにくい死のあり方、病院での死のあり方を考えさせてくれる。
死化粧をする看護師らの取り組みのことを指す。小林光恵氏らの定義によれば、医療行為による侵襲や病状などのために失われた生前の面影を可能な範囲で取り戻すための顔の造作を整える作業や保清を含んだ「ケアの一環としての死化粧」とされている。医師による死亡判定がなされた後、死後処置の段階において行われ、グリーフケアの意味合いも併せ持つ行為という。
病院で死を迎える場合、家族が頻繁に見舞いに来られないと、看取りまでの時間の多くを病院スタッフが共に過ごすことになる。そのため。看護師もまた、遺族の一人となる。そこで、医療行為としてではなく、最後のお世話をしたいという気持ちのもとに、看護師らによる最後のケアの一環としてエンゼルメイクが行われつつある。先に示した人口動態調査でも章化のように、人を見送ることが多い病院ではあるが、そこで働く人々にとって、人の死が悲しいものであることには変わりがない。そうして生前と同じように整えられた姿に、遺族は新たな悲しみを呼び起こされることもある。しかし、このことによって、改めて亡くなったこと悲しむ時間、つまり死ときちんと向かい合う時間が創出されるのだ。そもそも看取りの場面に立ち合った人々によってなされるエンゼルメイクは、手元供養(故人のお骨をお寺やお墓に納骨することなく、ペンダントや指輪などにして常に身につけていられるかたちにするもの)のように、個人化された死のニーズに応えるサービスには見出されにくい死のあり方、病院での死のあり方を考えさせてくれる。
(2)遺影プロジェクト
ヘアメイクアーテイストらの撮影とライターによる聞き撮りという、性格の異なる2つの遺影展の開催
ヘアメイクアーテイストらの撮影とライターによる聞き撮りという、性格の異なる2つの遺影展の開催
-
ノッキング・オン・ヘヴンズ・ドア」(2007年3月1日〜21日)
…東京芸術大学でヘアメイクを学ぶ南雲由子さんが、今生きている人にヘアメイクを施し、z カメラマンが遺影を撮影して展示するコンセプチュアル・アートの試み。地域性が反映されるかどうかも検証するため、後に東京でも同様のプロジェクトが行われた。 -
写真展「遺影、撮ります:76人のふだん着の死と生」(2007年10月10日〜14日)
…朝日新聞大阪版の夕刊で野寺夕子さんにより76回連載されてきた生前の「遺影」撮影と、それぞれの人生の物語をまとめたプロジェクトが出版されることになった。それを記念した遺影の展示会とトークショーが行われた。
(3)写真展「好奇心星人の挑戦:森木忠相写真展」(2008年3月1日〜15日)
小児がんのために5歳で入院し、17歳で亡くなった男性が、病院で撮影した写真を展示した遺作展。大阪市立大学附属病院の協力のもと、大阪市立大学と應典院寺町倶楽部の協働によって開催された。
小児がんのために5歳で入院し、17歳で亡くなった男性が、病院で撮影した写真を展示した遺作展。大阪市立大学附属病院の協力のもと、大阪市立大学と應典院寺町倶楽部の協働によって開催された。
…同じ闘病経験のある人や彼と同じ時間を病院で過ごした人々が写真を眺めて故人を振り
返る、まさに「協働想起」の場。特に同じ小児がんを患い完治した人やその家族にとって
は、もう一度自らの生に思いを馳せる機会ともなった。
4.まとめ
◎「教導」から「協働」へ
應典院が目指しているのは、死生観の結び直しの拠点となることである。そのため、他者と出会い、会話を交わし、関係性をとり結ぶことによって「わたしとは何か」をもう一度考え直す場が催しを通じて生み出され続けている。そこでは、教えによって信者を「教導」するというお寺の営みとは異なる側面を見出すことができる。すなわち、さまざまな人と手を結んで「協働」していくお寺のあり方である。そのためのチェンジ・エージェント(change agent:変革代理人)となったのがアーティストであった。特にアーティストの関心は、何かを「美化」することではなく「異化」することに向いている。彼らが持ち込む奇想天外な発想は、従来の発想をリセットしてもう一度やり直すためのきっかけを与えてくれる。そうして「あなた」に問いかけがなされ、問われた「あなた」が変わる。そして、変わった誰かがまた、誰か何かを変えていく可能性を生む。
“Art”を日本語にすると「表現」であるが、「表現」をもう一度英語にすると“express”となる。つまりアートの活動は「想いを届ける」ということである。表現という行為はその根本に、「届ける」という姿勢をも持ちあわせるのだ。そのため、アーティストが、まさに<いのち>をかけて届けようとすることに対して、それらを届ける場である應典院の方では最大限の敬意を払っている。こうして、届ける側と届ける場の双方が、互いに思い切り向き合うということをいかにして忘れないかが、地域社会における芸術拠点においては重要である。
“Art”を日本語にすると「表現」であるが、「表現」をもう一度英語にすると“express”となる。つまりアートの活動は「想いを届ける」ということである。表現という行為はその根本に、「届ける」という姿勢をも持ちあわせるのだ。そのため、アーティストが、まさに<いのち>をかけて届けようとすることに対して、それらを届ける場である應典院の方では最大限の敬意を払っている。こうして、届ける側と届ける場の双方が、互いに思い切り向き合うということをいかにして忘れないかが、地域社会における芸術拠点においては重要である。
◎広がる活動
2009年の夏、アサヒビール芸術文化財団によるアサヒ・アート・フェスティバルに参加し、大阪市の事業を受託した「住み開きアートプロジェクト」を展開した。これは「私の家」をクリエイティブな拠点となる「みんなのための場所」として開く際に必要とされる「ひと手間」から、公共性を考え直してみようという試みである。「われわれ」の場所として公によって設置される「箱もの」に比べて、完全に私的でクローズドな状態にある「わたし」の場所がオープンにされていくあいだに徐々に「みんなの場所」になっていく拠点とは異なる点は何か、を明らかにしよう、ということである。「わたし」から「わたしたち」への人称変化に着目しつつ、「公」から「私」へ視線を向けるものだ。本来公共性の高いはずのお寺を問い直してきた應典院寺町倶楽部ならではの実践である。

應典院のロゴ“out○in”…ローマ字の“en”の部分を○にすることによって、“out(外)”と“in(内)”を円でつなぐことを表すマークになっている。これもアーティスト(安藤新樹さん)の発想である。こうして多くの創意工夫が重ねられる應典院では、「わたし」と「あなた」がつながっていく取り組みを今後も続けていく。

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.


