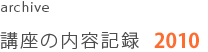

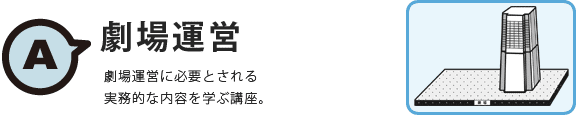
『舞台芸術と著作権・契約/実務力がつく4日間 2010』
Vol.2「著作権(2):実践編」
2010年9月21日(火) 19時~21時
福井 健策
(弁護士・ニューヨーク州弁護士/日本大学藝術学部客員教授)
《所 感》
著作権2回目の今回は、前回の残りである基礎編の続きと、実践編の途中までの講義がなされた。「著作権」という如何にもややこしそうなテーマであったが、講師の巧みな話術に、たちまち講義に引き込まれてしまう内容であった。
舞台芸術の制作を行う際の、具体的な著作権のお話はもちろんのこと、著作権の基となる「自然権論」と「インセンティブ論」が興味深かった。なぜ著作権が存在するのかということは、創作に関わる仕事をするうえで誰しも考えることではないだろうか。
この2回で著作権の全てを理解できたわけでは到底ない。しかし、今後予想される著作権を巡る困った事態への心構えと、そのときに何を調べ、確認し、どこに助けを求めればよいかという糸口を掴んだように思う。
著作権2回目の今回は、前回の残りである基礎編の続きと、実践編の途中までの講義がなされた。「著作権」という如何にもややこしそうなテーマであったが、講師の巧みな話術に、たちまち講義に引き込まれてしまう内容であった。
舞台芸術の制作を行う際の、具体的な著作権のお話はもちろんのこと、著作権の基となる「自然権論」と「インセンティブ論」が興味深かった。なぜ著作権が存在するのかということは、創作に関わる仕事をするうえで誰しも考えることではないだろうか。
この2回で著作権の全てを理解できたわけでは到底ない。しかし、今後予想される著作権を巡る困った事態への心構えと、そのときに何を調べ、確認し、どこに助けを求めればよいかという糸口を掴んだように思う。
記録:福西千砂都(東京学芸大学大学院教育学研究科博士前期課程修了)

1. 模倣とオリジナルの境界/どこまで似れば「侵害」なのか
1-1.「日々の音色」論争
映像:「日々の音色」(SOURによる同名曲のプロモーションビデオ)
“Pepsi Refresh Project”(「2010 年ペプシ社会貢献プロジェクト」CM)
「日々の音色」に酷似していると話題になったのが“Pepsi Refresh Project”だ。後者は前者の著作権を侵害しているのか、というこの問いに正解はない。ネット上で論争になっただけで、裁判にもなっていない。答えは曖昧なままであり、今後も真似されていくかもしれない。
しかしこの問題の論点は明確である。一つは、真似されたのはアイディアか具体的な表現かということ。(アイディアの真似は可能だが、具体的な表現を真似してはいけないと言われている。)もう一つは、真似を可能、もしくは不可能とすることによるメリットとデメリットの問題だ。可能とすることで新しい作品が生まれるか、あるいは、もともとのクリエイターの利益が阻害されてしまうのかを考えなければならない。
“Pepsi Refresh Project”(「2010 年ペプシ社会貢献プロジェクト」CM)
「日々の音色」に酷似していると話題になったのが“Pepsi Refresh Project”だ。後者は前者の著作権を侵害しているのか、というこの問いに正解はない。ネット上で論争になっただけで、裁判にもなっていない。答えは曖昧なままであり、今後も真似されていくかもしれない。
しかしこの問題の論点は明確である。一つは、真似されたのはアイディアか具体的な表現かということ。(アイディアの真似は可能だが、具体的な表現を真似してはいけないと言われている。)もう一つは、真似を可能、もしくは不可能とすることによるメリットとデメリットの問題だ。可能とすることで新しい作品が生まれるか、あるいは、もともとのクリエイターの利益が阻害されてしまうのかを考えなければならない。
1-2.「自然権論」と「インセンティブ論」
なぜ、このようにやっかいなことに悩むのか。アイディアと具体的な表現との境目は曖昧である。制度のあり方として、すべての真似を許可し、著作権をなくし、新しい作品をどんどん生みだしてもよいのである。実際、シェイクスピアの時代には著作権は存在していなかった。彼の作品には全て種本があるが、彼が手を加えることで初めて歴史に残る物語になったのである。
現在では、著作権の基盤となる主な考え方として2種類が挙げられる。
一つは「自然権論」。著作権があるのは当然だという考えである。自分の作品を真似されれば、それがどれだけ情けなく、酷いことかわかるだろう。著作権は、自分だけの作品を苦労して生みだした人間として、当然の要求であり、基本的人権と同じ当然の権利であるという考えだ。
もう一つは「インセンティブ論」。著作権は基本的人権とは異なり、あくまで人為的制度、政策的配慮からの制度であるという考えだ。この主張は、著作権によって生み出される制作上のメリットに基づいている。著作権がなく、誰が真似して構わないということになれば、発売後すぐに海賊版が発売される事態になってしまう。創作のためのコストを負担しない海賊版は価格的に安くなり、購入者は海賊版を購入し、結果、作家は作品をつくることで生活できなくなるという悪循環に陥ってしまう。そうなれば、作家を取り巻く環境は過去へと逆戻りしてしまうだろう。パトロンを持つ、お金持ちが余暇として作品づくりをする、あるいはお金に頼らず極貧の中で創作をしてやがて離れていく……等々、いずれにせよ創作する環境として理想的なものではなくなる。それ故に「作家が次の作品をつくるための一定期間は利益を守ろう」と考えるのが「インセンティブ論」である。あくまで作家の新しい創作を守るためのものであり、次の創作に関係がない部分では、力を発揮しない。
「自然権論」と「インセンティブ論」のいずれをとるかによって、著作権が力を発揮する範囲は大きく異なることになる。
現在では、著作権の基盤となる主な考え方として2種類が挙げられる。
一つは「自然権論」。著作権があるのは当然だという考えである。自分の作品を真似されれば、それがどれだけ情けなく、酷いことかわかるだろう。著作権は、自分だけの作品を苦労して生みだした人間として、当然の要求であり、基本的人権と同じ当然の権利であるという考えだ。
もう一つは「インセンティブ論」。著作権は基本的人権とは異なり、あくまで人為的制度、政策的配慮からの制度であるという考えだ。この主張は、著作権によって生み出される制作上のメリットに基づいている。著作権がなく、誰が真似して構わないということになれば、発売後すぐに海賊版が発売される事態になってしまう。創作のためのコストを負担しない海賊版は価格的に安くなり、購入者は海賊版を購入し、結果、作家は作品をつくることで生活できなくなるという悪循環に陥ってしまう。そうなれば、作家を取り巻く環境は過去へと逆戻りしてしまうだろう。パトロンを持つ、お金持ちが余暇として作品づくりをする、あるいはお金に頼らず極貧の中で創作をしてやがて離れていく……等々、いずれにせよ創作する環境として理想的なものではなくなる。それ故に「作家が次の作品をつくるための一定期間は利益を守ろう」と考えるのが「インセンティブ論」である。あくまで作家の新しい創作を守るためのものであり、次の創作に関係がない部分では、力を発揮しない。
「自然権論」と「インセンティブ論」のいずれをとるかによって、著作権が力を発揮する範囲は大きく異なることになる。
2. 例外的に許可のいらない場合/制限規定
ここからは、著作権の応用編となる。まず、著作権法において「例外的に許可のいらない場合/制限規定」と定められているものから、舞台芸術にとって特に重要なものを紹介する。
「私的使用のための複製」(著作権法 第30条)
「引用」(同32条)
「教育機関における複製等」(同35条)
「非営利目的の演奏・上映・貸与等」(同38条)
「公開の美術の著作物の利用」(同46条)
「引用」(同32条)
「教育機関における複製等」(同35条)
「非営利目的の演奏・上映・貸与等」(同38条)
「公開の美術の著作物の利用」(同46条)
例えば、自宅でTVドラマ(著作物)を録画(複製)して見ることが可能なのは、「私的使用のための複製」(第30条)によって、個人的に楽しむための複製が許可されているからだ。これは個人や家庭、もしくはそれに準ずる範囲内に限られている。
また、「引用」(第32条)について、例えば、「映画の台詞やポップソングの歌詞を戯曲で引用したい」場合はどうするか。引用は何を持って許されるのかという基準が曖昧である。第32条の条文自体が曖昧であり、判例も曖昧なのだ。
すべての制限規定を覚えることは不可能なので、制限規定の項目を一通り見ておいて、必要なときに、文化庁や著作権情報センター(CRIC)のウェブサイトで確認するとよいだろう。
また、「引用」(第32条)について、例えば、「映画の台詞やポップソングの歌詞を戯曲で引用したい」場合はどうするか。引用は何を持って許されるのかという基準が曖昧である。第32条の条文自体が曖昧であり、判例も曖昧なのだ。
すべての制限規定を覚えることは不可能なので、制限規定の項目を一通り見ておいて、必要なときに、文化庁や著作権情報センター(CRIC)のウェブサイトで確認するとよいだろう。
3. 保護期間と国際著作権
3-1. 保護期間の原則
保護期間の原則は、著作者の死亡の翌年から50年である。匿名やペンネーム、団体名義の場合は、公表の翌年から50年となる。
戦前・戦中の欧米(連合国)作品は、「戦時加算」による延長が行われる。
戦前・戦中の欧米(連合国)作品は、「戦時加算」による延長が行われる。
3-2. 著作権の国際的保護
著作権は、ほぼ全世界で自動的に守られる。日本で不可能なことは概ね海外でも不可能だ。ただし、保護期間など細部は異なる。
4.舞台芸術と著作権
4-1. 戯曲・台本
次に、舞台芸術を成立させる要素の著作権について検討していく。
戯曲・台本は著作物である。ただし、保護期間を過ぎれば許可を取らずに上演することができる。
座付作家が劇団を離れる場合、所属中に書いた戯曲・台本の著作権が問題になることがある。著作権は劇団の共有なのか、作家のものなのか。有名な裁判に「音楽座ミュージカル事件」や「新宿梁山泊事件」があり、どちらも作家の要求が認められた結果となっている。劇団側には戯曲・台本は劇団の皆で書いたもの(共同著作)であり、劇団を離れた人は権利を失うという意識がある。しかし、アイディアを出した、調べ物をした、感想を言った、助言をした、叱咤激励した、お金を出した、食事をつくった、といった理由があっても、共同著作とは認められない。アイディアや助言、愛は創作物にとってかけがえのないものであるが、著作物ではない。共同著作の場合は、著作物の中身である創作的表現の持寄りなどがなければ裏付けられない。
また、テキストレジーに関しては、当事者同士に暗黙の了承がなければ、訴えられた際に分が悪くなる。
戯曲・台本は著作物である。ただし、保護期間を過ぎれば許可を取らずに上演することができる。
座付作家が劇団を離れる場合、所属中に書いた戯曲・台本の著作権が問題になることがある。著作権は劇団の共有なのか、作家のものなのか。有名な裁判に「音楽座ミュージカル事件」や「新宿梁山泊事件」があり、どちらも作家の要求が認められた結果となっている。劇団側には戯曲・台本は劇団の皆で書いたもの(共同著作)であり、劇団を離れた人は権利を失うという意識がある。しかし、アイディアを出した、調べ物をした、感想を言った、助言をした、叱咤激励した、お金を出した、食事をつくった、といった理由があっても、共同著作とは認められない。アイディアや助言、愛は創作物にとってかけがえのないものであるが、著作物ではない。共同著作の場合は、著作物の中身である創作的表現の持寄りなどがなければ裏付けられない。
また、テキストレジーに関しては、当事者同士に暗黙の了承がなければ、訴えられた際に分が悪くなる。
4-2. 振付
振付も著作物である。ダンサーには一度踊った作品は自分のものであるという意識があるが、著作権は振付家が持っている。「ベジャール事件」では、振付家・ベジャールによって、彼の許可なく踊ったダンサーではなく主催者が訴えられた。主催者は舞台上で行われたほぼすべてに責任を持つ。契約書に「事故や著作権侵害は駄目だ」と書いている程度では、おそらく責任は免れない。
4-3. 装置・衣裳デザインと照明プラン
装置・衣裳デザインは、著作物の場合が多い。
衣類は一般には実用品であるが、舞台衣装など鑑賞目的の実用品は著作物であると考えられる。ただし、そこには創作性が必要となるため、黒の全身タイツや既存服などは当てはまらない。既存服を独創的に組み合わせた舞台衣装の場合は、組み合わせが著作物になることがある。ヘアメイクも、独創性があれば著作物に当たる可能性がある。CATSのヘアメイクなどがそれだろう。
装置・衣裳デザインの著作権はデザイナーである舞台美術家にある。制作を委託したからといって、著作権は移らないのが原則だ。 照明プランにおいても、著作物にあたるものはあろう。ただし、定石的な部分は著作物ではないと考えられる。
衣類は一般には実用品であるが、舞台衣装など鑑賞目的の実用品は著作物であると考えられる。ただし、そこには創作性が必要となるため、黒の全身タイツや既存服などは当てはまらない。既存服を独創的に組み合わせた舞台衣装の場合は、組み合わせが著作物になることがある。ヘアメイクも、独創性があれば著作物に当たる可能性がある。CATSのヘアメイクなどがそれだろう。
装置・衣裳デザインの著作権はデザイナーである舞台美術家にある。制作を委託したからといって、著作権は移らないのが原則だ。 照明プランにおいても、著作物にあたるものはあろう。ただし、定石的な部分は著作物ではないと考えられる。
4-4. 音楽(作詞・作曲)
CD演奏も演奏であり、イベントの客入れやBGMで使用する際にも許可が必要だ。ただし、非営利のイベントの場合は例外となる(制限規定 第38条「非営利目的の演奏・上映・貸与等」)。
日本音楽著作権協会(JASRAC)は、作詞家や作曲家から著作権の譲渡を受けて管理している。作詞家や作曲家本人、もしくは音楽出版社を経由して譲渡を受けるため、ほとんどの場合、演奏権はJASRAC が管理していると考えてよい。
舞台では、現在は「初演委嘱免除」というJASRAC特有の運用がある。
また、オペラやミュージカルなど、演劇的な外国の音楽作品に関しては、JASRACの管理領域ではない場合がある。これを「グランドライツ」と言う。例えば、アメリカでは作詞家や作曲家自身で管理するのが一般的であり、作家や彼らが所属している専門の音楽会社と直接交渉をする必要がある。音楽著作権に関しては、主催者側が処理をする場合が多いので、特に重要である。
オーケストラの譜面に関しては、著作権が切れていた場合でも膨大な量の譜面のすべてを手に入れることは現実的に難しいため、「貸譜料」を支払ってレンタルすることがある。貸譜には、放送の時は別途許可をとる必要があるなど、しばしば著作権と同じような付帯条件がつく。
また、アレンジ・オーケストレーションの際は、JASRAC以外の許可が必要な場合がある。アレンジには、編曲権の問題が関わってくる。ライブでも、大幅な編曲の場合は気を付ける必要がある。
日本音楽著作権協会(JASRAC)は、作詞家や作曲家から著作権の譲渡を受けて管理している。作詞家や作曲家本人、もしくは音楽出版社を経由して譲渡を受けるため、ほとんどの場合、演奏権はJASRAC が管理していると考えてよい。
舞台では、現在は「初演委嘱免除」というJASRAC特有の運用がある。
また、オペラやミュージカルなど、演劇的な外国の音楽作品に関しては、JASRACの管理領域ではない場合がある。これを「グランドライツ」と言う。例えば、アメリカでは作詞家や作曲家自身で管理するのが一般的であり、作家や彼らが所属している専門の音楽会社と直接交渉をする必要がある。音楽著作権に関しては、主催者側が処理をする場合が多いので、特に重要である。
オーケストラの譜面に関しては、著作権が切れていた場合でも膨大な量の譜面のすべてを手に入れることは現実的に難しいため、「貸譜料」を支払ってレンタルすることがある。貸譜には、放送の時は別途許可をとる必要があるなど、しばしば著作権と同じような付帯条件がつく。
また、アレンジ・オーケストレーションの際は、JASRAC以外の許可が必要な場合がある。アレンジには、編曲権の問題が関わってくる。ライブでも、大幅な編曲の場合は気を付ける必要がある。
4-5.演技・ダンス・歌唱・指揮・演奏
これらは実演なので、著作物ではなく、著作隣接権になる。著作隣接権は、4つの権利の総称だ。ここでは、実演家の著作隣接権について説明する。
- 録音・録画権(増製含む)
- 放送権・有線放送権
- 送信可能権
- 譲渡権
- 貸与権
著作権とは異なり、著作隣接権には演奏権・上演権と翻案権がない。著作権は模倣を禁止しているために強い力を持つが、著作隣接権ではそもそも模倣を禁止しておらず、実演の録音録画を介してしか権利が生まれない。また「ワンチャンス主義」など例外もいろいろとある。
以上が、舞台公演を構成する個別の要素に関する著作権の説明である。一つ一つが非常に興味深い問題を孕んでいる。例えば映画に関しては、シナリオや映画、演技といった要素以前に、映画全体をひとつの著作物として扱っているが、演劇公演全体、ライブイベント全体は著作物なのだろうか。この問題は、次回の講座にて検討されることとなった。
参考:福井健策「著作権とは何か」「著作権の世紀」(集英社新書)
福井健策編「エンタテインメントと著作権」シリーズ(①ライブ・エンタテインメント編。CRIC刊)
以上が、舞台公演を構成する個別の要素に関する著作権の説明である。一つ一つが非常に興味深い問題を孕んでいる。例えば映画に関しては、シナリオや映画、演技といった要素以前に、映画全体をひとつの著作物として扱っているが、演劇公演全体、ライブイベント全体は著作物なのだろうか。この問題は、次回の講座にて検討されることとなった。
参考:福井健策「著作権とは何か」「著作権の世紀」(集英社新書)
福井健策編「エンタテインメントと著作権」シリーズ(①ライブ・エンタテインメント編。CRIC刊)

copyright 2010 (c) SETAGAYA PUBLIC THEATRE / THEATRE TRAM. all rights reserved.


